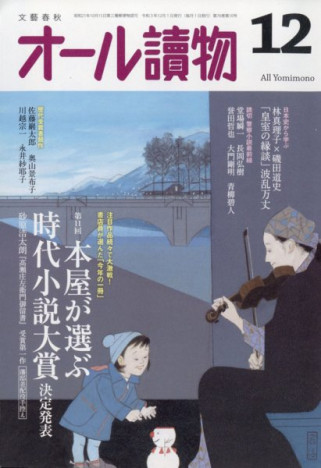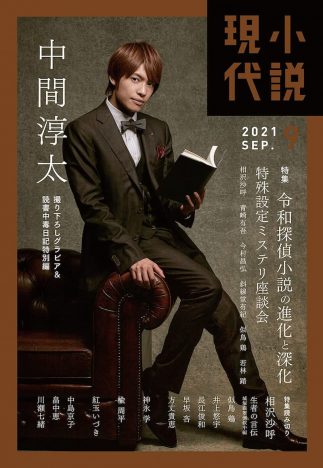「SFマガジン」91年生まれの新編集長・溝口力丸が語る、伝統への挑戦「手の届かない遠さまで未来を求めようとする姿勢が大事」

世のなかや読者に刺さる特集を作って、生きていることを確かめたい

――SFはかつて「冬の時代」と呼ばれた時期もあったわけですが、2年前に塩澤さんにインタビューした際、「梅田や溝口が真夏にしてくれるかもしれません」と話されていたので、いずれどちらかが編集長になるのだろうと予想していました。
溝口:塩澤は編集長を20年以上続けてまだ50代なので、あるいは終刊までやるのかな、とぼんやり考えていました。まさかこんなに一気に変化するとは予想せず、いまSFマガジン編集部は金本という新入社員1人と中途入社の米山という新人1人、それと私という構成になり平均年齢がいきなり26歳にまで若返った(笑)。前向きに捉えれば、会社からは雑誌をどう変えてもいいと思われているんでしょう。ただ、いきなり全部変えると一気に足場がガタガタになり、雑誌が蓄えてきた財産すら失くす恐れもあって、新しい2人が慣れるまでは抜本的な改革はまだやめておこうと決めました。
――「SFマガジン」はしばしば回顧的な特集を組みますし、最近刊行の『ハヤカワ文庫JA総解説1500』もそうですが、早川書房はこれまでの歴史をふり返りつつ新しいものを探す形でずっとやってきていますね。
溝口:日本文学史のなかでも、これほど歴史を大事にしているジャンルもなかなかないのではないでしょうか。誕生から現在まで全てを多角的に追えます。だから歴史がジャンルの一番の財産ですが、あまり保守的になっても人員が変わった意味がない。伝統を引き継ぐだけでなく、予想もつかない形でひっくり返していくのが今後の課題でもあるんです。
――編集長になって初の今年2月号は、特集「未来の文芸」という真正面のテーマでした。
溝口:いきなり変化球は投げられません。実務的にもいろいろ制約があり、新しい書き手の多様な短編・評論を載せました。割付などは新人に手伝ってもらいましたけど、小説は全部自分が担当なので、これなら一点突破で特集を作れると判断しました。集まった原稿の性質も含めて、「SFマガジン」のアイデンティティをもう1回問い直したとき、普通の文芸誌に手の届かない遠さまで未来を求めようとする姿勢が大事だと思いました。
――同特集の小説以外の記事は、SFというより出版全体の未来を扱っていましたね。
溝口:それこそ出版界がいつまで続くかという話でもあります。SFやミステリといった各ジャンルがどうこうではなく、小説文芸の未来を考えることは、出版業界にかかわる1人1人がどう豊かに生き延びていくかと切り離せなくなっているので、その経済や倫理にも向きあおうとしました。そんななか「SFマガジン」でも“幻の絶版本”特集中止という問題が起きたので、編集長就任挨拶でもあった同号の巻頭言でお詫びすることになりました。あそこで書いたことがすべてですが、今後の誌面で変化を見せていくしかない。
――「SFマガジン」は初代の福島正実編集長の時以来、批判や論争の歴史です。
溝口:心が折れないことが大事だと思っています。塩澤のインタビューで「生き残ることしか考えていなかった」とありましたが、私はあまり生きている実感がないので、生きている実感が欲しくてやっています。特集などで論争が起きると、まだこんなに雑誌を気にかけてくれる人がいるんだと逆に元気が出る……強がりです(笑)。基本は落ち込みますが、そう思うことにしている。今回の特集「BLとSF」も経緯が経緯だったので、創刊750号に合わせて本気で企画をして、ものすごく緊張して世に出したら、想像以上の好評をいただけて嬉しかった。なんとなく出して反響もほとんどなかったら、雑誌も自分も生きているか死んでいるかわからない。世のなかや読者に刺さる特集を作って、生きていることを確かめたい。『ファイト・クラブ』もそういう話ですね。痛みは伴いますけど。
ファンダムの豊かさも継承できるような雑誌作りを

――百合やBLを特集してきたわけですが、以前からジェンダーに関心があったんですか。
溝口:マーガレット・アトウッドやアーシュラ・K・ル・グィンが好きだったので当然、一つのテーマとして好きでしたが、ナラトロジー、テキスト論、ポストモダンなど多くの文学理論を学ぶなかでのジェンダー、フェミニズムという受けとめかたでした。ただ、ヒットした1回目の百合特集には書き手や内容に偏りがあり、2回目の百合特集は当時の自分を乗り越えるつもりで企画して、今回のBL特集に至った。その間にも世界は変わり続け、向きあうべき課題はどんどん増えています。雑誌の特集は、暗闇で石を投げて音が返ってきたところへ歩いていくような側面がある。今の社会でジェンダーをめぐる議論が大きくなっていることも無関係ではないと思います。早川書房で最近訳される海外SFにもそういう問いかけを持った作品は多いですし、SFではありませんが逢坂冬馬さんの『同志少女よ、敵を撃て』もそうでしょう。
――「SFマガジン」次号では河出書房新社の「文藝」とのコラボがありますね。これは塩澤編集長時代にツイッターで双方のやりとりがあったのが企画の始まり。
溝口:「文藝」の坂上陽子編集長は尊敬しています。リニューアル後の「文藝」は誌面が生き生きとしているし、なにより作品が面白い。実はBL特集の際、個人的に坂上さんに相談して、書き手の推薦もいただきました。「SFマガジン」がジェンダー面でどう開かれていくかというとき、「文藝」の執筆陣や誌面構成は参考にしています。それもあって、前々からコラボしたいという話があったのを今回動かしました。次号はアジア特集なので韓国SFをとりあげてきた「文藝」とも相性がいいかなと。ページ交換企画という形で、お互いにそれぞれの雑誌のなかで小特集を展開する予定です。こちらは《イーガン祭》と称して「文藝」にグレッグ・イーガンを持ちこみ、「文藝」は韓国SFを「SFマガジン」へ持ちこむ。お互いの読者に読んでほしいものを届けあおうということで。
――SFには独特のファンダムが形成されていますが、接してみて印象はどうですか。
溝口 作家とファンの距離が近ければ、プロとアマチュアの距離も近く、それが効を奏している。たとえば大森望さんがやっているゲンロンSF創作講座は、プロ作家の輩出率が尋常じゃないですけど、あれもSFコミュニティの力かなという気もします。一般に人がSFだと感じるのは現実を覆すような科学や超自然的な物語でしょうけど、実際のSF文芸は、内容以上にコミュニティが担保している節もあると思います。SFコミュニティでとりあげられていれば何でもSFとみなされるような、世間一般が持つSFのイメージと現場で繰り広げられているSFのイメージに乖離がある。それが今後どうなるか。コミュニティよりも広大な社会一般のSFのイメージに近づいていく気もしますが、そのときなにかが取りこぼされないか心配です。SFプロトタイピング(SF的発想で未来を試作しビジネスに活かそうとする手法)も注目されて、SFに対する社会の期待値は上がっているだけに、ファンダムの豊かさも継承できるような雑誌作りをしたいですね。
――最近、早川書房が催した「世界のリーダーはSFを読んでいる」フェアもそうですが、世界や未来を理解するためという実用書的な動機でSFに注目する傾向が目立ちます。

溝口:劉慈欣『三体』のヒットが、いろんなものを変えました。世間一般のSFのイメージもそうなら、SF小説が売れるというイメージもそう。劉慈欣は高度成長期の小松左京の立ち位置をなぞっている部分があり、実際最近は中国でも小松左京がブームのようです。実用書的な、早川書房や「SFマガジン」とは関係のない分野でSFのイメージが変わっていき、より社会的、企業案件的な出版が今後増えるかもしれません。最近は世相が荒れていて現実の言葉だけで現実をとらえにくくなっているから、社会の実態を掴むための必要にかられてSFが読まれたり生まれたりする。ジョージ・オーウェルなんかそうですね。でも、必要にかられたSFばかりになったらある意味貧しいとも思いますし、現実世界と関係ない不思議な話も楽しまれてほしい。とはいえ、これだけ残酷な戦争報道が続く状況では現実を無視することもできず、日々悩んでいます。
SF作家も多様化しているので、その人の持ち味を伸ばしたい。SF読者にしても、私が入社してから「SFはこうでなければならない」と強く出るような原理主義者はあまり見たことがないです。樋口恭介編『異常論文』のヒットもそうでしたが、面白ければなんでもいいと思ってもらえる土壌はあるようですし、SFはあらゆる文芸ジャンルのなかでも一番自由な場所であってほしい。自由な人たちが集まってきてほしい。
――今後の「SFマガジン」で考えていることは。
溝口:特集って個人では作れないものです。どれだけ面白い小説を書く人がいても、その作家の原稿だけでは特集にならない。「BLとSF」特集もそうですが、こういう小説や評論が集まりましたよと場を作ることで届けられるメッセージがある。続く世代へ、あなたもここに入ってくれると嬉しい、と伝えようとしたりですね。繰り返しになりますが、人を増やしたいんです。ジャンルの定義自体を広げることで読者や書き手が増えることもあるし、人が人を呼んでいくこともある。2010年代にSF新人賞や創作講座が活性化して作家は増えましたが、いっぽうでSFの未来にとっては翻訳家の増加も大事です。しかも英語ばかりではなく、中国語などべつの言語の翻訳需要も増えている。だから6月あたりのSFマガジンでは、翻訳という行為自体を盛り上げる特集をちょっと考えています。
――今は新しい翻訳家はどうやって探しているんですか。
溝口:人づての紹介が多いので、もう少し公募的というか、個人が版元に対して直接手を上げやすい枠組みを作れたらいいなと思っています。現状でもベテラン翻訳家の皆さんのおかげで海外SF界は豊饒ですが、数十年後も見据えていくのが雑誌としての使命かなと。ただ特集としては、新しいことばかりやろうとするうちまだまだ価値のある古典的名作が絶版になったりもするので、過去からの再発見も気を配りたい。それにSFといえば今は小説だけでなく映画やゲーム、漫画やアニメ、VRなど様々なメディアがあるからそれも目を向けて……あっという間に1年ぶんの特集が埋まっちゃう(笑)。今あげた以外にも、もっと予想外の方向へガッと外に広げる特集も考えたいですね。