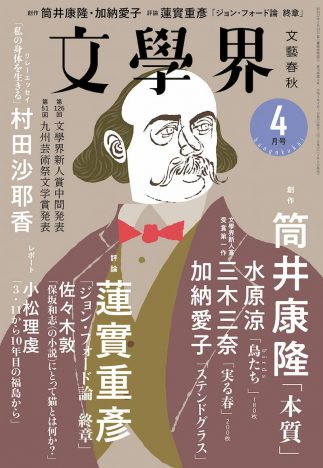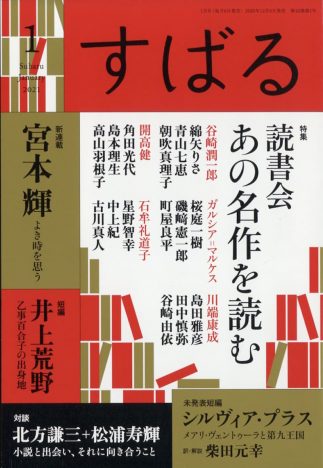「小説現代」編集長・河北壮平が語る、小説の未来 「外に開いていく革命へと意識を転換するようになった」

エンターテインメント系の小説雑誌をめぐっては、刊行ペースの変更、紙版から電子版への移行など各社が試行錯誤している。それに対し、2018年10月号でいったん休刊し、2020年3月号でリニューアル創刊した「小説現代」(講談社)は、長編連載中心の従来のスタイルを見直し、毎号読み切り中心にすることで新たな方向性を打ち出した。2015年にスタートしたレーベル、講談社タイガの編集長などを経て、2021年2月より「小説現代」の新編集長になった河北壮平氏は、メディアミックスの経験も多い。小説の面白さをどう伝えるかについて同氏に聞いた。(8月24日取材/円堂都司昭)
0.99が1ではない世界で仕事をしたい
――プロフィールでは、大阪大学大学院工学研究科中退後、2003年講談社入社となっていますから、大学院では理系の研究室に在籍していた。それがなぜ文芸の世界へ転身したんですか。
河北:大学では生産システムのシミュレーションの研究をしていて、直球の理系でした。でも、大学院にまで進んだのですがどうにも違和感が拭えず、遅ればせながら自分が本当にやりたいことは理系ではないんじゃないかと気づいたんです。0か1かの世界ではなく、0.99が1ではない世界で仕事をしたい、ずっと好きだった小説、文芸をやりたいと思って講談社に就職することに決めました。
――入社前、特にこのジャンルをやりたいということはあったんですか。
河北:文庫出版部志望でしたが、当時は知識がなく、自分が好きなものを読んでいるだけで単行本が文庫化される流れもよくわかっていませんでした。入社して同僚の話を聞くと、まるで読書量も足りなかったので、無知は恐ろしいですよね。よく入社させてくれたな、と。
――1990年代後半から2000年代はじめが学生時代にあたりますよね。その頃は講談社ノベルスに勢いがありました。1980年代末から綾辻行人、法月綸太郎、麻耶雄嵩などがデビューする新本格ミステリのムーブメントがあり、1990年代には京極夏彦、森博嗣、清涼院流水、2000年代には西尾維新や舞城王太郎など、講談社で河北さんが後に配属される文芸第三出版部は注目作家を多く輩出していましたが……。
河北:ノベルスに関してはもっと前の小学生の頃、読み終わらないものが読みたくて赤川次郎先生、西村京太郎先生、山村美紗先生を図書館で端から全部読んでいったんです。
――ああ、終わりそうにないシリーズばかり(笑)。
河北:でも、当時刊行されていた作品は全部読み終わりました。なにがしたかったんでしょうか。とにかく刊数があるものを求めていて、田中芳樹さんの『銀河英雄伝説』とか藤川桂介さんの『宇宙皇子』とか。読書歴も偏っていて、エンタメと純文学の違いもあまり認識しないまま学生時代は、村上春樹さん、江國香織さん、山田詠美さんなども読んでいました。入社して最初に配属されたのは、「コミックボンボン」という小学生向けのマンガ雑誌の部署です。マンガも好きだし編集者として頑張ろうと思ったんですが、同誌は2007年に休刊してしまい、入社時の志望だった文芸へ異動になりました。
小説ってこんなに新しいエンタメ性があるんだ
――入社5年目で移った文芸第三出版部(当時は文芸図書第三出版部)、通称・文三は、ノベルスのほか小説誌「メフィスト」(1996年創刊。2016年に電子版に移行。2021年10月から会員限定小説誌「メフィストリーダーズクラブ」へリニューアル)を発行し、編集者が選者となって新人を発掘するメフィスト賞を主催してきた部署で、ミステリが軸になってきた伝統があります。
河北:異動した当初、「本格ミステリ」が何たるかを正確に理解してなかった気もしますが、10年以上ノベルスやメフィスト賞に携わるうちに、ミステリ編集者だ、みたいな偉そうな顔をし始めて(笑)。
――本格ミステリとは、不可解な謎を探偵役が合理的に推理して意外な真相を解き明かす、そういう物語を基本とするジャンルですね。講談社を起点に若手作家によるそのリバイバルが1980年代末に起きて、新本格ミステリと称された。そのムーブメントについては……。
河北:なんとなくは知っていましたけど、横目でみていたところがあって。それが文三に配属され本格ミステリに間近で触れると、とにかく面白い。綾辻行人さん、有栖川有栖さんをはじめ新本格全盛の頃から「メフィスト」へという流れにあったキャラクターノベルの趣や、最近ミステリ界で話題の特殊設定の先駆け的な発想、ある種のマンガ的な要素など、同時代の若者をひきつけるいろいろなものが膨れ上がっている時代だった。小説ってこんなに新しいエンタメ性があるんだ、超面白いじゃんメフィスト賞、と、その魅力にどっぷり浸かりましたね。
――「メフィスト」は、さかのぼれば「小説現代」(1963年創刊)の増刊として始まっています。講談社で「小説現代」を編集している文芸第二出版部は、日本推理作家協会主催の新人賞である江戸川乱歩賞(初回は1955年。新人賞になったのは1957年の第3回から)の受賞作を書籍化する部署でもあります。年月を経て文二が大人向けのエンタメになったのに対し、文三はそのオルタナティブとしてもっと若年層に向けて展開していたようにみえました、2000年代くらいまでは。近年はそれが変化しているようですが。
河北:かつての文学、文芸、特に文三が持っていた志は、スクラップ&ビルドでなにか強大なものに立ちむかう、いわばロックのような感じがあった。でも、僕が文芸の部署に移った10数年前からは少しずつ変わり出している時期でした。文芸を変えるといっても会社や業界の内部の革命だったものを、外部の革命へ、外に開いていく革命へと意識を転換するようになったと思うんです。こんなものは文学ではない、大人の読む小説ではない、ミステリではない、みたいな内ゲバの論争ではなく、もっとポジティブに「小説って面白いよね」というムーブメントに変わりつつある10年だったと思います。その志は2015年にスタートした講談社タイガというレーベルや、リニューアル後の「小説現代」も引き継いでいる。今では、エンタメの文三、文二、純文学の文一といった区分けの話ではなくなり、各部署の横のつながりは以前より増えていますし、それぞれの役割でこれからの小説がどうあるべきかを試しているし考えています。
ウイスキーで例えると「タイガ」はロックかストレートの世界
――河北さんは講談社タイガの創刊に携わり、2017年にレーベルの2代目編集長になるとともに講談社ノベルス、文三単行本、「メフィスト」などの長を兼任しました。講談社タイガは講談社文庫とサイズは同等ですが、位置づけの違いは。ライトノベルと一般文芸の中間でキャラクターを重視した、いわゆるライト文芸とみられることが多いようですが。
河北: 20~30代のエンタメ感度の高い人たちを中心としたレーベルなので作家性が強いし、尖った作品が多い。でも、そういったオリジナリティの強い新しい作品が集まることで結果的に映像化などメディアミックスが増え、創刊から6年ほどで10作品ほどがアニメやドラマになり、この期間に一番映像化割合が多いレーベルだと思います。タイガをライト文芸の一種とみる方もいます。でも、ライト文芸で少し前まで多かったお店×妖怪、アヤカシ、今なら後宮など、流行りのラインをテーマにした小説は、タイガに少ないんです。うちがお店×妖怪をやるのだったら京極夏彦さんがマイルストーンになってしまいますよ?という発想なので。
――京極さんは、妖怪のガチの権威ですからね。次元が違う。
河北:アヤカシとは本来、海坊主のことだから、妖怪の総称とするのは間違っているって京極さんに注意されますね(笑)。流行っているからそのジャンルの小説を世に出そうではなく、本当に面白いものを追求した結果、映像化したいと思われるような尖ったものになると思うんです。
――その場合、尖っているとは、どういう部分ですか。キャラクターは前提ですよね。
河北:ライト文芸とタイガが一緒にされるのは、キャラクター小説だからでしょう。でも今売れているエンタメ小説は、基本的にキャラクターに魅力のある小説です。
――河北さんが、担当したメディアミックス作品でいうと野﨑まど『バビロン』、城平京『虚構推理』、相沢沙呼『小説の神様』、井上真偽『探偵が早すぎる』、藤石波矢『今からあなたを脅迫します』、複数作家執筆の『ネメシス』など、設定や登場人物の思考とか、どこかに極端さを含んだものが多い印象です。
河北:個性が強い作家さんが多いですから。企画の切り口としてなるほどこの手があったかというオリジナリティ、新しさ、味の濃さがある。僕は時々小説をお酒で喩えるんですが、ライトという意味で言うと、小説というウイスキーをソーダ水で割ってレモンを入れハイボールにして飲みやすくしたもの。何杯でも飲めて二日酔いにならない。タイガは、ウイスキーはロックかストレートでどうぞの世界。二日酔いになるけど、クセになる。『バビロン』なんてピーキーでスモーキーなウイスキーだと思いますし、『小説の神様』もある意味では読んでいられないくらい、つらい話です。かつての講談社ノベルスの持ち味といってもいいですが、どこか普通ではないものを出している。面白いのは前提ですが、飲みやすさ、読みやすさを過度に意識しなくてもいいレーベルです。僕がタイガ編集長をやっている時は、部員から上がってきた企画を通さないことはまずなくて、面白さをきちんと担当編集者が説明できて、その面白さを信じているのであればいい。でも、流行りの設定だけ揃えて、面白さの肝が「今売れているから」という理由なら通せません。そうしていました。
映画やドラマは、ヒット作に似たものを追う傾向があります。彼らはかかるお金が莫大だから当たっているものに近いものを作る必要がある。でも、小説はそれらに比べて、フットワークが軽いし、制作原価は映画の何百分の一かもしれない。それなら小説という媒体だからこそできるものを作ったほうがいいですよね。