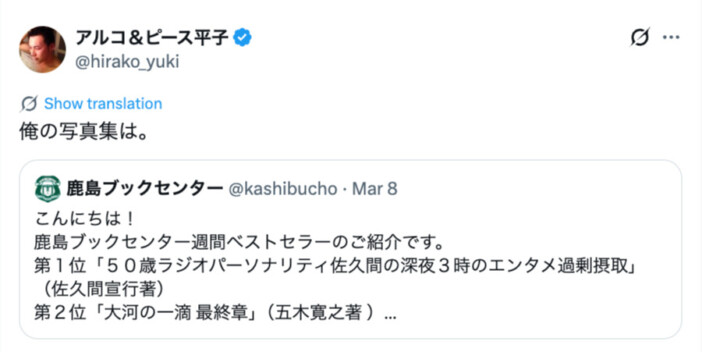『スピン』『GOAT』『アンデル』……安価な文芸誌、創刊相次ぎ大ヒットも 文芸評論家に聞く、版元の狙いとは?

河出書房新社の『スピン』、小学館の『GOAT』、そして本日1月9日に中央公論新社から創刊される『アンデル』。定価300~500円台という低価格帯でありながら、豪華な執筆陣と読み応えのある誌面で、出版・文芸の現場をにぎわせている。中でも『GOAT』は、創刊号からの累計が33万部を突破するなど、文芸誌として異例の成功を収めている。
いずれもA5判で、書店の棚に並べると手に取りやすいサイズ感。しかも『スピン』『アンデル』は創業140周年に合わせた企画として位置づけられており、出版社の節目とも連動した動きになっている。
こうした“安価な文芸誌”はなぜ今、相次いで生まれているのか。そして、それらは文芸と出版業界にとってどのような意味を持つのか。文芸評論家・円堂都司昭に話を聞いた。
近年の文芸誌をめぐる状況
円堂氏は、近年の文芸誌の現在地を以下のように整理する。
「講談社『群像』、新潮社『新潮』、集英社『すばる』、文藝春秋『文學界』、河出書房新社『文藝』といった純文学系の月刊・季刊文芸誌は、いまも継続して刊行されていますが、近年はそれぞれ誌面のリニューアルを図ったりと、試行錯誤を続けてきました。一方で、文藝春秋『オール讀物』、光文社『小説宝石』など、いわゆる“エンタメ系の小説誌”はこの数十年で刊行ペースを月刊から年10回刊とか季刊にしたり、電子版・Web版に移行したりしています。そうした手探りの延長線上に、最近の低価格帯文芸誌の動きがあるのでしょう」
実際、上で挙げられた純文学系5誌は、1冊およそ1,000円代の価格帯で、文芸シーンの中心として機能し続けてきた歴史がある。それに対し、エンタメ寄りの小説誌は部数減や読者層の高齢化のなかで、紙から電子・Webへと活路を求めてきた。しかし、電子やWebに移行すればそれで万事解決かというと、現場の肌感覚はそう単純ではない。
「Webや電子で読めるようにしても、昨今のWebはコンテンツがあまりに多いこともあり、“そもそも存在に気づいてもらえない”という問題があります。文芸誌がターゲットにしている“本好きの読者”に、作品や雑誌の存在が届きにくいんです。一方で、書店の数は減っているとはいえ、本好き・小説好きの人がいまも足を運ぶ場所でもある。そこで紙としてちゃんと置いておきたい、という発想があると思います。
既存の文芸誌や小説誌には長い歴史があり、誌面構成も含めて制約が少なくありません。リニューアルはしても、どうしても“身軽にはなりきれない”部分はあります。だからこそ、その外側で新しい雑誌を立ち上げる動きは、これまでにも定期的に出てきました」
2006年には新潮社が、通常の『小説新潮』『新潮』とは別に、よりライトでシンプルなレイアウトの『yom yom』を出し、一定の成功を収めた例もある(現在はウェブマガジンに移行)。既存のフォーマットから距離を取り、軽やかに読者へアプローチする試みは、繰り返し立ち上がっては消えてきた歴史があるのだ。近年、アメリカではWeb広告の氾濫や「デジタル疲れ」を背景に、紙の本が媒体として再評価される向きがあるというが、再び低価格帯の文芸誌が生まれているのは、そうした流れとも無関係ではないだろう。
「文芸そのもののPR誌」という発想
『スピン』『GOAT』『アンデル』の3誌は、どれも低価格という共通点があるが、そもそもの狙いはどこにあるのか。
「3誌に共通しているのは、とにかく“安い”ことですよね。あの価格帯で、分量や執筆陣を考えるとかなりお得なつくりです。でも、それ単体で採算を取ろうという発想ではないはずで、むしろPR的な意味合いが強い。“出版社の会社案内”というより、“文芸そのものをPRする媒体”として位置づけられているように感じます」
では、3誌それぞれの特徴はどのようなものか。
「『スピン』は、河出の文芸部門が好調ななかで、“それとは別に、日常的にさらっと読めるものを出してみよう”という発想から生まれているように見えます。キャッチコピーが「日常に「読書」の「栞」を」ですし。“ふと手に取ってもらう”日常性を目指している。だからこそ、価格は抑えめで、毎号使用する銘柄がかわる紙の手ざわりも含めて“読書の入り口”としての機能を持たせているんだと思います。
『GOAT』は、とにかくラインナップが華やかです。映像化と絡めた企画や、タレントと作家の対談も多い。俳優やミュージシャン、アイドルとして活動しつつ文筆業も行う人たち――加藤シゲアキ、松井玲奈、尾崎世界観といった顔ぶれ――を毎号誰かフィーチャーしている。かつてフジテレビで放送されていた文学バラエティ番組『タイプライターズ~もの書きの世界』のような、タレント的な華やかさを備えた書き手を起用して文学の世界へ橋渡しするような機能を、紙の雑誌として実現している印象があります。
さらに、『GOAT』には姉妹誌『GOAT meets』もあります。こちらはB5判・定価2200円(税込)と、むしろ“本誌より高い”価格帯で、作家同士の旅や対話をじっくり追うような企画が組まれています。510円の『GOAT』で読者を引き込み、濃いファンには『GOAT meets』のような高価格帯の本も手に取ってもらう、という二段構えの設計になっているようにも見えます」
“豊かな小一時間”のための「小さな文芸誌」と銘打って、本日刊行された『アンデル』は、A5判・80ページ、定価330円(税込)で、他の2誌と比べてさらに薄くコンパクトに作られているのが特徴だ。創刊号には朝比奈秋、石田夏穂、犬飼寅日子、古賀及子ら、近年話題の著者の読み切りが並んでいる。
「『アンデル』は、『スピン』をさらに薄くしたようなイメージですよね。創刊号の顔ぶれを見ると、極端に尖っているわけではなく、若年層や女性読者を含めた幅広い層を意識しているように感じます。村上春樹の翻訳作品も収録されるとのことで、その意味でも“入口としての読みやすさ”と“しっかりした文学性”の両方を備えた設計なのかなと。例えるなら、店舗の前で無料のコーヒーを配っている『カルディ』のようなイメージで、ちょっとした“試食感覚”で手に取ってもらえるような低価格とボリューム感なのかなと思います」
出版社にとってのより直接的なメリットとして、話題となった掲載作品を単行本化することでの収益化も見込めるだろう。
「小説誌であるからには当然、『GOAT』に載った作品をいずれ単行本化してヒットさせましょう、ということですよね。『GOAT』自体が何十年も続く雑誌になるかどうかは分からないけれど、注目を集めてヒット作を生み出すことができれば、成功と言えると思います。『スピン』と『アンデル』の場合、いずれも140周年記念の期間限定刊行ですし、はじめから短期的な活性化策として企画されている。新潮社の紙版『yom yom』もそうでしたが、“伝統的な文芸・小説誌ではない場所で、もう少し軽やかにやってみよう”という試みは、過去にいろいろありましたけど、長くは続いていません。『スピン』や『アンデル』が“期間限定”を明言しているのも理解できます。それでも本が売れないといわれるこの時代に、“文芸って意外と面白いかもしれない”と感じる機会を増やせれば、それだけで意味があると言えます」
文芸誌の世界は、これまでも「創刊→話題→休刊」という歴史を繰り返してきた。だが、その一つひとつが新しい書き手を見つけ、読者の裾野を広げ、のちのヒット作につながってきた面もある。安価な文芸誌が改めて話題になることによって、アメリカの出版業界のように、媒体としての紙の本の再評価が進む可能性もありそうだ。