「ロッキー像は映画の大道具から街のシンボルになった」ミュージアム研究者・小森真樹に聞く、歴史修正の光と影

美術館、博物館は、過去を保存する場所であると同時に、現在の価値観を映し出し、国家の物語を編み直す装置でもある。
世界各地のミュージアムを巡り、その「語り方」を記録してきたミュージアム研究者・小森真樹が明らかにするのは、展示やグッズ、エンターテインメントを通じて、歴史がいかに更新され、時に争われているかという現実だ。
包摂を目指す誠実な歴史修正と、権力による非誠実で否定論的な介入。その最前線として浮かび上がるのが、フィラデルフィアのミュージアムとロッキー像である。ミュージアムから読み解く、アメリカと世界の今。2025年9月に『歴史修正ミュージアム』を上梓した小森に話を聞いた。
ミュージアム研究とは

ーー小森さんのご専門に「ミュージアム研究」とありますが、ちょっと珍しい分野ですね。
小森真樹(以下、小森):確かにあまり聞き慣れないかもしれませんね。「博物館学」と名のつく講座が多くの大学にあるのはご存知かと思います。これに対応する分野を英語圏では「ミュージアム・スタディーズ(研究)」と呼びますが、日本でもここ20年ほどで、英米などの研究を意識した研究者のあいだで「ミュージアム研究」という呼び方が普及しました。
ーー比較的新しい学問なんですね。いわゆる日本の博物館学とどこが違うのでしょうか。
小森:簡単にいうと、この2つの学問は立ち位置が異なります。一般的に日本の博物館学は、学芸員の資格を取るための実学的な側面が強く、博物館の運営論など現場で働くために必要なテクニカルな知識を学ぶ学問になります。それに対してミュージアム研究はより人文学的で、ミュージアムがどのように権力と関わり、どのように歴史を構築し人々に提示してきたのかをクリティカルに分析します。
世界のミュージアムをリアルタイムで記録

ーー『歴史修正ミュージアム』はサバティカル(研究休暇)の間に世界各地の膨大な数の博物館を訪れて書いた、観察記録のような本ですね。
小森:私は普段の研究ではテーマをしぼり、長い時間をかけて問いを深掘りし、学術論文を執筆しています。なのでサバティカルでは、もっと違うアプローチを取りたかったんです。一年間まるまる使って世界各地のミュージアムの動向や語り口を同時期に観察できる機会なんて滅多にありません。2024年のミュージアムがどのように歴史と向き合っているのか、リアルタイムで切り取ることが本書の目的でした。
ーー訪れた場所も、かなりユニークなところが含まれていますよね。
小森:はい、あえて多様なミュージアムを訪れました。ニューヨークの倉庫街の目立たない裏口を開けたら、実はそこがアーティストの作ったマニアックなミュージアムになっていたというような場所から、ロンドンのテート・ブリテンのような超王道の美術館まで様々です。さらにそれを、「そこにいる私が観察している」という身体性を伴った人類学的な視点で記録したいと考えていました。
「歴史修正」の本来の意味
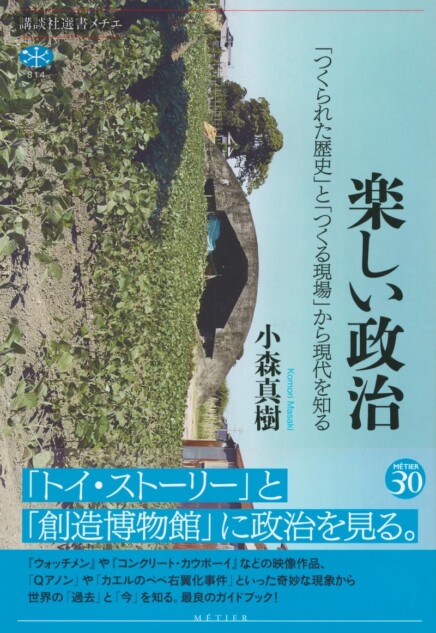
ーー本のタイトルにある「歴史修正」は、少しドキッとする言葉ですよね。この言葉を選んだ理由は?
小森:日本語で「歴史修正」と言うと、たとえば南京大虐殺やホロコーストはなかったとか、その被害者の数は実は少なかったというように、検証可能な学術的根拠を無視して、自分たちの都合の良いように過去を書き換える「否定論」として語られることがほとんどです。本書では、この言葉のネガティブな使い方に問題提起をしたかったんです。欧米言語では「歴史修正(Revision)」と「否定論(Denial)」は、最近明確に使い分けられるようになってきていますが、日本語では一緒くたにされてしまっている。この現状を変えられたらと、タイトルに入れました。
ーー本来の「歴史修正」には、もっとポジティブな意味もあるんですね。
小森:そうですね。本来の歴史修正は、これまで白人男性や勝者といった特定の視点に偏っていた歴史を、より包摂的に、例えば女性やLGBTQ、黒人、先住民といった、歴史の表舞台から見過ごされてきた人々の目線から書き直していく作業を含みます。ミュージアムに限らず、たとえば映画の西部劇では、これまで白人中心主義的でマッチョに描かれてきた世界観をニュートラルに描き直す例があります。ジョン・ウェイン主演の『勇気ある追跡』をコーエン兄弟が『トゥルー・グリット』で女性主人公中心の視座から、原作小説に近いものに作り直しています。こうしたジャンルを映画批評では「リビジョニスト・ウエスタン」といいます。(参考文献:小森真樹『楽しい政治』講談社選書メチエに解説あり)
ーー小森さんが訪れた中には「否定論」を唱えるミュージアムも?
小森:そう、残念ながらあります。近年ではキリスト教福音派の人たちが聖書に基づいた世界観で歴史を書き換えようとしていて、しかもその影響力がとても強く、そのおかげでビッグビジネスをつかみ取るミュージアムも増えています。ただ、読者には歴史修正のポジティブな面に目を向けて欲しかったので、本書にはそういった博物館はあえて入れず、その対極にある誠実なアップデートを試みているミュージアムについてまとめました。
ミュージアムにおける「脱植民地化」
ーーそもそも、ミュージアムにおけるキュレーションの役割とはなんでしょうか。
小森:私が考えるキュレーションとは、モノを用いて物語を紡ぎ、それを市民に語る行為です。ミュージアムは単に物を並べる場所ではなく、国民国家体制の発展とともに、ときにプロパガンダに利用されながらも、「国家とは何か」という物語を語ることで人々を「国民」としてまとめ上げる機関としてその役割を果たしてきました。
キュレーションの重要性は、同じモノを使用した展示であっても、見せ方次第で語られる意味が大きく変わる点にあります。たとえば、この容れ物は私がアラブ首長国連邦のシャルジャで購入したものですが、デザインの展示に置かれればデザイン史の文脈で語られるでしょうし、アート作品や歴史資料として展示されれば、まったく別の意味が付与されるでしょう。展示の枠組みが変わるだけで、同じモノが語る物語は180度変わります。展示に物語を与え、それを社会と共有していくことこそが、キュレーションの役割なのです。
美術館における歴史修正の問題を考えるうえで象徴的なのが、本書でも紹介しているフィラデルフィア美術館のアメリカ芸術セクションの展示組み替えです。かつては白人、男性、健常者といった強者の活躍を英雄的に称える展示が中心でしたが、近年のリニューアルによって、先住民の視点や奴隷たちの存在が前景化されるようになりました。これは、キュレーションを通じて、国家や歴史の物語そのものが修正されている一例だと言えるでしょう。
ーーしかもフィラデルフィア美術館は、展示を完全に入れ替えるのではなく、リニューアル以前から置いていたものを配置換えして歴史修正を試みているそうですね。
小森:そうなんです。例えば、ジョージ・ワシントンの肖像画のすぐ隣に、それまでは影に隠れがちだった妻のマーサ・ワシントンの肖像画を並べたり。あるいは、建国当時に実は存在していたアラブ系の人々と大統領との意外な関わりを強調したり。こうすることで、白人男性中心のアメリカ建国物語が、多層的な人々の歴史へと修正され、それを絵画や彫刻などの芸術作品を通して視覚的に伝えることができるわけです。こういったミュージアムの「脱植民地化」は、ここ10年ほどミュージアムの世界で進行している新しい動きです。
エンタメ大国アメリカのキュレーション術
ーー米国建国の地、フィラデルフィアの美術館ならではのキュレーションですね。
小森:そうですね。フィラデルフィアには他にも「合衆国憲法センター」というミュージアムがあり、ここは憲法の歴史を扱いながらも“超”がつくほどのエンターテインメント施設になっています。一見退屈そうなテーマですが、そこでの体験は驚くほどスペクタクルで、なんと入って最初に見られるものが演劇なんです。プロジェクションマッピングや舞台美術、音響を駆使した円形劇場で、プロの役者が「We the People」つまり「私たち」人民が主体なんだという憲法の精神を観客一人ひとりに直接語りかけるように、条文を引用しながら情熱的に演じるんです。子供たちにも伝わる見せ方で、修学旅行生もたくさん訪れています。ほかにも模擬投票や宣誓といった体験型の展示があり、一番最後に本物の歴史資料が置いてある。本当に見せ方が上手いです。アメリカのミュージアムは国民にとってエンタメコンテンツであり、人々の生活にも近く、いかに楽しんでもらうかという戦略が極めて洗練されています。
合衆国憲法センターのキュレーションにはテーマパークの制作チームが関わっています。最初に動画などを用いて、強い印象を残す視覚的な体験をさせるというテーマパークで典型的に採られる手法が、アメリカのミュージアムにはどんどん投入されています。
ミュージアムグッズで歴史を学ぶ
ーーミュージアムを楽しい場所として提示する工夫は、キュレーション以外にもあるのでしょうか。
小森:ひとつ挙げるなら、ミュージアムグッズもそうでしょう。これは私がベルリンのDDRミュージアム(東ドイツ博物館)を訪れたときに買った、かつて東ドイツの家庭で使われていた卵置きです。私は薬入れに使っていますが(笑)。ミュージアム側はこのグッズを旧東ドイツの歴史を伝えるためだけでなく、ポップなお土産品としても売っていたはずで、訪れた人もなんとなくレトロで可愛いから買っていく。これもまた歴史を語ることだと思うんです。あらゆる娯楽には、歴史を語る要素があります。近年の歴史学では、こうした歴史を語る対象を拡大する視座を「パブリック・ヒストリー(公共史)」と呼んでいます。
オランダのアムステルダム国立美術館の例を挙げてみましょう。1906年ごろ、シモン・マリスが黒人少女を描いた絵画《イサベラ》を展示しながら、その作品をプリントしたトートバッグを公式グッズに採用しています。バッグの裏にこの少女の名がプリントされていることは注目に値します。これは、絵画に描かれた女性を「黒人」や「女性」といった属性ではなく、“個”として扱うというミュージアムの姿勢を強調しているのです。この展覧会に際して、これまで知られていた名ではなく実際には「イサベラ」だったことが判明したというエピソードがつけられてもいます。
「部族美術」というカテゴリーが芸術品にはあります。西洋の近代以降に描かれた肖像画には、作者や描かれた人物の個人名が記録されているケースが大半ですが、アフリカの仮面などは誰が作ったものなのかは載せられず、何族だとか、ひどいときは地名だけが記されるといった非対称性がありました。こういったグッズは、そうした流れに対するアンチテーゼと読解することが可能です。
ーー欧米以外のミュージアムの取り組みについてもお伺いしたいです。
小森:国立台湾歴史博物館では、日本による植民地時代の展示があります。日本軍がどのように台湾を統治していたのかについて等身大人形を使って説明しており、一見生々しい展示ですが、現地の観光客の中には人形の横で楽しそうに記念撮影をしている人が意外と多いことに驚かされました。こういった楽しい体験を提供することは歴史否定論ではなく、誠実な歴史修正の一つの手法と言えると思います。
そこでは公式グッズとして日本の植民地時代に作られていたバッグが売られていて、レトロで可愛いので私も自省心を感じながら購入しました。歴史を忘れないため、歴史を語り継ぐためには、こういったエンターテインメント性も有効だと考えさせられた事例です。ミュージアムを訪れた人に、いかに「自分事」として展示が語る歴史を持ち帰ってもらうか。日本のミュージアムも見習うべき点が多いと感じます。
スミソニアン博物館への権力の介入
ーー最後にアメリカの現状について教えてください。今、北米のミュージアムは、現在進行形で悪い方向に修正されている印象があります。現場の空気はいかがでしょうか。
小森:まさに激動の最中です。私はアメリカ研究者として、フィールドワーカーの立場から、保守派、最近では「MAGA派」と呼ばれる人たちを追いかけてきました。トランプ集会にも通い、彼らが何を「正しい歴史」だと考えているのかを聞いてきたのですが、ミュージアムは今、文化戦争の最前線に置かれています。
日本のみなさんもご存知だと思いますが、第2次トランプ政権以降、大統領令によって文化全般への介入が急速に進みました。地名の改称や記念物の扱いなどは、支持層への分かりやすいパフォーマンスです。「ウォークな(意識高い系。リベラル派への蔑称となっている)」文化を解体するという名目で、ミュージアムも標的になっています。
ーー特にスミソニアン博物館が「反アメリカ的」だとして攻撃されていますよね。
小森:そうですね。スミソニアンの場合、理事会には副大統領のヴァンスや議員が関わるため、強い圧力がかかっている。展示内容に対しては、「ここが反アメリカ的ではないか」と検討を求める形で修正を迫る。形式上は穏やかですが、実のところ、短期間で膨大な箇所を直せという無理難題を押しつける脅迫的な方法です。
象徴的なのが、「初期大統領が奴隷を所有していた」という展示すら反アメリカ的とされる点です。現政権が用いるのは、栄光の歴史だけを語る方が社会の分断を煽らない、というロジックですね。反対側から見れば歴史否定ですが、分極化が進んだ社会では、支持者には筋が通って見えてしまう。
実害はほかにも出ています。私はスミソニアンが管理している国立肖像画美術館にトランプ大統領の就任式当日に訪れたのですが、トランプの肖像画のキャプションには「重罪で訴追されているが、大統領であるため免責されている」と書かれていました。これは歴史的事実です。その後、館長は退任に追い込まれています。アフリカ系アメリカ人のミュージアムでもこれに近い退任劇が起きていますし、ブラック・ライヴズ・マター以降に進んだ女性史博物館やLGBTQ関連のミュージアムの構想も凍結され、進歩的なテーマの特別展は次々と中止になっています。
さらに厄介なのは、ホワイトハウスが「リベラルこそが歴史修正をしている」と、逆に歴史修正という言葉で攻撃している点です。名前を変える、歴史を多声化する――現象としては同じ「書き換え」に見える部分もある。でも、誰が何を不可視化するために行っているのか、その政治的意図を見ないと状況を誤読してしまうでしょう。
私は研究者として、展示パネルをできる限り記録しています。写真が撮れない場合は全文をタイピングすることもあります。文化戦争の中では、いつ展示が変わるかわからない。ミュージアムは今、最も生々しく歴史語りが更新される場所だからです。
2026年はフィラデルフィアに注目
ーーその「不誠実な歴史修正」を象徴する例として、本書には映画ロッキーの彫像の話が出てきますね。
小森:ロッキー像は、政治・文化・ビジネスが絡み合う象徴です。この映画の制作者で主演のシルベスター・スタローンがトランプを称賛していますが、それにはビジネスとして近づいている側面もあるでしょうが、他方で文化的に見れば、このポピュリストの大統領を「ロッキー的存在」、つまり市井の人々の方を向いた反エリート的存在として見ているからでしょう。スタローン自身が述べているように、ディケンズ的な英雄像ですね。
フィラデルフィア美術館前のロッキー像は、かつては低俗な映画の大道具としてミュージアム側から設置を拒否されていました。それが長い時間をかけて受け入れられ、街の象徴となり、今では公式グッズまで作られるようになりました。ミュージアムグッズは、いわば態度表明です。何を街や美術館の顔として差し出すのか、その選択が可視化される。最近ではフィラデルフィア国際空港にも新しいロッキー像が設置されました。街の玄関口でロッキーが迎えるーーこれは単なる観光ではなく、「私たちはロッキーの街だ」という国際的な自己表象です。
ここで重要なのが『ロッキー』が公開された1976年という年です。『ロッキー』はこのアメリカ建国200周年の年に公開され、白人アンダードッグ(負け犬)の復活が、ベトナム戦争後の黄昏れたアメリカを再生する物語と重ねられました。旧都フィラデルフィアという象徴的な街で、その物語は国家神話になったのです。そしていよいよ2026年は、アメリカ建国250周年で全米がナショナリズム、愛国主義の祭りに沸くことになります。ロッキーが再び前景化しているのは偶然とは言えません。
もちろん街が盛り上がること自体は悪いことではないと思います。ただ、スポーツや映画が生む昂揚感が、現実の構造について深く考えなくていい一体感や過剰な愛国心に接続されることには危険が潜んでいます。2025年のスーパーボウルでは、フィラデルフィア・イーグルスの優勝時に暴動が起き、死者も出ました。写真一枚で見れば楽しそうであっても、現場ではときにこうした暴力が噴き出す瞬間があることを忘れてはいけません。
ミュージアムの展示も、街の像も、どちらも公共の「物語」を通じて人を動かす。だからこそ、今何が語られ、何が消されているのかを見る必要があるのです。アメリカの現在は、こうした歴史修正の緊張のただ中にあります。2026年は、フィラデルフィアに注目しています。





























