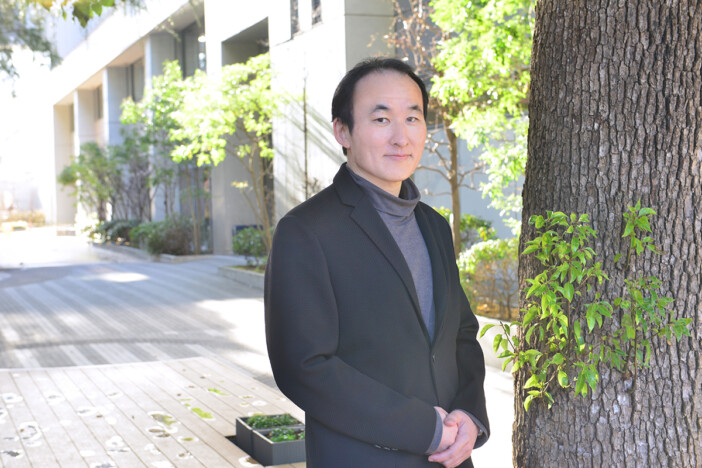『さよならドビュッシー』から『とどけチャイコフスキー』へーー中山七里が語る、唯一無二の“音楽ミステリー”執筆の背景

天才ピアニスト・岬洋介の周囲で巻き起こる事件を解決する異色の人気ミステリー小説である岬洋介シリーズの最新作で、第10作となる『とどけチャイコフスキー』(宝島社刊)が刊行された。モスクワ音楽院で起きた学部長殺人事件の顛末と、ロシア人ピアニスト・ヴァレリーの苦悩を描いた物語だ。
岬洋介という魅力的な“探偵”によって導かれる驚きの真実。チャイコフスキーのピアノ協奏曲の調べとともに語られる複雑な感情のドラマと、音楽が持つ力への祈りにも似た希望――「音楽ミステリー」と称されるその独特な世界について、作者である中山七里に語ってもらった。
岬洋介の出生秘話は第1作目から決めていた

――最新作『とどけチャイコフスキー』はロシアとウクライナの関係が物語の背景になっていて、さらに岬洋介の出生も明かされています。このタイミングで描いた理由を聞いた。
中山:シリーズ3作目の『いつまでもショパン』ではショパンコンクールのファイナリストとして、ポーランド、日本、中国、フランス、アメリカ、ロシアと6カ国のピアニストを揃えました。それはいずれそれぞれの国で1話ずつ書くための布石だったんです。前作『いまこそガーシュイン』はアメリカだったから、次はロシアかなと題材を選びました。
岬洋介がロシアの血を引くクオーターという設定も、実は第1作を書いた時から決めていました。これまでは「瞳が鳶色」とそれとなく匂わせるだけでしたが、ちょうど10作目ということもあり、彼の出生にもまつわるロシアを題材にしよう……と構想した瞬間に、クリミア半島併合からのウクライナ侵攻が始まったんです。
――期せずして切実な社会情勢が反映されることになったわけですね。
中山:ロシアを代表する作曲家・チャイコフスキーが、実はウクライナに思慕を傾けていたという事実は、以前から知っていました。それから、オリンピックのドーピング問題によってロシア国歌が使用できないとき、選手の表彰式に使われたのがチャイコフスキーの『ピアノ協奏曲第1番』です。実はこの曲もウクライナにルーツがあります(※主要なメロディーがウクライナ民謡のリズムを基にしている)。その件も大変象徴的だと感じました。
曲に固有の存在意義をいかに説得力のある形で物語のなかに盛り込んでいくかが、僕の腕の見せ所だと思っています。わざわざタイトルに作曲家の名前を入れているのはそういう理由です。
――「音楽を通して描かれる物語」について、どんな構想があるのでしょうか。
中山:音楽は他の要素を融合しやすい。『とどけチャイコフスキー』は音楽と戦争です。音楽と政治、音楽と文学、音楽とスポーツ、音楽とLGBT。そんな風に何かのテーマと音楽というのは差し込みやすく、話が成立しやすくなります。
――岬洋介というキャラクターは、どのように設定されているのですか。
中山:岬洋介は主人公のように思われますが、狂言回しでしかない。彼のような一種のスーパーマンが主人公になると葛藤が生まれないので、むしろ周囲にいる人間を主人公にしたほうが話を作りやすい。そういう意味で僕の小説の主人公は必ずみんな、何かが欠けている。だから話が作りやすくてシリーズも長く続けられるし、読者にとっても読みやすいと思います。
――“狂言回し”としての岬洋介というキャラクターは、どのように生まれたのでしょうか。
中山:岬洋介は、第1作『さよならドビュッシー』の主人公であるすべてを失った女の子のサポート役兼教育係として初登場しました。そういうキャラクターは非の打ち所がないほうが話を進めやすいのです。
主人公だけで例えば岬洋介にも何らかの短所を背負わせてしまうと、読者が両方に感情移入してドラマが二重になってしまう。それはそれで面白いこともあるけれど、話が複雑で少し読みにくくなってしまう。だから『さよならドビュッシー』で岬洋介は絶対に安心できるサポート役に徹しようと思いました。
それに、サスペンスに限らず物語が緊張する場面ばかりだと、読者は疲れてしまう。だからどこかで空気を緩めないといけない。その際に緩急が付けられる安心感あるキャラクターがいることは大事です。岬洋介シリーズに限らず、僕の作品では必ずそういう存在がいるはずです。
――岬洋介は天才的ピアニストでありつつ誰からも好感を持たれる人物です。
中山:つまり大谷翔平です(笑)。ただし、本当に完全無欠だと小説の登場人物としては面白味がないので、ウィークポイントを設定しています。ですがとにかく音楽に関しては飛び抜けていて、人柄も魅力的。そういうキャラクターが作れたのは、我ながら良かったなと思っています。
音楽と政治、音楽と文学…要素を融合すると物語が生まれる
――そんな岬洋介を15年間描き続けて、変化や成長した部分はありますか?
中山:どんどん金田一耕助のようになっています(笑)。つまり、起きてしまった事件を解決し、みんなの心を解きほぐす。横溝正史が好きなので、書いているうちに自然とそうなってしまうのかもしれない。ただ、“名探偵”というものは、みんな金田一耕助になっていく気がします。
――岬洋介自身は何かに悩むわけではない。もしくは、悩んでいるのかもしれないけれどそれは描写されていません。
中山:「名探偵が悩む」というモチーフは80~90年代にピークを迎えているんです。ミステリーの世界でいわゆる「新本格派」と呼ばれる作家たちが、主人公である名探偵自身が「俺は何のためにここにいるのか」といった事柄で悩む物語に取り組みました。そういうテーマはその時代に突き詰められたので、令和の時代に自分がわざわざ書かなくてもいいだろうという思いもあります。
――岬洋介シリーズの特徴である「音楽を通して描かれる物語」についてどんな構想があるのでしょうか。
中山:シリーズ1作目の『さよならドビュッシー』も最終的にはサスペンスになりますが、そこに音楽を挟むことで新機軸を作れるのではないかという目論見が最初からありましたから。「音楽ミステリー」という自分なりのスタイルを確立できたことは運が良かったなと。
――音楽の「希望」と「限界」の両面をしっかりと見据えた語り口も印象的です。
中山:「音楽は地球を救う」時代はもう過ぎてしまったと感じる方もいるかもしれません。「音楽には国境がない」という言い方も実はちょっと正確ではなくて、その国、その土地、その民族、その時間でないと成立しない音楽というのは確かにある。
ただその一方で、音楽はやはり人の垣根、民族の垣根、宗教の垣根、思想の垣根を跳び越えられるものだということを信じたい。音楽の力を信じ、希望と限界のギリギリを突き詰めて、そこに曲や演奏の描写を重ね合わせることでリアルな物語を書ければと思っています。
――本作のクライマックスであるヴァレリー指揮、岬洋介のピアノによる『ピアノ協奏曲第1番』の演奏。その全曲を描写する緻密でエモーショナルな文章は読み応えがありました。
中山:今となっては、僕の専売特許かなと思います(笑)。だって、どんなに音楽が好きだって協奏曲をまるまる1曲、文章で描写しようとは思わないですよね。実際、音楽を描写するのはとても大変ですし。これは初めてお話しますが、演奏シーンを書くときは、普通の地の文の2倍の時間がかかります。でもそうすることで、ある種の感動が生まれることは、実験でわかっています。
――実験ですか?
中山:『さよならドビュッシー』からの実験です。何か音楽を聴いた時に頭の中でイメージされることは誰でもあると思うんです。感情だったり、情景だったり。
それをトレースしながら、なおかつ実際に奏でられている音や繰り出されている演奏者のテクニックの描写をクロスさせることで、実際に音楽が奏でられているかのような効果を文章で生み出すことができるのではないかと。そう考えて実験したらうまくいった。それをシリーズ10作にわたって続けています。
“ミステリー小説”であることを忘れさせる仕掛け
――確かに演奏シーンを読んでいると曲が聞こえてくるような感覚があります。同時に文章だからこその感情や情景も伝わってくるという、独特な読書体験でした。演奏シーンを書く際に心がけていることはありますか。
中山:これはもうデビュー時から実践していることですが、「説明するな、描写しろ」ということにつきます。「説明っぽいな」と感じる小説はどうしても読みにくい。では、もっとも描写するのが難しく、しかし描写できたら非常に効果的なものは何かと言えば、五感に訴えるものです。
五感の中で、音楽の描写だったら書けるかもしれないと思ったんですね。自分の文章は音を描写することに向いていたのかもしれませんね。
――ミステリー小説であることを忘れ、音楽家の物語にのめり込むように読んでいました。ある瞬間にミステリーに引き戻される。そのギャップに驚きます。
中山:シリーズの最初から狙っていました。岬洋介シリーズは「音楽ミステリー」と言いつつ大がかりなトリックは使っていないんです。その分、読者の意識を他のテーマに持っていくように意識しています。違うジャンルの小説を読んでいたら、ある瞬間に突然ミステリーになったというほうが驚いてもらえるし、一粒で二度美味しいお得感があると思います。
7作目『合唱 岬洋介の帰還』だけは音楽を扱っていないのですが、それを除けばシリーズすべて同じ構成になっています。それがある程度、読者にも受け入れられたから10作目まで続けてこられたのかなと。
岬洋介シリーズは、ミステリーを入り口にして音楽を信じる力を楽しんでもらいたい。それはもうデビュー作の時から変わりません。
――岬洋介シリーズの次回作はどうなるのでしょうか?
中山:今は岬洋介シリーズと併行していた『カエル男シリーズ』が完結して、それに代わるシリーズを考えています。(同席した担当編集さんに)新しいシリーズの題名、言ってもいいですか? いいですよね? 『殺人鬼探偵』というタイトルで、いわゆる「レクターもの」です。
――『羊たちの沈黙』に登場するハンニバル・レクター博士のような異常犯罪者が探偵役となるスタイルのミステリーですね。
中山:それを日本を舞台に書いたらどうなるか、と。レクターの名前を出すまでもなく、犯罪者や主人公が探偵のマネをするという作品はたくさん書かれていて、ひとつの定番ジャンルです。どう料理するかは物書きの腕の見せ所なので、それに挑んでいるところです。
■書誌情報
『とどけチャイコフスキー』
著者:中山七里
価格:1,870円
発売日:2025年11月7日
出版社:宝島社






![[Alexandros]川上洋平、2ndエッセイは過去最高の「さらけ出し」 発売迎え「とてもすっきり」](/wp-content/uploads/2025/12/20251226-kawakami-01-702x468.jpg)