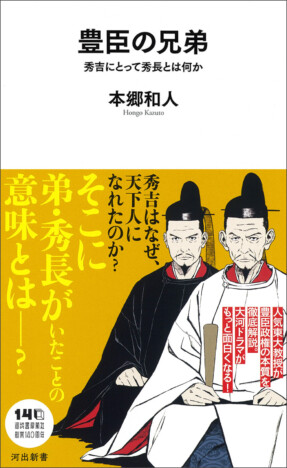『豊臣兄弟!』豊臣秀長という「最強のNo.2」が現代に響くワケ 堺屋太一、司馬遼太郎らが綴った補佐役の真髄

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』がついに幕を開けた。1月7日の第1回「二匹の猿」の放送直後、SNS上には「仲野太賀にぴったり過ぎる」「バイトリーダー並みの調整力」といった称賛の声が溢れ、早くも大きな反響を呼んでいる。
物語は、村の揉め事をニコニコと収め、野盗の襲撃という非常事態にも冷静に対処する弟・小一郎(後の豊臣秀長/仲野太賀)の姿から始まった。現場の混乱を的確にさばくその手腕は、まさに現代の「有能な現場責任者」を彷彿とさせるものだ。そこに8年ぶりに帰還した野心家の兄・藤吉郎(後の豊臣秀吉/池松壮亮)が加わることで、平和主義者だった小一郎の運命は激しく動き出したのである。
戦国時代という弱肉強食の極致において、天下人・秀吉の影に隠れながらも、現代のビジネスパーソンから支持を集めているのが秀長という男だ。なぜ秀長が組織を支える補佐役たちのバイブルとなるのか。その歩みを振り返ると、数々の文学作品や漫画、映像作品が、時代ごとに異なる「No.2の美学」を彼に託してきた事実が浮かび上がる。
秀長が「有能な補佐役」として広く再発見された最大の契機は、作家・堺屋太一による小説『豊臣秀長 ある補佐役の生涯』だろう。通産省出身の官僚でもあった堺屋は、秀長の事績を現代の組織論に置き換えた。秀吉という「天才だが暴走しやすいカリスマ」の夢を、現実の予算、兵站、外交交渉へと落とし込む最高執行責任者(COO)としての側面を鮮やかに定義したのだ。この作品によって、単なる「兄思いの弟」だった秀長像は、実務によって勝利を確定させるビジネスヒーローへとアップデートされるに至った。
一方で、歴史小説の巨星・司馬遼太郎は、短編集『豊臣家の人々』収録の「大和大納言」において、より多角的で冷徹な「防波堤」としての秀長を描き出している。司馬作品における秀長は、急激に膨張しすぎた豊臣家というベンチャー企業の歪みを一身に引き受け、ガバナンスを維持する最後の要であった。司馬が名著『新史太閤記』や『関ヶ原』の伏線としても機能させた「秀長の死」という転換点は、その後の豊臣家が千利休の切腹や朝鮮出兵という破滅へと突き進む契機となり、組織におけるNo.2の不在がいかに致命的かを逆説的に証明したといえる。
映像や漫画の世界に目を向ければ、1981年の大河ドラマ『おんな太閤記』で中村雅俊が見せた包容力や、1996年の『秀吉』で高嶋政伸が演じた献身的な「小一郎」像が、お茶の間に「理想の弟」としての印象を強く植え付けてきた。こうした解釈は、2023年の大河ドラマ『どうする家康』で佐藤隆太が見せた、秀吉(演:ムロツヨシ)の狂気を飼い慣らせる唯一のストッパーとしての身体性にも通じている。
また、石井あゆみによる人気漫画『信長協奏曲』においても、秀長は極めて個性的かつ重要な役割を担っている。本作での彼は秀吉の副官として遠征に同行し、口が軽い一面を見せつつも巧みなフォローで周囲を支える存在だ。しかしその本質は「重度のブラコン」であり、兄に殺されるのも本望としているような危うい献身を見せる。敬愛する秀吉の陰謀にも喜んで協力するが、兄が腹黒い本性を現した発言をしたときなどは「……」と黙り込むなど、何を考えているのかよくわからない面も併せ持つ。
さらに、宮下英樹の漫画「センゴク」シリーズでは、軍事、外交両面で秀吉を支える副官として描かれ、四国征伐の際は出陣を取りやめた秀吉の名代として四国征伐軍の総大将を務めるなど、「将」としての活躍も見せている。
『豊臣兄弟!』では初回から秀長の「調整役」としての資質が表現されていた。仲野が挑むのは、堺屋や司馬が愛した「最強のNo.2」という系譜に、彼自身の持ち味である「泥臭い人間味」を融合させる作業になるだろう。また、脚本を担当する八津弘幸氏は、これまでにドラマ『半沢直樹』(TBS系)などの企業ドラマを手がけてきたヒットメーカーだ。八津氏は秀長と秀吉の関係を固い絆で結ばれた兄弟愛として描くと同時に、史実をビジネスエンターテインメントとしても鮮やかにアレンジしてくれることだろう。
誰もがトップランナーになれるわけではない世において、誰かを支え、調整し、組織を完遂させる秀長の生き様は、働く人たちが職場で直面する役割と地続きだ。池松とのバディを通じて、戦国史上最高の補佐役がどう再起動するのか。初回の世帯平均視聴率は13.5%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)と滑り出しは上々。月曜日からまた戦場(職場)へ向かう人たちの背中を、力強く押してくれるような一作となりそうだ。