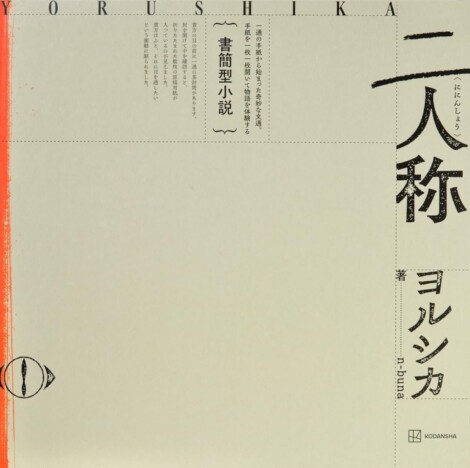【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第14回:私を運営する私――キュレーション・推し・身体

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。
第14回では、21世紀の情報環境において人々がどのようにアイデンティティを構築するのかを整理し、その中で「推し」とはどのような行為なのかを解説。また、そのような行為で重度な依存症や中毒の沼にハマってしまう状況を改善するための方法を示す。
第1回:21世紀の美学に向けて
第2回:探索する脳のミメーシス
第3回:アウラは二度消える
第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去
第5回:電気の思想――マクルーハンからクリストファー・ノーランへ
第6回:鏡の世紀――テクノ・ユートピアニズム再考
第7回:21世紀の起源――人間がメディアである
第8回:モデル対シミュレーション
第9回:パラ知能としての生成AI――あるいは言語ゲームの多様性
第10回:マルクスとAI
第11回:戦争の承認、承認の戦争
第12回:ポストトゥルースから物語中毒へ
第13回:心的なワークスペースとしての小説
1、一元論の世紀の人間観
21世紀を特徴づけるのは、社会を模倣した「ソーシャル」が、さらには人間そのものがメディアになるという事態である(第7回参照)。ここに次の論点を付け加えよう――すなわち、この人間とメディアの共生において、「私」こそが、情報に対して感度の良いメディアになるように訓練される。なぜなら、ソーシャルメディアが実体的な力をもつには、個々の「私」のアカウントが、情報のフィードバック・ループの拠点として実効的に機能する必要があるからだ。

この≪メディア化した私≫を育てる土壌となったのは、サイバネティクスの思想である。哲学者のユク・ホイは「21世紀はサイバネティクスの世紀である」と宣言しながら、サイバネティクスが「機械的なもの」と「有機的なもの」を融合させ、情報一元論を確立したと論じている。従来の機械が有機体(自然)と二元論的に対立するのと違って、サイバネティクス機械はむしろ有機体をモデルにしながら、再帰的なフィードバックを動力とする一元論的なネットワークを作り出した。その結果、動物が自然環境とのコミュニケーションのなかで生存するように、インターネットの「私」も擬似的な自然環境――落合陽一の言う「デジタル・ネイチャー」――とのコミュニケーションのなかで自己像を輪郭づけるように誘導される。ホイが指摘するように、それは一元論が二元論を凌駕したことを意味するだろう(※1)。
思えば、自然と文化の二元論に根ざしたヨーロッパの近代思想は、ゲーテの『ファウスト』を典型として、自然を克服し征服しようと遮二無二前進したあげくに、限界に直面する人間を象ってきた。長い冒険の最後に視力を失うファウストは、まさに近代の「悲劇的」な英雄にほかならない。それに対して、21世紀の「私」はもはやファウスト的な悲劇性をもたない。今や「私」は環境と二元論的に敵対するドラマティックな英雄ではなく、むしろ環境から学習する柔軟なサイバネティクス機械に近づいた。「ミラーワールド」のような21世紀のテクノユートピアニズムも含めて(第6回参照)、今日の情報社会では一元論的なイデオロギーの優位が鮮明になっているのだ。
※1 Yuk Hui, “Machine and Ecology”, in Hui ed., Cybernetics for the 21st Century Vol.1, Hanart Press, 2024, p.50.ホイによれば、すべてを情報技術によって統合しようとする一元論こそが「われわれの時代の危機の源泉」であり、従来の二元論批判は意味をなさない。ブルーノ・ラトゥールを筆頭とする近年の一元論的なエコロジー思想を批判し、むしろ二元論を方法論的に保持せよと説く斎藤幸平『マルクス解体』(講談社、2023年)も、ホイの主張と関連するだろう。今は情報一元論の夢よりも、二元論の正しいアップデートが必要なのである。
2、「私というメディア」を運営する私
21世紀の人間は、自らの役割をドラマではなくメディアのなかに探し求める。つまり、環境に打ち勝とうとして失敗する悲劇の英雄ではなく、むしろ環境と共生する≪メディア化した私≫が人間像の中枢を占める。そのとき、「私」は無数の情報=商品が通過する中継点として現れてくるだろう。
要するに、私はいわば「私というメディア」の運営者となる――この現象の背景に、社会構造の変化があることも見逃せない。近代の産業社会では、総じて「標準化」の圧力が強かった。工場や軍隊、学校は人間を鋳型にはめて、合理的に行動できるような訓練を施してきた。そこでは、不揃いな個別性よりも、むしろマニュアルに沿って斉一的に動作する均質性が重視される。マックス・ヴェーバーが「鉄の檻」と呼んだこのシステムは、まさにその強い合理性の要求ゆえに個人を窒息させかねない。ただ、産業社会の生産システムを円滑に動かすには、このような標準化・規格化の手続きが欠かせなかったのだ。
しかし、1970年代以降のポスト産業社会、さらにはポストモダンな情報化社会になると、このような標準化の圧力は「個人の自律」を損なう暴力と見なされ始める。この暴力を抑制し、個々人がそれぞれに個別の「善」を自由に構想するように推奨するのがリベラリズムである。リベラリズムは共同体の規範ではなく、個人の自己決定を価値の源泉と見なす。マジョリティの視界からは消えてしまうような、弱いものや小さなもの、はかないものも含めた多様性が尊重されるのは、まさにこのリベラルな脱標準化(=個人化)の要求の帰結である。
それに伴って、たんに形式的な「個別性」を承認されるだけでは飽き足らず、質的な「独自性」(singularity)を望む新しい中産階級が現れるようになった。それは、文化を「他者」としてではなく、むしろ自らの特別な主観を創出するための「素材」として運用するタイプの階層である。
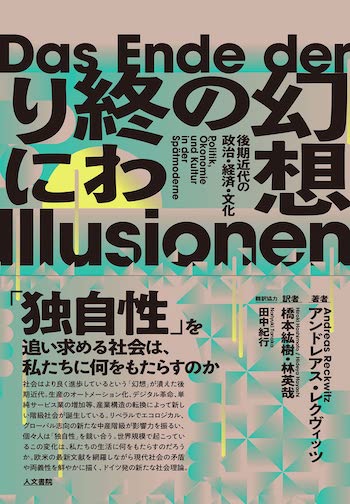
ドイツの社会学者アンドレアス・レクヴィッツが指摘するように、この新しい中産階級は自らの「独自性」を象るのに、文化を「自己研鑽のための財」として利用する。具体的に言えば、読書や料理、旅行、カフェや美術館めぐり、あるいはマインドフルネスやフィットネスなどを自在に組みあわせて、社会的なステータスと自分専用のアイデンティティを創造するというふるまいが一般化するのだ。しかも、その自己研鑽のための財(コンテンツ)はもっぱら無形資本、つまり認知や情報と深く関わっている。そのとき「私」というメディアの運営は、美術館のキュレーターの仕事と似てくるだろう(※2)。なぜなら、キュレーションとはさまざまなコンテンツを再配置しながら、そこに情報的な価値を与える仕事なのだから。
こうして、21世紀の中産階級は国家的なアイデンティティの確認よりも、個人的なライフスタイルを核とする「主観性の文化」(ゲオルグ・ジンメル)に傾倒してゆく。この脱標準化した「私」は自らを鋳型にはめこむのではなく、情報環境とのフィードバックのなかで、人生をたえず「自作自演」するように促される。自分で人生の脚本を書いては、それを修正し、増補し、ケアしながら自己の独自性を演出し続ける≪メディア化した私≫――このキュレーターとしての自己は、再帰的なフィードバックを作動原理とするサイバネティクス機械ともはや見分けがつかない。「21世紀はサイバネティクスの世紀である」というユク・ホイの評言は、あながち極論ではないのだ。
※2 アンドレアス・レクヴィッツ『幻想の終わりに』(橋本紘樹他訳、人文書院、2023年)38、171頁。