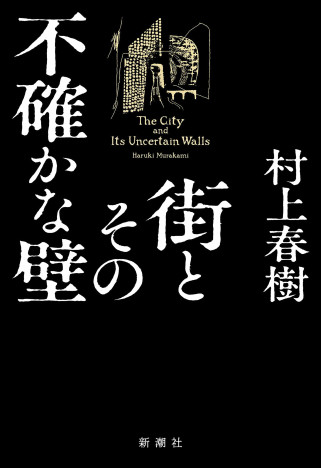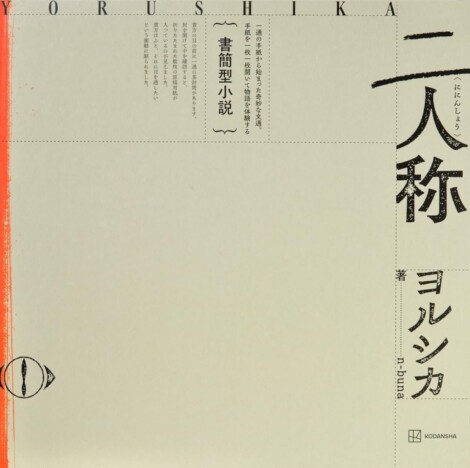【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第3回:アウラは二度消える

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。第3回では、 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの消失」を、スマートフォンの時代に照らし合わせて再考する。
第1回:21世紀の美学に向けて
第2回:探索する脳のミメーシス
1、アウラの二度目の死

ヴァルター・ベンヤミンが1936年の論文「複製技術時代の芸術作品」で「アウラの消失」を問題にしたことは、よく知られている。ベンヤミンによれば、アウラは芸術を享受する際の〈今・ここ〉の一回性と結びつくが、写真やレコード、映画のような複製技術は芸術作品を〈今・ここ〉から引きはがし、市場で流通する商品に変えた。それによって、芸術作品の性格も根本的に変わる。アートの複製が大量に流通するとき、それまでの作品のもっていたかけがえのない神秘性、つまり「礼拝価値」は全面的に清算されることになるだろう。
しかし、今にして思えば、ベンヤミンの見解に反して、レコードや映画にはまだ「アウラ」が残っていたのではないか。レコードは複製物とは言っても、決して均一化されたメディアではない。盤面に傷があったり、ジャケットが破れていたり、汚れや埃で音が飛んだりする――それらすべて含めてレコードの聴取体験なのだとしたら、レコードは複製物でありながら唯一無二性を内包している。レコードをターンテーブルにそっと載せる行為も、それ自体が室内での個人化された「礼拝」や「儀式」に近いだろう。映画館での体験についても似たことが言える。フィルムそのものは複製物だとしても、それを他の観客とともに体験するのは、依然として〈今・ここ〉の一回性を伴った出来事である。
ベンヤミンの時代の複製技術においては、アウラはまだ十分に失われなかったように思える。アウラの真の消失は、むしろ1990年代以降のインターネットとスマートフォンの普及によってもたらされたのではないか。ネットではデータが劣化することなく、大量にコピーされて流通する。ユーザーは面倒な儀式もなく、クリック一つで自由に音楽や映像を再生しては、すぐに別の対象へと気ままに移動する。そこにはいかなる「礼拝価値」も生じない。サブスクリプションが一般化した今、音楽や映画はますます情報のフロー(流れ)のなかに溶け込んでいる。強いて言えば、個々の作品ではなく、このフローそのものが現代の信仰(礼拝)の対象なのである(※1)。
さらに、スマートフォンはこの文化享受の体験を、映画館や自宅のような空間から完全に解放した。レコードや映画館は特定の空間と時間に紐づけられており、だからこそそこには「一回性」のアウラの生じる可能性があった。それに対して、スマートフォンはあらゆる文化を〈いつでも・どこでも〉体験できるという全面的なモビリティに向けて解き放った。〈今・ここ〉の一回性に拘束されないモバイルな文化を指すのに、「芸術」という古語はもはやしっくりこない。アウラの消失に対応するのは、思想や観念の歴史を背負わないコンテンツ(コンテント)という中性的な呼び名である。
要するに、アウラは二度消える――一度目は写真やレコードによって、二度目はスマホによって。この変化は不可逆であり、それを嘆くだけではもはや事態は好転しない。

そもそも、芸術が手軽に複製可能なコンテンツになったことは、一概に悪いことばかりではない。音楽に限っても、誰でも膨大な音源へのアクセスが可能になったことは、音楽史上における画期的な「民主化」と考えてよい。そこでは、古い音楽もただの懐旧ではなく、現役のフレッシュな音楽として聴き直されるチャンスを得るだろう(現に、新旧の音楽がヨーイ・ドンでポストモダン的に並列化されたことを前提に、過去の優れた楽曲や演奏を再評価しようとする機運も生じている(※2))。加えて、音楽が〈今・ここ〉から切り離されたBGMになることは、いつでもどこでも潜在的な音楽教育がなされるようになったことを意味する。実際、かつての閉ざされたサロンやコンサートでの聴取と比べても、BGMによる聴取はジャンル的にもスタイル的にもはるかに豊富で多彩な音楽に耳をなじませるだろう。アウラの消失を代償として、音楽への扉はいたるところに開かれることになった。
その一方、21世紀における≪アウラの二度目の死≫を経て、過剰な流動性への疑念が生じていることも見逃せない。スマホとサブスクリプションが全盛の現代において、かえって不便なレコードが復活したことは不思議ではない。それはまさに、音楽の聴取があまりに手軽で「スマート」になりすぎた時代に、アウラを人為的に回復しようとする試みなのだ。
※1 美術批評家のボリス・グロイスは『流れの中で』(河村彩訳、人文書院、2021年)において、20世紀前半のロシア・アヴァンギャルドをフローの物神化の起源と見なしている。個々の作品は有限で滅びゆくものだとしても、作品の流れは無限というわけだ。この点について、詳しくは拙著『書物というウイルス』(blueprint、2022年)参照。
※2 インターネットの音源をたえず参照しながら、ジャズの「音」を徹底的に解析し「耳」の再教育を試みたマイク・モラスキーの『ジャズピアノ』(上下巻、岩波書店、二〇二三年)は、注目に値する労作である。音楽がありふれたコンテンツになったからこそ、それを聴く「耳」が自覚的に組織されなければならない。
2、「近さ」へのオブセッション
以上を前提にして、再びベンヤミンの議論に戻ろう。ここで重要なのは、ベンヤミンがアウラの概念を説明するのに、「遠さ」をキーワードとして取り上げたことである。「複製技術時代の芸術作品」では、アウラは以下のように定義された。
そもそもアウラとは何か。空間と時間から織りなされた不可思議な織物である。すなわち、どれほど近くにであれ、ある遠さが一回的に現われているものである。夏の午後、静かに憩いながら、地平に連なる山なみを、あるいは憩っている者の上に影を投げかけている木の枝を、目で追うこと――これがこの山々のアウラを、この木の枝を呼吸することである。(※3)

アウラとは、空間的・時間的な「遠さ」を織り込んだ織物である。だが、この神秘的な「遠さ」は、大衆社会では「近さ」への欲望に取って代わられる。ベンヤミンによれば「事物を自分たちに〈より近づけること〉は、現代の大衆の熱烈な関心事」である。複製技術はまさにその関心を増大させた。レコードは自宅に音楽を引き寄せ、繰り返し再生可能なものにし、写真は対象を手元で所有できるようにした。事物をコピーして、できるだけ手元に近づけること――それが一回的な「遠さ」に根ざしたアウラの神秘を消失させる。
要するに、大量の複製物に取り囲まれた大衆社会は「近さ」へのオブセッションを内包している。それを1930年代に鋭く指摘したベンヤミンの議論は、スマートフォンに代表される21世紀のメディア環境にも応用できるだろう。スマホは人間に近い器官、つまり手と一体化した。この物理的な合一を断ち切ることはきわめて難しい。この「近さ」との癒着こそが、21世紀のメディアの核心にある。
思えば、20世紀のメディアは「近さ」への関心と「遠さ」への関心を複雑に交差させてきた。例えば、telephoneやtelevisionという装置の名称は、テクノロジーの再構成した音や映像が、tele(遠隔性)を内包していることを隠さずに示している。しかも、電話の通話を典型として、その遠くから届く情報が、目や耳の近くでしばしば異様に生々しく響くというのが、テレコミュニケーション特有の逆説であった(電話の声がしばしば肉声以上に蠱惑的なのはなぜか?)。コロナ禍を経て一挙に普及したテレワークにも、それと同じ両義性が認められる――仕事場の「遠さ」は、在宅勤務の「近さ」と裏腹の関係にあるのだから。
こうして、テレコミュニケーションは遠さと近さの尺度そのものを攪乱する。それはいつの時代でも変わらないが(文字メディアはすでに空間的・時間的な遠隔性を手元性に変換した)、20世紀はこの攪乱が特に目立った時代であった。というのも、20世紀のエレクトロニクスは、コミュニケーションのネットワークを人類史上で前例のない規模にまで拡大したからである。その結果、何が自分に近くて何が遠いのかという人間の心象地理の感覚は、たえず揺るがされることになった。
それは21世紀のメディアにおいても本質的には変わらない――見ず知らずの人間のSNSの書き込みを信じてしまうとき、遠さは近さに反転しているのだから。ただ、21世紀の情報社会は、このテレコミュニケーションの逆説をそれと気づかせない。その代わりに、immersion(没入)を謳い文句とする娯楽産業からメタバースに到るまで、企業は「事物を人間により近づける」というミッションをいっそう加速させた。これはたんなるテクノロジーの問題ではなく、明らかにイデオロギーの問題である。マーク・ザッカーバーグ率いるメタを筆頭として、現代の娯楽・情報産業は仮想世界への没入に、ほとんど宗教的な価値を与えてきた。彼らはまさに没入に没入しているのだ。
※3 「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション1』(浅井健二郎編訳、ちくま学芸文庫、1995年)592頁。