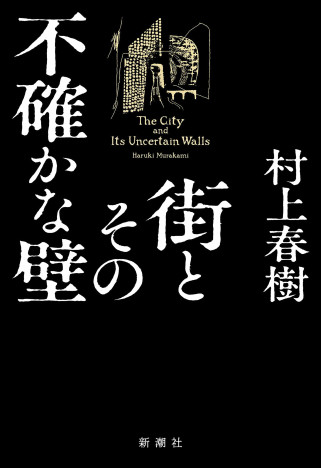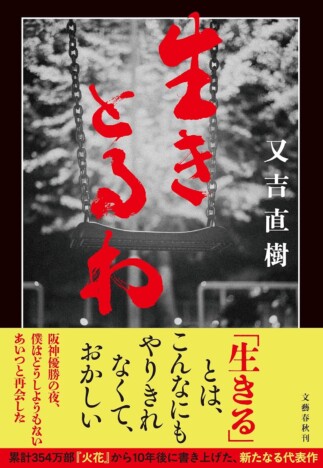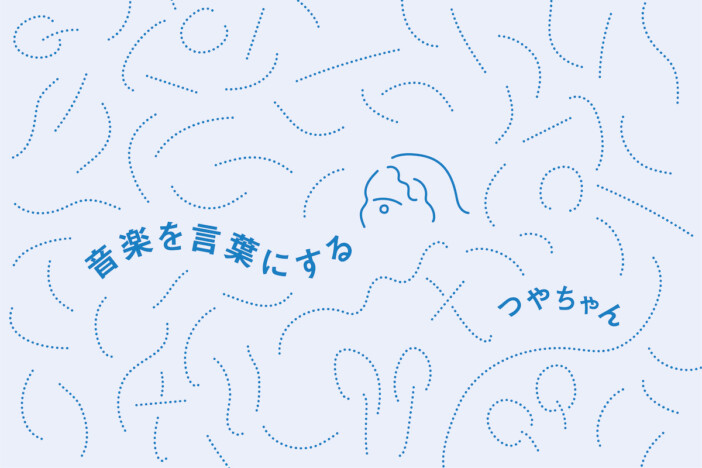【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。第4回では、20世紀のモダニズム理論を改めて振り返るとともに、コンピュータやインターネットの登場以降、どのような美学が生じうるのかを考える。
第1回:21世紀の美学に向けて
第2回:探索する脳のミメーシス
第3回:アウラは二度消える
1、モダニズム――超人間的なエイリアンの探索
芸術の本質とは何か? 20世紀のモダニズム理論は、この問いの鍵を「メディウム・スペシフィシティ」に見出した。アメリカの美術批評家クレメント・グリーンバーグは、芸術の母胎となるメディウムに固有の特性(specificity)を探索し、それを批判=吟味することを、モダニズムの核心とした。グリーンバーグの考えでは、絵画のメディウムは音楽とも文学とも建築とも異なる特異性、すなわち「平面性」を備えている。モダニズム芸術とはこの特異なメディウムを際立たせ、純粋化し、そこに自律性を与えるプロジェクトとして位置づけられる。
この「メディウム・スペシフィシティの探究」というモダニズムの理論的指針には、超人間性への志向が隠れている。例えば、映画をエイリアン的な機械と見なす濱口竜介の議論(第1回参照)も、広く言えばモダニズムの系統に属する。濱口によれば、映画の「機械の眼」の捉える運動はきわめて特異なので、人間の意識を超過し、ときには眠りにいざなう――そのとき、他のジャンルにはない、まさに映画特有の超人間性が露呈されるだろう。映画とは、エイリアン(他なるもの)を利用しながら「動きの研究」を進める装置なのだ。

さらに、このような映画の超人間性は、濱口に先立つ蓮實重彦の批評も基礎づけている。蓮實は「映画を見た」という体験そのものを疑う。先ほど見たはずの映像の流れは、すでに瞳の奥でおぼろげにゆらめく残像にすぎず、映画そのものはとっくに立ち去った後ではないか?――そう問う蓮實にとって、映画とは決して人間の前に全貌を現さない「不在なるもの」であり、歴史と無関係に「生成」し「反復」されるものである(※1)。もし映画が超人間的なエイリアンであり、人間はその「後ろ姿」をかろうじて捉えられるだけだとしたら、確かに映画の生を人間の歴史に回収することはできない。
このように、メディウムの特性を個別化・純粋化するモダニズムの理論を突き詰めてゆくと、個々のジャンル(絵画、映画、建築、音楽……)がそれぞれ本性上異なるエイリアンとして、異様な立柱のように並ぶ情景が浮かんでくる。モダニズムの観点から言えば、メディウムが法ならば、ジャンルは立法者であり、かつその法は人間の社会や歴史の規則を超えている。私なりに定義すれば、モダニズムとは≪人間の制作した超人間的なエイリアン≫を探索しようとする技法の総体なのだ。特段モダニストを自称するわけではない蓮實や濱口の批評も、その技法を共有している。
※1 蓮實重彦『映画の神話学』(ちくま学芸文庫、1996年)および同『ショットとは何か 歴史編』(講談社、2024年)参照。
2、メタメディアとしてのコンピュータ

ただ、以上のモダニズムの戦略は、20世紀後半以降のコンピュータやインターネットの問題を理解するには、さほど有益ではない(※2)。というのも、コンピュータはメディアの意味そのものを変質させる発明であったからである。
思えば、クレメント・グリーンバーグがニューヨークを拠点として、同世代のジャクソン・ポロックの抽象画をモダニズムの先端に仕立てた20世紀半ばは、ちょうどコンピュータの構想と開発が飛躍した時代であった。1946年にはアメリカのペンシルバニア大学でENIACが公開される一方、48年にはクロード・シャノンの「通信の数学的理論」、1950年にはイギリスのアラン・チューリングの「計算機と知能」という記念碑的な論文が発表される。さらに、シャノンの周辺にいたジョン・マッカーシーを中心に、ハーバート・サイモンやマーヴィン・ミンスキーらが集った1956年のダートマス会議では、人工知能(AI)という言葉が初めて議論の俎上にのぼった。
彼ら初期の計算機科学者たちは、知性を拡張する「思考のための道具」(ハワード・ラインゴールド)としてのコンピュータを構想した。コンピュータの主な仕事は計算と通信であり、さしあたり芸術とは無関係である。だが、1970年代に大きな転機が訪れた。この時期、マクルーハンに強く触発されたパロアルト研究所のアラン・ケイが、現代のパーソナル・コンピュータの原型となるダイナブックのアイディアを提示した。それが、コンピュータを論理計算の「道具」から視聴覚的な「メディア」に変える契機になったのである。
GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を備え、アイコンの操作によって指令を出せ、小型で持ち運びも自由という理想化されたダイナブックは、画期的なアイディアであった。ケイにとって、このコンピュータは教育の道具、特に子どもの教育に関わる装置である。ケイは著名な教育心理学者ジャン・ピアジェおよびジェローム・ブルーナーを参照しながら、マルチメディアのコンピュータ――たんなる道具以上のダイナミックな「本」――の構想を具現化し、計算機の歴史におけるブレイクスルーを引き起こした。
では、アラン・ケイのアイディアはメディア論的にはどのように位置づけられるのか。レフ・マノヴィッチはケイの「メタメディア(metamedium)」の構想に重要な意味を与えている。従来のメディアは、先行する特定のメディアを模倣しながら進化してきた。それに対して、メタメディアとしてのコンピュータは、ソフトウェアの使用によってあらゆるメディアを模倣することができる。マノヴィッチが言うように、メタメディアとはメディアそのものを恒常的に「拡張」し続ける装置なのであり、それゆえに本質的に実験的でアヴァンギャルド(前衛)である。
ケイ自身「シミュレーションがダイナブックの中心的な概念である」と宣言していたが、そのシミュレーションの対象にメディアを含めたところに、彼の技術思想の画期性があった。マノヴィッチの面白い言い方を借りれば、ダイナブックは「万能チューリング・マシン」(形式的な記号操作によってあらゆる計算を実行できる機械)を「万能メディア・マシン」(あらゆるメディアを擬態する機械)へと転回させることによって、今日の「ソフトウェア社会」を準備したのである(※3)。
そのメディアのシミュレーションにおいて、GUIのデザインの果たした役割は大きかった。ケイは主にブルーナーの認知心理学を参考にして、複数の心的能力を活気づけるようなインターフェースを設計した。ブルーナーは行為的(enactive)、アイコン的(iconic)、象徴的(symbolic)という三つの発達段階を分けるが、ピアジェとは違って、それらが大人になっても共存すると考えた。ケイはそれを応用して、GUIを搭載したダイナブックにこの三つのレベルを共存させようとした――すなわちマウスの操作(enactive)、アイコンやウインドウのイメージ(iconic)、スモールトークのプログラミング(symbolic)(※4)。チューリングやフォン・ノイマン以来の計算機科学に、ブルーナー流の認知心理学を融合させることによって、ケイはコンピュータを教育的なメタメディアに仕立てようと試みたのである。
※2 なお、モダニズムの理論そのものは、すでにコンピュータの普及以前に試練を迎えていた。美術批評家のロザリンド・クラウスは、モダニズムの理念が、テレビやビデオ――ジャンルの境界を溶かす放送や再生の技術――の普及によって解体されたと見なし、そのメディア状況を「ポストメディウム」と呼んでいる。『ポストメディウム時代の芸術』(井上康彦訳、水声社、2023年)62頁。
※3 Lev Manovich, Software Takes Command, Bloomsbury Academic, 2013, pp.70, 93.
※4 ibid, p.98.ブルーナー自身、Acts of Meaning(1990年/邦題『意味の復権』)では、チューリング以来のコンピュータの思想が心的なものと計算的なもの(情報処理)を安易にイコールで結んだことを強く批判しながら、むしろもともと認知革命の関心の中心にあった「意味形成」のテーマへの回帰を訴えている。