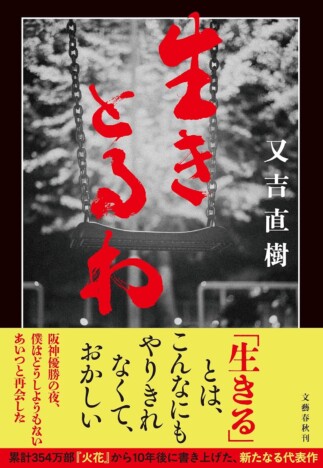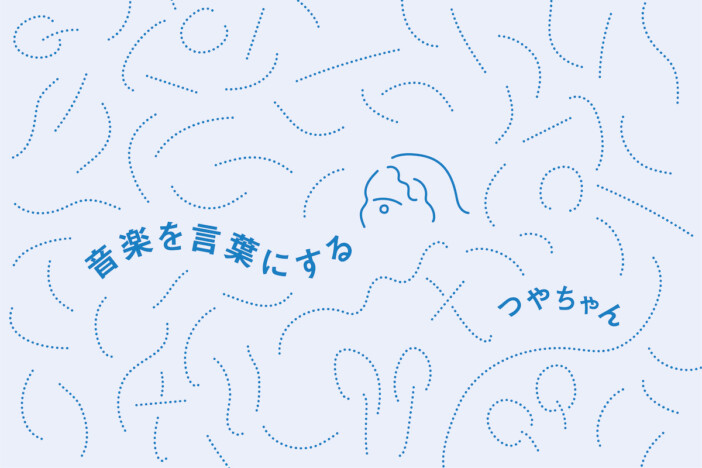【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第11回:戦争の承認、承認の戦争

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。
第11回は、21世紀の戦争が戦場を越えてメディア空間へと拡張されていることについて。ドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』を例に、映像は単なる記録ではなく、観客の承認を得ることで「戦争そのもの」と化すことを示しながら、戦争・政治・メディアが交錯する現代の「承認の戦争」を読み解く。
第1回:21世紀の美学に向けて
第2回:探索する脳のミメーシス
第3回:アウラは二度消える
第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去
第5回:電気の思想――マクルーハンからクリストファー・ノーランへ
第6回:鏡の世紀――テクノ・ユートピアニズム再考
第7回:21世紀の起源――人間がメディアである
第8回:モデル対シミュレーション
第9回:パラ知能としての生成AI――あるいは言語ゲームの多様性
第10回:マルクスとAI
1、21世紀の戦争ドキュメンタリー

2025年のアカデミー賞長編ドキュメンタリー部門を受賞した『ノー・アザー・ランド』は、ヨルダン川西岸に住むパレスチナ人に対する迫害の光景を捉えた映画である。もともと、エドワード・サイードやサラ・ロイらが指摘してきたように、イスラエル人の入植者たちは、パレスチナ人の身体や財産を傷つけるだけではなく、生存や尊厳の拠点となるインフラ――住居から井戸、学校まで――を、開発の名のもとに徹底的に破壊してきた。このブルドーザーを武器とする「収奪のポリティクス」(サイード)がいかに残酷かつ非人道的なやり方で、パレスチナ人の魂の力を削ぎ落としてきたかを、『ノー・アザー・ランド』は克明に記録する。しかも、この悲惨なヨルダン川西岸以上の悲惨さがガザという「天井のない監獄」を覆っているのは明白だから、観客はただ慄然とするしかない。
振り返ってみれば、ロシア軍によって包囲・破壊されたウクライナの都市マリウポリを記録した『マリウポリの20日間』(2023年)や、香港の民主化闘争を最前線で記録した『香港、裏切られた約束』(2022年)をはじめとして、ここ数年のドキュメンタリー映画では、決死の覚悟で撮影された≪この映像≫をいかに観客に送り届けるかが、そのまま核心的なテーマとなっていた。観客はウクライナ人や香港人の闘争に感情移入しながら、この映像のデータが敵に没収されたり破壊されたりせずに、ぶじに外部に送り届けられることを願わずにはいられない。つまり、映像の内容だけではなく、自分たちが現に目撃している≪この映像≫を記録し送信しようとする命がけの撮影者が、映画の主人公のようにも感じられるのだ。このとき、これらのドキュメンタリーは実験的・前衛的な志向をもたないのに、いわば自然と「メタ映画」(映画や映画監督そのものを主人公とする映画)に近づくだろう。

このようなメタ映画的な性格は、『ノー・アザー・ランド』にも認められる。そこでは、パレスチナ人とイスラエル人の二人の監督にも頻繁にカメラが向けられ、彼らの苦悩および両者の境遇の差異が重要なテーマとして語られる。特にパレスチナ人監督は、イスラエルの蛮行を記録する行為にいかなる意味があるのかを、どうしようもない無力さのなかで自問自答せざるを得ない。そのため『ノー・アザー・ランド』の全体には、イスラエルへの怒りとともに、映画を撮る側の、すべてを剥奪されているがゆえの抑鬱的な気分が染み込んでいる。
不謹慎な言い方に響くかもしれないが、『マリウポリの20日間』や『香港、裏切られた約束』は、一種の戦争映画としてのスリルも備えている。ハラハラドキドキしながらウクライナ人や香港人の危機に没入する体験は、虚構の戦争映画に没入することと本質的に変わるわけではない。だからこそ、これらの映画は観客を強く刺激し、ロシアや中国の理不尽な暴力に対する怒りや抗議の感情を組織することができる。
それに対して、『ノー・アザー・ランド』はこれらの映画と違って、あるいは半世紀前にパレスチナゲリラと日本赤軍の共闘を宣伝した若松孝二&足立正生の『赤軍-PFLP』(1971年)とも異なり、映像のデータを「戦争映画」に仕立てる気力も残っていない。パレスチナ人監督のバセル・アドラは水たばこを吸いながら、スマホを片手に、インスタグラムにアップロードした映像へのアクセス数を気にするしかない。彼にとって、世界への入口は封鎖されてしまっている。このお手上げの状況は、傍らのイスラエル人監督ユヴァル・アブラハムと、はっきりした対照をなしている。両者の表面的な「近さ」が、かえって埋めがたい「遠さ」を浮き彫りにするのだ。
あえて言えば、『ノー・アザー・ランド』は映像作品としては単調で面白くない。ブルドーザーと銃器を使った一方的な破壊と収奪がひたすら反復されるばかりなのだから。しかし、この単調な反復――それはユダヤ人のカフカが『城』で描いた不毛な反復をも思わせる――こそが、尊厳や創造の基盤を根こそぎにしてゆく「収奪のポリティクス」の実態をあからさまにする。つまり、世界から締め出され、どこにもエントリーできないうちに、刺激的な映像を制作する力も尽きて打ちひしがれたパレスチナ人映画監督のありさまが、ある意味でこの映画の最大のメッセージなのである。
2、メディアが戦争である

もともと、20世紀における映画と戦争の交差については、多くの分析がなされてきた。カメラのshotと銃のshootを重ねるのは、すでに表象文化論の常套句である。21世紀のドローン戦争の時代になると、戦争は映画以上にゲームに接近した。軍用ドローンの視線を操縦して敵を狙撃するのは、ゲームをプレイするのと変わらない。現に、ゲームのコントローラは戦車やドローンの操縦に転用可能なため、一部ではその輸出規制も行われているのだ。軍事とエンターテインメントを融合させた、いわば≪軍娯複合体≫の伸長によって、戦争のイメージや手法は、市場で流通するゲーム(商品)と相互に似通ってくることになった。
フランスの思想家グレゴワール・シャマユーが指摘するように、ドローンのカメラで敵に照準をあわせることは、安全地帯から標的を追跡して「狩る」ことに等しい。どこにでも入り込める無人小型飛行機の登場は、戦争の空間的な制限を取り去り、標的とハンターがたえず移動する狩猟のモデルを再来させた。シャマユーは、ドローンが「戦争の地理学」を変容させたことを強調する。
戦争が結局のところ戦闘行為によって定義されるとすれば、狩猟のほうは本質的に追跡によって定義される。これら二つの活動には、異なる二つの地理学が対応している。戦闘行為が勃発するのは、力と力が衝突する場所においてである。狩り出しのほうは、獲物が行くほうに自分も動いてゆく。(※1)
こうして、ドローンに搭載されたカメラが獲物を恒常的に監視しながら「追跡」するとき、21世紀の戦争の「脱領土化」(=空間的制約の解除)がいっそう加速してゆく。つまり、軍どうしの衝突する前線以外(敵国の主要都市や要人)も「狩り」の射程に入ってくるのだ。しかも、カメラの標的は今や敵だけではない。21世紀のドキュメンタリー映画が明確にしたのは、空間的に離れたオーディエンス(観客)こそが、狩り=追跡の主要な対象になったということである。ここにも「戦争の地理学」の変容が刻印されている。
実際『ノー・アザー・ランド』にしても、イスラエルの蛮行を「標的」として記録するだけでは意味がない。その映像が没収されずに映画館まで伝達され、ドローン(もとは「雄バチ」の意)の射出するミサイルのようになって遠隔地のオーディエンスに刺さったとき、ようやく映画の意図は達成されるだろう。安全地帯にいる観客がそのショッキングな映画を目撃することそのものが、作戦の「成功」となる。映画のヒット(当たり)は、まさに観客の価値判断に対するヒット(打撃)でもあるのだ。興味深いことに『マリウポリの20日間』では、当の映像をロシア軍から命がけで守り抜くことが、ウクライナ軍の重大な戦術目標となった。なぜなら、オーディエンスに刺さる映像は、通常の兵器以上に強力な兵器として機能するからである。要するに、映画(映像)とは戦争の延長なのだ。
私はこのような状況を、1990年代初頭の湾岸戦争の時代と比べたい。湾岸戦争は、テレビで初めてリアルタイムで中継された戦争として語られる。アメリカを中心とする多国籍軍が、イラクに向けて大量のミサイルを撃ち込むスクリーン上の光景は、戦争がまるで仮想のビデオゲームのように演出されたという点において、ひとびとに衝撃を与えた。

この戦争の仮想化・メディア化を受けて、当時ボードリヤールがその悪名高い論説で「湾岸戦争は起こらなかった」と挑発的に言ったとき、戦争はもはや歴史を生み出す闘争ではなくなったと見なされた。ボードリヤールに言わせれば、湾岸戦争は「始まる前から終わっていたようなもの」であり、当初の筋書きどおりに進行した「清潔な戦争、漂白された戦争、プログラミングされた戦争」にすぎない。戦争がメディアを宣伝し、メディアが戦争を宣伝するという鏡像的な反射のゲームのなかで、湾岸戦争はいわば形式だけの戦争、つまりシミュレーションとしての戦争になる……(※2)。このボードリヤールの主張はただちに批判と嘲笑を浴びたが、実のところ、多国籍軍によるイラク攻略は一か月ほどで終了したので、確かにプログラミングされた戦争という印象が生じても不思議はない。
しかし、それから30年以上経って事態はいっそう進み、ボードリヤールの挑発をも牧歌的なものに変えてしまった。21世紀の戦争は、インターネットで配信されるコンテンツとなる。それは、戦争の存在をスクリーン上で「承認」するオーディエンスがいっそう重要になったことを意味する。その結果、「(戦争が映像化・仮想化されたために)戦争は起こらなかった」というボードリヤール的な命題は「(戦争を映像化・仮想化しなければ)戦争は起こらなかったことになる」という、ある意味ではもっと恐ろしい命題に取って代わられた。戦争の存在が「承認」されるためには、むしろビデオゲームのような映像として、オーディエンスに受信され評価されなければならない。われわれが直面しているのは、文字通り≪メディアが戦争である≫という事態なのである。
※1 グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』(渡名喜庸哲訳、明石書店、2018年)67頁。なお、ウクライナ戦争は、AIで制御されたFPV(一人称視点)ドローンが大量に投入された歴史上最初の戦争である。その技術的な側面については、以下のロイターの記事(2024年3月26日)が参考になる。
https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/DRONES/klpydorqevg/
※2 ジャン・ボードリヤール『湾岸戦争は起こらなかった』(塚原史訳、紀伊國屋書店、1991年)33、84、93頁。