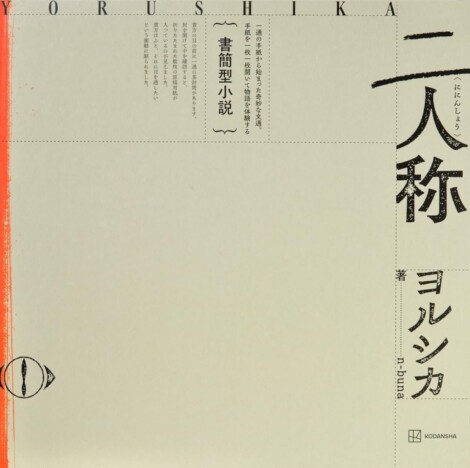【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第5回:電気の思想――マクルーハンからクリストファー・ノーランへ

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。第5回では、。マクルーハンが重視した「電気」の思想に改めて着目するとともに、クリストファー・ノーラン監督の映画作品との類似性を探る。
第1回:21世紀の美学に向けて
第2回:探索する脳のミメーシス
第3回:アウラは二度消える
第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去
1、ヴァーチャル・リアリティとしての電気
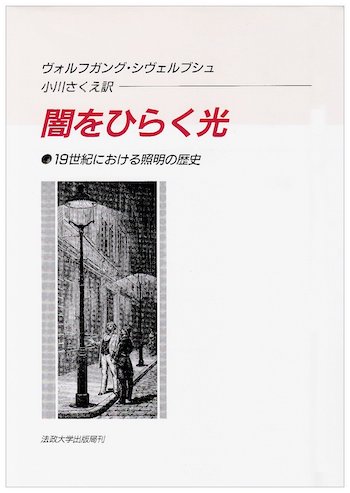
一般に現代は「情報社会」と呼ばれるし、たいていのメディア論もそれに従っている。しかし、メディア論の開祖マクルーハンは、いささか意外なことに、情報以上に「電気」を重視した思想家であった。実際、電気がなければ、ハイテクの情報機器も無用の長物にすぎない。21世紀の情報社会は、電気に深く依存しており、莫大な電力を必要とする生成AIの開発によって、その傾向はますます強まっている(例えば、グーグルはデータセンターへの安定的な電力供給のために、2024年に原子力発電所と契約を結んだ)。ならば、われわれもマクルーハンに倣って、エレクトロニクスの思想について改めて考えてよいのではないか。
その社会的な重要性にもかかわらず、電気はもともと、哲学上のテーマとしては明確な地位を与えられてこなかった(※1)。この思想的な空白をいわば逆用するようにして、「電化」に途方もない力を見出したのが20世紀初頭のレーニンである。彼が≪ソビエト+電化=共産主義≫という公式を掲げたことはよく知られている。ロシア革命後、レーニン率いるボリシェヴィキは電気のもつ神秘的なエネルギーを宣伝し、芸術や広告には、ソビエト全土を結ぶ電化の計画を讃えるプロパガンダが溢れた。「電気の伝道師」となったレーニンは、大衆を照らす明かりとして偶像化された(※2)。
電気は個人の限界を超えて、集団を浄化する革命的な力をもつ――このようなレーニンふうの神秘主義は、実は電気が実用化されたときに早くも現れていた。エジソンは1879年に白熱灯を発案し、それを二年後のパリの電気博覧会で大いに宣伝したが、この発明にはすでに電気の「意味」をめぐる数々の興味深い問題を見出せる。
歴史家のヴォルフガング・シヴェルブシュによれば、エジソンの電灯はそれまでのガス灯のあらゆる特性を備えながら、ガス灯とは違って清潔かつ無害で、より洗練された「明かり」として称賛された。つまり、電灯とはガス灯のシミュレーション、あるいはvirtual(仮想的/事実上)な火なのであり、そのクリーンな記号性ゆえに市民社会にも熱狂的に受け入れられたのである。しかも、電気はたんに部屋を明るくしただけではなく、健康を増進する神秘的なエネルギーをもつと期待されるようにもなった。面白いことに、シヴェルブシュは電気が薬と等置されたことに注目している。
清潔、無臭、そして形体のないエネルギーであることが電気の特徴だったので、たちまち上流社会入りを果たしたわけである。電気は健康に無害で、生命にかかわるような危険もないばかりか、逆に、とても健康によい、いわば一種のビタミンのようなものとみなされていた。ヘルマン・フォン・ヘルムホルツの時代には、電気とエネルギーと生命は同義語であった。電気は、エネルギーの消耗を回復する薬とみなされたし、またそのように利用されもした。(※3)
電灯とは本物の火を模倣したいわば記号的な火であり、その透明性ゆえにすばやく社会に浸透した。情報社会がヴァーチャル・リアリティを定着させる以前に、すでに電気が安全無害なヴァーチャル・リアリティのように受容され、しかもそれが生命力を回復するサプリメントとすら見なされたのは、非常に興味深い。電気は、個人を活気づける環境のエネルギーであり、現代ふうに言えば「エンパワーメント」の場そのものであった。
要するに、電気を意味づけるとき、個人の限界を超える清潔で無害なエネルギーが重点化される。シヴェルブシュはそこに金融資本との類似性を認めた。
電気と金融資本のあいだには、否定できない類似性が存在する。大銀行による経済力の集中化〔…〕に照応するのが、大発電所によるエネルギーの集中化だった。第二次産業革命の新しい世界を迎えながら、なおも企業家の個人的活動やエネルギーの自給自足にこだわるのは、ドン・キホーテふうの愚行と化してしまった。(※4)
銀行が巨額の資本を調達し、企業に出資するように、電気はそのクリーンなエネルギーを蓄えては大衆に惜しみなく注ぎ込み、諸個人をエンパワーする――このような電気=銀行のモデルが支配的なものになれば、バラバラに分断された個人が自給自足でやっていくという考え方は、確かに時代遅れなものになるだろう。ユーザーを活気づけ、世界全体をクリーニングする力をもつ無色透明な電気は、個人主義の限界を超える。ソビエトの人民を結合する「電化」を神聖化したレーニンは、まさにこのような電気の意味論の継承者なのである。
※1 現に、ヘーゲルのような体系的な哲学者も、電気を「自然哲学」の題材に組み込んだものの、その「概念」を規定することはできなかった。ホルスト・アルトハウス『ヘーゲル伝』(山本尤訳、法政大学出版局、1999年)511頁。
※2 ナタリア・ニキフォロワ「電気はいかにしてソビエトのプロパガンダになったか」(2021年)
※3 ヴォルフガング・シヴェルブシュ『闇をひらく光』(小川さくえ訳、法政大学出版局、1988年)75‐6頁。
※4 同上、80頁。
2、電気の思想家マクルーハン

このように、エジソンからレーニンに到るまでに、電気はそのヴァーチャルな記号性ゆえに、集団を組織する力と紐づけられてきた。では、20世紀後半のマクルーハンは電気をどう意味づけたのだろうか。
カナダのマクルーハンもある意味でロシアのレーニンと同じく「電気の伝道師」であったが、それを政治的なプロパガンダにしたわけではない。というのも、マクルーハンはエレクトロニクスをいたずらに理想化したのではなく、むしろ電子革命が人間に与える多面的な影響を「探査」したからである。ここで、彼の歴史観に二つの軸があったことに注目したい――一つは≪活字の時代から電気の時代へ≫という移行であり、もう一つは≪機械の時代から電気の時代へ≫という移行である。
第一のポイントは、活字メディアを普及させたグーテンベルク革命の衝撃が、電子革命によって終わりに近づいているというマクルーハンの認識である(※5)。彼によれば、印刷された文字が人間に与えた能力は、非密着性(デタッチメント)と非関与性、つまり「反応することなしに行動する力」であった。印刷された文字は世界の計量化への道を開き、それが個人をべったりとした部族的な関係から解き放った。外界からのデタッチメントを可能にする「内面」も、活字の力で生み出された。感情に任せて行動するのではなく、感情は感情、思考は思考として分離すること、さらに部族から個人の精神を切り離すこと――このような「分割統治」が活字メディア時代の心の特徴になったのである。
しかし、電気はこのようなデタッチメントを解消し、再び部族的な「統合」への扉を開いた(前回紹介したアラン・ケイは、諸感覚の統合をインターフェースのレベルで実現した)。この再部族化した人類の住む地球を指して、マクルーハンは「グローバル・ヴィレッジ」と呼ぶ。つまり、人類は狭い村を出て拡大の道を歩んできたはずが、電子革命によってむしろ村に戻ったというわけだ。地球を巨大な村に変えたエレクトロニクスの時代には、じっくり内面を育む活字の時代と違って、電子的ネットワークの内部における即時的な反応(レスポンス)やコミットメントが主流となるだろう。
第二のポイントは、機械の時代が電気の時代に取って代わられたという認識である(※6)。マクルーハンは活版印刷を含めて、機械の本質を画一化・平均化・規格化に見出した。それは中央から指令を発して、全体をコントロールする集権的な社会には適応していた。しかし、エレクトロニクスはむしろ「有機的」な生き物に似ており、たえず相互作用を生起させるので、機械的な画一化を受けつけない。マクルーハンによれば「電気メディアは、事件が相互に作用し合い、われわれがそこに関与せざるをえないような全体的な場を、即座に、しかも常時つくりだす」。
活字メディアが、思考を頭脳というクローズドな神経系のなかに隠匿し分離したのに対して、電子メディアはむしろ思考をオープンな相互作用のなかにむき出しにした。この「中枢神経系の拡張」によって、機械的な画一化・平均化の時代は終わるが、その反面で独特の「不安」が生じてくる。マクルーハンが指摘するように、1844年に画家のサミュエル・モールスがモールス信号を実用化し、テレグラフ(電信)の時代を切り開いたまさにその年に、キルケゴールの哲学書『不安の概念』が刊行されたのは示唆的である。「電信の発明以来、私たちは人間の脳と神経を地球全体に拡張させてきた。その結果、電子時代は実に不安な時代となった。人間は、頭蓋骨を内部に入れ、脳みそを外側に出して耐えている。私たちは異様に脆弱になった」(※7)。
電気の時代は人間を再部族化する一方、その神経系を「外化」し、異様に脆弱にする――これは21世紀のインターネットの診断としても、十分に通用するものだろう。ソーシャルメディアはまさに脳を外にさらし、それゆえに過敏性の炎症(炎上?)を頻繁に引き起こしているのだから。60年前のマクルーハンの直観は、現代社会の特性と弱点を見事に射抜いているのだ。
※5 マクルーハン『メディア論』176頁以下。
※6 同上、253頁以下。むろん、電気の時代になったからと言って、機械の時代の諸問題が解消されたわけではない。特に、生成AIが再来させた機械論については、近々この連載で取り上げる。
※7 マクルーハン「外心の呵責」宮澤淳一『マクルーハンの光景 メディア論がみえる』(みすず書房、2008年)8頁。