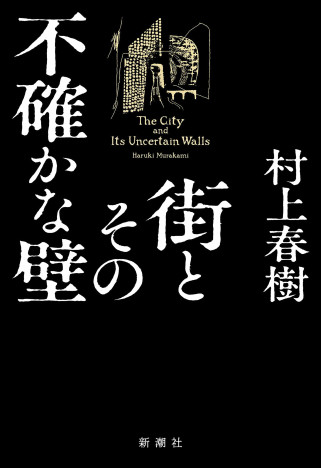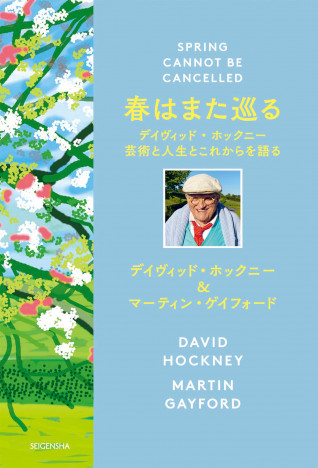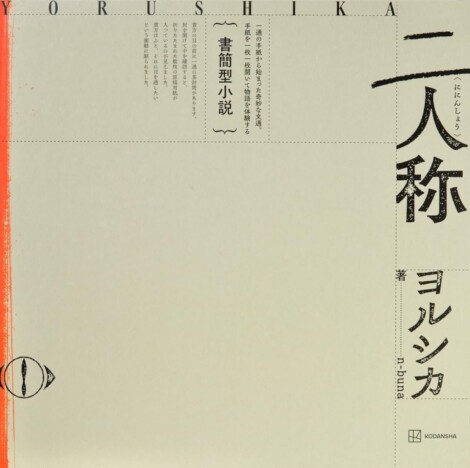【新連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第1回:21世紀の美学に向けて

1、エイリアンとしての映画
映画監督の濱口竜介は、近年のレクチャーをまとめた著書のなかで、次の素朴な問いを発している――なぜ映画を見ながら寝てしまうのか?
映画が人間にとって「他なるもの」、つまりエイリアンだから、というのがその答えだ。カメラは人間の関心や生理にはお構いなしに世界を記録し、プロジェクターは観客の状態を無視して、スクリーン上に機械的に映像を映し続ける。濱口によれば、カメラの視覚は人間のそれとは根本的に異なる。人間の眼が生の有用性や関心に基づくのに対して、映画の眼はむしろ徹底した「無関心」によって特徴づけられる。
我々はカメラのように見ることは決してできません。なぜなら我々は生き物で、カメラは機械だからです。カメラはただ、レンズの前のありようを機械的な無関心をもって、隈なく記録します。一方で、我々は生き物としてものを見る。(※1)

この濱口の指摘を、私なりに言い換えてみよう。日々生き残りを賭けている生き物と違って、非生物のカメラは対象の選り好みや差別をしない。機械の眼は、モノもヒトもひとしなみに対等のものとして取り扱う。この恐るべき無関心ぶりと比べれば、習慣や好み、偏見に支配された人間の眼は、もともと無自覚の差別主義に染まっている。カメラというエイリアンは、生物的な眼による補正(感情移入)とは無縁のまま、フレームのなかで対象の質的な差異を打ち消すleveler(平等主義者)なのである――それはちょうど、貨幣が対象をひとしなみに数値化された商品に変える「急進的な平等主義者」(マルクス)であることと似ている。
もとより、このような「機械的な無関心」への注目そのものは、決して新しいものではない。例えば、1920年代にハンガリーのモホリ゠ナジやソ連のジガ・ヴェルトフは、まさにキノ‐アイ(映画‐眼)のもつ独自の法則や可能性を探求した(※2)。あるいは写真でもやはり20年代に、モホリ゠ナジとは異なるより即物主義的なアプローチをとったウジェーヌ・アジェやアウグスト・ザンダーらが、構成的な写真に取り組んでいた。さらに、1930年代初頭の日本の新興写真においても、「機械の眼」で産業社会の構成(コンポジション)を捉えようとした堀野正雄のようなモダニズム写真家がいたことが思い出される。要するに、濱口の映画=機械論は、ちょうど一世紀前の古典的な写真/映像論を反復したものなのだ。
ただ、濱口の主張が面白いのは、それを眠りと結びつけたことにある。映画は人間の知覚に強い負荷をかける。映画館で二、三時間も椅子に座り、スクリーンを見続けるように拘束されていると、喉は渇くし腰も痛くなる。退屈な場面が続けば、あっけなく眠りに落ちる。逆に、息苦しくなるほどの暴力シーンにも映画は事欠かない。それでも、このような「苦行」をものともせずに、観客はハラハラドキドキしたい、胸を締めつけられたいと願って映画館に足を運ぶ――映画という産業を成り立たせてきたのは、このマゾヒスティックな快楽だと言って差し支えない。
※1 濱口竜介『他なる映画と1』(インスクリプト、2024年)26頁。
※2 レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』(堀潤之訳、ちくま学芸文庫、2023年)209頁。なお、カメラの移動性を際立たせたジガ・ヴェルトフの試みが、現代ではコンピュータ・ゲームにおけるヴァーチャル・カメラに再来しているというマノヴィッチの指摘は興味深い。
2、投影と拡張

ともあれ、映画はたんに快適なだけの娯楽ではない。人間的関心に従属しない映画の機械性は、ときに感覚を超過するような強いショックを観客に与える。そして、中枢神経を過度に緊張させるショックに襲われたとき、人間は「感覚の麻痺」に陥る――これが今から60年前の記念碑的著作『メディアの理解』(1964年/邦題『メディア論』)でマーシャル・マクルーハンが指摘したことだ(※3)。メディアへの接触の負荷が強くなりすぎたとき、感覚は半ば強制的にシャットダウンされる。濱口竜介はそれを「眠り」と言い表した。
ただし、機械の与えるショックは、たんに観客を麻痺や眠りへと導くだけではない。なぜなら、そこには眠り(切断)とは異なる「没入」のモードもあるからだ。観客は映画という機械=エイリアンに熱中し没入するうちに、日常とは別の地平へと誘導される(※4)。それを可能にするのが、プロジェクターによる「投影」である。
映画の生態は、世界を吸って吐き出すというエイリアン的=非人間的な呼吸の動作を思わせる。カメラは世界を吸収し、プロジェクターはその記録された世界をスクリーン上で解放する。つまり、観客の知らないところで集められた映像データが、観客の頭上を通り越してスクリーンに映写されるのだ。そして、この人間たちを背後から光の速度で追い抜く「投影」のテクノロジーによって、映画は集団的な体験となる。演劇とは違って、映画はどの席から見ても映像は基本的に変わらない。映画とは、同じ時間に同じ映像を、ある集団に向けて効率的に発信するテクノロジーなのである。
しかも、スクリーンへの投影によって、人間は不定形な存在となる。映写されたスターは、実在の人間よりも巨大化される。と思えば、スクリーン上の群衆はむしろ小人に近づき、その動きもときに人形や昆虫じみたものになるだろう。ちょうど巨人国と小人国を登場させたスウィフトの『ガリヴァー旅行記』のように、スクリーン上の人間の身体はその比率をたえず変更されるのだ。
こうして、映画的な投影は、人間に人間以上(ないし人間以下)のイメージをまとわせる。ここでもう一歩踏み込めば、20世紀における人間集団は映画的に組織=投影されたとすら言えるだろう。例えば、映画評論家のジャン゠ミシェル・フロドンは「国民国家」と「映画」の相似性を強調している。近代の諸個人は映画館の観客と同じく、お互いを見知ることがないまま、メディアに「投影」された国民のイメージに統合される(※5)。ひとびとは、映画のスクリーンに同一化するようにして、より巨大なイメージとしての国民に同一化する……。
このような議論は、メディアの本質を「人間の拡張」に認めるマクルーハンの考え方を髣髴とさせる。マクルーハンは言語に始まり、衣服や住宅から、自動車、ゲーム、書物、電話、蓄音機、さらには漫画やラジオ、テレビに到るまでを、すべて人間の身体や意識を拡張するメディアとして捉えた。メディアは人間とは異質な機械であるからこそ、人間の内的な限界を超えることができる。人類はさまざまなメディアによって自己を補完しながら、時間と空間の拘束を取り外してきた。それが閾値を超えると、ときに「感覚の麻痺」が引き起こされるのだ。
なかでも、映画による「人間の拡張」は、20世紀の文化的なモデルになり得るだけのインパクトをもっていた。フロドンが言ったのは、映画的な投影のメカニズムによって、個人は国民にまで拡張されたということである。映画は「人間の拡張」を促す人間離れしたエイリアンとして、ときにひとを一人孤独に眠らせ、ときにひとをナショナルな主体に覚醒させるプロパガンダとなった。「映画とは他なるものである」という濱口の言葉には、このような20世紀のメディア体験が濃縮されている。
※3 マーシャル・マクルーハン『メディア論』(栗原裕他訳、みすず書房、1987年)6頁。
※4 念のために言えば、映画を人間にとってのエイリアンと断定することにも反論はあり得る。例えば、ベルクソンの主著『創造的進化』は、映画の仕組みと思考の仕組みを類比したことで知られる。
※5 ジャン゠ミシェル・フロドン『映画と国民国家』(野崎歓訳、岩波書店、2002年)8頁以下。