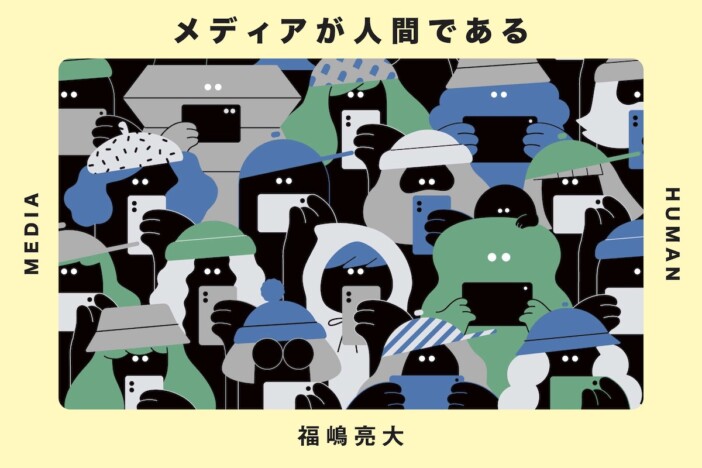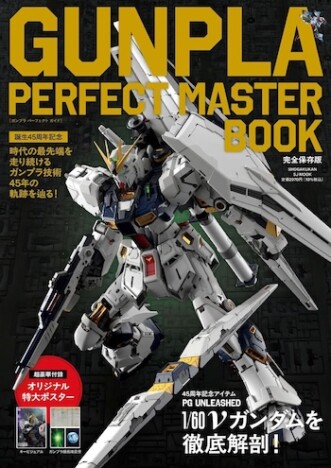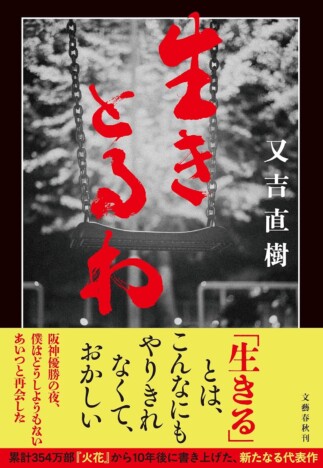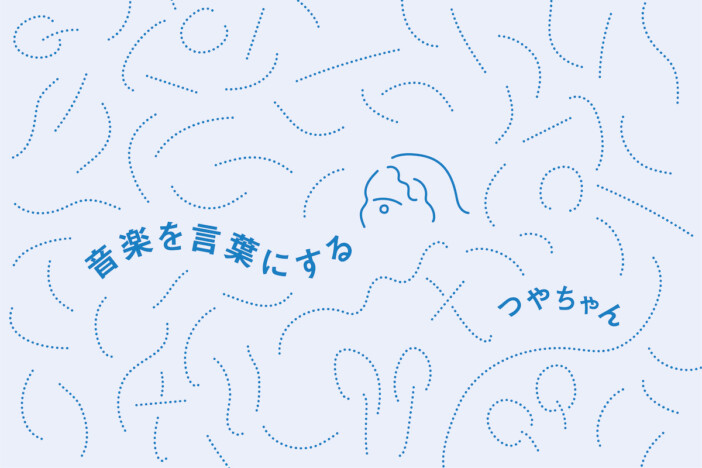【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第9回:パラ知能としての生成AI――あるいは言語ゲームの多様性

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。第9回では、生成AIを人間に「並行」する≪パラ知能≫であると位置付けた上で、人間の言語とAIの言語の違いを、ウィトゲンシュタインが提示した「言語ゲーム」と「生活形式」という概念で読み解く。
第1回:21世紀の美学に向けて
第2回:探索する脳のミメーシス
第3回:アウラは二度消える
第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去
第5回:電気の思想――マクルーハンからクリストファー・ノーランへ
第6回:鏡の世紀――テクノ・ユートピアニズム再考
第7回:21世紀の起源――人間がメディアである
第8回:モデル対シミュレーション
1、目的から生成へ
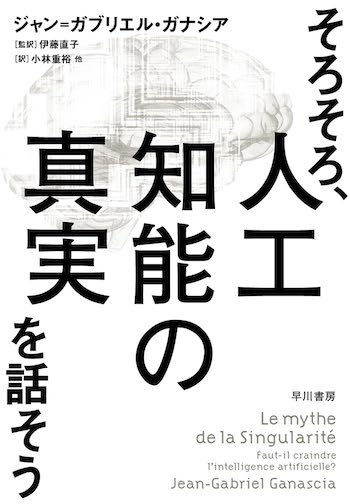
私は第5回で「機械の時代から電気の時代へ」というマクルーハンの歴史観を取り上げたが、それで機械の問題が解消されたわけではない。それどころか、21世紀はむしろこの問題を大々的によみがえらせたと言ってよい。「人間の労働はいずれ機械に置き換えられるのではないか」「機械が知性的にも人間を支配するのではないか」という古風な問いが、生成AIの進化にともなって再浮上しているのは、周知のとおりである。
機械が人間を凌駕する――そう聞くと、われわれはついチャップリンの映画『モダン・タイムズ』で描かれたような、機械の歯車に組み込まれた不自由な人間を連想しがちである。知能爆発を果たしたAIが絶対的な主人となり、人間がそれに服従するという極端なシンギュラリティ論は、その最新版と言えるだろう。しかし、これはかなり誇張された考え方であり、知能爆発の根拠となるムーアの法則を無制限・無批判に拡大していることにも、大きな疑問符がつく(※1)。結局のところ、実際に懸念されるべきなのは、人間支配に駆り立てられた「悪いAI」ではなく、AIを悪用する「悪い人間」であり、さらにはAIの発明する「事故」のほうだろう。だからこそ、行政でもビジネスでも学問でも、AIを倫理に沿って有効に機能させるためのアーキテクチャの設計が急務なのだ。
ともあれ、われわれを取り巻くのは、人間を一方的に締め上げる≪硬い機械≫ではなく、エレクトロニクスと融合して人間の多様な欲望を追尾しつつ商品に変える≪柔らかい機械≫である。この新しい機械論の性質は、まさに「生成」という標語に凝縮されている。20世紀の共産主義が上からの「目的」や「計画」を掲げたのに対して、21世紀アメリカのテック・ジャイアンツは表向き、ユーザーの自由を最大限に尊重するような企業理念を掲げる(第2回参照)。このテロス(目的)なき風土から、ユーザーの多様な要求にそのつど即時的に反応する「生成AI」が出てきたのは、決して偶然ではない。
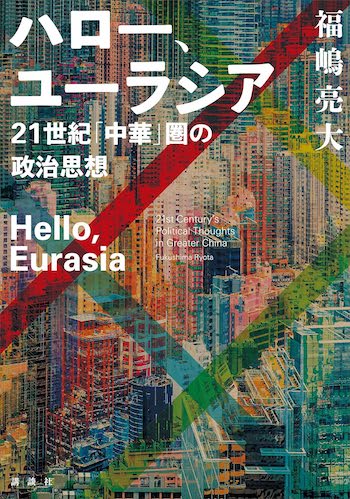
トップダウンの「目的」がボトムアップの「生成」に置き換えられること――それは政治思想の文脈では、リベラリズムの浸透と共振する。リベラリズムの基本的な考えは「善の構想はひとそれぞれ」ということにある。共通善を排するリベラルの理念において、国家は個々人の魂の問題に干渉してはならない。善は国家がトップダウンで教え込むものではなく、あくまで自律的な個人の行為と選択によって、おのずと「生成」されるべきものだ。プラトンの『国家』をはじめ古典的な政治学が、魂の問題にコミットしたのとは逆に、リベラリズムは魂の問題を個人に委ねた。それによって、生(身体)の管理を統治の基盤とする「生政治」(ミシェル・フーコー)はいっそう加速することになる。
アメリカ発のITが急速に拡大したのは、たんに技術的に優れていたからというだけではなく、そのテロスなき「生成」の志向が、リベラリズム(さらには個人の自由の価値を強調するリバタリアニズム)の望む社会観と合致していたからである(※2)。このリベラルな技術社会においては、上からの「強制」は表向き嫌われる。生成AIは無定形(フォームレス)であり、ユーザーのプロンプトにあわせて、そのつど具体的な言語や画像を生成するが、命令がなければ抽象的なデータとプログラムの集合体にすぎない。つまり、生成AIは一方的に命令を下す主人ではなく、命令を下される使用人として随時姿を現しながら人間をコントロールする≪柔らかい機械≫なのだ。
※1 ジャン゠ガブリエル・ガナシア『そろそろ、人工知能の真実を話そう』(伊藤直子監訳、早川書房、2017年)44頁。加えて、ガナシアはカーツワイルのシンギュラリティ論を、あるがままの自然と身体の超越をめざしながら、真の神の到来を待望するグノーシス主義的な「神話」として位置づけている(88頁以下)。同種のデジタル・グノーシス主義は、メタバースやAI、ミラーワールド等の分野でも見出せるだろう。
※2 その一方、中国やロシアの指導者に言わせれば、リベラリズムは目的をもたないという目的を強制したあげく、人間を精神的に堕落させる有害な思想にすぎない。今やいかに権威主義的な国家であったとしても「民主主義」を完全に撤廃することはできない。プーチンや習近平の政権も、民意を失えば、たちどころに存亡の危機に陥るだろう。それに対して「リベラル」と「民主主義」のデカップリング(切り離し)が比較的容易であることは、近年のilliberal democracy(非リベラルな民主主義)の勃興からも分かる。詳しくは、拙著『ハロー、ユーラシア』(講談社、2021年)参照。それらの国家では「生成」のテクノロジーは、非リベラルな政治体制と衝突しないように再調整されるだろう。
2、「怪しい隣人」としてのAI
この柔軟性ゆえに、生成AIはいわば人間の隣人として現れる。私がこの連載で「鏡」や「影」や「シミュレーション」という語を多用してきたのは、この≪柔らかい機械≫の隣人性を捉えるためである。生成AIとチャットするとき、それは人間に似ているとも、似ていないとも言える。それは鏡像を見て「これはいつもの自分だ」と思うこともあれば、どうもしっくりこないこともあるのと同じである。
人間の知能を部分的に模倣しながらも、それと完全には一致しない新種の知能――私はそれをひとまず≪パラ知能≫、つまり人間に「並行」する知能と呼びたい。なぜこのような言い方をするかと言えば、この隣人性や並行性を見逃すと、議論はたいてい不毛な紋切り型に陥ってしまうからだ。
例えば、AIやテクノロジーをめぐって、一方には、技術は人間を画一化された「一次元的人間」(マルクーゼ)に変え、現状を変更するための批判能力を喪失させるという昔ながらの疎外論がある。そして他方には、AIはむしろ人間の知をエンハンス(強化)し、場合によっては徳をも涵養するという技術的な楽観論がある。前者がAIと人間を峻別し、前者を危険な「敵」と見なすとしたら、後者は賢いAIを愚かな人間を導く「教師」と考えるのだ。
このうち、前者の議論は必ずしも間違っているわけではないが、その有効性をかなりの程度失っている。AIを批判し、人間の知能を聖別しようにも、すでに人間の知能そのものが情報技術と広告産業の環境のなかに取り込まれて久しい。われわれは人間の知性のデジタル化、つまり「凡庸化」をまずは受け入れるべきである。さもなければ、テクノロジーに汚染されない人間の本来性なるものを幻想的に設定するお決まりの疎外論(さらには人間中心主義)に陥るだけだろう。
その一方、後者についても誇大広告という難点がある。AIはせんじ詰めれば膨大なデータを用いて計算する数理モデルであり、明らかに万能ではないのに、まるで、人間のさまざまな限界や課題を超越する魔法の杖のように扱われている。しかし、AIが徳を復活させるとか、お金で価値を計測する時代を終わらせるとか、いずれ人類の未来を予言し始めるとかいう摩訶不思議な主張の数々――どれも私が最近目にしたもの――は、ほぼ何の根拠もないハイプ(誇大広告)ないしスネークオイル(蛇の油のようなインチキ万能薬)にすぎない(※3)。これらのデタラメな広告的言説においては、たんに論者の願望が新しいテクノロジーに投影されているだけである。
私が≪パラ知能≫という呼び名を提案するのは、このような不毛な疎外論や誇大広告から逃れるためである。AIは全知全能の神ではない。それは人間に並行する知能であり、ゆえに人間を一方的に抑圧することも、人間を新人類に劇的に生まれ変わらせることもない。ただ、この人間との並行性ゆえに、AIに対する認知はしばしば混乱し、無根拠な過大評価が横行することにもなる。結局のところ、われわれを戸惑わせているのは、至高の神ではなく、人間から半歩ずれた「怪しい隣人」なのである。
※3 特に、AIが未来を予知できるというのは典型的な誇大広告である。機械学習に基づく「予測AI」の開発は進められているものの、目立った成果をあげておらず、この点では、短期間のうちに驚くほどの進歩(社会的なリスクの増大も含め)を遂げた生成AIとは比較にならない。「生成AI(generative AI)とは対照的に、予測AI(predictive AI)はしばしばまったく役に立たない」。Arvind Narayanan & Sayash Kapoor, AI Snake Oil, Princeton University Press, 2024, p.9.