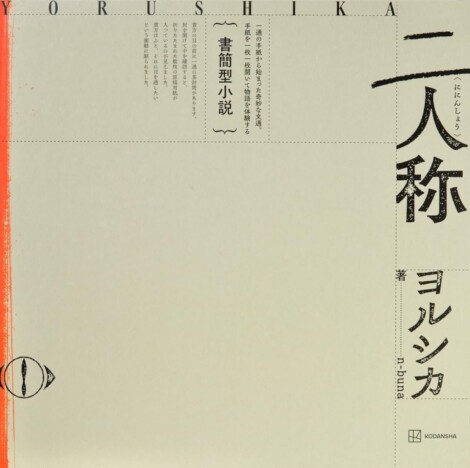【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第6回:鏡の世紀――テクノ・ユートピアニズム再考

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。第6回では、21世紀のメディアが鏡=シミュレーションの反射性に特徴づけられることを確認しつつ、ARやVRの技術によって期待されるテクノ・ユートピアニズムの是非を再考する。
第1回:21世紀の美学に向けて
第2回:探索する脳のミメーシス
第3回:アウラは二度消える
第4回:メタメディアの美学、あるいはメディアの消去
第5回:電気の思想――マクルーハンからクリストファー・ノーランへ
1、鏡=シミュレーションのゲーム
21世紀という時代は、日系二世の建築家ミノル・ヤマサキの設計したニューヨークのWTC(世界貿易センター)が、2001年のアメリカ同時多発テロで崩壊したことに始まった。巨大な二つのタワーが鏡像のように向かいあったWTCについて、ジャン・ボードリヤールが『象徴交換と死』(1976年)で次のように評したことは、よく知られている。
二つの塔は、お互いに見つめあうことで、類似性という威信をいっそう高めるわけだ。つまり、これらの塔がお互いに指示しあっているのは、モデルという観念であって、それぞれの塔がお互いに相手のモデルになっている。こうした双生児的性格のもつ価値はもはや相手を乗り越える価値ではない。(※1)
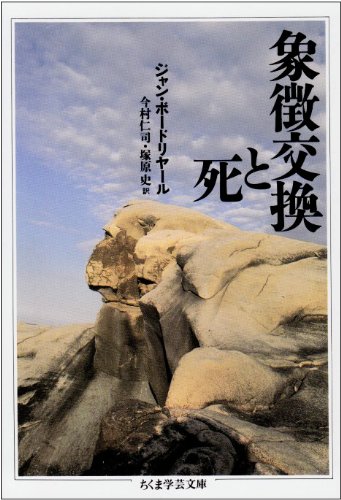
ボードリヤールによれば、世界貿易センターのツインタワーは「二重化という眩暈のなかでひとつのシステムが閉ざされたことの明らかなしるし」である。誰がいちばん高いかを競う近代の進歩のゲームではなく、二進法の数列のような双生児が、エンドレスに反射し模倣しあっては、富を加速度的に増大させてゆくシミュレーションのゲーム――それが、世界貿易センターという静粛な「しるし」から浮かぶ資本主義の肖像である。そこにはもはや外部はないし、がむしゃらな発展の物語もない。ただ、お互いに見つめあい、お互いを模倣する≪鏡のゲーム≫が、無感覚の静寂のなかで続くだけだ。
イスラム過激派のアルカイダは、この双生児的な建築物にアタックし、システムを閉ざす鏡のゲームの象徴を崩落させた。だが、皮肉なことに、それは鏡=シミュレーションの時代の終わりではなく、むしろその開幕を告げる号砲になったように思える。
実際、21世紀のプラットフォーム企業はユーザーの挙動をシミュレートし、その行動を予測することによって莫大な富を獲得する一方、ユーザーどうしはエコーチェンバーの内部で同質の意見を反射(反響)しあうように誘導されている。かたや生成AIは、与えられた問いへの回答をまさに「反射的」に出力するが、その答えそのものが、大量に学習されたデータの反映=反射である。情報社会の富の基盤になったのは、まさにこのような≪鏡のゲーム≫のエンドレスな続行なのだ。
※1 ジャン・ボードリヤール『象徴交換と死』(今村仁司+塚原史訳、ちくま学芸文庫、1992年)166頁。なお、記念碑的な建築を望ましくないと考えたミノル・ヤマサキは、重厚長大なものが粗野なものに転じることを強く懸念していた。彼によれば、建築とはそのマッシブな威容によってではなく、美しい静寂によって評価されるべきものである。ボードリヤールがWTCという二進法のプログラムに見出したのも、このヤマサキ好みの静粛性のもつ反記念碑的な性格だと言えるだろう。
2、情報論的な思想に内在する鏡のテーマ
21世紀のメディアを特徴づけるのは、この鏡のもつ反射性あるいは即時性(第4回参照)である。メディアは人間を模倣し、人間はメディアを模倣する。メディアは人間を利用し、人間はメディアを利用する。メディアが人間であり、人間がメディアである――このめくるめく即時的な反射には内在的な終わりがない。テロで破壊されたはずのツインタワーは、むしろ無限の断片となって、情報環境のなかで再生されたように思える。
ミノル・ヤマサキが世界貿易センターを設計し、ボードリヤールがそのツインタワーを資本主義の肖像と見なした1970年代が、21世紀という「鏡の世紀」の準備期間になったのは確かである。もっとも、この鏡(シミュレーション)のテーマが、20世紀半ばの初期の情報論的な思想にすでに内在していたことにも、注意を向けるべきだろう。
現に、1940年代以降の計算機科学者たちは、人間の思考のシミュレーションを自らの課題としてきた。「われわれが思考するごとく」(ヴァネヴァー・ブッシュ)や「マン・コンピュータ・シンビオシス(人間・機械共生体)」(リックライダー)のような標語は、コンピュータと人間を相互に関連づけようとする彼らの欲望を明示している(※2)。しかも、ブッシュらが機械によって人間の知能をシミュレートしようとするとき、実は人間の知能こそが機械をモデルにして理解されている。つまり、彼らは人間と機械を、お互いを照らす鏡の関係に置いたのである。
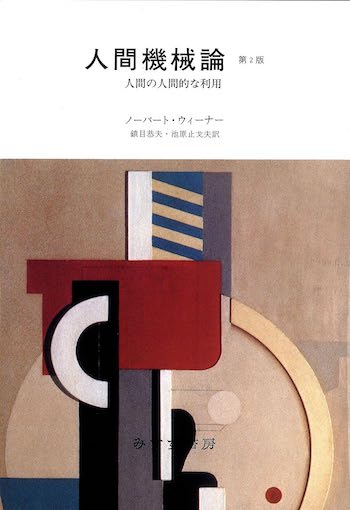
この人間と機械の相互作用を新たな学問分野として確立したのが、サイバネティクスの創始者ノーバート・ウィーナーであった。その主著『人間の人間的な利用』(邦題『人間機械論』/1954年に改訂第二版刊行)で強調されるように、ウィーナーは生命(人間)と機械を区別しない。なぜなら、生命も機械もエントロピー(無秩序)の増大という宇宙の流れに抗して、エントロピーを減少させる組織と秩序を備えた「飛び地」だからである。問題は、この組織と秩序が、いかなるコミュニケーションによって形作られるかにある。
ウィーナーは機械と人間、あるいは機械と機械のコミュニケーション(通信)が今後いっそう増大すると予想した。サイバネティクスとは、このコミュニケーションを工学的に「制御」するための学問である。ウィーナーによれば、サイバネティクスの生み出す秩序は、ファシズムのような強権的で抑圧的なもの、つまり人間を非人間的にがんじがらめにするシステムではない。
それはむしろ、絶え間ないフィードバック(学習)を通じて――つまり人間と機械、あるいは機械と機械がお互いを修正し模倣することによって――、敵意に満ちた環境のなかに「飛び地」を設置する柔軟な情報システムである。ウィーナーはこのフィードバック・システムの作動を、「人間の人間的な利用」という意表をつく言葉で呼んでいた。
生命と機械をともに情報システムとして把握した20世紀半ばのウィーナーのサイバネティクスは、まさに革新的な思想であり、その後のテクノ・ユートピアニズムの核となった。ただし、ウィーナー自身は決して楽観的なユートピア主義者ではなく、あくまでエントロピーの増大を不可避と見なす立場から、滅亡への流れに一時的にでも抗する「飛び地」の役割を、サイバネティクスに期待したのである。人間の生を「難破船」にたとえる以下の厳粛な言葉には、ウィーナーの思想が凝縮されている。
ある意味で確かにわれわれは死を宣告された一惑星上の難破船の乗客である。にもかかわらず、難破に臨んでも人間の体面と人間の価値とは必ずしも全く消滅しはしない。そしてわれわれはそれらを十分重んじなければならない。われわれは滅びてゆくであろう。しかしわれわれはそれをわれわれの尊厳にふさわしいと思える仕方で迎えようではないか。(※3)
ユダヤ系の神童であったウィーナーにとって、この世界には永遠の幸福などは存在せず、エントロピーや死や絶滅を忘れた進歩主義は薄っぺらな虚妄にすぎなかった。しかし、ウィーナーの影響を受けて出てきたテクノ・ユートピアニズムは、むしろこのエントロピーの問題を忘れて、人間の解放と進歩を「鏡」のメタファーを用いながら、留保なく語るようになってゆく。今日のユートピア主義において、人間は難破船の乗客ではなく、安全を確保されたデジタルな鏡=シミュレーションの国の住人として象られているのだ。
※2 ブッシュやリックライダーの代表的な論文は、西垣通編『思想としてのパソコン』(NTT出版、1997年)に収録されている。
※3 ノーバート・ウィーナー『人間機械論 第2版』(鎮目恭夫他訳、みすず書房、2014年)39頁。なお、このウィーナー的な屈折をメタフィクションとして再創造したのが、1960年代のトマス・ピンチョンの小説である。