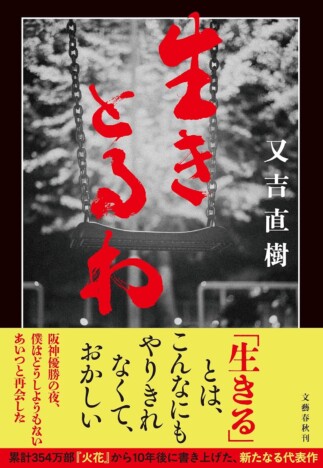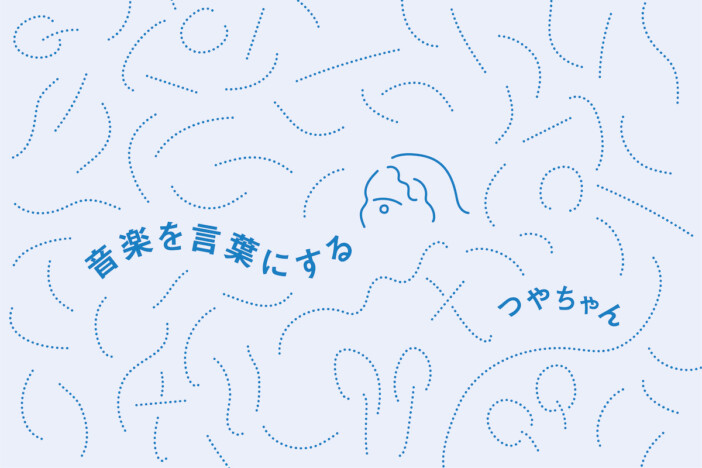結婚しなくても幸せになれる時代、それでも結婚したいのは――『婚活迷子、お助けします。』最終回

婚活迷子、お助けします。 仲人・結城華音の縁結び手帳
橘ももの書き下ろし連載小説『婚活迷子、お助けします。 仲人・結城華音の縁結び手帳』は、結婚相談所「ブルーバード」に勤めるアラサーの仲人・結城華音が「どうしても結婚したい!」という会員たちを成婚まで導くリアル婚活小説。母の干渉から婚活が難航していた〈小川志津子 28歳 通訳〉は、秘密裏で進めていた見合いへの母親の乱入を機に一人暮らしをすることに。自分と向き合ううちに結婚を逃げ場と考えていたことに気づいた彼女は、見合い相手の幸次郎に「今すぐは、結婚できません」と謝罪する。そんな彼女に対して幸次郎が発したのは「僕と、結婚を前提にお付き合いをしてくれませんか?」という真剣交際の申し込みだった。(稲子美砂)
第一話:婚活で大事なのは“自己演出”?
第二話:婚活のためにメイクや服装を変える必要はある?
第三話:成婚しやすい相手の年齢の計算式とは?
第四話:男性はプロフィール写真だけでお見合い相手を決める?
第五話:見合いとは、互いのバックボーンがわかった上で相性を見極める場
第六話:婚活がうまくいかないのは“減点制”で相手を判断してしまうから
第七話:結婚相談所で成婚退会できるのは約3割……必要な努力は?
第八話:婚活迷子に“プロレス”が教えてくれること
第九話:女性に“優しい”と言われる男性が結婚できない理由は?
第十話:成婚できるかどうかは、親との関係性にかかっている?
第十一話:母親が気に入らない相手と結婚しても、幸せにはなれない?
第十二話:「結婚して、今と違う自分になれたら、何かが変わる」は幻想か
これで終わりにするの、もったいないと思いませんか?
志津子とともに「ブルーバード」の事務所を訪れた幸次郎は、華音が想像するよりもしゅっとしていた。ガタイのいい無骨な熊のような印象を志津子の話からは受けていたのだけれど、営業の仕事をしているだけあって清潔感はあるし、目は小さいけれどやわらかく優しい光が宿っている。ぽっちゃりというよりがっちりしているので、不健康な感じもしない。この人ならば志津子を任せられる、とまるで母親のようなことを思いながら、華音は幸次郎に名刺を差し出した。
「結城華音です。本日はお越しいただきありがとうございます」
「田中幸次郎です。こちらこそ、お時間つくっていただき、ありがとうございました。僕の仲人さんもご挨拶したいって言っていたんですけど、あいにく都合がつかなくて……」
「ハッピーマリッジの河原さんですよね。何度かお目にかかったことがあるので、先ほどメールをいただきました。……どうぞ、おかけになってください。今日はお二人の話をゆっくりうかがいたいと思って、時間をしっかり確保しているんですよ」
志津子から、幸次郎と真剣交際に入りたい、という申し出があったのは2週間ほど前。幸次郎と久々のデートをした直後のことだ。真剣交際を決めると他の会員との見合いは一切できなくなるし、仮交際中だった相手にも「交際終了」の知らせをしなくてはならなくなる。さらに、期間は6カ月と限定される。つまり「結婚したいかどうか」ではなく「結婚する」というゴールに向かって本気の調整に入る段階、ということだ。母親との問題がなにひとつ解決していない志津子が、まさかこんなにもすぐ結論を出すとは思っていなかったため、華音だけでなく、所長の紀里谷もさすがに驚いていた。
「所長も絶対同席するんだってうるさかったんですけど、どうしてもはずせない打ち合わせが入ってしまって……。もしかしたら帰り際に、ギリギリ間に合うかも」
「そのかわり今日は僕も同席させていただきます! 幸次郎さん、飲める人って聞いてますけど、お祝いにワインでも開けちゃいます?」
「あなたはまだ仕事が残ってるでしょ! それより紅茶出しなさい」
いつもどおりの賑やかしさで口をはさんだ高橋陽彩をにらみつけると、やはりいつもどおり気にするそぶりはなく、ふざけた調子でへいへーいと答える。来客中の態度としては最悪だが、緊張していた様子の志津子がようやく表情をやわらげたのを見て、まあいいか、と華音は微苦笑を浮かべた。志津子から力が抜けたのを察したのか、隣で、幸次郎も相好を崩す。
「僕たち、まだ成婚退会するわけではないので。これからの半年でじっくりみきわめたいと思っているんです。だから、お祝いはもうちょっと先にとっておいてください」
「皆さんに幸次郎さんをご紹介するのも、まだ早いとは思ったんですけど……。どうしても、結城さんに会っていただきたくて」
言いながら、二人はソファに腰をおろす。
「母のことでご迷惑とご心配をおかけしましたし……いきなり真剣交際ってどういうことだよ、って思ってらっしゃいますよね」
「ええ、まあ」
「私も最初は、この人どうしちゃったんだろうと思ったんです。結婚を前提におつきあいしてくださいって言われたとき。というか、人の話をこんなにも聞かない人だったのかと、ちょっと引きました。ああ、お断りして正解だったのかなあなんて一瞬、思ったんですけど」
「えっ、そうなの?」
「そりゃそうでしょう。あまりにいきなりだったもの」
「じゃあ僕、一瞬でフラれてもおかしくなかったんだな」
「まあ……告白のタイミングとして最適、とは言えなかったと思う」
「そうかあ……難しいなあ」
まるで長年付き合ってきたカップルのような空気感で語りあう二人を、華音はにやつきそうになるのをこらえながら見守る。ティーバッグの紅茶を淹れたカップを陽彩が置いた音で、二人ははっと顔を見合わせたあと、照れくさそうにうつむいた。その初々しさに、華音も、隣に腰かけた陽彩と顔を見合わせ、笑ってしまう。
「……でも幸次郎さん、言ってくださったんです。もったいないと思いませんか、って」
――今のお話を聞いていると、志津子さん、僕のことがいやなわけじゃないんですよね。むしろ、お見合い相手としてはそこそこいい印象をもってくださっている。……僕の、うぬぼれでしょうか?
率直に問うた幸次郎に、いつにない押しの強さを感じて、志津子は思わず「はい」とうなずいてしまったという。そして「ガーン」と効果音が聞こえてきそうなほど悲壮な表情に転じた幸次郎を見て、慌てて訂正した。「いえ、あの。うぬぼれじゃないです。いい印象、っていうか……素敵な人だって、思っています」と。その様子を想像して、華音はまたくすりとする。
はにかみながら、その続きを引きとったのは幸次郎だった。
「今考えれば、確かにずいぶんとうぬぼれたセリフだと思うんですけど。……でも、本心だったんですよね。お互いにいいなあって思ってるのに、これで終わりにするの、もったいなくないですか、っていう。だって……婚活をやっていてそもそも、いいなあって思える人に出会えることがまず少ないじゃないですか」
華音も陽彩も、大きくうなずく。
男女問わず、婚活中の会員からいちばんよく聞く言葉が「ピンとこない」だ。とくべつ不服があるわけじゃない。嫌悪感があるわけでもない。だけどときめかないし、いいなあとも思わない。「悪くない」というだけで、結婚までは考えられない。もしかして好きになれるかもしれない、という希望をほのかに抱いて、なんとなくデートは重ねるものの、決め手に欠けるからだんだん飽いてしまうし、しだいに相手のだめなところばかりが目についてしまって、会うのが億劫になってしまう。
いいなあ、と思えた相手が、同じようにいいなあと思い返してくれる。それは確かに、奇跡的な確率なのだ。
「そう言われて……私も、たしかにもったいないなあとは思いました。でもやっぱり、今は余裕がないんです。母から自立するのに精いっぱいで、幸次郎さんのことを母にちゃんと伝える自信はない。そんなネガティブな精神状態で、幸次郎さんにもちゃんと向き合えるかわからない。そう言ったら……伝えなきゃいいじゃないですか、って言うんです、この人」
「伝えない?」
「あ、今はまだ、ってことですよ。無視して結婚しちゃおうってことじゃないですよ!」
聞き返す華音の声に険がまじったように感じたのか、慌てた様子で幸次郎が首を振る。
「実家暮らしの志津子さんが、お母さんに内緒で僕と会い続けるには、嘘をつく必要も出てくるだろうし、それはきっと心苦しいことでしょう。でも一人暮らしなら、言わずに済ませられるじゃないですか。お互いにいいなあと思っているとはいえ、僕らは会った回数も少ないし、いつだめになるともしれない。だとしたら、最初からお母さんともめるのってあんまり得策じゃないというか……」
言葉を慎重に選びながらも、迷いのない口ぶりで幸次郎は言った。
「まずは、別々に考えたほうがいいと思ったんです。僕とは一から関係を育んでみる。お母さんとは、これまでよりも少し距離をおいた、自立した関係を構築してみる。そのどちらもがうまくいきそうだとわかったとき、初めてひとつの問題として取り組んでみたらどうかなあ、と」
なるほど、とうなずきながらも、華音は意外な思いで聞いていた。志津子から聞いていた幸次郎の内面的な印象は、包容力はありそうだけれど、やや受け身で流れに任せるタイプ。細かいことは気にしないけれど、面倒事に巻き込まれそうになったときは、及び腰になりかねない、と思っていたのだ。だから、志津子が強く言うことにも強いて反論はせず、別れを告げればあっさり引くのではないか、と。
その疑問を表情から透かして見たかのように、「意外でしょう?」と志津子が小首をかしげた。
「こんなふうに熱弁する方だと、私も思っていなかったんですけれど。……その意外性が、また、いいなあって。じゃあちょっと頑張ってみようかな、って自然と思っていたんです。……ううん、ちがうな。ちょっと頑張ってみたいな、って」
「プレゼンが成功してよかった。これでも営業成績は悪くないほうなんですよ」
と、幸次郎はからっと笑う。
「真剣交際といえども、絶対に結婚しなきゃいけないわけじゃない。やっぱりだめだ、と思えば引き返せばいい。そのために仲人さん……結城さんたちがいるわけですし」
「そうっすよ。まちがっても『せっかく成婚しそうなのにもったいない!』とは俺たち言わないです。幸次郎さんの言うもったいないって、そういうことじゃないっすもんね?」
「はい。幸せになれる可能性が少しでもあるならつかみたい、っていうだけです。志津子さんが、僕とじゃ幸せが思い描けないっていうなら、いつでも引き返してもらってかまいません。……そうならないように気をつけますし、できるだけ一緒に幸せになりたいとは思っていますけど」