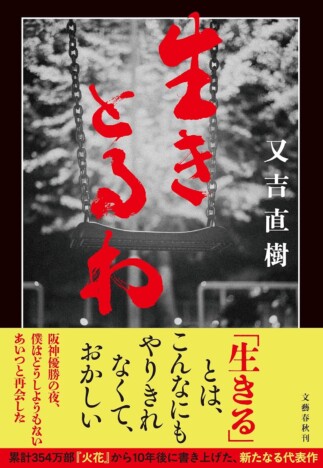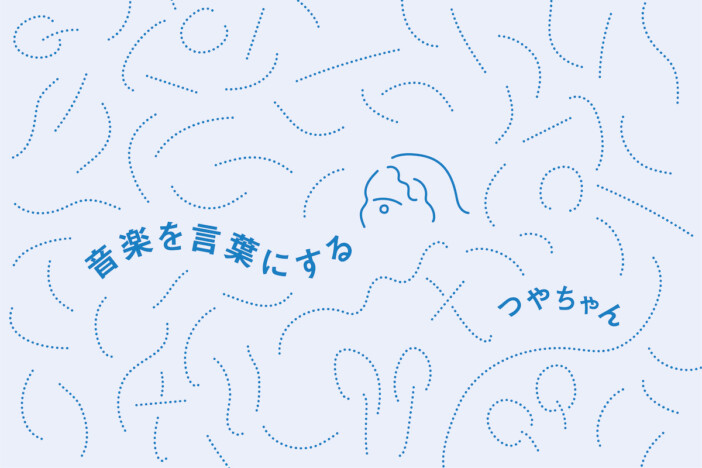見合いとは、互いのバックボーンがわかった上で相性を見極める場ーー『婚活迷子、お助けします。』第五話

婚活迷子、お助けします。 仲人・結城華音の縁結び手帳
橘ももの書き下ろし連載小説『婚活迷子、お助けします。 仲人・結城華音の縁結び手帳』は、結婚相談所「ブルーバード」に勤めるアラサーの仲人・結城華音が「どうしても結婚したい!」という会員たちを成婚まで導くリアル婚活小説だ。第5回は、中邑葉月の初回お見合いの模様を描く。相手は〈笠原友則、35歳。職業、システムエンジニア〉。華音に見送られてホテルのラウンジで笠原と対面した葉月。見合いとは、互いのバックボーンはわかったうえで結婚相手としての相性を見極めていく場なのだ。「これが、婚活……」と彼女に実感させたやりとりとは?(稲子美沙)
第一話:婚活で大事なのは“自己演出”?
第二話:婚活のためにメイクや服装を変える必要はある?
第三話:成婚しやすい相手の年齢の計算式とは?
第四話:男性はプロフィール写真だけでお見合い相手を決める?
いわゆる“恋活”と“婚活”は、ずいぶん様子がちがう
――大丈夫かな、中邑さん。
ラウンジに吸い込まれていく二人の背中を、華音はやや憂いを帯びたまなざしで見送る。中邑葉月は、素直というよりは合理的で、自分の気持ちはさておいて助言をとりあえず聞き入れることができるし、人見知りも物怖じもしないから、仲人としては安心して太鼓判を押せるありがたい会員だ。
けれどだからこそ、心配だった。恋人と別れて間もなく、気丈にふるまってはいるし未練もそれほどないようには見えるけれど、日常に食い込んだダメージは小さくないはず。彼女のように理詰めで考えるタイプは、ときに自分の感情を置き去りにしたまま突き進んでしまい、どこかでひどい揺り返しがやってくることがある。
――私も、そうだった。
いまの葉月と同じ29歳のとき、婚約者と別れたあとのことだ。
感情的にとりみだすのがいやで、つとめて理性的にふるまい、友人の前でも軽く愚痴を言うことはあってもとりたてて泣いたり落ち込んだりすることはなかった。考えても仕方がない。だめなものはだめだったんだから前を向くしかないのだと、ひとりきりの時間でさえ自分の感情に蓋をした。いま思えば、ちゃんと一度発散しておくべきだったのだと思う。胃がなんとなく重たくなり、食欲が失せて、だるさと眠さが抜けなくなった。こんなんじゃいけないと友人と約束をとりつけ、休日は必ず誰かと出かけるようになったおかげで、元婚約者を思い出すまもなく楽しく過ごせていたはずなのに、突然、死にたくなるほどの気鬱に襲われるようになった。あのときこうしていれば。私がこうだったらもしかして。迫りくる後悔と自責に押しつぶされそうになるのを必死ではらいのけながら、華音は少しずつ病んでいった。
救ってくれたのは、意外な人たちだ。
スマホに貼ってあるライオンのステッカーを華音はそっと撫でる。ひとりで立つことの勇気をくれた彼らに、華音は感謝しかない。いつか葉月にもそんな話をしてみたい、と思ったけれど、今はまだそのときではないような気がした。スペックだけ見ればすぐに結婚の決まりそうな彼女も、遠からず壁にぶつかるような気がしてならない。華音が自分のことを話すとしたら、どこにも出口の見えない暗闇で彼女が助けを求めたときだけだ。
特定の会員に思い入れすぎるのはよくない、といつも所長には言われる。会員全員に重すぎる愛をもって思い入れている彼にだけは言われたくないと思う反面、所長のように全員に平等の愛を注げるならば問題ないのだろうな、とも思う。
まだまだ未熟だ。所長のレベルにはほど遠い。
静かに息を吸うと、華音は着席したふたりを確認してきびすを返した。仲人にできるのはあくまでサポート。お膳立てと助言だけだ。結婚に至ることができるかどうかは、けっきょくのところ二人の人間性と相性にかかっている。
*
軽い挨拶をかわして着席した見合い相手・笠原友則を、葉月は失礼にならない程度にこっそり、けれどしっかり観察する。
写真で見た笠原は、新緑を背景に穏やかそうに笑っていた。黒縁眼鏡をはずしたら人ごみで見分けることは難しいかもしれない、という薄い顔立ちをしていたが、もともと葉月はぱっちり二重だったり眉毛が太かったりと、濃い顔立ちの男性はあまり得意ではない。ひょろっと背が高く面長の彼はなんだかキリンみたいだなあ、と安心感とともに好印象を抱いた。会ってみると想像していたよりは少し猫背だけれど、気になるほどではない。
「なに飲まれますか。僕は和菓子セットにしようと思うんですけど」
「そんなの、あるんですか」
「煎茶でもほうじ茶でも好きなのが選べて、小さな大福がついてくるんです。本当は初回のお見合いで食べ物は頼まないほうがいいって言われてるんですけど、中邑さん、甘いものがお好きだってプロフィールに書いてあったでしょう。よかったら、なにか召し上がりませんか」
「あ……ええと、どうしようかな……」
「召し上がって下さったら、僕も頼みやすいです。あ、もちろん、食べながら話すのがいやだったら、僕も今日はやめておくから大丈夫です。仕事場がここから近いので、いつでも来ようと思えば来られるので」
「……じゃあ、私も注文します。パウンドケーキと紅茶のセットにしようかな」
「いいですね! 僕、生ケーキよりは焼き菓子のほうが好きなんですよ」
そう言って、片手をあげて店員を呼ぶと、葉月のぶんも注文してくれる。ずいぶんと慣れた様子だが、婚活をはじめて長いのだろうか。もう何人くらいの女性と会ったのだろうと純粋な好奇がわく。婚活中の知り合いがいない葉月にとって、笠原は見合い相手であると同時に、はじめて出会う同志でもあるのだ。
――よかった。いい人そう。
雑誌やインターネットには、写真と風貌がまるで異なる人がやってきただの、第一声から横柄で相手を気遣うそぶりもなかっただの、ひどい体験談があふれていたので、すこし警戒していたのだ。とくに笠原は、ブルーバードに所属している会員ではなく、ブルーバードと同じ連盟に籍をおいている結婚相談所からの紹介だから、なおさらだった。
お見合いというのは、同じ結婚相談所のなかだけで組まれるものかと思っていた葉月だが、同一連盟に加入している相談所の会員はすべてお見合い相手の対象となるのだと知って驚いた。会員情報はすべてインターネット上で共有され、会員ならば誰でも見ることができる。相手が望んでくれなければもちろん見合いは成立しないが、申し込むだけなら自由だ。何人か条件にあう男性を華音から紹介された葉月は、自分でも気になった人とあわせて5名ほどとりあえず申し込んでみた。そうして最初に了承してくれたのが笠原だったというわけだ。
「中邑さんは、航空会社で働いていらっしゃるんですよね。僕は飛行機に乗るのが得意ではなくて。いつ落ちるんじゃないかとひやひやしちゃうんです。……って、失礼だな」
「いえ、わかります。私もいまだに離陸と着陸の瞬間には慣れません。そういう人、けっこう多いんですよ。笠原さんはシステムエンジニア……なんですよね。なんだかお忙しそうなイメージですけど」
「といっても、小さな専門商社の社内SEなので。それほど納期に追われることもないですし、基本的には定時で帰っています。料理が趣味で、できれば夕食は自分でつくって食べたいんです」
「へえ、すごい」
「煮込み料理とか、得意です。あ、でも、中邑さんのお母さんは料理教室の先生なんでしたっけ。そんな方に自慢するようなことじゃないかな」
「いえ、私は全然。冷蔵庫をあければなにかしらの手料理が入ってたので、親が料理得意だと、かえって子どもはやらなくなるんですよね」
「羨ましいな。でも確かに。僕の母はとにかく料理が苦手でトリッキーな味つけばかりするから、自分でつくるようになりました」
いい感じだ、と緊張感がほどけていく一方、笠原もまた葉月を条件で選んだのだということがひしひしと伝わってきて別の緊張が襲ってくる。華音は、男性はプロフィールを読まないひとが多いと言っていたけれど、なかなかどうして、笠原はしっかり読み込んでいるらしい。
――これが、婚活……。
お互いさまとわかっていながら、これまでのいわゆる“恋活”とはずいぶん様子がちがうことに葉月は戸惑いをおさえきれなかった。ぴんとそろえて斜めに寄せた足、ひざの上においたハンカチ、指先まで気を配りながら飲む紅茶。これほど誰かに「気に入られよう」と思ってふるまうのは初めてだったし、人となりを知る前から自分のバックボーンを知られているのも初めてだった。葉月がそうしたように、笠原もまた、ゆうべ会話のシミュレーションをしてきたのかもしれない。会話のとっかかりを探る必要がないのはとても楽だけれど、見知らぬ人と出会う高揚感は少ない。そのぶん、冷静に自分の心を見定められるのだろうけれど。
――好き、になれるものなのかな。