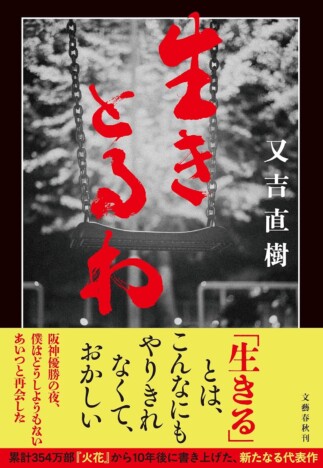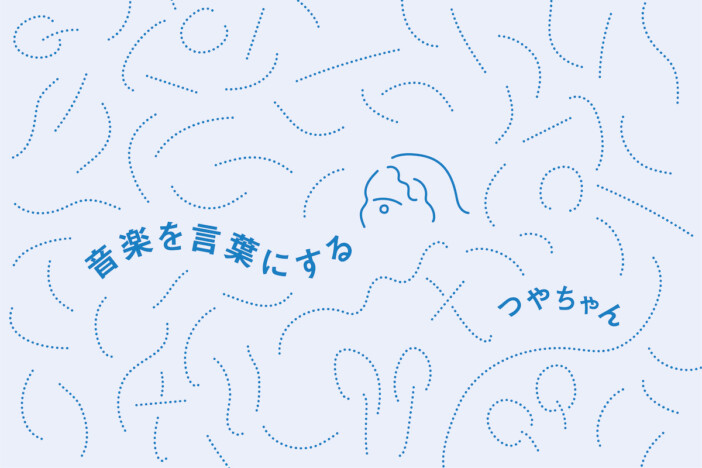母親が気に入らない相手と結婚しても、幸せにはなれない? 『婚活迷子、お助けします。』第十一話

婚活迷子、お助けします。 仲人・結城華音の縁結び手帳
橘ももの書き下ろし連載小説『婚活迷子、お助けします。 仲人・結城華音の縁結び手帳』は、結婚相談所「ブルーバード」に勤めるアラサーの仲人・結城華音が「どうしても結婚したい!」という会員たちを成婚まで導くリアル婚活小説だ。前回、母に幸次郎とのデート現場を押さえられ、ブルーバードからの退会を宣言されてしまった志津子。前進の兆しが見えた彼女の婚活は、ここで振り出しに戻ってしまうのか。第十一回は、そんな志津子を助けるような所長・紀里谷の一言からスタート。(稲子美砂)
第一話:婚活で大事なのは“自己演出”?
第二話:婚活のためにメイクや服装を変える必要はある?
第三話:成婚しやすい相手の年齢の計算式とは?
第四話:男性はプロフィール写真だけでお見合い相手を決める?
第五話:見合いとは、互いのバックボーンがわかった上で相性を見極める場
第六話:婚活がうまくいかないのは“減点制”で相手を判断してしまうから
第七話:結婚相談所で成婚退会できるのは約3割……必要な努力は?
第八話:婚活迷子に“プロレス”が教えてくれること
第九話:女性に“優しい”と言われる男性が結婚できない理由は?
第十話:成婚できるかどうかは、親との関係性にかかっている?
お母さんには敵わない
「まずは、志津子さんお一人とお話をさせていただけますか」
と、ひとしきり母の絢子が話し終わったあとで、静かに口を開いたのは所長の紀里谷だった。片眉をわずかにあげることで不服の意思を示した絢子に、紀里谷はあくまで穏やかに続ける。
「契約や退会に関するお話は、原則、会員様だけとさせていただくことにしているんです。結婚には、もちろんご家族も関わってきますが、個人情報の問題にもなってきますし、何よりこういうことは当人さまのお気持ちが重要ですからね」
そうできるのなら志津子にとってもありがたい話だったが、おまえは関係ねーだろ、と言われたに等しい母が、激昂するのではないかと内心、おびえる。ところが予想に反して、絢子はかすかな息を漏らすのみだった。
「……それはそうですね」
と、同意を示して立ち上がった母の姿に、目を丸くしていると、
「娘もいい歳ですから、親が過度に干渉するのもおかしな話です。そんなことをしなくてもきっと、この子なら自分が何をすべきかわかるはずですもの」
続いた言葉に、志津子はこれまで以上に身体をかたくこわばらせた。それは、つまり、乱暴に言えば(母は決してそんな物言いはしないが)、退会しなかったら後でどうなるかわかってるだろうな?という念押しにほかならなかった。
心臓がぎゅっと締めつけられて、手と足の先が冷えていく。先ほどまでの厳粛な態度はどこへやら、誰もが讃える柔らかな微笑を口元にとりもどした母は、まっすぐ志津子を見下ろした。
「そうよね、志津子」
澄んだソプラノの声に、志津子は思わずうなずいてしまう。
なんて美しいんだろう、とこんなときなのに思った。同時に、どこか打ちのめされたような気持ちになる。――お母さんには敵わない、と。
母は、いつだって美しく、賢く、そして正しかった。今は専業主婦をしているけれど、長兄を産むまで勤めていた銀行でもきっちり丁寧な仕事ぶりは評判で、対しておっとりとした雰囲気をまとわせているそのギャップに落ちない男はいなかった、といつだったか母の友人に聞いたことがある。けれど、たしかに表面的には柔らかくおっとりしている母が、何かの拍子に刻む眉間の皺や、ため息とともに吐き出す静かな怒りの声は、真逆のギャップとして作用する。母が美しければ美しいほど、志津子は母の表情の歪む瞬間がおそろしくてたまらなかった。
産後の肥立ちがわるく、皿洗いさえままならなかった時期もあった母は、心配する周囲をよそに努力を惜しまなかったという。仕事ができなくなったのだからと、子どもたちに常に気を配り、プロ顔負けの料理上手で、家を整えておくことにも余念がなかった。母は、完璧だ。みんなが、褒める。いいお母さんだね、と羨ましがられる。志津子も、いつだって母が誇らしかった。そんな母が怒ったり悲しんだりするのは全部、自分が至らないから、努力が足りないせいだと思っていた。
母の意に背いてまで婚活する意味がどこにあるのだろう、と思う。母が気に入らない幸次郎と仮に一緒になれたとして、そこに志津子の幸せは本当にあるのだろうか。
わからない。何もかも、わからなくなってしまった。
混乱する志津子の視界に、けれど、ちらちらと華音のスマホが写りこむ。拳を握って、激闘に歓声をあげたときのかつてない躍動感が、汗の匂いとともに思い起こされ、心が揺らぐ。
「志津子さんは、どうしたいですか」
紀里谷の声に、はっとする。
志津子はいつのまにか立ち上がり、閉じた扉をぼんやり見つめていた。母を見送ったようなのに、出ていった母の記憶がない。だめだ、こんなにぼんやりしていちゃ、紀里谷にも華音にも失礼だ。と、自分の情けなさに下唇を噛んで、志津子はもう一度、腰を下ろした。
紀里谷は、迷惑そうなそぶりなど微塵も見せず、微笑んでいた。その柔らかさは、母のものとは、すこし違う。
「結城から少し話は聞いています。今日は、久しぶりに田中さんとデートだったんですよね。いかがでしたか?」
「え?」
「根津の和食屋さんで待ち合わせだったんでしょう? 志津子さんのお話を聞いているだけですごくおいしいのが伝わってきた、って結城が興味津々で。素性を隠して僕たちも3人で行こうか、って話していたんですよ」
3人? と首をかしげて、お茶を出してくれた陽彩がうしろに控えていることに気づく。華音との面談に同席してくれたこともある、気さくな若者の姿が、志津子にはまるで目に入っていなかった。事務所に足を踏み入れたときから、志津子は我を失っていたらしい。
紀里谷が心をほぐそうとしているのがわかって、ようやく志津子は小さな笑みを浮かべた。とたんに、目の前に座る華音が、いつものポーカーフェイスを崩して一瞬、泣き出しそうな顔になる。ああ、この人たちは私を心の底から心配しているのだ、と実感すると、鼻先をローズに似たゼラニウムの匂いがくすぐった。先ほどまでより呼吸がしやすくなった気がして、そっと息を吸いこむと、ブレンドしてあるのかかすかにシトロネラの匂いがいりまじる。
「……楽しかったです。お食事はもちろんおいしかったですし、時間もあっという間に過ぎて」
「それはよかった。では、またお会いしたいということで、先方にお伝えしてよろしいですか」
志津子は目をしばたたいた。
どうしたいか、というのは退会するかどうかではなく、幸次郎のことだったのか。さすがに面食らう志津子に、迷いのない口調で紀里谷は言う。
「だって、あっという間に感じたってことは、もっと一緒にいたいってことでしょう? 志津子さんがそんなふうにお相手を好ましく評価するの、初めてじゃないですか。これはもう、日を空けずに会ってどんどんお互いを知っていったほうがいいですね。あ、もう仮交際に進んじゃいます? そうしたら連絡先を交換できるから、電話もLINEもし放題ですよ」
「ちょ、ちょっと所長」
さすがの華音も、困惑した様子で口をはさむが、紀里谷は「え? なに? なにか問題ある?」ときょとんとしている。
……この人はどこまで、本気なのか。
意図ははかりかねたが、志津子は神妙に首を横に振った。
「きっと、田中さんのほうからお断りされると思います。母を見て、めんどくさいなって思われたでしょうから」
紀里谷は、ええーっと大げさに声をあげた。
「そんなの聞いてみなくちゃわからないでしょう。それに、そんなことで引くような男は、こっちからお断りですよ。志津子さんにとって大切なご家族の問題を、たった一度お母さんに会っただけでめんどくさがるような男と、この先の人生をともに歩めるとは思いませんからね。結婚生活なんて、面倒の連続なんだから」
「あの、ですから所長。いまお話しすべきは、そのお母さまのことなのでは……」
そう言う華音に、うしろで陽彩もうんうんとうなずいていたが、
「どうしてよ。志津子さんの結婚だよ。まずは、志津子さんが田中さんを気に入ったのか。気に入ったならどうしたいのか。お断りするならするで、次はどんな人に会いたいのか、聞くのが何より大事でしょう?」
と、紀里谷はやはり断固とした口調で言う。「でも……」と食い下がる華音に「でもじゃない!」とぴしゃりと言い放ち、
「僕はまだ、志津子さん本人の口から、退会したいって言葉を聞いていません。志津子さんからその申し出を受けていない以上、外野が何を言っても聞くつもりはありません」
と、志津子に向き直った。
瞼の裏が、熱くなる。何か言わなきゃと思うのに、言葉にならない。
「もちろん無理強いするつもりはないし、今日のデートが楽しくなかったというなら話も変わってくるけれど……。時間を忘れるほど一緒にいて楽しい相手と出会えたのに退会したいなんて会員さまに、僕は会ったことがないからなあ」
「そりゃ……そうかもしれませんけど……」
あまりに話の進め方が強引だ、と華音の顔には書いてある。志津子もそう思う、が、その強引さが先ほどまで志津子の心にのしかかっていたものを軽くしてくれたのは確かだった。
「景気づけに酒でも飲みます?」
と、妙に華やいだ声で口をはさんだのは、陽彩だった。
「こういうときはちょっと強めの酒でも入れると、気分がすかっとして、いろんなことがどうでもよくなりますよ」
「どうでもよくなっちゃだめでしょ!」
と、顔色を変えたのはやっぱり華音だ。
「だいたい、事務所に強い酒なんか」
「それがあるんですよー。俺のとっておき、アランモルトの21年。なんか祝い事でもあったときにみんなで飲もうと思って……」
「職場に酒を持ち込むんじゃない!」
「もー、2人とも今はそんな話をしているときじゃないでしょ。志津子さん、困ってるじゃないの」
コントのような3人のやりとりに、志津子はだんだん、先ほどまで母がいたのは幻だったんじゃないかとさえ思えてきた。あれほどぴりついて深刻だった空気が、すっかり霧散してしまっている。問題は何も解決していないのに、どうにかなるような気さえしてきてしまう。
その想いが表情に出ていたのか、陽彩が志津子を見て、にっと笑った。
「はちみつみたいな香りがして、ウイスキーに慣れてない人でも飲みやすいですよ。ちょっと試してみます?」
「高橋! いいかげんにしないと、あんた」
「いやーでもさあ、ねーさん。実際問題、どうでもいいって思うくらいじゃないと、志津子さん、前に進めなくね?」
と、陽彩は肩をすくめた。
「あのお母さんを説得とかまじむりでしょ。志津子さんはとくに。だったらさ、田中さん……じゃなくてもいいけど、自分が結婚したい相手か、お母さん。どっちかを諦めてふりきるしか、志津子さんに道はなくね?」
綿あめみたいに軽いのに、ぐさりと刺さるその言葉に、志津子の身体に抜けていたこわばりが戻ってくる。幸次郎か、母か。どちらかしか選べないのだとしたら、母を選ぶのが道理だと志津子は思う。あんなに自分を案じてくれる母を、自分勝手な我儘で裏切れるはずがない。そう言おうとしたそのとき、
「でもさー志津子さん。お母さんの言うこと聞き続けて、それで未来永劫、お母さんを恨まないって断言できる?」
甘い笑顔で、容赦なく、陽彩は聞いた。
「自分の不幸とか満たされなさを、絶対お母さんのせいにしないって誓える?」
その言葉に、撃たれたように硬直したのは、志津子だけではなかった。華音もまた、釣りあげていた眉を下げて、まじまじと陽彩を見つめている。陽彩は、何かを思い出したように口をへの字に曲げた。