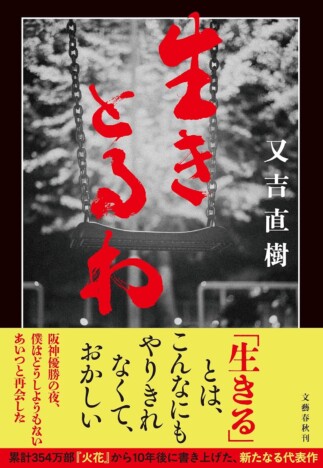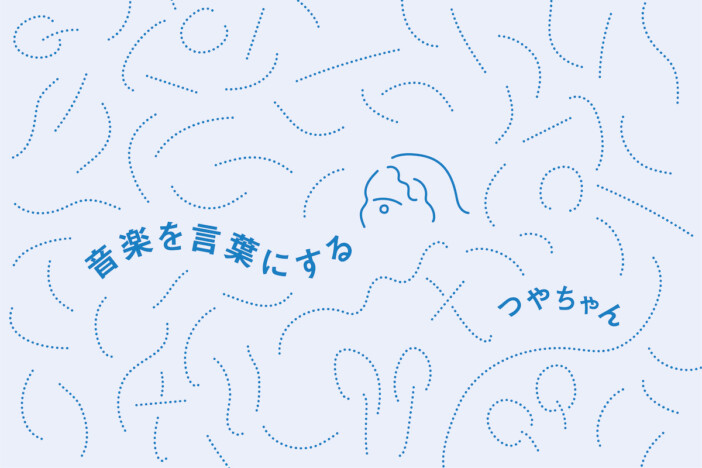婚活迷子に“プロレス”が教えてくれることーー『婚活迷子、お助けします。』第八話

橘ももの書き下ろし連載小説『婚活迷子、お助けします。 仲人・結城華音の縁結び手帳』は、結婚相談所「ブルーバード」に勤めるアラサーの仲人・結城華音が「どうしても結婚したい!」という会員たちを成婚まで導くリアル婚活小説だ。第8回は、何回見合いをしても母親の評価を気にして交際に進めない小川志津子を、華音がある場所に誘う。そこは、かつての華音に自らの結婚をちゃぶ台返しする勇気をくれた場所――この“ちゃんとした結婚”で、私は幸せになれるのか――周りの大反対を押し切って破談を選んだその胸中にあったのは?(稲子美砂)
第一話:婚活で大事なのは“自己演出”?
第二話:婚活のためにメイクや服装を変える必要はある?
第三話:成婚しやすい相手の年齢の計算式とは?
第四話:男性はプロフィール写真だけでお見合い相手を決める?
第五話:見合いとは、互いのバックボーンがわかった上で相性を見極める場
第六話:婚活がうまくいかないのは“減点制”で相手を判断してしまうから
第七話:結婚相談所で成婚退会できるのは約3割……必要な努力は?
よろしければ一緒にプロレスを観に行きませんか
その場にいるだけで額に汗が滲みそうな会場を包みこむ熱気は、残暑のせいだけではないと志津子は思った。客席数2000人程度の後楽園ホールには、酒と煙草、それからときどき揚げものの匂いが漂ってくる。といっても居酒屋ほどではないはずなのに、場を支配する高揚感はその比ではなかった。
かたくひんやりした座席は小さくて、小柄な志津子でも座っているだけで隣の人と肩がぶつかってしまう。黒いTシャツを着て、なにやら楽しげに連れと論議をかわすガタイのいい男の、柔らかいやや汗ばんだ肩が触れたときはびくりとしたが、時間が経つうちにだいぶ慣れた。
――私、なんでこんなところにいるんだろう。
物珍しさにあたりをみまわしていると、レモンサワーをふたつ手にした華音が戻ってくる。志津子の隣に腰かけた彼女からはふんわり金木犀の香りがする。場違いのような気がするけれど、よく見れば会場には華音や志津子のような年頃の女性も少なくなく、隣の男同様に黒いTシャツに首まわりをタオルで巻いた人もいれば、表参道を歩くようなワンピースを着ている人もいた。
自分はこの場からひどく浮いているのではないか、そんなちゃらちゃらした格好で来てんじゃねえよと誰かから怒られるのではとびくびくしていた志津子だが、どうやら何も気にしなくていいらしい、と知ってほっと息をつく。大画面に流れ続けている、プロレスラーとおぼしき人たちのマナー紹介動画も、どこかひょうきんで心が和んだ。
「すみません、急に誘ってしまって」
志津子にレモンサワーを渡した華音が、乾杯を誘うようにプラスチックカップを傾ける。ありがとうございます、とカップに自分のそれを静かに重ねると、二人で一気に咽喉を潤した。緊張のせいか、炭酸がいつもより沁みる。
――小川さま、このあとはお時間ありますか。
面談していたホテルで、田中さんに会いたい、と涙ぐんだ志津子に、華音はややあって唐突に聞いた。とくに用事はありませんが、とか細く答えると、
――では、もしよろしければ一緒にプロレスを観に行きませんか。
華音はずいと身体を前のめりにして言ったのだった。
はあ、と漏らしたのは了承の意ではなく、この人はいったい何を言っているんだろうという呆けた息だったのだけど、華音はにっこり笑って、決まりですねとさらに勢い込んだ。
「よくご覧になるんですか、プロレス」
2口め以降はちびりちびりと舐めるように志津子がレモンサワーを飲む横で、華音は咽喉を鳴らしてカップの中身をあけていく。仲人としての華音はいつも冷静で、感情の揺れを大きくみせることがないので、あけすけに見せられる豪快さは新鮮だ。
でも、意外ではなかった。思いきりがよくて、他人に依存しない。きっと華音は常に自分の足で、自信をもって歩いてきた人なのだろうと思っていたから。だから、意外だったのは、彼女もまたかつては自分の母親に縛られて、ちゃんとした結婚をしなければならないと思っていたということだ。その後、やってられるかと元恋人にみずから婚約解消を申し出たというのは、さすがだけれど。
――いつも受け身の私には、そんな度胸、きっとない。
母が自分にばかりあれこれ指示するのも無理はない、と志津子は思っていた。兄や姉は優秀であるばかりでなく、自立心がある。母は基本的に規範意識が強く、しきりたがりなところがあるから、何かにつけ彼らにもあれこれ口を出してきたけれど、兄は「はいはい」と聞いている顔をしながら適当にいなし、要領よく自分の望みを叶えてきたし、姉は「もうお母さんはうるさいなあ」とからっと笑って、あとくされなく家を出た。
いつまでも小さな末っ子という扱いが抜けなかったせいもあるけれど、内向的で、人付き合いが器用ではなく、何事も決断するのに時間がかかる志津子を、母を筆頭に家族はみんないつも心配していた。母たちの言うとおりにしておけば何かを大きく間違えることはなかったし、自分の望みと多少違っていたとしても、反対を押し切ってまで我を貫くほどの気概は志津子にもなかった。心配による干渉が、いつしか束縛と支配に変わっていったのは、だから、自分のせいもあると志津子は思っている。意見が食い違ったとき、どう抗っていいのかわからないのは、その訓練を自分が怠ってきたからだと。
――結城さんみたいに、強くなれたらいいのに。
羨望、というよりはやや嫉妬のこもった視線を、華音に向ける。誰かに決めてもらうばかりの志津子の人生は、華音からはどう見えているのだろうと、いまさらながら不安になる。
「……そういえば、今日はどなたかご一緒するはずじゃなかったんですか。大丈夫だったんですか」
スマホで調べてみたら、チケット代は一人あたり約5000円。決して安くはないはずなのに、強引に誘ったのだからと支払いはかたくなに固辞された。当日券も販売してはいるものの、キャパシティは大きくないし、今日の出場者の人気が高いせいですぐ売り切れてしまったらしいこともわかった。後方の端っこ、とはいえ、プロレスのルールもわからない志津子が座っていていい席ではないのでは、と思ったのだが、
「全然、大丈夫です」
と華音は力強く断言する。そして空になったカップを、蹴飛ばさないように椅子の下にそっと置いた。
「一緒に来るはずだった人も、しづこさん、っていうんですよ」
「え?」
「紀里谷静子さん。所長のお母さまです」
「あ……一度だけ、事務所でお目にかかったことがあります。お歳をうかがって驚きました。とても溌溂とした方で、二十くらい若くみえたので」
同じ名前なのに、佇まいから何から何までずいぶんちがう。と、あのときも志津子は軽い嫉妬を覚えて、すぐに打ち消したのだった。羨むな、比較をするな、自分が何もしていないのを棚に上げて他人の功を妬むほどみっともないことはない。――それもまた、母の教えだった。もっともだ、と志津子も思う。
「きっと喜ぶので伝えておきます。じつは私、この後楽園ホールで静子さん……ええと、紀里谷さんに出会ったのがきっかけで、ブルーバードに入ったんですよ」
「ええ?」
どういうことか、と聞こうとしたそのとき、爆音とともに会場中に音楽が流れはじめた。と同時に、過去の試合とおぼしき動画が流れはじめ、レスラーたちの咆哮と技が画面から飛びださんばかりの勢いで迫り、観客が歓声にわきたった。
「初心者にも親切なんで、動画をみていればなんとなく流れもわかると思います。気になることがあったらいつでも聞いてください」
囁く華音の瞳も、らんらんと輝いている。聞きたいことはいろいろあったけれど、すべてのみこんで、志津子はこくりとうなずいた。