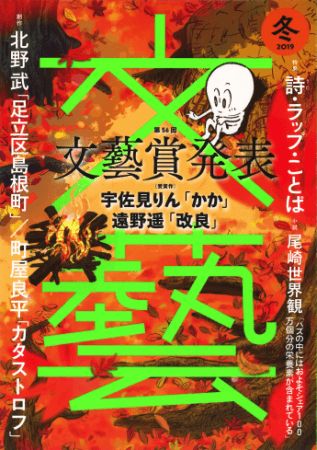純文学雑誌は転換期を迎えているーー『文藝』リニューアル成功が浮き彫りにした重い課題

先に触れた通り、純文学雑誌で他のカルチャーをとりあげることは、かなり以前から行われてきたわけだ。しかし、「文学と○○」とする構図はいつまでたってもなくならない。他のカルチャーと融合しきれない境界線が、純文学にとっての聖域がある風なのである。それは、人間を深く描くことかもしれないし、エンタメ小説にはない実験かもしれない。とにかく純文学なる領域は、特有の良識や知が、あるかのごとくふるまっている。
とはいえ、純文学雑誌を発行する出版社が、偏見に満ちたヘイト本も出していたりする。2018年に杉田水脈や小川栄太郎のLGBT差別を助長する論を『新潮45』が載せ、問題になった(後に休刊)。その際、同じ新潮社発行の『新潮』は、『新潮45』に対する小説家たちの批判を載せた。また、『新潮』2018年12月号の「差別と想像力」特集、『文藝』の「韓国・フェミニズム・日本」特集は、書店に中韓ヘイト本が多く並ぶ残念な現状に抗う姿勢を示したものでもあった。
フェミニズム関連では以前にも『早稲田文学』(早稲田文学会発行)が2017年に川上未映子責任編集の増刊で女性号を制作し、『すばる』が2018年5月号で「ぼくとフェミニズム」特集を組んでいる。それらは現実社会での女性差別を踏まえたものだった。だが、文芸批評家で純文学雑誌に寄稿していた渡部直己が、早稲田大学の指導教員の立場を用いて女性へのセクシャル・ハラスメントを行っていたと報じられ、同年7月に教職を解任されたのだ。同問題の報道では、渡部も執筆していた『早稲田文学』の編集に携わってきた人物の学内対応の不適切さも指摘された。
この件に関し同誌は、関係者による口止めはなかったとする声明をホームページに出した。批評家でもある疑惑をかけられた関係者がこの件を語ることはなく、経緯が明らかになったとはいえない。女性差別が純文学の外の問題ではなく、業界内部の問題でもあったと印象づけたのである。その後に『文藝』が韓国文学の特集でフェミニズムのテーマもとりあげたのは、早大の問題を直接対象にしたのではないにせよ、業界へのメッセージを含んだものと私は受けとった。
それだけに、しばらく刊行が停滞した後に2019年冬号でリニューアルして発行された『早稲田文学』が、「ポストフェミニズムからはじめる」と題した特集を行ったのには違和感を持った。先の問題をどうとらえ「ポスト」「はじめる」としたのか、疑問が残る。
純文学をめぐっては、第61回群像新人文学賞を受賞して『群像』2018年8月号に掲載され、芥川賞の候補にも選ばれた北条裕子『美しい顔』の騒動もあった。東日本大震災を扱った同作では、被災者に取材した複数のノンフィクション作品を下敷きにした表現が散見されるのに、参考文献を記載しておらず、無断流用と批判された。作者は謝罪のうえ、単行本化では多くの修正を加えている。こうしたことがあったのだから、ルポなどを増やすという今回の『群像』リニューアルは、フィクションとノンフィクションの言葉のありかたをあらためて考えるものになるべきだろう。
一方、小説より実用的な文章を読ませる方向に国語教育を改革しようとする動きが現実化している。それに対し、『文學界』2019年9月号は「文学なき国語教育」を批判する特集を掲載した。小説の側からの防戦である。
出版界の商売の種になっているヘイト、業界内にもある差別、国語教育改革、そして出版不況など、自分たちの基盤にかかわる問題にとりまかれながら、他のジャンルとは違う文学特有の領域があると示さなければならない。この課題が従来以上にシビアになっていることが、特集主義に結びついてもいる。デザインのポップ化や内容のバラエティ化に注目しがちだが、転換期を迎えた純文学雑誌は、重いものを背負っているはずなのだ。
■円堂都司昭
文芸・音楽評論家。著書に『エンタメ小説進化論』(講談社)、『ディズニーの隣の風景』(原書房)、『ソーシャル化する音楽』(青土社)など。