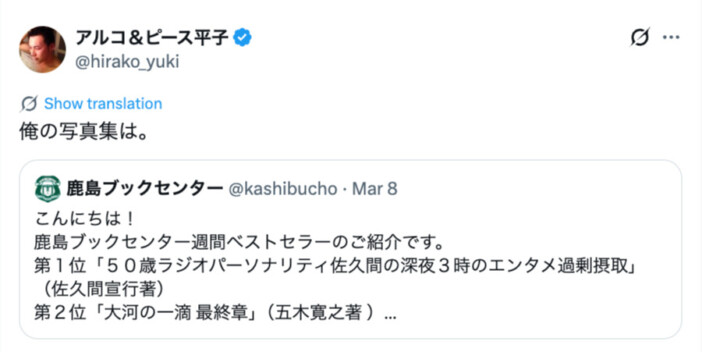大槻ケンヂ、小泉今日子、酒井順子……2026年に還暦を迎える注目の世代「1966年生まれ」の生き様

人口では“少数精鋭”の1966年生まれ
「え? あの人がもうそんな年齢」――ニュースを目にして、こう思うことはよくあるだろう。2026年には1966年生まれの人々が還暦、すなわち60歳を迎える。同年生まれの著名人は故人も含めて幅広い、たとえば以下のような人々がいる。
【ミュージシャン】
大槻ケンヂ(筋肉少女帯)、トータス松本(ウルフルズ)、櫻井敦司(BUCK-TICK)、吉井和哉(THE YELLOW MONKEY)、スガシカオ、高橋洋子、永井真理子、中村あゆみ、渡辺美里
【歌手・俳優ほか芸能人】
髙嶋政伸、永瀬正敏、東山紀之(元少年隊)、薬丸裕英(元シブがき隊)、小泉今日子、斉藤由貴、早見優、安田成美、江角マキコ、松本小雪、国生さゆり(元おニャン子クラブ)、高井麻巳子(元おニャン子クラブ)
【スポーツ関係】
長嶋一茂(野球選手)、佐々木健介(プロレスラー)
【アニメ関係】
大張正己(監督:代表作『勇気爆発バーンブレイバーン』)、谷口悟朗(監督:代表作『プラネテス』『コードギアス 反逆のルルーシュ』)、冬馬由美(声優)、冨永みーな(声優)、皆口裕子(声優)
【漫画家】
冨樫義博(代表作『幽☆遊☆白書』『HUNTER×HUNTER』)、三浦建太郎(代表作『ベルセルク』)、すぎむらしんいち(代表作『サムライダー』『右向け左!』)、森川ジョージ(代表作『はじめの一歩』)、山口貴由(代表作『覚悟のススメ』『シグルイ』)、山田玲司(代表作『Bバージン』『絶望に効くクスリ』)、森田まさのり(代表作『ろくでなしBLUES』)、モリナガ・ヨウ(代表作『築地市場 絵でみる魚市場の一日』『ワールドタンクタンクミュージアム全集』)
【文化人】
酒井順子(エッセイスト:代表作『負け犬の遠吠え』)、佐藤健志(作家:代表作『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』)
――彼ら、彼女らが生まれた1966年とはどんな年だったのか? 時の総理大臣は佐藤栄作、日本の人口が1億人を突破、東京都内で初のコインランドリーが営業開始、明星食品がインスタントラーメンの「チャルメラ」を発売、集英社が『週刊プレイボーイ』を創刊、『週刊少年マガジン』で漫画『巨人の星』が連載開始、テレビで『ウルトラマン』が放送開始、ビートルズが来日して初めて武道館で公演……といった年だ。
そして、この年は干支が丙午(ひのえうま)の年だった。この「ひのえうま」に関しては、関連記事の「2026年の干支「ひのえうま」の迷信はいつ生まれ、どんな影響を与えたのか?」を参照して頂きたい。「ひのえうまの年に生まれた女性は気性が荒く、夫を食い殺す」という謎の迷信のため、1966年の出生数は136万974人で、前年よりじつに46万人以上も少ない。そのためか仲間意識が強いようだ、大槻ケンヂ、スガシカオ、小泉今日子らは、同年生まれが一堂に会するライブイベントの「ROOTS66」を10年周期で開催している(2026年は3月20月、3月22日に開催)。
「机SNS」で交流した大槻ケンヂ

それでは、1966年生まれはどんな世代体験を経て、60歳を控えた現在にいたったのだろうか? ひとつの参考例になるのが、大槻ケンヂが自分の半生を記した『サブカルで食う 就職せず好きなことだけやって生きていく方法』(角川文庫)だ。
幼児期は身体が弱かった大槻は、よく病院に行かされ、そこで石ノ森章太郎の『スカルマン』(『仮面ライダー』の原形となったダークヒーロー漫画)や、ジョージ秋山の『アシュラ』(戦乱で荒廃した中世の日本が舞台で、ショッキングな人肉食シーンもある)や、『銭ゲバ』(金のためあらゆる悪事を働く男が主人公のピカレスク漫画)といった作品に出会い、怖がりながらも読みふけったという。
大槻といえば心霊やUFOといったオカルト趣味で知られるが、彼が小学校に入った頃の1973年には、五島勉『ノストラダムスの大予言』(祥伝社)が刊行され、米ソ冷戦下で危惧されていた核戦争、公害、第1次オイルショックに端を発するエネルギー危機、人口爆発による食糧危機などの恐怖が叫ばれていた時期だ。それを反映して、子ども向けのメディアもダークな世界観の作品が少なくなかった。
そんな空気の中で育った大槻少年は、小説では江戸川乱歩、ヘミングウェイ、橋本治、漫画では諸星大二郎、大島弓子、萩尾望都、竹宮恵子、山岸涼子などを濫読した。小学校6年生となる1978年、大人びた友人を介してKISSとエンジェル(アメリカのグラムロック系バンド)を教えられ、ロックと出会い、映画では『ゾンビ』(1978年)、『狂い咲きサンダーロード』(1980年)など、大量の作品を視聴した。
――と、ダークなサブカルを愛好した大槻少年だが、何しろネットのない時代だから、同行の士を見つけるのは大変だった。マイナーな趣味を持つ少年少女はクリアファイル型の下敷きに雑誌の切り抜きなど自分の好きな物を入れたり、机に漫画のキャラクターを描いたりして、自分の好みを人目に付くようにアピールして周囲の反応を待ったという。これを大槻は「机SNS」と呼ぶ。
中学校に入った1979年、のちの筋肉少女帯ベーシストとなる内田雄一郎と出会い、一緒に漫画を描いていたが、漫画は地味なので、もっとパッとした表現活動をやりたくなってバンドを結成。これは同時期に流行していたヒカシュー、プラスチックスといった、演劇的なギミックを凝らしたり、文学・歴史・映画・漫画などを楽曲のモチーフに用いたニュー・ウェイヴの影響だという。
青春はバブル絶頂期のバンドブーム
ネットがなかった1980年代当時、ロック少年にとってレコード屋とライブハウスに直接足を運ぶことが、知らない楽曲や新しい友人との出会いと交流の場だった。東京都中野区出身の大槻は、杉並区高円寺のレンタルレコード屋に通い詰める。江戸アケミのじゃがたらや遠藤ミチロウのザ・スターリンに憧れたが、実際に対バンするまで、怖くてそれらのライブには行けなかったという。当時の遠藤は、客席に放尿したり豚の頭を投げつけるといった過激なパフォーマンスで知られた、ロック好き、サブカル好きの間では、直に見たことはなくても伝説が独り歩きして広まるという時代だ。
同世代で、ロックではなくオタクジャンルの若者ならば、出会いと交流の場は、漫画専門書店、ゲーセン、模型店、画材屋、各地の同人誌即売会といったところだろう。
1982年、大槻は高校生にしてナゴムレコードからインディーズデビュー。以降はバンドにかまけて学校の勉強はほとんどやらず、大学受験に失敗して日本デザイナー学院に入学、その後、東京国際大学に入るも中退。時は1980年代後半、バブル景気に向かうなかでリクルートが「フリーター」という新語を作り、若者向けのマスメディアでは、就職せずに好きなことをする自由な生き方が新しいと報じられていた頃だ。
バンドブームが広がるなか、1988年に筋肉少女帯はアルバム『仏陀L』でメジャーデビュー。陰キャ少年からお茶の間の有名人となった大槻は、2020年代の推し活に劣らぬ過激なファンのバンギャに囲まれてモテまくった。だが、バンドブームが終息した1990年代中期以降はしだいに低迷し、所属事務所も経営破綻、精神を病むなかで1998年に筋肉少女帯は活動休止。ただし、一方では小説家として、『新興宗教オモイデ教』『グミ・チョコレート・パイン』などの作品を次々と発表する。
その後も音楽活動は続け、2006年に筋肉少女帯が復活。続いて、2007年にはアニメ『さよなら絶望先生』の主題歌をオファーされる、まさにニコニコ動画のサービス開始と時期が重なり、OP動画は何十万回も再生され、ファンによる二次創作動画も次々と広まった。数々のアニソンイベントにも呼ばれ、その盛り上がりには驚いたという。2009年にはアウェー感を覚えつつもフジロック・フェスティバルに参加して成功を収める。新しいファン層を獲得した大槻は、音楽や著述のほか、映画出演や声優まで務めるようになった。今や、いわば陰キャの若者たちの大先輩といった立ち位置だろう。
『3年B組金八先生』に熱中した小泉今日子

それでは、同じ1966年生まれで、女性の場合はどのような感じだったのだろうか。
一例を挙げると、別冊太陽の『小泉今日子:そして、今日のわたし』(平凡社)によれば、小泉今日子が子供の頃に好きだったヒーローとヒロインは、『突撃! ヒューマン!!』(1972年)で夏夕介が演じたヒューマン1号こと岩城淳一郎(体育の先生という設定)と、『魔法のマコちゃん』(1970~1971年)の浦島マコ。初めて買ったレコードはずうとるび、好きだったドラマ主題歌は、沖雅也主演の『俺たちは天使だ!』(1979年)の「男達のメロディー」(SHŌGUN)といった具合だ。
また、小泉のエッセイ『黄色いマンション 黒い猫』(スイッチ・パブリッシング)には、一時的に親元を離れてアパート暮らししていた中学2年生のころ、『3年B組金八先生』(1979年)に熱中したと記している。出演者たちは同世代で、それまでの「青春バンザイ」的な学園ドラマではなく、校内暴力や中学生の妊娠といったリアルな内容を、「他人事とは思えない気持ち」で観ていたという。
そんな小泉、1981年に15歳で日本テレビの『スター誕生』に出演して合格。テレビの影響力が絶大だった当時、オーディション番組からのデビューはアイドルの王道だった。この直後に高校に入学するも、父親と教師の判断でいつの間にか退学、16歳で一人暮らしをしながらスターダムを駆けのぼる。
1984年にはNHKの紅白歌合戦に初出場。翌年には『なんてたってアイドル』が大ヒット、アイドルがみずからアイドルを語るこの曲のように、半分楽屋を見せて観客との共犯的なノリを作り出すのが1980年代の新しい流行だった。この手法が如実だったのが、同時期に人気を博したおニャン子クラブだ。また、小泉もパーソナリティを務めたニッポン放送の「オールナイトニッポン」に代表される、1980~90年代の深夜ラジオ番組は、出演者がプライベートを語って素の顔をさらす一方、リスナー投稿を積極的に取り上げ(自分の名前を読んでもらえる)、テレビよりも観客との距離感が近いことが売りだった――この感覚、2020年代のVtuberとその観客の関係性にも似てるのではないか。
1990年代に入ると、小泉は歌手より女優としての活躍が目立つようになる。ことに2013年のNHKドラマ『あまちゃん』では、能年玲奈演じる主人公の母親役(元アイドルという設定)で円熟した演技を見せ、すっかり大人らしい貫録と深みを示した。
ネット以前、雑誌も交流の場だった
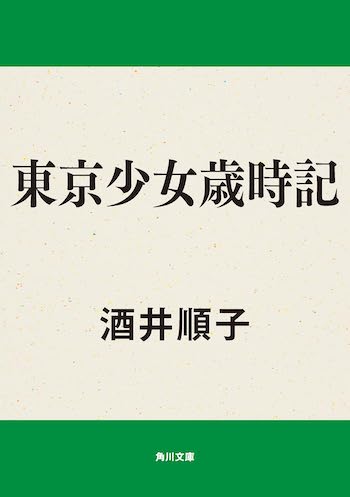
女性の例をもう一人挙げると、酒井順子は『東京少女歳時記』(角川文庫)で、10代~20代当時の記憶を数多く記している。高校時代、雑誌の『POPEYE(ポパイ)』と『Olive(オリーブ)』(マガジンハウス)を愛読し、泉麻人の影響を受けて『Olive』に投稿したものが採用されたことから文筆の道に入った。そう、ネットがなかった当時、先にふれた深夜放送ラジオのリスナー投稿と同じく、雑誌投稿もアマチュア参加による若者の表現と交流の場だった。彼女が最初に投稿したのは、女子高生自身による女子高生のタイプ分類だったという、あるあるネタだろう。
また、酒井の「誇り」の一つは、立教女学院中学校・高等学校の出身なので、ユーミン(松任谷由実)の後輩であることだという。ただし、本格的にユーミンの歌に目覚めたのは、大学に入り恋愛経験を重ねるようになってからだ。酒井の大学生時代ならば、バブルに向かう1980年代中期、まさにユーミンの全盛期だった。
吉川徹『ひのえうま 江戸から令和の迷信と日本社会』(光文社)には、酒井が2023年に『読売新聞』の記事で、「私自身は丙午(ひのえうま)だから嫌な思いをしたことはない」と述べたことが引用されている。実際、上記の1966年生まれの女性の著名人には、スキャンダルを報じられた者もいるけれど、それをひのうえまと結びつけた誹謗は、さすがに1980~1990年代でもほぼない。
***
今回ここに記したのはほんの数例だが、2026年を迎えるにあたり、60年という時間を意識しつつ、以上に挙げた1966年生まれの人々の著作、楽曲、出演作などに触れてみるのもまた一興だろう。(文中敬称略)