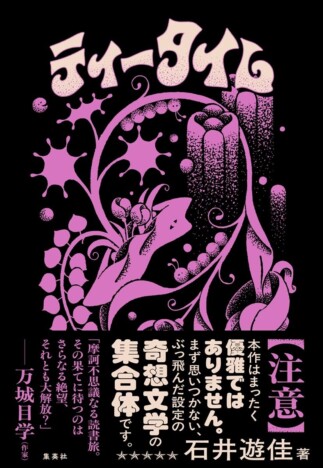杉江松恋の新鋭作家ハンティング 芥川賞候補作『BOXBOXBOXBOX』の美点

ページをめくるたびに感心し、ページを閉じてまた感心した。
第62回文藝賞受賞作の『BOXBOXBOXBOX』(河出書房新社)は坂本湾のデビュー作だ。1999年生まれ、まだ20代という若い才能が世に出たことを心より歓迎する。本作は第174回芥川龍之介賞の候補作にもなっている。
舞台となるのはとある宅配所である。ベルトコンベアに載って運ばれてくる大小さまざまな箱を仕分けする作業が延々と続く。宅配所の中には時折声が響く。スピーカーが天井に等間隔で取り付けられており、放送担当の社員が仕分けの間違いを発見すると、ここぞとばかりに罵声を浴びせるのである。ベルトコンベアに貼り付けられた作業員たちは、初日にまず、その声を無視することを教えられる。
視点人物が四人準備されている。彼らが順番に紹介されていくのが小説の序盤だ。一人は共稼ぎだった妻が重い病を発したために一人で家計を支えなければならなくなった中年男の斉藤だ。彼は作業か、もしくは自分の人生そのものから目を逸らすために酒を飲んでいる。宅配所のロッカーに預けた荷物の中にはウイスキーの350ml瓶が入っていて、それに口をつけてから斉藤は仕事をする。
新人の稲森は宅配所で働き始めたばかりである。本当はもっと別の仕事をしたかったのだが、選択肢がなくてやむをえず宅配所にいる。そんな彼女のスマートフォンには不採用を告げる人材派遣会社からの慇懃なお祈りメールが届く。ベルトコンベアを蹴りながら作業を続ける稲盛は膝の痛みを訴えるようになる。稲盛と同じ女性の神代は、作業を管理する立場だが身分は契約社員である。面倒な事態が頻繁に起きることが彼女の心身に影響を及ぼし、複数の服薬が欠かせなくなっている。
三人と比べて記述の非常がやや大きいように見えるのが、男性の安だ。坂本湾のwanという音にanは含まれるので、視点の主務という意味を背負っているのかもしれない。ただし安には特権的な役割は与えられておらず、他の者たちと同様に作業所のベルトコンベアに貼り付けられている。
安の中では抑えがたい思いが沸き起こっている。流れてくる箱の中を覗きたいという欲動だ。箱の外装に内容が書かれているものには関心を覚えない。わからないものにはたまらない好奇心が働く。「安が箱をみつけて、持ち上げて、レーンに流すまで、この一連の動きのあいだ、箱の中身はさまざまな可能性が変幻自在に重なり合って、ぬいぐるみでありながらポテトチップスであり、肥料袋であり水槽でありつづける」という決定不可能性が彼を惹きつける。「想像の答え合わせをしてやりたいという欲望」は募る一方である。あるときそれが臨界点を迎え、小説は別の局面へと入っていく。
絶え間なく続く作業によって人間は機械の部品化する。この比喩はチャールズ・チャップリン監督映画『モダンタイムズ』の時代から延々と続くありふれたものだが、非人間化された人間の内面を覗きこむために技巧が凝らされており、場面に応じて手を変える工夫もあって退屈させられることがない。たとえば冒頭では、1行目から延々と現在形の記述が続く。言うまでもなく、読者を宅配所の中に誘い、そこにいるかのような臨場感を味わわせるための技巧である。常に真正面を見て先に進むことを強いるような現在形語尾の連続は、読者に視野狭窄に似た緊張感を覚えさせる。その記述が4ページ初めの「安は朦朧とした労働の時間を凌ぐために、取り上げた荷物の中身を想像していた」という文章に到達したとき、読者は解放感を覚え、安と一部同化するだろう。そうやって記述を前へ前へと進めていくのである。
安の視点では他にも意図的な変化が見られる箇所がある。あることで秘密を抱えるようになった安は、思いがけず神代と二人きりで面談しなければならなくなる。時間がない神代は安に断ってコンビニエンスストアで買ったサンドイッチを食べながら話し続ける。その挙動が(飲み込む)(口端を指で拭く)(手に持ったサンドイッチを口の中に押し込んで指先を舐める)といった具合に、撮影で言えば接写の距離で安は神代を凝視している。やましい心があって神代の挙動に注目しなければならないということを、そうした形で表現しているのである。視点移動が本作では実に効果的に行われる。
彼らが働く宅配所のように、人間に非人間的な役割を強いる職場は無数に存在するだろう。ただ作者は現実を愚直になぞるのではなく、そこに虚構ならではの粉飾を行っている。宅配所の中にはなぜか霧が蔓延しているのである。内部は常に濡れており、鳩が迷い込んで作業員にぶつかるほどには視界が効かない。安は霧の中を歩いて、思いがけない宅配所の秘密を知るが、そのあたりから叙述が幻想であるのか、それとも本当の現実なのかは曖昧になっていく。霧は視点人物をその不分明の中に誘い込むための装置である。
四人に分割された視点人物たちは小説の最後で〈私〉という一人称に統合される。人間の非人間化という状況を描いている以上、それは予定調和と言ってもいい終わり方だ。個々の固有名詞に意味がなければ、それは代名詞で置き換えられるのである。物語の終わり近くに「精神と肉体がふたたび共鳴をはじめた」という記述があるが、一人になった〈私〉は宅配所に向かう夢を見る。決して解き放たれたわけではなく、ベルトコンベアに縛り付けられていることを暗示して小説は終わる。
この結末に向けて周到に計算された小説だと感じた。前述したような、個々の場面で用いられている技巧も、その場を飾るだけではなく全体に寄与するような形で使われている。結末近く、事態が急を告げる直前に、視点人物が自らの内面について語り出すくだりがあり、それは不要だったと私は感じた。読者に納得されることで醸成した緊迫感が薄れるのと、非人間化した身体にありきたりな魂を入れてしまえば全体の趣向を損ないかねないからだ。しかし致命的な瑕瑾にはならずに踏みとどまった。
とにかく読まねばならないという圧力を感じさせてくれる作品である。視覚的描写が優れているということもあり、どのページを開いても絵面が目に浮かぶという美点もある。優れたデビュー作としてお薦めしたい。まだ候補作をすべて読んだわけではないが、芥川賞の本番でどのような選考が行われるのかも楽しみにしている。