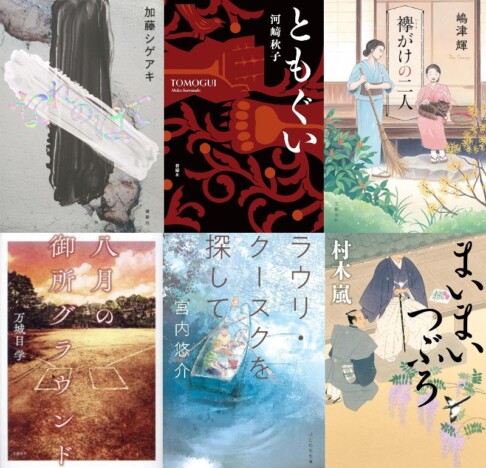杉江松恋の新鋭作家ハンティング 限りない不安を催す重量級ホラー小説『対怪異アンドロイド開発研究室』

ホラーというジャンルは本当に人材輩出の宝庫だと感心する。
饗庭淵『対怪異アンドロイド開発研究室』(角川書店)を軽い気持ちで読み始めたら、予想以上に重量級の作品だったので居住まいを正すことになった。
主人公、というか中心にいるのはアリサである。ごく普通の若い女性に見えるが、実は近城大学の白川有栖教授によって生み出された超高性能アンドロイドなのだ。華奢なみかけだが体重は130キロある。だから重量級。いや、そういうことではなくて作品の中味が外見よりもずっとみっしりとしている。軽い読み味だが、複数の着想が詰め込まれ、隅から隅までよく考えられた構造になっているのである。
アリサに搭載されたAIは、対怪異、すなわちおばけの解析用に特化している。ディープラーニングによって情報処理のパターンが蓄積され、遭遇した対象にどの程度怪異の可能性があるかを確率計算することができるのである。人型をしているので、どこへでも歩いていき、群衆に混ざって調査を進めることができる。内臓されたドローンを飛ばせば高所など視界の届かない場所を撮影することも可能だし、背面にもカメラがついているので対象の監視にも力を発揮できる。ただし、電源が切れたら動けなくなるので、完璧ではない。定期的に白川研究室に戻り、充電器に座らなければならないのだ。ヒーロー/ヒロインに弱点を設けるのはエンターテインメントの鉄則で、この充電切れ問題が作中でもうまく使われている。
連作短篇集に近い構成で、毎回アリサがさまざまな場所に派遣されて調査を行うという内容だ。第1話の「不明廃村」では住民に捨てられた集落に足を踏み入れられて不審人物と出会い、第2話の「回葬列車」では最終が行ってしまった後にやってきて、乗客をどこかに連れ去るという謎の列車に乗り込む。各話の終りに「対怪異アンドロイド開発研究室」という断章が付されており、白川教授と研究員の会話により、怪異のその後が語られるという構成である。実況中継と後日談という組み合わせはありふれたものだが、白川教授が何を考えて対怪異アンドロイドなるものを開発したのかということが次第にわかる流れになっているので、続けて読みたい気持ちにさせられる。
本書の読みどころは、第一にアリサのキャラクターだろう。人工物であるアリサは、いくつかの命令に従うように作られている。創造主である白川教授の指示を別にすれば、最も優先権があるのは対怪異調査だ。アリサにとって、遭遇する事物はすべて、そのためのサンプルなのである。相手は普通の人間に対するように話しかけてくるが、アリサにとっては対怪異判定のための情報収集になっているわけで、会話が成り立っているようで噛み合わない。そのちぐはぐさが主人公に際立った個性を付与している。首が取れたり、生体の約5倍の筋力を有していたり、といろいろな属性を持ってはいるのだが、アリサを特徴づけているのはこの、一般の人間とは存在理由が異なるという点だろう。大勢の中に一人だけ異なる方向を見ている者がいるという、キャラクターの立て方としては正しいやり方である。
このアリサが遭遇する怪異が多種様々である点が第二の読みどころである。第3話の「共死蠱惑」には魅力に引き寄せられた男がみな変死する文字通りの〈運命の女〉が登場するし、第4話ではうら寂れた商店街の雑居ビルが一棟そのまま怪異になっている。そうかと思えば第5話「異界案内」では、登場人物たちがいる世界そのものが怪異なのかもしれないという不安の状況が作り出されるのである。しっかりと自分の足で立ち、自分の目で見ているはずの世界が、実は怪異によって作り出されたまがいものかもしれないという恐怖は、本書の根幹にあるものだ。この第5話を転換点として、物語は剣呑な方向に曲がり始める。
作中で白川教授が言及する世界5分前仮説の思考実験は、バートランド・ラッセルによって提唱されたものだ。何億年も前から続いているように見える世界が、実は5分前に何者かによってそう見えるように作られたものかもしれない、という懐疑主義は底無し沼で、合理的思考を停止させる。オカルティズムの源泉ともつながった考え方である。白川教授は、実は足枷に囚われた人だった。だからこそアリサという存在を作り出したのだ。
「現実は一つより多いが複数より少ない。怪異はきっと、そんな隙間に存在する。客観的というものはあっても、客観というものはない。だから、私は客観(かみ)をつくりたかったんだ。そうすれば怖いものなどなにもない。アンドロイドならば現実を生(き)のままに認識できるかもしれない。はじめからわかっていたように、そんなものは夢物語だったがな」
世界をありのままに観察するための視点として対怪異アンドロイドは創造されたのだ。本作の中に流れる声、狂おしいほどに何かを求めているのに決して手にすることができず、その渇きに悩まされているような人々の呻きは、ここから来ているものだろう。万能感を求め、それが得られずに絶望へと向かう心と敷衍して言えば、この社会に満ちた空気そのものにもつながっていく。『対怪異アンドロイド開発研究室』を読む人を捉えて離さないのは、実はこの点なのである。他のジャンル小説と同様、優れたホラーもまた社会を写す良質の鏡となるだろう。これが読みどころのその三だ。