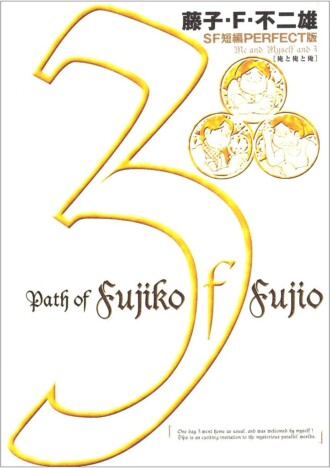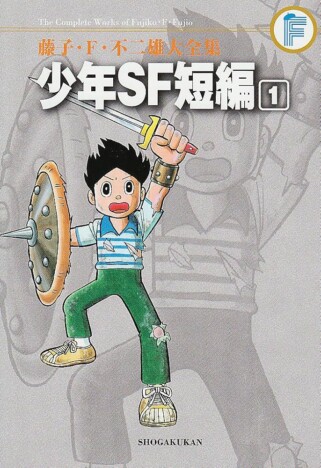藤子・F・不二雄 SF短編の最高傑作『みどりの守り神』とはどんな物語なのか?

NHK BSで3夜連続放送中の、「藤子・F・不二雄SF短編ドラマ シーズン3」。本日3月26日の1本目、23:00から「前編/後編」にわけて計30分で放送されるのは、『みどりの守り神』(初出:『マンガ少年』1976年9月号)だ。原作は48ページに及ぶ、藤子・F・不二雄のSF短編のなかでも堂々たる「大作」である。
まず、タイトルを見てみよう。「みどりの守り神」。この「みどり」とは何を指すのだろうか。
作品を読みはじめた時点では、主人公となる少女のことを指すように思える。冒頭、人気のない森の中で目を覚ました少女は、一瞬パニックに陥るが、半袖のシャツを着た青年が現れ、「落ち着きなさい!! みどりさん」と声をかける。ここで始まる会話から、少女の名前とともに、彼らの置かれた状況が読者には伝わってくる。坂口五郎と名乗るその青年は、ふたりが乗っていた飛行機が墜落し、生き残りは自分たちだけだったこと、また自身が意識を取り戻した際には、周囲に大量のコケが生えていたことを述べる。そして救助を求めようと、自分たちがいる山を下りはじめ、現在に至るのだと。そしてかなりの高山と思わしき山を、ふたりは再び歩きはじめる。
旅の過程で、みどりは周囲の状況に違和感を覚えていく。飛行機が墜落したのは4月だというのに、夏のような暑さが感じられること。豊かな自然が広がっているにもかかわらず、小鳥を見かけないこと。いや、それ以前に、自分たち以外に生きて動いているものをまったく見かけないこと。坂口も同様の違和感は覚えており、「核戦争が起こったのではないか」という仮説を立てる。
歩みを重ね、藁ぶきの屋根が並ぶ村に行けども、いかだに乗って進む川の周囲を見渡せども、人っ子ひとり、いや、虫一匹すらも見かけない。こうした中で、ふたりの不安も高まっていく。
坂口はいささか感情的な、暴力的なキャラクターとして描写されている。足を痛めて歩きが鈍くなっているみどりに対して「たった一人の道づれが足弱の女の子だなんて」と嫌味を口にし、果ては「さっさと歩けよ」「のろま」「ぼくだからがまんしてんだぞ」などという暴言にまで発展する。人を思いやる気持ちがないわけではなく、みどりに対して言葉が行き過ぎた点があったことを謝罪したり、動けなくなったみどりを担いで村に運んだりもするものの、坂口に対し、寛容な人間という印象を持つ読者は多くはないだろう。
彼らの置かれた状況の過酷さを考慮すれば、坂口個人を責めるのはフェアではないだろうし、自分が同じ状況に置かれたとして、そばにいる人への優しさや思いやりを維持できるかと問われると、正直心もとなくはある。とはいえ、本作においては、坂口はみどりを、自分と対等な存在と見なしていないことには着目する必要がある。「ぼくが助けてやらなきゃきみなんかとても」「きみにはぼくしかたよれる者がないんだから」などという言葉から、そうした認識の一端が見受けられるし、少しでもみどりが自身の意に沿わない発言をすると、「偉そうにいうな」「ぼくにさからうのか」と激昂したりもする。
現実の人間関係を考えれば、いわゆるパートナーであれ、仕事仲間であれ、友人であれ、自身に対して居丈高な態度をとる人間からは離れたほうが良いようには思えるし、感情的な負担を常に強いる/強いられるような関係性に何かしらの発展があるとも思えない。じっさい、本作においても、みどりと坂口の関係はやがて臨界点を迎え、坂口はみどりのもとを去っていく。