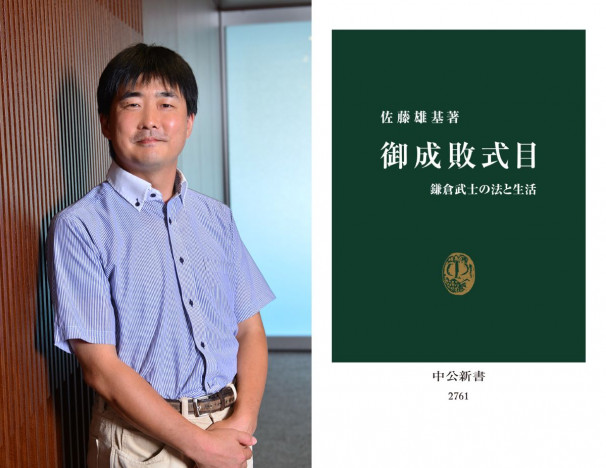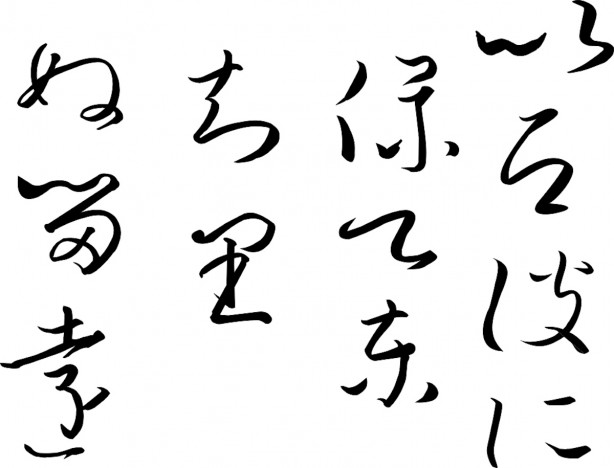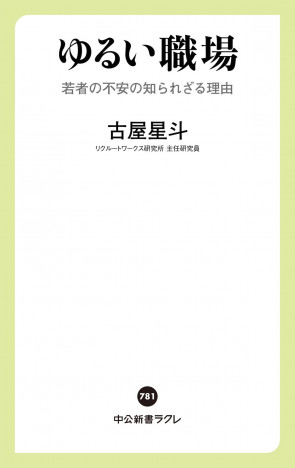恐怖はなぜ時間の流れを遅くするのか? 精神科医が考察する「恐怖の正体」

一方で人間には残酷さや良識の逸脱の極限を知りたいという、「怖いものみたさ」の感覚もある。その欲求を疑似的に満たす存在として挙げられるのが、映画や文学におけるホラー要素のある作品である。
殺人事件の手口がとにかくエグくて悪趣味な、ジョン・バーデットの警察小説『最後の600万秒』。浦島太郎の物語に漂う「嫌な感じ」を濃縮したような、都筑道夫の短篇「猫の手」。「生き埋め」というテーマと親和性の高いジョルジュ・シュルイツァー監督の映画『ザ・バニシング-消失-』に、「広大かつ絶望的な場所で右往左往していたと思っていたら、実はそこはちっぽけで無害な区画でしかなかった。オレは独り相撲を取っていただけなのか?」と親和性の高いガス・ヴァン・サント監督の『GERRY ジェリー』。本書で紹介されている人間の恐怖のツボを押さえた作品を、実際に観たり読んだりしたくもなってくる。だが恐怖を娯楽として味わおうとする人間の心持ちは、果たして健全といえるのか。
子ども向け番組『きかんしゃトーマス』が人形劇だった頃のエピソードに含まれるブラック要素、その是非について著者はこう語る。〈わたしはこのような物語が何食わぬ顔で日常にまぎれ込み、子どもや大人の不意を突いて凝然とさせる事態を好ましく思う。ときおり退屈な毎日がささやかなグロテスクや恐怖で脅かされたり変質することによって、わたしたちは生きることの意味を問い直す。そうであってこそ、まっとうな人生を歩めるというものだろう〉。
恐怖とは苦痛にもエンターテインメントにもなる、複雑で矛盾したものである。だからこそ、迫りくる死の恐怖に対しても〈とにかくそれを克服しなければ何も始まらないという優先順位のつけ方――その硬直した「こだわり」こそが変なのだ〉と、「怖い」で思考停止することはない本書。「死はなぜ恐ろしいのか」を探るその思考の道筋を追っていると、どんな恐怖にも〈発狂してオシマイというほど人間の精神は単純にはできていない〉ことを実感させられるのである。