『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の戦闘シーンはなぜ説得力があるのか? ミリタリーマニアが分析

世の中にいろいろなマニア・オタクがいる中、ひときわ業の深い存在としてミリタリーマニアという人々がいる。「ミリタリー」と書いている通り、兵器や軍事、実際の戦争やそれにまつわる諸々について強い興味を持ち、資料を読んで調べたり、兵器のプラモデルを買って作ったり、エアガンで戦争ごっこをしたり、時には実物の兵器や装備品を買ってしまったりする人々である。自分を含め、そういう人たちが常に強い興味を持っているのが、「実際の戦場とはどういうものか」という点だろう。
もちろん、自分を含めて大半のミリタリーマニアは「自分も戦争に参加したい」とは全く思っていない。実際の戦争について調べれば調べるほど、人類の愚かさや戦争の悲惨さや馬鹿馬鹿しさについての知識をつけることになり、ゲンナリすることも多い。しかし自分はそのゲンナリ感も含め、兵器や戦争にまつわる諸々を「面白い」と思っている。強力な兵器のスペックを見れば「すごいなあ」と思い、実際の兵士たちの戦いに関する資料を読めば「凄まじいなあ」と思い、非常に幸運なことに自分が体験せずに済んでいる「実際の戦場」とは一体どういったものなのか、本や映像を手がかりに想像する。不謹慎は承知の上で、そういうことを全体的に「面白い」と思ってやっているのが、ミリタリーマニアとしての自分である。
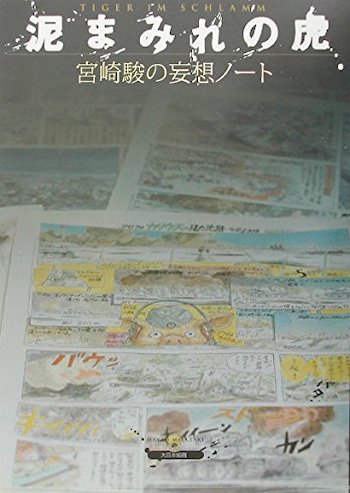
実際の戦場とはいかなるものか。兵士たちは何を食べて何を見て何を感じているのか。それらを考えて積み上げていくことで、兵器や戦争とはどういうものなのかに迫りたい。そういったアプローチで組み立てられた作品は色々と存在する。例えば宮崎駿氏による『泥まみれの虎』は、第二次世界大戦中のごく限られた戦域でごく限られた期間に活動した、たった二両のティーガー(大戦中のドイツ軍が運用していた重戦車)の戦いに顕微鏡的な細かさで迫ったコミックである。オットー・カリウスという伝説的な活躍をした戦車兵を題材にした作品だが、講談・軍記物的なハデな面白さではなく、「ナルヴァという戦場で若き戦車長カリウスは一体何を見て何を考え、どう行動したのか」を現地取材までした上で緻密に想像し、その結果をコミックの形でまとめた傑作だ。

実際に自衛官として勤務した経験を持つ砂川文次氏の『小隊』も、顕微鏡的な細かさで戦場を眺めることで、戦争という状況を描き出そうとした作品と言えるだろう。冒頭から「人が長時間野外活動を続けるとどういうことになるのか」という点を「頭の痒み」で表現し、敵が迫ってくるという状況下でも「とにかくダルいから早く終わってほしい」と考える自衛官の心の動きを詳細に追った内容は、まさにミリタリーマニアが知りたかった「実際の戦場」の情報と言っていい。その後の凄惨な戦場の描写も大所高所からではなく、あくまで戦場で一人の自衛官が目にし、感覚で捉えることができる範囲に収まっており、一人の人間が感覚することのできる戦争の描写として説得力があった。
前置きが長くなったが、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、自分にとって上記の作品に連なる説得力を感じるものだった。前作『閃光のハサウェイ』も含め、アニメ版『ハサウェイ』の戦闘シーンは根本的に「この状況でこの位置にいる人物には、この戦場はこう見えるはず」「この場にいたらこういうものが見え、こういう音が聞こえるはず」という点を徹底して突き詰め、観客に生々しく追体験させる方向で設計されている。
『キルケーの魔女』の冒頭は、徒歩の部隊が連邦軍のモビルスーツによって蹂躙される映像から始まる。カメラは映画的にフィックスされたものではなく、激しい動きや撮影者の息遣いから、ボディカメラによって撮影されたものであることがわかる。「もうもうと砂塵が舞い上がる中で記録されたボディカメラの映像」というだけで、マニアにはすでに伝わるものがある。21世紀に入って、戦場から伝わってくる映像には格段の進歩があった。カメラ自体が小型化・軽量化されたことで、兵士が自分の体や装備にカメラをつけて映像を撮影することが可能になり、さらにWEB上の映像配信のプラットフォームが整備されたことで、そうして撮影された映像をパソコンやスマートフォンで気軽に見ることができるようになった。『キルケーの魔女』冒頭の「右往左往する撮影者によって撮られた、激しい戦闘のど真ん中の映像」は、そういったものをわざわざ好んで見る人々にとってはお馴染みのものなのだ。
冒頭の連邦軍のモビルスーツの動きや見え方も、シミュレーションが行き届いたものだった。モビルスーツは大きい。特に『ハサウェイ』に登場する機種は20m以上の高さがある。そんな物体が我が物顔で歩き回るとき、その足元にいる人間にはどう見えるのかが、見事なまでに映像になっていた。そして自分が感心したのは、さっきまで超巨大に見えたモビルスーツがすぐに遠くに行ってしまい、それほどの大きさがあるように見えなくなってしまったところである。我々はもうすでに、実物大のモビルスーツの量感や、ちょっと離れた時にどのくらいのサイズ感で視界に入るかを、お台場や横浜や福岡や大阪の万博会場に建てられた、設定上の実寸を再現したガンダムによって知ってしまった。高さ18mの人型兵器は近くによれば巨大に見えるが、20mも離れれば「こんなもんか」というサイズ感になってしまう。特に周囲に高層建築物が並ぶ市街地ならば尚更だ。モビルスーツは「寄れば大きく、離れれば妙に小さく見える」ものであり、それを知った上で『キルケーの魔女』の冒頭を見ると、本当にそのように描写されている。こんな映像は見たことがない。
さらに『キルケーの魔女』でのモビルスーツの戦闘シーンは、総じて暗い。マフティーは連邦に比べれば圧倒的に戦力の小さい反体制テロ組織であり、連邦に移動や補給の状況を気取られるわけにはいかない。ならば見通しの効く昼間に巨大なモビルスーツを動かすことはできるだけ避けるだろうし、連邦側はそういった部隊を攻撃するのだから、必然的に戦闘は夜間になるだろう。「暗くて何がおこっているのかわからない」のは、マフティーの狙い通りなのだ。
そして『キルケーの魔女』は、夜間のモビルスーツ戦の見せ方として、「こういうことになればこうなるだろう」という現実的な描写を積み上げる。暗い中での目視での戦闘は難しいので、基本的にセンサーやレーダーとそれらが鳴らすアラート頼みの戦闘となり、ビーム兵器は文字通り光の速度で着弾するから、遠くでピカピカッと何かが光ったら、その一撃でモビルスーツは撃墜される。光源は排気ノズルからの噴射やビーム兵装の閃光やモビルスーツの爆発くらい。薄暗くだだっ広いオーストラリアの風景の中、パイロットの神経だけがすり減る戦いが続き、勝敗は一瞬で決着する。今思えば、前作でのダバオ上空での戦闘やクスィーガンダムとペーネロペーの戦闘は、『キルケーの魔女』のものよりもまだフォトジェニックだった。
この、「映えない」戦闘を見た時、自分は「ロボットアニメってまだこんなことができたのか!」という驚きを強く感じた。思えば、80年代のリアルロボットブーム以降、ロボットアニメは現実的な描写の追求と、派手で分かりやすいケレン味やカタルシスの間に板挟みになってきた。生まれた時からアニメがあった世代の、特に濃いマニア層がアニメーターとして現場に入り、実物のマシンの動きや生々しい戦闘描写を盛り込みつつ、同時にアニメとして見応えもある描写を次々と生み出し続けてきた。「リアルで面白いロボットアニメが見たい/作りたい」という欲求が生み出したものは、例えば『機動警察パトレイバー』だったかもしれないし、『マクロスプラス』だったかもしれないし、『第08MS小隊』だったかもしれない。スタッフや視聴者の「こういうものが見たい」という欲求は、さまざまな方向へと「リアルなロボットアニメ」の範囲を押し広げてきたのである。これらの作品はこれらの作品で素晴らしいが、それはそれとして『キルケーの魔女』ほど「こういう時にはこういうことが起こり、パイロットの目にはこう見えるはず」というシミュレーションの痕跡を強く感じさせるものは初めて見たように思う。つまりまさに今、目の前でリアルロボットアニメの可能性が押し広げられているのだ。これに興奮せずして、何に興奮しろというのだろうか。
暗くて何が起こっているかわからないなかで次々にモビルスーツが撃墜されていく映像を見て、自分は村上春樹の『スプートニクの恋人』に書かれていた、サム・ペキンパーとアーネスト・ボーグナインのエピソードを思い出していた。ペキンパーは畳み掛けるような流血描写で知られる監督だが、代表作の『ワイルドバンチ』が公開された際に女性ジャーナリストから「一体どのような理由で、あれほど大量の流血描写が必要なのですか?」と質問される。その質問に対し、出演者であるアーネスト・ボーグナインは困惑しつつ「いいですか、レディー。人が撃たれたら血は流れるものなんです」と答えたという。
同じである。人は撃たれた血が出るし、暗いところでモビルスーツ同士が戦ったら何が起こっているかわからないものなのだ。『キルケーの魔女』がすごいのは、一見して何が起こっているのかわからない映像を、そのままよくわかりづらいものとして公開した点にある。『ワイルドバンチ』の凄まじい流血と『キルケーの魔女』の夜間戦闘は地続きであり、そしてそれは「戦場での兵士の五感の再現」という、ミリタリーマニアとしての自分が欲してやまないものに直結している。たとえフィクションであっても、というかフィクションという他人事であればこそ、戦場で人が撃たれて流血しているところや、暗いところで戦っていて何が何だかわからないところが見たい。自分には、そういった欲求が間違いなくある。そしてそれを見透かしたような戦闘シーンを提供してきたのが、『キルケーの魔女』だった。
さらに恐ろしいのが、『キルケーの魔女』はありとあらゆる手段で「戦場での兵士の五感」を再現し観客に追体験させつつも、プラモデルの販促アニメとしてのパワーを失っていないところだ。特に今回ペーネロペーの代役として登場したアリュゼウスに関しては、「ガンプラのプロモーション」という役割もきっちり果たしていたと思う。現実的な描写を積み上げに積み上げた末、これまでのどのガンダムでも見たことがないほど奇怪なフォルムと過剰なディテールを持った異形のシルエットが、排気ノズルからの噴射を輝かせながら飛んでくる。このギャップ。この落差。しかも一皮剥けば中身がほとんどνガンダムなのだ。中二病的ド派手さとケレン味、そしてそれらの要素がハサウェイのトラウマへと結びついていく作劇の丁寧さ。よくこんな落とし所を見つけたものだと思う。
とにかく、ミリタリーマニアとしての自分は、あの暗くてよくわからない戦闘シーンを目撃して、激しく興奮した。これは自分が見たい見たいと思っていたものだし、こんなものが大きな予算をかけたロボットアニメとして見られるとは考えていなかった。ロボットアニメにこんなことができるとは、全く思っていなかったのである。生々しい描写のピースをひとつひとつ積み上げ、高い解像度で戦場の兵士の五感を観客に追体験させ、さらにその一方で複雑怪奇なモビルスーツのプラモの販促という任務も果たす。こんな作品が成立したこと自体に、ガンダムというコンテンツが今現在獲得した豊かさ、そしてロボットアニメというジャンルが持つ可能性を強く感じる。少し大袈裟かもしれないが、「この作品と同じ時代を生きることができて幸運だった」とすら思える。『キルケーの魔女』は、そんな作品だった。
























