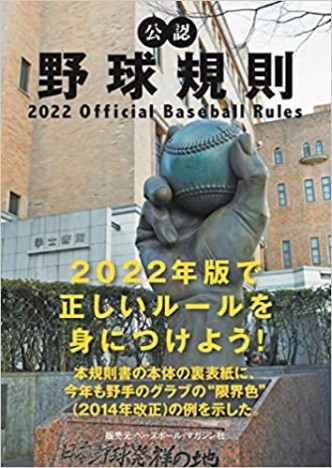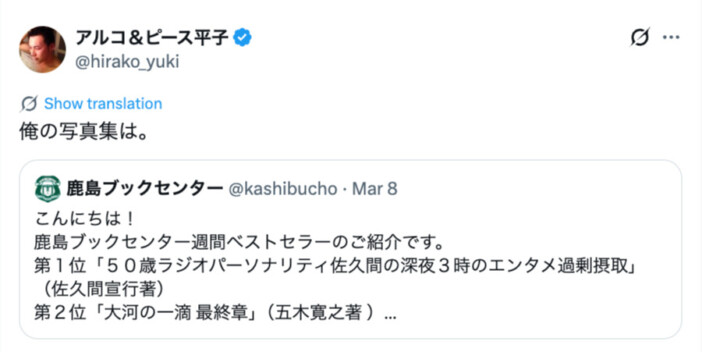「清原が甲子園に……」 その響きだけで野球ファンは心地いい 清原和博の次男・勝児が春の選抜確実視へ

清原選手がいる慶応高校が選抜へ
また、清原が甲子園に……。
そんなフレーズが話題になっている。1980年代、甲子園を沸かした清原和博氏の次男、清原勝児選手の所属する慶応高校野球部が関東大会で4強入りし、2023年春の選抜出場が確実視されているからだ。
高校野球専門誌の『報知高校野球2023年1月号』(報知新聞社)においても、勝児選手が表紙写真になり、「清原が甲子園へ」というキャッチが添えられている。
古くからの高校野球ファンならば、それだけでドキドキしてしまうのだ。
常勝PL学園の4番に1年生!
知っている人も多いだろうが、清原和博という高校野球選手が甲子園球場を沸かせてから、40年近くも過ぎている。
だから、かんたんに振り返ってみよう。
清原氏が入る以前から、中村順司監督(当時)が率いるPL学園は強かった。甲子園に来れば、まず優勝争いに絡む、いや優勝した。今の大阪桐蔭みたいなものだ。それ以上とする人も多いだろう。
しかし、1983年の夏。その超強豪校の4番打者は1年生で、エースも1年生だった。清原和博、桑田真澄(現ジャイアンツファーム総監督)という、後に「KKコンビ」とされるふたりだ。
「あのPLのエースと4番が1年生?」
みんな驚いた。
「どんだけスゴイねん?」
「いうても、1年やぞ。数カ月前まで、中坊やぞ」
そんな印象だったと思う。
だけど、彼らのパフォーマンスは強烈だった。このチームはそのまま優勝してしまったのだ。
KKコンビは一躍、話題の人になる。1年生にして十分に完成しているように見えた。でも、伸びしろも感じさせる。ファンはワクワクしたものだ。
そして、彼らはその期待を裏切ることはなかった。1年生の夏から出られる甲子園には全部出場した。
多くの球児たちが、「1度でいいから、その土を踏みたい」と汗を流しながら、ほとんど踏めずに終わる甲子園の土を、何度も何度も踏みしめた。あまりに強いために、判官びいきやアンチの感情を持つファンも多くなる。だから、彼らが負けた試合ばかりが名勝負として記憶されてしまう。
翌年春決勝の「岩倉×PL学園」の桑田、山口の投げ合いもそうだし、その夏決勝の「取手二×PL学園」は木内幸男監督(当時)の“木内マジック”が話題になった。1985年春、「伊野商×PL学園」などは、「桑田の調子が悪く、ベスト4までしか行けなかった」というのが、今でいうトレンドワードだった。
「甲子園は清原のためにあるのか!」
だからこそ、1985年の「KKコンビ最後の夏」は話題になった。
選手らの努力と鍛錬があってのことだとはわかっているが、それでも、多くのファンにはPL学園が、当たり前のように決勝まで勝ち進んだように見える。
ただし、決勝の相手の宇部商には、ここまで大会4本塁打を放っていた藤井進もいて、大会3本塁打の清原との長打力比べも注目されていた。
しかし、そこは清原。4回の第2打席に本塁打を放つ。この舞台で、それができてしまうのが彼だった。今風に言えば、「持っている」存在だった。
でも、宇部商の藤井も三塁打を放って逆転に成功する。
「最後の夏も負けたことが話題になるのか?」
そんな空気が甲子園に流れはじめる。
6回、また清原に打席が回る。
打球が飛び出す。見ていた人全員が唖然とした。センターバックスクリーンまで目で追う。
2打席連続本塁打だった。
「甲子園は清原のためにあるのか!」
当時の朝日放送アナウンサー、植草貞夫氏の実況は今でも伝説だ。
勢いに勝ったPL学園は9回裏に決勝点を挙げ、KK最後の夏は優勝で終わった。
そんな夏だった。
だから、進学と思われていた桑田がジャイアンツに指名され、6球団競合となった清原がライオンズに指名されたドラフトも話題になった。
高卒1年目に3割30本
プロ野球に場所を移しても、清原はファンを驚かせ続ける。
なにしろ、高卒1年目で、打率.304、本塁打31本を記録したのだ。そんな選手はこれまでいなかった。そして、その後もいない。
そのまま、彼は球界を代表する打者になった。
ただ、ここまでファンは清原に驚かされ続けていた。唖然とすることに慣れていた。
だから、清原がいくら打っても、それは普通だと思ってしまう。もっと、驚きたいという思いで見る。
ラルフ・ブライアントやオレステス・デストラーデがバカスカ本塁打を打っているのを見ながら、
「清原よ、もっと打て!」
そんなことを思ってしまう。
失った何かの先に
だから、彼のプロ野球におけるキャリアは間違いなく偉大であるのに、何か物足りなさを感じる人が多いのだろう。
これについては、清原がジャイアンツに移籍した後、打撃コーチとして多くの時間を過ごした内田順三氏の言葉が妙に納得する。
私自身が編集に携わった本なので手前味噌にもなるが、清原本人が何度も「いちばんお世話になった指導者」として名を挙げている人なのでリアリティがある。
その内田氏の著書『二流が一流を育てる ダメと言わないコーチング』(KADOKAWA)には、清原は高校時代、上体のやわらかさを備えた好打者タイプだった、とある。
だが、それは高校生という成長途上の身体における特徴であって、そのまま大人のアスリートの身体になるものでもない。若年のアスリートが成長の中でバランスを失う例は、野球に限らず、よくあることだ。
そして、身体ができていく中で、彼の柔軟さは変化したのではないか、そう内田氏は解説している。そして、その柔軟さを要求されるのが、清原が不得手とされたインコース。
なるほど、と思う。
ただし、内田氏は清原という打者のストロングポイントを解説することも忘れていない。
彼は軸足(後ろの足)が半端なく強いという。その蹴りの力があるから、引っぱらなくても打球を飛ばせる。
「広角に打つのがケタ外れにうまい。逆方向に大きな打球を打てる日本人なんか、キヨしかいない」
内田氏はそう言いきっている。
でも、長距離打者というのは、どうしても「飛ばしたい」という思いに突き動かされ、引っぱり方向を向き気味になるそうだ。現在の強打者たちも、調子を崩す理由の多くは、そこにある。
だから、内田氏は清原に口酸っぱく、「センターから逆方向をねらえ」と言ったそうだ。その甲斐もあり、ジャイアンツで打率.298、本塁打29本を記録したのは、プロ入り16年目のこと。何かを失い、一度下降した成績を、その年齢でそこまで取り戻せる選手は少ない。
あのとき、ファンはもう一度清原に驚いてよかったのだ。
冒頭の『報知高校野球』によれば、清原勝児選手の帽子のつばに、父、和博氏がいくつかの言葉を書いてあげたそうだ。
そのひとつが、「センター返し」。
なるほどな、と思う。自身を戒めてきた言葉を息子に贈ったのだろう。
父と子は別人格であり、別の個性だ。同じことを期待するのは野暮で無知すぎることはわかっている。同じことを期待したりはしない。
でも、甲子園で「清原」という響きは、どうにも心地いい。そればかりは、どうにもならないのだ。