円堂都司昭 × 小川公代 対談 オペラ座の怪人、大江健三郎、メアリー・シェリー……重なる関心領域とそれぞれの文学観

ケアの倫理を論じた理由

円堂:小川さんは『ケアの倫理とエンパワメント』(講談社/2021年)以降、ケアの人というイメージが強くなったと思います。小川さんが文芸誌に意欲的に執筆するようになったのは、群像新人評論賞やすばるクリティーク賞が終了した頃だったでしょう。私は様々な文芸誌・小説誌編集長のインタビューをするなかで、批評というものの行方にも関心を持ち続けてきたので、小川さんはインタビューしたい相手でもあったんです。それは、「群像」で『ケアの倫理とエンパワメント』の連載が始まった時、タイトルの文字列を見て衝撃を受けたからでもあります。
先ほど話したように、母親が介護状態になって施設に入れていました。自分が直接介護するわけではないのですが、施設から電話がかかってきて病院に連れていくようなことはよくありました。ケアという言葉がいきなり日常語になったわけです。そこで「倫理」といわれるとドキッとしますよね。自分は何もかも善人なわけではない。要するに施設にアウトソーシングしている段階で、自分で世話してないという意味では、多かれ少なかれ負い目を感じてしまうじゃないですか。
今考えると自分は、文芸誌でケアというテーマが扱われる際、「倫理」や「エンパワメント」という言葉が真っ先に上げられたことにも驚いたんだと思います。私が1970年代後半に文学に触れ始めた頃、中島梓や大江健三郎の作品に出会いました。中島梓の弟には重度の障害があって、ほぼ寝たきりだった。最初、本人はそのことを語っていなかったのですが、彼女の文芸評論『文学の輪郭』では檀一雄の私小説『火宅の人』に触れていた。檀も子供に日本脳炎の障害がありました。
しかし彼には外で浮気するなどの悪徳があった。この時代の私小説で言うと、島尾敏雄の『死の棘』も同類でしょう。旦那が浮気して、奥さんが精神を病んでいく。当時はその種の作品が目立っていたので、ケアに反するような悪徳をあえて描くのが文学だという、倫理とは逆のイメージを受けとっていたんです。斎藤美奈子『妊娠小説』で指摘されていたように、無責任な男性と交際し妊娠した女性が中絶を考えざるをえなくなるというのは、純文学の一つのパターンになっていましたし。
中島梓は栗本薫名義で小説を書いていましたが、中島梓名義で私小説を書いたことがあって、それが「群像」に掲載された「弥勒」でした。「ご兄弟はいらっしゃるんですか」と聞かれた時に「一人のようなものです」と答え続けるという内容で、そう答えるたびに弟を殺している気持ちになるという話でした。対談した相手の作家から「一人のようなものって何だよ」と聞き返されるという展開です。この小説はあまり評価されず単行本に収録されることもなく、本人は亡くなってしまいました。それ以外にも弟を扱った私小説でボツになったもの(「ラザロの旅」)があったことが、死後にわかりました。
大江健三郎にしても障害のある長男を育て、『新しい人よ眼ざめよ』など親子関係を描いた作品も多いから、優しいお父さんというイメージがあるかもしれないですけど、『個人的な体験』は生まれたばかりの障害児を生かすか安楽死させるか迷う話ですし、『空の怪物アグイー』では殺した場合を書いていた。大江の思考も、ケアに関して倫理的なばかりではなかったわけです。中絶をモチーフにした作品もありましたし。
だから『ケアの倫理とエンパワメント』は、私には文学におけるケアとの向きあい方が昔と違ってきたことを象徴する論考に思えて、大きなインパクトを感じたんです。
小川:確かに私も正直、それまで文学研究をしてきてケアと結びつくことはなかったんです。しかし「群像」の連載でフェミニズムについて書くとなった時に、ケアの倫理を書こうと思いました。そう決意したとたん、ケアを描いている作品が思い出されたんです。
意識下にあったものを浮上させただけだと思うんですけど。ある意味で抑圧しているんですよね。ケアをする善人が主人公の作品なんてないという思い込みがある。特に私は三島由紀夫が命だというくらい読んでいました。結局、『ケアの倫理とエンパワメント』では、三島の『美しい星』と共に『金閣寺』を論じることでようやく「ケア」を発見することができたのですが(笑)。しかし一方、多和田葉子さんなど、現代に活躍する小説家はケアを描いて読者に勇気を与えるような作家もいる。そこで自分の中では、エンパワメントという言葉が出てきました。
しかし『ケアの倫理とエンパワメント』を書いて以降、ケアについて書かせていただく機会が増えたことで、SNS上ではバッシングを受けることが増えました。たとえば、ある著名な学者から執拗な批難があったり、男性文筆家からは今でもネットの書き込みで誹謗中傷を受けたりしています。そこで「抵抗」ということを意識しはじめた。ケアの倫理を論じたキャロル・ギリガンにも、去年邦訳された『抵抗への参加』という本があります。そんな抵抗への参加を意識したケアの倫理を書こうと思って、続く『ケアする惑星』『世界文学をケアで読み解く』は、「抵抗」の比重が大きくなりました。
そして『ゴシックと身体』で自分が30年やってきたゴシック小説の研究をまとめるという時に、不思議と誹謗中傷をしてきた人の顔が思い浮かんでくるんですよね。あの時に私がいじめられたのは何だったのかと落ち着いて考えてみたら、あれこそがバックラッシュと呼べるものだったんだなと。そうすると、いろんなものが繋がってきました。ゴシック小説を書いたメアリ・ウルストンクラフトも、彼女の娘であるメアリ・シェリーも、男性文筆家たちにこっぴどく批判されて誹謗中傷された。既婚者のパーシー・シェリーと駆け落ちしてヨーロッパに行ってしまった後、彼女たちへの風当たりが強かったようです。「ウルストンクラフトの娘だからやることが派手だ」というような。。
女性が規範から外れる道に行くと、保守派の間ですぐに黙らせようという運動が起きてしまう。あるいは、女性が社会で声を上げることによって、バックラッシュが起きる。その当事者になったときの辛さは本当に例えようがありません。
特にゴシック小説については、ウルストンクラフトとメアリ・シェリーが親子で選んだという共通点がある。それはやはり2人とも自由な生き方、道を外れる生き方を選んだ挙句にバッシングを受けたからです。そこで真正面から何かを言うということがもはやできなくなってきました。彼女たちはおそらく戦術として、ゴシック小説で暴露するという方法を取ったんだと思うんです。
円堂:ゴシックを戦略として見るという意味では、『物語考 異様な者とのキス』で取り上げた作品の最近のアダプテーションでは、多かれ少なかれジェンダーの問題を意識していますよね。魔女の呪いが発端となる『美女と野獣』、人魚が主人公の『リトル・マーメイド』、超能力者の苦悩が描かれる『アナと雪の女王』といった一連のディズニー作品がそうですし、死神らしき存在が恋の相手となる『エリザベート』などもそうでしょう。『ゴシックと身体』で語られているような、家父長制に抗う女たちがゴシックを戦術として用いるということが、それらの作品にも受け継がれている。そして、ゴシックの戦術の偉大な先達としてメアリー・シェリーがいる。
小川:私が発する言葉の端々にメアリ・シェリー先生の言葉が宿ってしまっている。長年付き合うと、その人が乗り移ってしまうことがあるじゃないですか。私の中にはメアリ・シェリーとウルストンクラフトとパーシー・シェリー、そしてジョージ・オーウェルと、マーガレット・アトウッド……と抵抗しまくる人ばかりが共存している。彼らの精神をある種、自分のエンジンにして書いています。だから『ケアの倫理とエンパワメント』も無意識にエンパワメントになっていくんですね。
野上弥生子の戦略
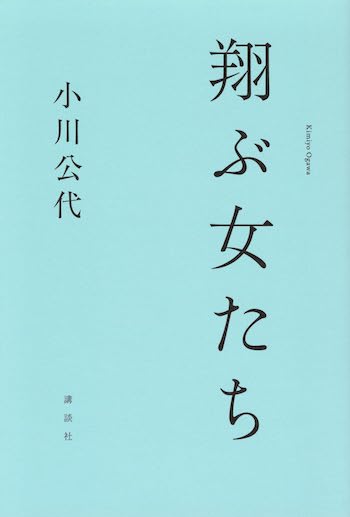
円堂:今挙げられた人たちは、小川さんの新刊『翔ぶ女たち』の中で言われているアルファ・タイプ(気が強くアグレッシブ)、ベータ・タイプ(控えめで健気である)でいうと、アルファ・タイプが多いですね。
小川:確かにそうですね。それがちょっと耳が痛いんですよ。どちらかというと野上弥生子はベータでしょう。彼女は最初はベータから始まるんだけども、99歳まで長生きするので、途中からちょっとずつアルファ化していきます。
私も学生時代はもちろんベータでした。30歳頃に今の職につくまで、長いこと学生をしていましたから。大学で職を得られなかったら私は一生、非正規雇用で生きていくような道を選んでしまったわけです。社会から疎外されているような立場でした。普通の企業では就職をする時、ハイスペックな女性は最も嫌われる時代でしたし。大学で専任のポジションを得る前にも嘱託講師の時期がありましたから、それは大変でした。下手にアルファのような言動をとるとかえって順応できない。そんな女性特有の悩みもありました。
だからこそ、とくに女性は戦略を立てる必要があるのだと思います。完全に「ぶりっこ」で武装して、「何でもやります」「私は従順です」というような感じでした。実際に何でもやりましたし、あちこちでこき使われましたが、女性として生きるということは、ほぼべータとして振る舞うことを意味するんだなあとしみじみ思います。野上弥生子もひたすらベータとして生きながら、少しずつ自己実現した人なんだと思います。
円堂:そして、ケアという問題設定自体がベータの側から考えられたものですね。
小川:『ケアの倫理とエンパワメント』にも繋がりますが、ベータの人たちというのは、要するに周りに気を遣い、ケアをし続ける人、つまり自己主張ができない人でもあると思います。私も長いことそうでしたし、女性というだけでそういう態度を常に期待されているようなところはあります。結婚して家庭に入ることを期待して、専業主婦になっていたかもしれない。ベータの人はベータでいる限り、声を発することがなかなか難しいポジションです。そこでどうやったらエンパワメントできるかという難題を抱えています。自分もいろんな戦略を使って生き延びてきた。その大大大先輩が野上弥生子なんです。
野上弥生子がすごいなと思うのは、伊藤野枝のように大恋愛を経て大杉栄と一緒になったものの、早逝してしまった人とは違い、細く長く、という生き方をしたからです。もちろん野枝は何も悪いことはしていません。ただ、自由に生きようとする人はバックラッシュにあう時代でした。他方、弥生子は、戦略を使って長生きしたことで、何冊もの小説を書き続けことができました。『迷路』や『森』といった力作は晩年に書かれています。弥生子と野枝はお友達だったし、同じ青鞜という組織のメンバーで、フェミニストだった。野枝は家庭を捨てて、自由恋愛を選んだけれども、弥生子は、夫の嫉妬狂いや所有されているという感覚にものすごく抵抗しながらも、決して家庭は捨てずに3人の息子を立派に育て上げた。つまり、ベータであり続けることで戦った人でした。
伊藤野枝は公にミソジニーに対して声を上げる。野枝は時の内務大臣後藤新平にも「あなたは一国の為政者でも私よりは弱い」と書いた書簡を送り、持論をぶつけました。 このように、野枝は公的な発言をすることで、フェミニストとして知られるようになりましたが、野上弥生子は家庭に入って普通の専業主婦を演じながら、目立たずに着々と小説を書き進めていくんです。何冊も何冊も出版することで、書いたものだけで勝負している。小説を読めば、本人が演じているベータ的な女性とは全く違う、アルファ的な側面がよぎってきます。そこには驚くほどのギャップがある。仕事をやり遂げることで実績をつくり、そうしてアルファ化していく(=声を上げていく)ことは『虎に翼』もそうだと思いますが、最近のポップカルチャーが訴え続けてるものと響き合うと思いますね。

円堂:『翔ぶ女たち』は、夏目漱石門下の作家としてスタートし、一九八五年に99歳で亡くなるまで旺盛な執筆活動を続けた野上弥生子を論じています。それだけいうと古い話と思われるかもしれないけど、松田青子、辻村深月、『エヴリシング・エヴリウェア・オール・アット・ワンス』、『水星の魔女』、テイラー・スウィフトなど、近年の作家、映画、アニメ、音楽と野上作品との内的関連を縦横無尽に論じ、女性をめぐる表現史にもなっているところが面白かったです。
私は『ディストピア・フィクション論』、『ポスト・ディストピア論』を書いた時、それぞれジェンダーに関する章を設けたのですが、後者では、クリスティーナ・ダルチャー『声の物語』のように規制して女性から声を奪う設定のディストピアSFがしばしば書かれてきたことを踏まえ、女性の「声」をポイントにして考察しました。『物語考 異様な者とのキス』でとりあげた『美女と野獣』、『ノートルダムの鐘』、『リトル・マーメイド』、『エリザベート』などでは旧弊な考えによって女性の声が抑圧される状況を考察しています。その意味で『翔ぶ女たち』で女性がどのように声を上げるかを論じたところは、特に興味深く読みました。

小川:私はアルファのように振る舞ってしまうことも多いのですが、賢い女性はうまいことベータを演じて後でやっつける。しっかりと戦略を立てれば、こんなやつすぐにやっつけられるということをしたのだと。野上弥生子は何十回も痛い目に遭ってきて、日記には憎しみを書き連ねています。例えば、能楽師で人間国宝の宝生弥一は、安倍能成の言葉に触れつつ、「弥生子は、誠に利口な人で所謂、一を聞いて十を知る、正にその通りの人であるが、弥生子をあれだけにしたのは、〔夫〕野上(豊一郎)の力が大いにあるのですよ」などと言う。今、そんなことをSNSで書いたら炎上ですね。でもそういうことに対して、野上弥生子は公然と声をあげるわけではありません。あえてそれをスルーして、書きたいことは作品でちゃんと書くということをしました。
野上弥生子は最終的には99歳まで生きて、やりたいことを全部やって、多くの人に尊敬された。一定の地位を獲得して、作家としてちゃんと生きることができた。素敵な人生を生きられた方で、すごく尊敬しています。自分があまりにも不甲斐ないので自戒を込めて、「書くことでアルファである」ことも戦略になりうるということを読者に伝えられたらと思っています。

■書籍情報
『物語考 異様な者とのキス』
著者:円堂都司昭
価格:2,860円
発売日:2024年7月24日
出版社:作品社
『翔ぶ女たち』
著者:小川公代
価格:1,760円
発売日:2024年5月30日
出版社:講談社

























