円堂都司昭 × 藤田直哉『ポスト・ディストピア論』対談「多様化が進んで軋轢も多くなるという図式になっている」

文芸/音楽評論家の円堂都司昭氏が最新批評集『ポスト・ディストピア論 逃げ場なき現実を超える想像力』(青土社)を刊行した。パンデミック、異常気象、監視社会などが身近な現実となりつつある現代にあって、小説、舞台、音楽、映像などを幅広く読み解く、「その先」のディストピア論となっている。
本書刊行を記念して、円堂氏とSF/文芸評論家・藤田直哉氏の対談が実現した。藤田氏は『シン・エヴァンゲリオン論』、『新海誠論 』、『東日本大震災後文学論』といった一連の著作で、同じくディストピアとフィクションについて論じてきた。お互いの著作内容を起点に、現代世界とディストピア、新海誠論、生殖とジェンダーなど、幅広いテーマを縦横無尽に語り合った。(編集部)
ディストピア論が困難である理由

ーー円堂さんの10冊目の単著『ポスト・ディストピア論』が刊行されました。まずは藤田さんのご感想を教えてください。
藤田:円堂さんは昔から同時代のいろんな作品を「面」で捉えていき、その時代の兆候や特徴を提出する技法で論じられてこられたと思います。今回はディストピアものの作品が増えてきた現代の状況を、様々な作品を縦横無尽に論じていらっしゃり、円堂さんにしかできない仕事だと思いました。なかでも生殖とジェンダーのテーマが前景化してきて、力を入れていらっしゃる印象で、そこが面白かったです。既存のディストピア論やポスト・ディストピア論では、そこまで重要視されてこなかったテーマでした。
僕も時代論的に「面」で作品を捉えようとしたことがあります。『新世紀ゾンビ論』(2017年)では、ゾンビの流行を通して同時代を見ようとしました。その次の『娯楽としての炎上』(2018年)は、真実が存在しなくなっているミステリーを論じることで、ポスト・トゥルース時代を論じました。また共著で『東日本大震災後文学論』(2017年)を刊行し、東日本大震災後の文学、エンターテインメント、美術、映画の変化を面で捉えようとしました。
震災後の日本文学ではディストピアものがたくさん出ていたんですよね。斎藤美奈子さんの『日本の同時代小説』(2018年)でも、日本の文学史上、2010年代は最もディストピア小説が書かれたことが指摘されています。中村文則『R帝国』(2017年)のように安倍政権的なものを想定した作品、村田沙耶香『殺人出産』(2014年)のように生殖とジェンダーをテーマとした作品などがありました。円堂さんの今回のご高著は、震災後の僕らのディストピア的な気分の正体に迫っていくような本で、そこに知的な興奮を覚えました。
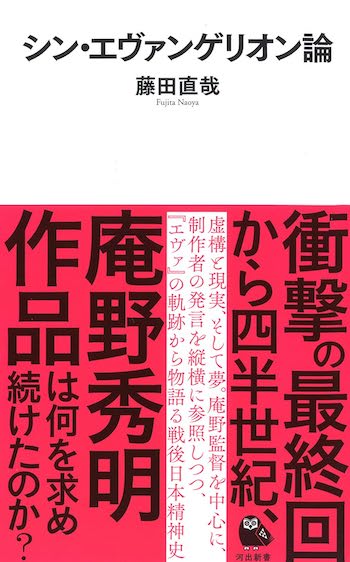
円堂:前回は2019年に藤田さん企画・編集の文芸誌「ららほら2」で、藤田さんと対談しましたね。それ以降、藤田さんは『シン・エヴァンゲリオン論』(2021年)、『攻殻機動隊論』(2021年)、『新海誠論 』(2022年)、『ゲームが教える世界の論点』(2023年)を刊行していますが、いずれもディストピアに関わる内容でした。「図書新聞」でもディストピア論の連載をされていましたね。
藤田:「図書新聞」のディストピア論の連載は途中で挫折してしまったんです。子どもが生まれたので物理的に書くことが無理になったということもあるのですが、ディストピア作品を調べていて思ったのは、基本的に、ディストピアものってあるイデオロギーで「洗脳」された社会を批判的に描くことが多いのですが、『一九八四年』(1949年)の場合だと、元はソビエト批判ですよね。しかし、その後、資本主義や管理社会批判に読み替えられる。日本でも、1980年代には、保守派がむしろ左派を批判するために持ち出すことが多かったですが、今は逆の使われ方が多いですよね。このように、対立している二つの信念を持つ陣営が、お互いに相手をディストピアに洗脳されていると罵り合いをしている状況だということに直面し、僕自身も特定の思想や信条を信じている状態で、その問題を扱いきれなくなってしまったんです。政治的思想の違いで左右が対立していたり、ジェンダーの問題でフェミニストと家父長制支持者が対立したりする、そして両者とも相手を洗脳されて真実を分かっていないと罵り合っている。この状況の構図をどう理解したらいいのかわからなくなって、書けなくなってしまいました。円堂さんは今回、そのような主題に正面から挑まれ、格闘されている痕跡を随所に感じました。
円堂さん自身はリベラルに近い思想ではないかと思われますが、扱っている作品が示すどちらかの思想に肩入れをせずに、作品を腑分けされている手つきが、特徴的だと思いました。この手法の問題も後程伺いたいですが、まず最初に円堂さんに伺いたいのは、東日本大震災から現在まで、日本でもアメリカでも、これだけディストピアものが出てきたのはなぜなのかということですね。そして両方のサイドから見て互いにディストピアだと罵り合うような現在の状況をどのように見ていますか。
冷戦崩壊した現代社会のディストピア
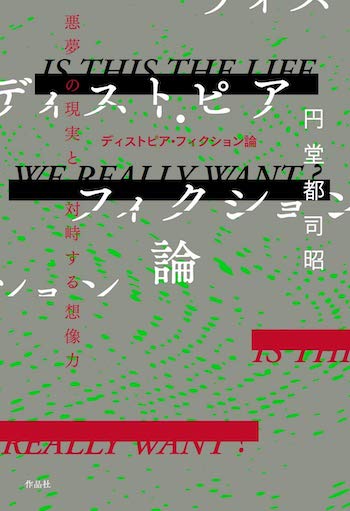
円堂:いきなり大きな質問がきましたね(笑)。どうなんでしょう。
双方がディストピアだと罵っているという話で思い出すのは、『ポスト・ディストピア論』の前に書いた『ディストピア・フィクション論』(2019年)です。そこでは、百田尚樹『カエルの楽園』(2016年)と、島田雅彦『虚人の星』(2015年)や田中慎弥『宰相A』(2015年)を対照的に論じました。
異なる意見がある時にはゾーニングをすればいいという考え方がありますが、一方でゾーニングすること自体が差別だという言われ方もしてしまう。その辺りはどうにもならないような状況がずっと続いていると思っています。
藤田さんと私は年齢差が20歳ありますね。僕が子どもの頃は冷戦の頃だから、アメリカとソ連がお互いをディストピアだと罵り合うのが当たり前だったんですよ。そこに戻ってきたようなイメージですね。
藤田:やはり冷戦構造は関係があるのでしょうね。先に少し言及したジョージ・オーウェルの『一九八四年』は今のディストピアもののモデルの一つですが、そこで描かれている世界のモデルはソビエトでしたし、「冷戦」という言葉を発明したのも、オーウェルでした。
冷戦崩壊後、多元的な世界になったと言われましたが、それが逆行するような状況が起こっているのかもしれませんね。今は「新冷戦」が起こっていると国際政治学者の方々が仰っていますが、互いに相手の体制をネガティヴに表現し、自分の体制を過大に素晴らしく見せかける情報やイメージの戦争が冷戦の特徴です。ロシアやウクライナ、イスラエルとパレスチナを巡って行われている「世論戦」「認知戦」「ナラティヴ戦」などは、典型的に冷戦という感じがします。
円堂:冷戦は大国同士の話でしたが、今はそれぞれ国内の分断もひどくなっていますね。一方で多様化を喧伝しながら、多様化が進んでるからこそ軋轢も多くなるという図式になっていると思います。
藤田:そうかもしれないですね。アメリカでトランプ支持者は、リベラルのエスタブリッシュメントに世界が支配されて、自分たちが搾取されていると考えている。一方、リベラルは、共和党を支持するような人は田舎の無知な狂信者たちだと思っていたりする。お互いに相手が洗脳されていると思っているんですね。一つの国の中で内戦のような状況にある。
アメリカでは、トランプ当選の時期に『一九八四年』が大変話題になり、ディストピアものが流行るようになりました。アメリカ政府は、トランプの当選にあたって、ロシアが介入したと認定していて、ロシアはヒラリー陣営を貶めるような陰謀論の流通にも関わっているようなので、他国の政治に介入する「積極工作」が広範に行われているという政治的現実の反映として、冷戦的な構図であるディストピアものに共鳴しやすいリアリティの中に人々が生きるようになったのかもしれない、とも思ったりしています(この辺りは、夏ごろに刊行予定の単著『現代ネット政治=文化論』で本格的に論じていますので、参照していただければと思います)。

ーーお二人は共通して新海誠を論じています。どのように評価しているかを教えてください。
藤田:最近はディストピアものが増えていますが、新海誠の『天気の子』(2019年)はそのような認識が蔓延していることを逆手にとった作品でした。円堂さんも引用されていたように、新海さんは国連広報のインタビューに応えて「日本の観客について言うと、気候変動を連想する人はほとんどいなかったような気がします」と話していました。私も毎年授業で扱いますが、初見で気候変動の話だと認識している学生はほとんどいないですね。
キャラクター文化が強く、推し的な感性が流行している時代なので、キャラクターを中心に見ていて、その背景に起こっていることは認識できていない傾向があります。画面に異常気象の様子が露骨に映っているのに見えていないし、同じくあからさまな貧困の主題も認識されない傾向があります。その様子について考えさせられることが多いのですが、おそらく、我々が現代社会を生きる時、現実にあることや未来の深刻な現実を自然と否認するようになっているんじゃないかと思うんです。気候変動や少子高齢化や日本の衰退、深刻な現実や社会の問題は、考える無力感があるし鬱や不安が出てくるから、脳が認識せずキャンセルしてしまう癖がついているのではないかと。むしろ、それを忘れるためにこそ、アニメやゲームの世界に没入したりしている。あるいは、「日本スゴイ論」とか陰謀論を信じて、現実に起きていることを否認してしまう。それがおそらく、現代的な適応なんだと思うんですよ。『天気の子』はそういう文化的な感性が蔓延した社会に向けて、その構造自体を突きつける野心作だと思います。
円堂:しかし結局、観客はキャラクターしか見ていないと……。物語の構造としてはかなりはっきりと描かれていますよね。特に少女・陽菜は経済的に困窮していて、貧困問題があるのは明らかなはずです。なのに伝わらないのかと。
藤田:不思議なんですよね。他の国では、そういう傾向は少ないようなので、日本の特徴なのだと思います。そのような感性は、一時的に楽になるかもしれないけど、最終的に自分たちの首を絞めるので、やめたほうがいいと思うのですけれど。一方、新海さんと同じように僕も子どもがいるから思うんですが、世界が危機的な状況であることをわかっていても、子どもたちが生きていく未来に対して、生命力を信じていきたいという気持ちもわかるんです。だから、気が滅入ることや絶望的なこと、無力感を覚えて未来を悲観してしまうことばかり突きつけるだけでなく、ポジティブに励ますことも必要である。「大丈夫」と言う必要がある。難しいですよね。
もう人類の絶滅が国連で話題になるような現状である。世界で気候変動は深刻で毎年暑くなっていて、山火事が起こっているし、戦争は各地で起こっている。日本の衰退や貧困化も毎日報道されています。こんな時代にとても子どもを産みたいなんて思えないでしょうし、子どもたちが元気が出ない、自殺率が上昇していくし、非現実に逃避したくなるのはよく分かります。でも宮﨑駿は「子どもたちに向かって絶望を説いてはいけない」という旨を述べています。それでは、生きていけない。まだ滅びていないんだから、可能性を信じるしかない。『天気の子』は、そういうジレンマの中で、エンターテインメントの現代的使命を必死に考えている感じがしました。




















