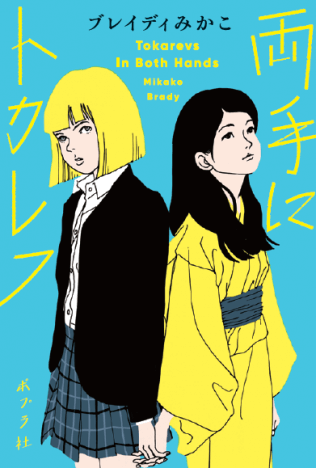「あらゆる場面で意識する存在」三谷幸喜、ジェームズ・サーバーからの影響と『世界で最後の花』の魅力
――村上春樹さんの新訳はいかがでしたか。

三谷:まず、どうして僕に訳を依頼してくれなかったのかと(笑)。それはさておき、誰にでもわかる平易な言葉で、しかし決して言葉足らずにはならない表現で、サーバーの想いを汲みとって訳してくださったことに感謝しています。何より、リズムがいいですよね。原文を生かしているんでしょうけれど、最後の数ページは口ずさむだけで心地がいい。戦争の悲惨さを伝えるものだから、内容的には決して心地いいものではないんだけれど、くりかえしページをめくらずにはいられなかった。
――言葉だけでなく、絵の線もシンプルで、より心を打たれました。
三谷:独特のタッチですよね。すごく好きです。たぶん、この絵じゃなかったら作品の印象もずいぶん変わっていただろうな。
――公演中の舞台『オデッサ』はアメリカが舞台ですが、ウクライナの都市の名前でもありますよね。ストレートにテーマを掲げたことはない、とのことでしたが、言葉や文化背景による人のすれ違いなど、時勢に照らして描きたいと思われたものもあったんでしょうか。
三谷:ごめんなさいね、全然そんなことは考えていないんです。出発点は、宮澤エマさんと迫田孝也さんの出演が決まったこと。宮澤さんはアメリカ出身のお父さんの影響で英語がペラペラ。そして迫田さんは鹿児島出身で、大河ドラマの薩摩弁指導をされるくらい鹿児島弁がペラペラなんですよ。だったら、英語と薩摩弁が入り乱れるようなお話にしようと。
――その設定だけでおもしろそうですね。
三谷:でしょう。じゃあ舞台はどこにするかと考えて、アメリカの片田舎がいいと思いつき、テキサスで印象的な名前の町を探していたら、オデッサに行き当たったというだけ。オデッサはかつて鉄道を敷くために移民労働者を大勢受け入れていて、そのなかにいたロシアの方が「ウクライナのオデッサに風景が似ている」ということで名づけられたそうです。でも、物語そのものは戦争とも関係はないですね。
――深読みしてしまいました。『オデッサ』のなかにも、三谷さんの中のサーバーイズムは流れているんでしょうか。
三谷:『オデッサ』に限らず、僕の作品には全てサーバーイズムが流れています。そもそも老後の理想は、サーバーのような偏屈なおじいさんになることですから。のらりくらりと視点をずらしながら物事を見て、自分なりに解釈しながらユーモアをまじえて語れる、そんな年寄りになりたい。『ニュースキャスター』に出ているときも、理想はそれです、難しいけど。ただ、サーバーの短編なんかを読んでいると、この人はオブラートに包んだふりをして、実は何も考えていないんじゃないかと思うときもある。深読みしたければ勝手にどうぞ、みたいな。案外そっちが正しいんじゃないかな。
――三谷さんが、オデッサという町を、たまたま響きのよさで見つけたように。

三谷:本来は、サーバーに裏の意味なんて探っちゃいけないような気がするんですよね。皮肉屋の作家が見たニューヨーカーたちの生態を、冷静に突き放して描く。そこに自然とユーモアが浮かび上がる。それ以上でもそれ以下でもない。それがサーバーの正しい読み方なんじゃないか。だからこそ、繰り返しになりますけれど、『世界で最後の花』のようにメッセージ性の強いものを描いたときに、逆に凄まじいパワーが生まれるのかもしれないけど。