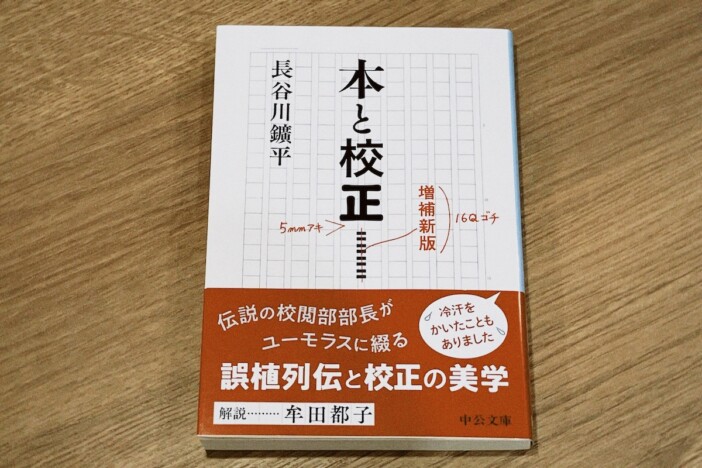小説家・小川哲が問う「噓の功罪」とは『君が手にするはずだった黄金について』書評

「僕」曰く、小説家とは、空手形に終わる可能性のある契約を繰り返し、その都度どうにか作品を綱渡り的に成立させ続けるアクロバティックな職業である。ならばたとえば、希望の職を得るために自身をより良く誇張して書かれたエントリーシートと、誰かの好意を得ようと咄嗟に口から出た作り話と、相談者の安息を願って演出された占いと、小説家の仕事はいったい何が異なるというのか。ゆえに「僕」は、小説家である自らを「虚構を売り買いして生きるだけの偽物」と卑下し、詐欺師に共感しさえする。かくして本書のひとつの見所は、「僕」あるいは小川哲という小説家が、いまの世の中で噓を仕事にする、すなわち小説家であるとはどういうことか、という難問にいかに取り組むのか、という点にある。むろん、答えを出すのは容易ではないが、それでも自省的にみずからの噓を点検し、少しでも誠実であろうとすること。本書中のある短編で「僕」は、このように心境を吐露する。
僕は、結局短編小説をすべて書き直した。できあがったものは相変わらず噓ばかりだったし、改稿する前より面白くなっていたのかどうかもわからなかったが、少なくとも噓に対して誠実に向き合うことができたのではないかと思っている。(『君が手にするはずだった黄金について』P124より)
たとえば、「理性」に基づく知的な文化社会の構築可能性を模索しようとした「近代」という時代であれば、フィクションはその補完物として多少なりとも有益性を持ったかもしれない。だが、ある者はなんの躊躇いもなく噓を世に放ち、ある者は噓を諸悪の根源として敵対視する、そんな現代で、噓を生業とする「小説家」は「誠実」たり得るか。ひとつの歴史的な職業としてその座を自明視するのではなく真摯に、噓をつくという行為と向き合い、嘘との共生可能性を模索する以外に小説家という仕事を、小説という営みを「誠実」に継続する方途はないだろう。むろん、そうした反省的な態度もまたパフォーマンス=噓である可能性は拭い切れない。が、それでも、嘘の功罪に目を向けようともしない者よりは、よほど信頼に足るように思われるのだが――そういう言い方をすると小説家に肩入れしすぎだろうか。「でも僕には、そうとしか思えなかった」のだ。まるで小説家の「僕」が、詐欺師となった旧友・片桐に、最後まで共感の心を捨て切れなかったのと同じように。
本書の最後に置かれた一文で、すなわち、断片的な自省を繰り返し、ひととおりの点検を終えたのち、あらためて「僕はラップトップに向かって文章を書きはじめる」。それは「「あなたの人生を円グラフで表現してください」という質問で、それまで順調だった僕の手が止まってしまった」という、ある種のライターズブロックの描写から始まった本作に相応しい感動的な結末であるだろう。ふたたび小説は書き始められる。「僕」が繰り返し夢見た「奇跡」のような瞬間にむかって。