痔、八百長告発、自決……定年のない文豪たちにとっての「45歳」とは
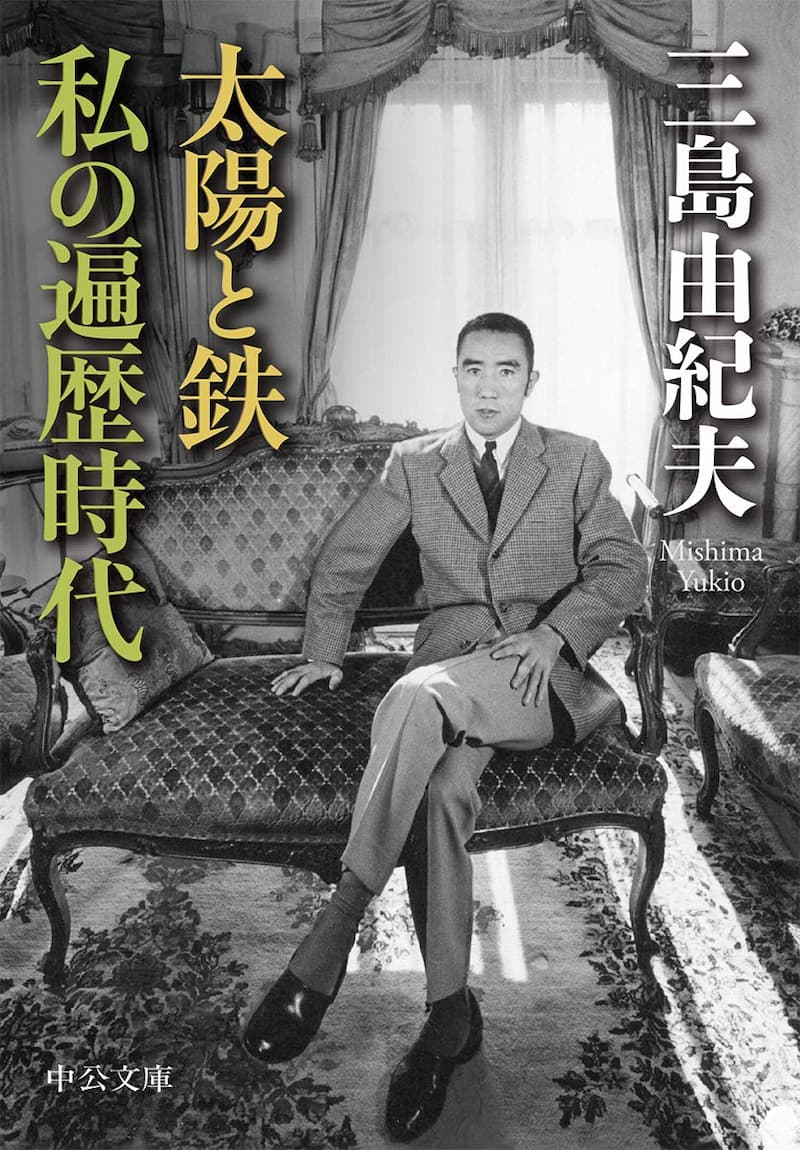
人材の流動化の一環として経済界で提案が出され、物議を醸している45歳定年制。45歳というと、会社一筋の人間なら管理職にでもなっている頃。まだバリバリ働ける年齢で、しかし転職するのは厳しそうな微妙なラインといえそうだが、定年という制度のない作家にとって45歳とはどんなものなのだろう。日本文学を代表する作家たちの年譜を見てみると、それぞれに興味深い年となっている。
たとえば夏目漱石は、1912年9月に2度目の痔の手術を受けている。その時の様子を〈秋風や屠られに行く牛の尻〉なんて句にした漱石は後年、小説の中でも痔の治療を描いている。作者病没により未完となった長編小説『明暗』、この作品で鍵となるのが主人公・津田の患う痔なのである。
津田が痔の手術を受けるにあたり、入院期間は1週間程とまあまあ長いが、深刻な病というわけではないし術後に喋る元気だってある。それゆえに、妻のお延がずっと付き添う必要もない。津田は妻の居ぬ間に、元恋人・お清への未練について過去を知る人物と話し合える。お延はお延で夫の隠し事に勘づいて、密かに真相を突き止めようとすることもできる。しかも痔は、気持ちのすれ違う夫婦を、バラバラに動かすための設定として機能するだけではない。津田の痔の症状=失恋の苦しみと、読者にイメージさせることもできる。痔瘻はつらいが役に立つとは、入院当時、漱石といえども思いもよらなかったのではないか。
日本における探偵小説の先駆者である江戸川乱歩は、数え年45歳の時に逆境を迎える。短篇「芋虫」が初出から10年経った1939年3月に、時局にそぐわないとして発禁処分となってしまったのだ。
一体どんな小説だったのかというと……。戦争で腕と脚をほぼ根元から失い、耳は聞こえず口もきけない状態で生還した夫。妻の時子はその姿に慣れてくると、彼の体を玩具とみなし、〈肉慾の餓鬼〉となって弄ぶことに喜びを見出す。時子の嗜虐性は過激さを増していき、やがて悲劇が起きてしまう。
反戦を意図したわけではなく、作者曰く〈極端な苦痛と快楽と惨劇とを描こうとした〉(『探偵小説四十年』)本作は、罪に対する赦しを描いた作品でもある。酸いも甘いも噛み分けた年齢、それこそ40代も半ばになって読んでみると、より物語の味わいが増しているはずだ。
文豪たちの中でも、特に波乱万丈な45歳の年を過ごしているのが、評論『堕落論』や小説『桜の森の満開の下』で知られる無頼派作家・坂口安吾である。10月で45歳となる1951年の1月1日に、新聞社の企画で旅客機の戦後初飛行に搭乗。5月に税金滞納で留守中に家財と蔵書を差し押さえられる。9月には、遊びに行った静岡県伊東市の競輪場でレースに不正があったとして、検察庁に告発状を提出。11月に催眠薬の多量接種で半狂乱となり、居候先である作家・檀一雄の家にライスカレー100人前を注文する(筑摩書房『坂口安吾全集 別巻』年譜より)。
安吾との結婚生活を綴った坂口三千代『クラクラ日記』によると、安吾は好きな仕事相手に原稿を依頼されると断れない癖があり、限度を超えた仕事量をこなすために覚醒剤と睡眠剤を常用していたという。次第に精神状態は悪化し、正気を失い、いら立ちを人にぶつけることもあった。それでも三千代は別れようとは思わず、夫を見守り続ける。
不可解なくらい不正レースに入れ込むのも、〈これも、やはり探偵趣味と実証精神に他ならない〉と奇行扱いせず、カレー事件もユーモアたっぷりに当時の状況を描写しながら、〈いまはオカシクてしようがないような気持ちで思い出される〉と語る。
本書のあとがきで三千代は、〈どうも彼のいい面、善行の部類はとうとう書けずじまいで、(中略)善いこと、というものは誰がしても同じようなことをするので、余り個性がない故(せい)ではないだろうか、などと思いました〉と書く。作家の個性を尊重する人と一緒になれた安吾は幸せ者だと思うし、夫婦揃ってすごい書き手だと唸らされる。


























