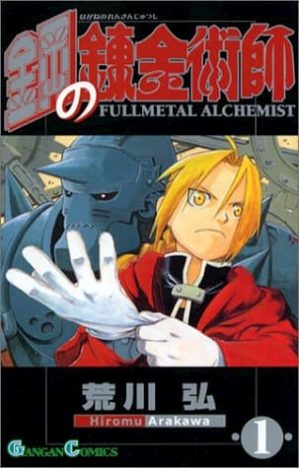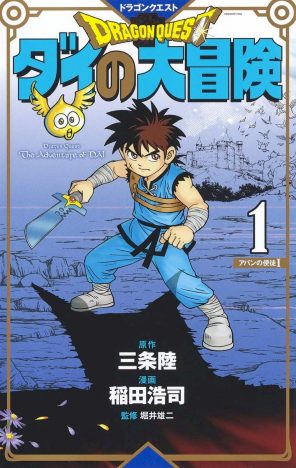セガは任天堂からいかにして「クリスマス」を奪った? 「PlayStation」誕生のサブストーリーも読ませる『セガvs任天堂』

2020年11月、新たな家庭用ゲーム機が登場する。ソニーの「PlayStation5」とマイクロソフトの「Xbox Series X/S」だ。そこに任天堂の「Nintendo Switch」が加わり、現在のゲーム機戦争はこの三者によって繰り広げられている。そこにはかつて独特な存在感を発し、アメリカで一大旋風を巻き起こしたゲーム機メーカーの姿はない。セガである。
『セガvs任天堂 ゲームの未来を変えた覇権戦争』は1990年代のアメリカで家庭用ゲーム機で90%というシェアを築いていた任天堂という帝国に、当時ほとんど無名であったゲーム機メーカーのセガ(アメリカ支社セガ・オブ・アメリカ)が5%だったシェアからたった3年で55%まで伸ばし、任天堂を抜いて北米ゲーム市場のトップに立つまでの物語だ。
本書の主人公であるトム・カリンスキーはバービー人形で有名な米国の玩具メーカーを退職後にセガの社長中山隼雄から引き抜かれ(プールサイドで対面する2人はまるで引退したエージェントに現役復帰をもちかけるスパイ映画のワンシーンのようだ)セガ・オブ・アメリカ(SOA)社長に就くと、セガの16ビットの新型ゲーム機「ジェネシス(日本ではメガドライブ)」を武器にマーケティングによって瞬く間に任天堂のシェアを切り崩していった。

遡るとアメリカのゲーム市場の売上げは1982年の時点で約32億ドルに達していたが、1985年にはわずか1億ドルまで激減していた。原因は「アタリショック」だった。
「アタリショック」(米国では“Crash of 1983”)と呼ばれるアメリカのゲーム市場の崩壊は、流行の終焉や出来の悪いソフトの粗製乱造、マーケット規模以上の供給による飽和、PCゲームの台頭などいくつかの要因で引き起こされた(アタリショックのアイコンともなったクソゲー『E.T.』が砂漠に埋められたという都市伝説を追ったドキュメンタリー映画『ATARI GAME OVER』が面白い)。
このアタリショックによって焦土と化した北米のゲーム市場に「Nintendo Entertainment System NES」(ニンテンドーエンターテインメントシステム、日本のファミコン)で新たな秩序を生み出し、北米でゲーム市場を再び興したのが任天堂だった。
任天堂はアタリショックの同じ轍を踏まないよう慎重にゲーム市場を育て(商品名にcomputerやVideo Gameという言葉を避けたほど)、アタリショックの反省のもと90%というシェアを背景に任天堂が市場をコントロールにしていた。
一例として「任天堂品質保証シール」は他メーカーのゲームを任天堂が厳しく審査し任天堂にふさわしいゲームかを審査、保証する制度で、承認を受けなければ任天堂のゲーム機からゲームを発売できない。また流通においてライセンシーや小売店からの発注数より意図的に出荷数を低く抑えることで品薄感を出し消費者の熱狂的な購買意欲を掻き立てる流通戦略をとった。そのほかソフトメーカーには高額なロイヤリティ(1本10ドル)や年間5本というリリース制限、生産やスケジュール、価格までも任天堂が管理していた。
その厳格なまでの任天堂の支配体制にはそれだけの見返りがあるだけに小売店やメーカーは不満があるものの渋々従っていた。そこにもう一つの選択肢を提示したのがセガのカリンスキーだった。
彼は任天堂に対して自社のポジションを明確にするために、取引面では小売やメーカーに対して任天堂への不満を解消する方向で動き、ソフト製作については自由と解放を目指した。また任天堂のメインユーザーである子どもを獲得するのは諦め(「子どもは全部任天堂にくれてやる」)、「ティーン層」をターゲットに“クールなセガ”というイメージ戦略でティーン層を総取りすることになる。
そのマーケティング戦略は日本では馴染みのない比較広告だった。カリンスキーが(チビの配管工と呼ぶ)任天堂の顔である「マリオ」に対抗し、セガは独自のキャラクター「ソニック」を誕生させ、いままでにないハイスピードなゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のCMに時間が止まって見えるほどの任天堂のゲーム映像を比較としてはさみ込んだ(ソニックのデザイン誕生についても面白い)。果たして「子どもたちがクリスマスに欲しいプレゼント」は任天堂からセガに変わり、任天堂から「クリスマスまでも」セガは奪うことに成功する。
また任天堂が極秘にしていた重大発表直前にセガのチームはスパイ活動(笑)で発表内容を知り、任天堂の発表の出鼻を挫くべくカウンターとなる施策を“以前から予定してた風”に徹夜ででっち上げるなど、挑戦者特有の高揚感にも包まれていてセガの行動一つ一つにワクワクしてくるのだ。