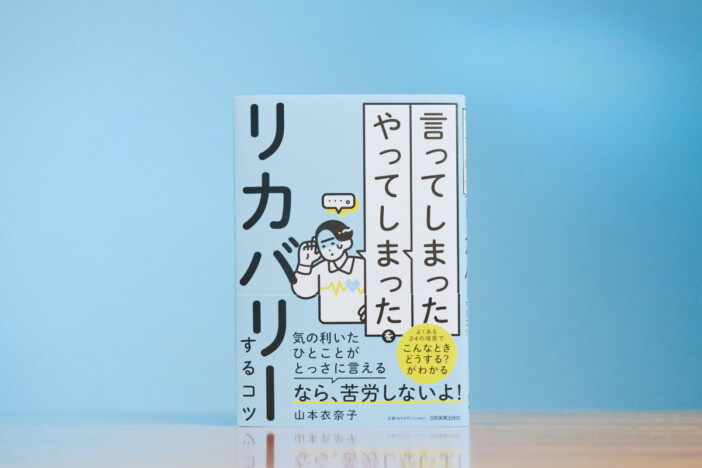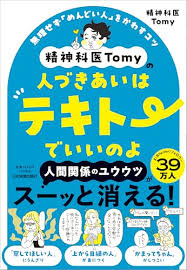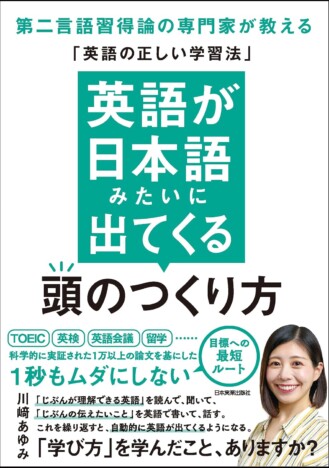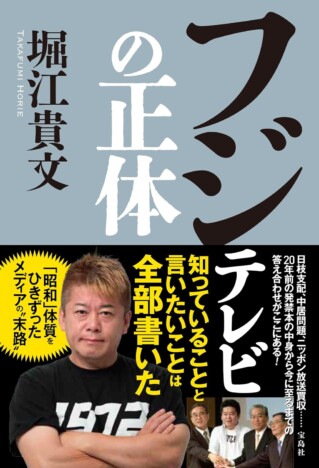話題書『「言ってしまった」「やってしまった」をリカバリーするコツ』から学ぶ“コミュ力”の基本
■気の利いたひとこと、なんて言えばいい?
SNS全盛の時代、大手企業ではトラブルの火消しがうまくいかずに、後々大問題に発展するケースが増えている。
ビジネスパーソンともなれば、ミスやピンチは誰にでも起こりうる可能性がある。家族や友人、ご近所付き合いでもちょっとしたトラブルは日常茶飯事ではないだろうか。しかし、その後どのようにフォローをしたらいいのか、わからなくなってしまうことも多いはず。そんなときに役立つ話題の書籍が『「言ってしまった」「やってしまった」をリカバリーするコツ』(日本実業出版社)だ。
著者は、プレゼンテーションプランナー・伝わる表現アドバイザーの山本衣奈子氏。コミュニケーションの講師として、企業研修や講演を多数手がけており、これまでの総受講者数はなんと5万人を超えるという。まさにコミュニケーションを熟知したプロフェッショナルだ。
この度、刊行された本書『「言ってしまった」「やってしまった」をリカバリーするコツ』では、日常のよくある24の場面を具体例として取り上げて、それぞれの適切な対応策を明快に解説している。
たとえば、知人と会話をしていて、うっかり相手を否定してしまった場合のフォロー方法が紹介されている。相手から「なんでそんな否定的な言い方しかできないの?」とムッとされてしまったとき。特に「だけど」「でも」「だって」「どうせ」といった、頭文字「D」から始まる「Dワード」は、相手にネガティブな印象を与えてしまうという。それをうっかり言ってしまったときの対処法として山本氏が勧めるのは、その後に「というのも」と付け加えて、理由を説明すること。人は何かを納得するためには、理由が必要だからなのだという。
たとえば、エレベーターで顔見知りの人と乗り合わせて挨拶をしそこねてしまったとき。そこまで近しい関係でないと、どういう一言を声をかけたらいいのかわからなくなる。そんな気まずい状況では、去り際に一言「お先に失礼します」「どうぞ」などと一言添えて会釈をするといい、と山本氏はアドバイスする。これは心理学の「ピークエンドの法則」に基づいているそうで、人の記憶や印象に最も印象が残るのは感情が高まったとき(ピーク)と最後(エンド)の部分であるため、別れ際の一言によって好印象を残すことができるとのこと。この法則は、エレベーターのシチュエーションに限らず、関係性がぎこちなくなってしまった状況一般に応用できそうだ。
リアルサウンドブックに掲載されたお笑い芸人・オズワルド伊藤氏との対談のなかでは、山本氏は、もし相手の意見に同意できないならば、必ずしも自分の意見を抑圧する必要はないと語っている。
「コミュニケーションは必ずしもいつも『そうだよね』『わかるわかる』となるわけではありません。お互いに違う部分を出し合ってもいい。ただそこでは攻撃し合うのではなく、相手を尊重しながら意見を言えるといいと思います」
大ピンチ発生! リカバリーどうすれば? 話題書の著者・山本衣奈子×謝罪のプロ・オズワルド伊藤に聞く極意
これまで5万人以上にコミュニケーションのアドバイスをしてきた山本衣奈子氏が『「言ってしまった」「やってしまった」をリカ…
相手を真っ向から否定するのではなく、そして同時に自分が率直に感じた思いを大事にしながら、会話を前向きで建設的なものに発展させていくべきなのだ。
上記のような事例を読んでいると、自分自身のこれまでの失敗を思い出すはず。そういう場面では、なんとなく気まずい関係性が持続してしまって、その後に適切にリカバリーができていないということも多い。大失敗であれば、すぐに謝ることになるかもしれないが、ちょっとしたモヤモヤが生じたような状況では、その対処法は意外とむずかしいもの。それが本書では、心理学などの幅広い知見をベースとした上で、具体的で実践的なリカバリー法が紹介されている。一度通読したあとは、日常生活でそれに類する悩みに実際に直面したときに、その箇所を読み返してみるのもよさそうだ。
近年「コミュ力」という言葉が広く浸透している。仕事でも友人・恋愛関係においても、必須スキルだとされることも少なくない。確かにそれがあるのにこしたことはないのかもしれないが、そういう価値観が流布したがために「自分にはコミュ力がない」と劣等感を持つ人も多い。しかし、本書は、コミュニケーションの失敗は誰にでもあって、完璧じゃなくてもいいということを教えてくれる。言葉のかけ方は相手や状況によって変わるし、そこに絶対的な正解はないのだ。
さらに新鮮だったのは、山本氏が書籍の中でコミュニケーションにおいて一番大事なのは「あなたが“良い気分・良い状態”であること」だと指摘していること。過度な無理や我慢の上にメソッドを磨いたとしても、コミュニケーションを楽しむことからは遠かってしまうのだという。まさにその指摘の通り、本書を通読すると、コミュニケーションの失敗を糧にしながら、人との関わりを前向きに楽しもうという気持ちが湧いてくる、ポジティブな気分になれる清涼感ある書籍である。