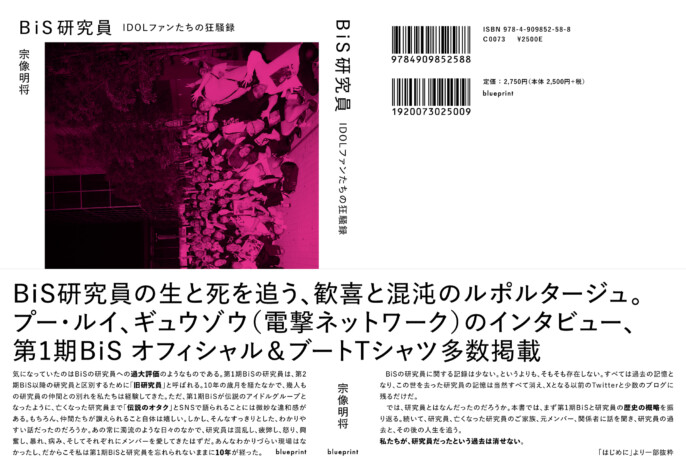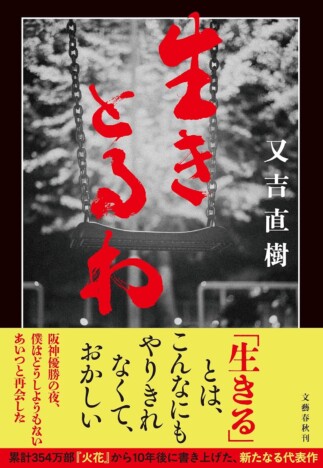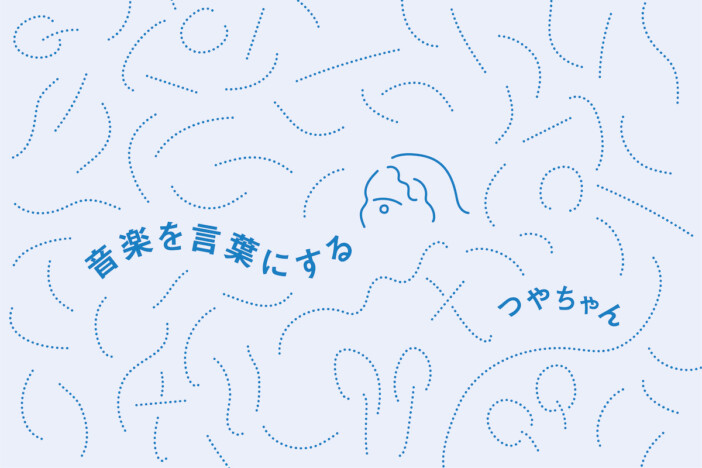【新連載】柳澤田実 ポップカルチャーと「聖なる価値」 第一回:孤独なポップスターの音楽に聖性は宿る

音楽や映画、アニメなどのポップカルチャーは今、どのような形でユーザーに受容されているのか。「推し活」という言葉の広がりとともに、多くのユーザーは一時的な楽しみではなく、生きがい等の精神的な価値をも見出しているのではないだろうか。
現代のポップカルチャーやそのファンダムには「聖なる価値」を求める指向性が存在する。そう指摘するのが、哲学・キリスト教思想を専門とする哲学者の柳澤田実である。音楽や映画の創作および受容において、「聖なる価値」を求める動きはなぜ生まれ、どう広がってきたのか。柳澤田実が具体的なアーティストや作品を論じつつ、ポップカルチャーの動向と「聖なる価値」について探求する新連載をお届けする。(編集部)
1.ストリーミングとコロナ禍が産んだ没入型の音楽体験
ストリーミング・サービスが日本に広がり、2020年代半ば現在、多くの音楽リスナーはインターネットを通じて、一人で音楽を聴くようになった。もちろんCDやカセットテープやレコードしかなかった時代、テレビやラジオを通じて音楽を視聴した時代にも、音楽は徐々に一人で聴かれるようになっていただろう。しかし、2019年の年末から世界中がコロナ禍に席巻され、人と集まること自体が困難な数年間を過ごす中で、音楽のみならずあらゆるジャンルの作品を、ネットを介して個人的に消費する傾向が強まったのは間違いがない。私たちは1日の長い時間をスクリーンを観るか、ストリーミングの音楽を聴いて過ごすようになり、自分にとって好ましい知覚体験に没入しながら生活をしている。
こうしたメディア体験の変化の中で、すでに1990年代以降徐々に強まっていた、ポップミュージックの内省的な傾向、つまりアーティストが作品のなかで自分自身の感情や思考に沈潜していく傾向もまた、一層強まったように感じる。それ以上に興味深いのは、こうしたタイプの楽曲が、リスナーの大きな支持を得る、時代を代表するポップソングになったことだ。これらの作品では、パーソナルな問題がスケールの大きな世界や宇宙、生や死をめぐる実存的問いや宗教的世界観に結びついている。また、アーティスト個人が、深い内省を、「捧げる」とさえ言えるような仕方でパブリックに示す態度によって、独特の聖性を纏う作品やパフォーマンスが増えているように見える。
この連載では、2020年代のポップカルチャーに見られる、この時代特有の宗教性、神聖性について探究してみたい。それは一方で1960年代以降の個人主義的で没入体験を重視するカルチャーの展開を追うことを意味する。と同時にそれは、パンデミックの四年間が私たちの精神文化に与えた影響の一端を検討することにもなるはずだ。コロナ禍は確かに私たちに不可思議な空白の時間を与えたが、そこで知った孤独がアーティストやカルチャーの受容者に対し、様々な創造的展開を生んだ可能性を示したい。私たちが皆体験した時間の中で起きた変化は、きっと悪いことばかりでもなかったはずだ。
2.祭りと儀式
始まりに立ち返って考えるならば、音楽は、人類史上、常に宗教と密接だった。複数の進化生物学者は、音楽が人間同士の絆、共同体の結束を強めるために生まれたと考えている。進化生物学者のダンバーによれば、音楽はエンドルフィンという脳内物質を出すことにより、他の人との一体感を生むのと同時に、人を痛みに強くする(※1)。このことを根拠に、先史時代の人類は戦いの前に歌を歌ったと主張する研究者もいる(※2)。また、エンドルフィンは人に帰属意識を与えることから、人は地元や民族が同じであること以上に、同じ音楽の趣味の人に親近感を感じるというデータもある(※3)。音楽はその始まりから人々を励まし、鼓舞し、一つにするものだったのだ。
宗教もまた、人間の共同体が数百人規模から数千人規模に移行した時点で、より多くの人たちを結束させるために生まれた(※4)。どんな宗教にも音楽がある。キリスト教は、欧州でオルガン曲や合唱曲として高度に礼拝音楽を発展させ、アメリカ合衆国ではゴスペル(黒人霊歌)を産んだ。後者がブルース、ジャズ、そしてロックのベースになったことはよく知られているところだろう。これらの音楽もまた人々の一体感を強めるものだったが、同時にキリスト教という宗教の特徴でもある、人間の内面を重視する傾向は、内省的な音楽の発達を促した。特に過酷な差別を生きていたアフリカ系アメリカ人の音楽は、非常にスピリチュアルで没入的な性格が強い。この伝統は確実に今日のブラック・ミュージックに継承されているし(このことは連載の中で改めて取り上げたい)、聖霊の働きを信じるペンテコステ系の黒人教会から影響を受けた1950年代のエルビス・プレスリーは、祭りとしての一体感と共に、内省的で没入的なキリスト教音楽の性格をロックへと架橋した。
音楽が持つ二つの性格、つまり一体感を強める「祭り」的な性質と内省的性質は、個々の時代の流行のなかで前傾化したり後景化したりしているように見える。最初にロックが全面的に華開いた1960年代、ウッドストックのような文字通りの「祭り」が最高の盛り上がりを見せたが、同時に内省的な音楽も豊かに生み出された。例えばボブ・ディランは、哲学的で聖書へのレファレンスの多い、預言者のような詩を歌うアーティストだが、60年代当時は彼単独でスタジアムツアーをできるほどの大スターでもあった。しかし、続く70年代、80年代になり音楽業界がより巨大な産業になるにつれ、コマーシャルな音楽がメインストリームになり、内省的でスピリチュアルな音楽は、本流に対する傍流(オルタナティブ)として位置付けられるようになる。この時期に、臆面もなく難解で宗教的なテーマの楽曲(例えば「サイン・オブ・ザ・タイムズ」のような曲)をポップソングとして商業的にヒットさせることができるのは、プリンスのような例外的な存在だけだったように思う。
こうした80年代までの商業主義に反発する形で80年代後半から90年代に世界的なヒットを放ったU2やREM、The SmithsやRadioheadなどのオルタナティブ・ロックが、今日に直結する形の内省的な音楽がメジャーになる可能性を開いたのは間違いがない。他方でこの時期に若者を没入体験に導いたのはテクノだった。この時期、米国から欧州、そして日本においてさえ、クラブでは夜な夜なレイヴやパーティーが開かれ、多くの若者たちが光と音のなかで踊り、我を忘れた。しかし、これらの90年代の没入型の音楽が現在の「聖性」を感じさせる作品群とどこか違って見え、聴こえるのは、ロックやテクノの激しいビートに集団が熱狂する空間は、集団の一体感のほうが全面化した「祭り」だからだろう。今日のスピリチュアルなポップ・スターたちが作り出す世界は、「祭り」というより、孤独で崇高な「儀式」としての性格が強い。
現代の内省的なポップスに特徴的なのは、何より演奏するミュージシャンが孤独な個人であることを全面的に表現し、その個人的な孤独にリスナーも、個人として呼応し、向き合う点にある。例えば50、60年代の「ロックの王様」、プレスリーや、80、90年代の大スター、マイケル・ジャクソンが、心身ともに不健康だったことは、今ではよく知られている。しかし当時は彼らがいかに目に見えて異常だったとしても、それをオーディエンスが「わかっている」ことはタブーだった。ところが2020年代現在、自分の不安、暗い願望、焦燥や孤独を歌うことは、むしろマジョリティの聴衆に求められている。孤独であることを表明するポップ・スターの孤独な音楽に没入するために、数万、数十万単位の群衆が結集する。巨大ホールやスタジアムで、たった一人で内省的な歌を歌い上げるアーティストと、光る携帯電話を掲げ、音楽に沈潜しているファンが集結している様は、しばしば荘厳な「儀式」のような雰囲気を醸し出す。
オルタナティブ・ロックの内省的性格が、ジャンルを超えて影響を与え始めていることを批評家たちが認識したのは2000年代のことで、2004年にデビューしたYe(カニエ)はこうした表現をヒップホップに持ち込んだ先駆者として位置付けられている。そこから20年の時を経て、最もストリーミングされる音楽を制作するのは、不安に満ちた内省をポップソングへと昇華できるポップスターになった。2024年にニュー・アルバムを出し、ヒットを記録しているアーティスト、ビリー・アイリッシュやザ・ウィークエンド、宇多田ヒカルや米津玄師はこの系譜の代表格だ。この神聖性を体現するアーティストの系譜には、先述のYeやケンドリック・ラマー、フランク・オーシャン、トラヴィス・スコット、ラナ・デル・レイ等を加えることもできるだろう。
(※1)ダンバー、148頁。
(※2)ジョーゼフ・ジョルダーニア『人間はなぜ歌うのか?:人間の進化における「うた」の起源』森田稔訳、2017年。
(※3)ダンバー、122頁。
(※4)ロビン・ダンバー『宗教の起源』小田哲訳、白揚社、198頁。