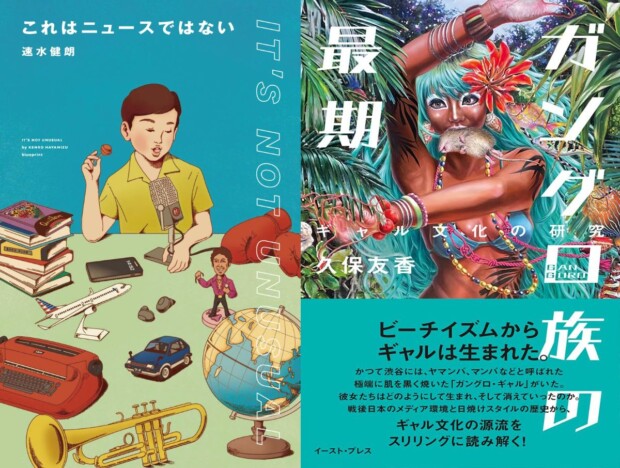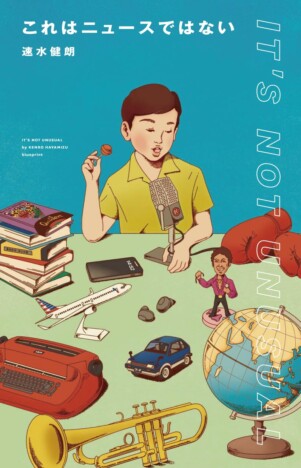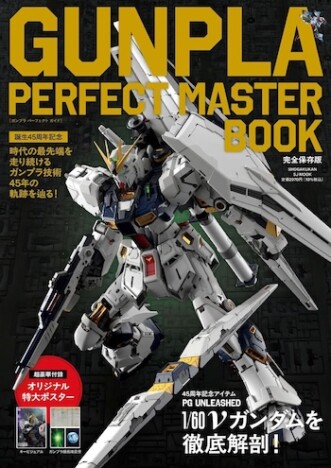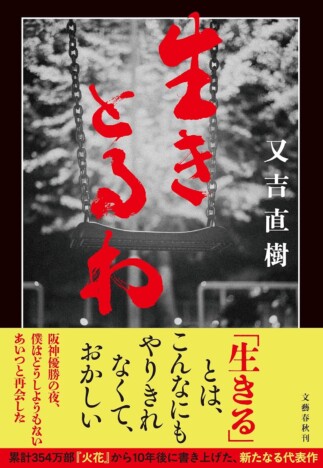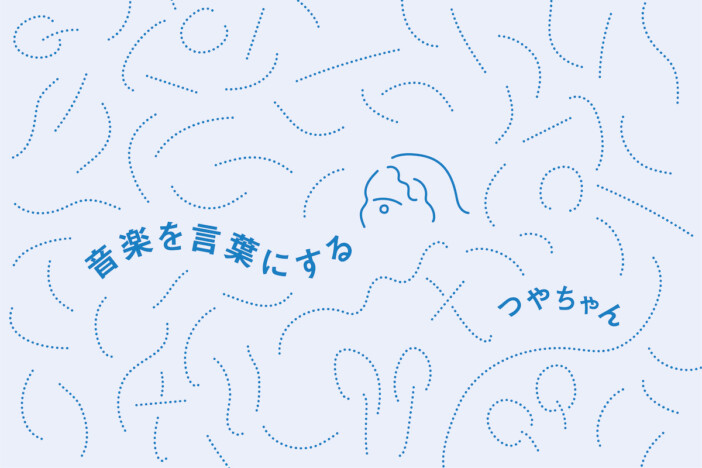速水健朗のこれはニュースではない:共感から反感へ、そしてデスゲームの時代
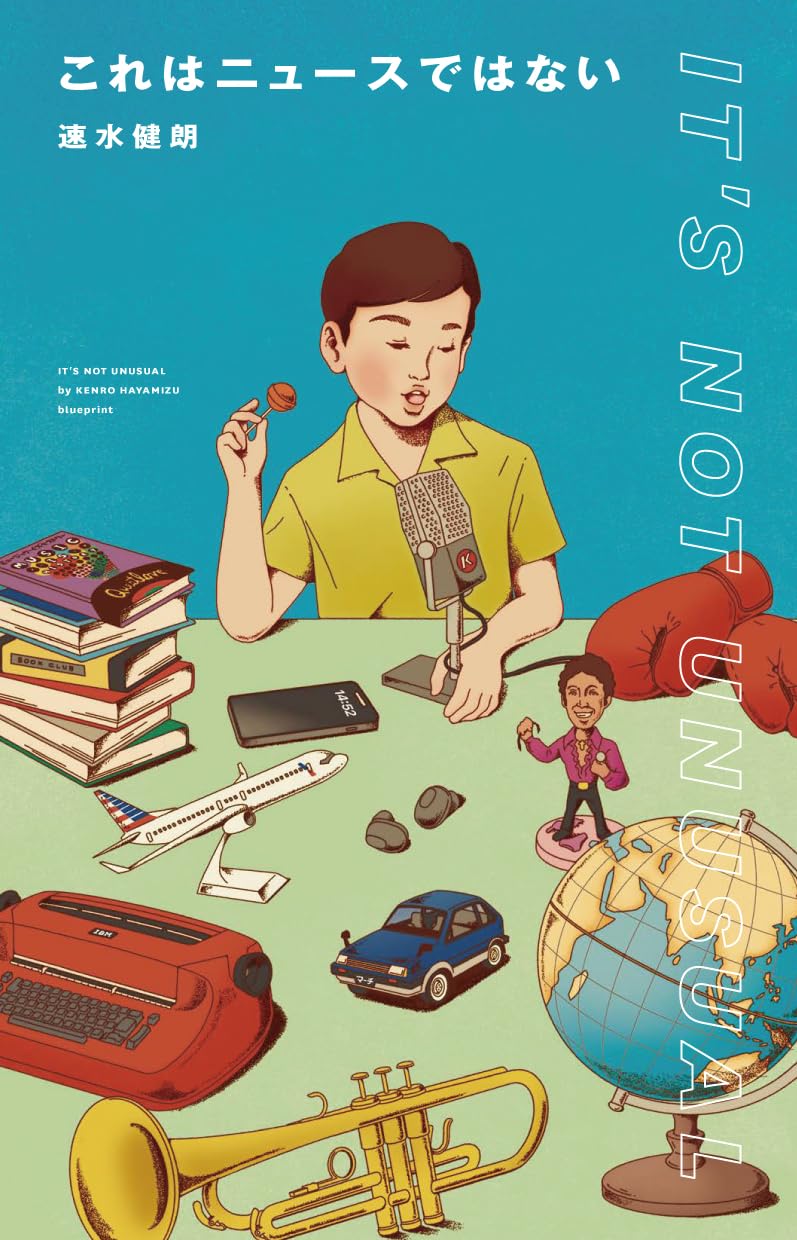
ライター・編集者の速水健朗が時事ネタ、本、映画、音楽について語る人気ポッドキャスト番組『速水健朗のこれはニュースではない』との連動企画として最新回の話題をコラムとしてお届け。
第20回は、トランプ次期米大統領が設置を決めた新組織「政府効率化省」のトップに就く実業家のイーロン・マスクについて。
国全体を「イカゲーム」に放り込むようなもの
「政府効率化省」のトップに就任したマスクは、一体何をやるのだろう。ちなみにマスクの経営の本質は、コストカットではない。事業目標の数値を無理なラインに打ち立て、プロジェクト全体を追い詰め抜いた末に達成させるというもの。彼がこのやり方を踏襲する理由を3つの側面から考えてみる。
1つは、人もチームも追い詰められたところでしか成長できないという考えゆえ。優秀な人材でも、難易度の低い仕事ばかり向き合っていれば能力も下がっていく。2つ目は、加速度的に進むテック業界では、無理な数値でも予測不能な技術革新が登場して届いてしまうからという理由。その経験則ゆえ目標をとんでもないところに置くということ。
理由の3つ目は、マスク自身の性癖の問題だ。崖っぷちの環境でなければ「生きている実感」が持てない。回りからはぎりぎりの綱渡りに見えても、マスクにとってはあくびが出るほど退屈な環境に見えている。中本の蒙古タンメンでしかラーメンを味わえなくなっている人と似ている。
彼に似た人物が思い当たる。第二次世界大戦時の海軍の将軍で、B-29の開発を指示したカーティス・ルメイ。彼は、将軍だから本部で構えていればいいのに、いつも自ら爆撃機の先頭機体に率先して乗り込んで、敵地に向かって飛んでいった。士気を高めるためか、危険が好きだったのか。その両方なのだろう。マスクも同じ。率先して前線に飛び込んで行き、主に混乱を巻き起こそうとする。
そんな彼が、政府の重要な任務に就くというのは、国全体を「イカゲーム」に放り込むようなもの。突然鳴り響くファンファーレで目を覚ますと、いつの間にか番号の付いたジャージを着せられている。運営側からルールが発表される。デスゲームの始まり。
共感能力のないシリコンバレーの起業家たち


マスクは、トランプに共感したのではなく、リスクをとってトランプに賭けた。そもそも政治への関心は低いし、人付き合いも苦手、すぐに反感を買うタイプなので、自身が政治家になるというのは難しいだろう。ただ選挙戦をパズルのように楽しんでいる可能性は高い。そして、毎日ゴルフばかりするトランプの生活には付き合いきれず、すぐに飽きてどこかに行ってしまう可能性もある。