なぜ学校で音楽を学ぶのか? 大谷能生『平成日本の音楽の教科書』が浮き彫りにする、音楽教育の意義
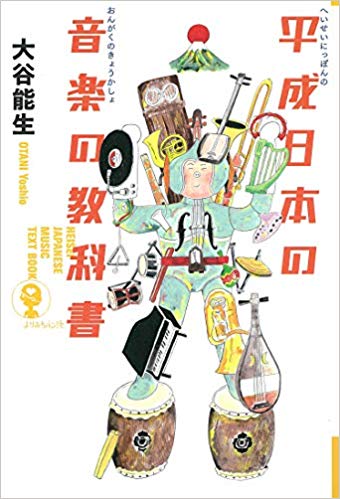
大谷能生『平成日本の音楽の教科書』(新曜社、2019年)はちょっと変わったアプローチで音楽について考える本だ。なにがユニークかというと、「日本の音楽の教科書にはなにが書いてあるか」に的を絞っているということ。あくまで主役は教科書。大谷の言葉を借りれば、「「音楽の教科書」をアタマからトータルに、予断を持たず、一つの読み物として、いわばひらたく読んでみること」(p.49、強調は原文ママ)。ひたすらこれに徹した本なのだ。
しかし果たしてそこからなにが得られるか、と思って読み進めると、驚くほどに鮮やかに「学校で音楽を学ぶ」ことに込められた思惑(つまり、国が音楽を通じてなにを身につけて欲しがっているか)や意義(反対に、いち個人が音楽教育からなにを学びうるか)が浮かび上がってくる。さらにそこからまた一歩踏みこんで、そもそも音楽っていったいなんなのか、どういうふうに付き合っていけばいいのか、という原理的な問いにまで思索は及ぶ。
とはいえ基本的に語り口はごく易しく、率直。この本の問題意識を明らかにする「イントロダクション」にはじまって、小学校、中学校、高校の3章におおまかにわかれているが、各章の末尾には、だいたい2~3頁くらいの「まとめ」がついてくる。教科書から学びうることの要旨と、それを踏まえた教育の現場にのぞみたいことの提言なんかが簡潔にまとめられていて、こういう言い方はなんだけれど、とても実用度が高そう。各章の節ごとに付された見出しも丁寧で、本全体の見通しがとても良い。
扱われているトピックの多様さは、ここではとても書ききれない。それだけ音楽の教科書が実は読み物として結構よく出来ていることの反映であり、また著者が持つ問題意識の射程の大きさの反映でもある。
たとえば第一章の前半で小学校低学年の教科書を読みながら論じられるのはこんなことだ。楽器の演奏や歌を通じて「ドレミ」を身体化しつつ、見ず知らずの人間のあつまりを「みんな」につくりかえる。(p.70)その限りで「「唱歌」=「こころのうた」は、じつは「からだのうた」なのだ」。(p.76)ごく素朴に見えるリコーダーや鍵盤ハーモニカや歌の練習が、いかに“私”を社会のなかに位置づけ、かつ社会を“私”のうちへと内面化させるかをさらりと示している。
あるいは第二章で中学校の教科書を読み解きつつ、日本の音楽教育からなにが排除されているか、それはなぜかを考察していくプロセスも興味深い。序盤では、西洋音楽を教えるためにオミットされた日本の伝統音楽の系譜が、後半では芸術としての音楽の観念を教えるためにオミットされた商品としての音楽(≒ポップミュージック)が取り上げられる。こうした対立をときほぐすなかで、日本における戦後の歌謡曲、西洋近代の和声や調性を軸とした音楽理論、あるいはいまのポップミュージックの特徴について、縦横に思索が繰り広げられる。このあたりの記述は、大谷の菊地成孔との共著『憂鬱と官能を教えた学校』(河出書房新社、2004年)と地続きの批評性を湛えている。
ひととおり音楽の教科書を読み通した第三章の終盤では、音楽学者のクリストファー・スモールによる「ミュージッキング」のアイデアが紹介される。(pp.253-257)ここが本書のキモだと思う。「ミュージッキング」は“music”という名詞に無理やり現在分詞の“ing”をくっつけて疑似動詞化した造語で、音楽を「作品」からではなく、人びとの「行為」から捉えなおそうという企図を持つ言葉だ。もっとひらたくその含意をまとめると、「ミュージッキング」において音楽は、知識や技術を身につけた一部の人びとが楽しむだけのものではなく、もっと開かれたものであり、雑多で身近なさまざまな行為にも見いだせるものなのだ。それはまさに、教科書が提示する音楽観に対するカウンターである。























