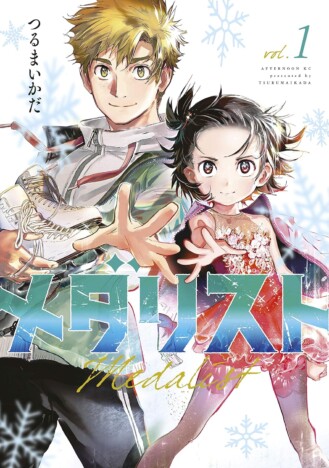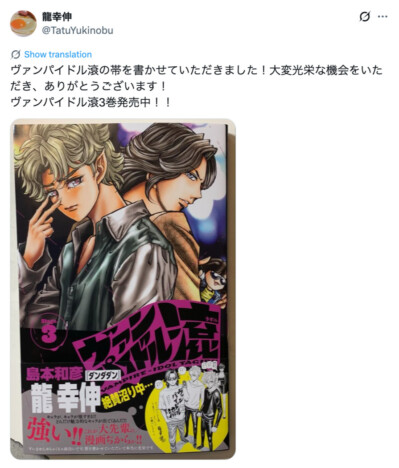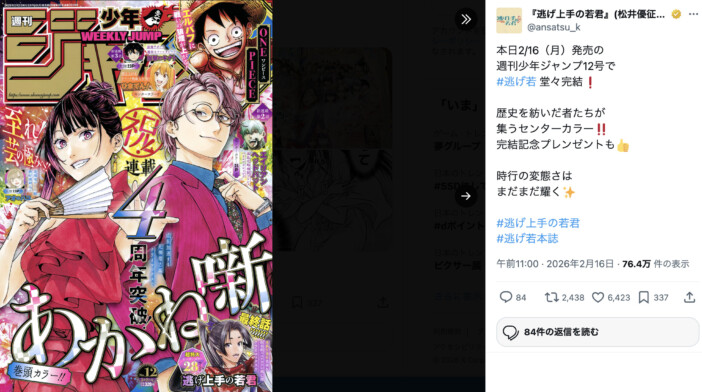アニメ『メダリスト』原作漫画の魅力を広げる3DCG制作 名作『ユーリ!!! on ICE』とのスケートシーンの違いは?

米津玄師が歌う主題歌『BOW AND ARROW』のMVに羽生結弦が出演するなど、実際のメダリストたちとのコラボレーションが話題となっているアニメ『メダリスト』。本稿では、2016年に放送されたもう1つの名作スケートアニメ『ユーリ!!! on ICE』とのスケートシーンの違いから、その特徴を考察したい。
3DCG制作を用いた『メダリスト』手描き漫画との違い
アニメ『メダリスト』を語る上で外せないのが、3DCGを活用したスケートシーンの臨場感だ。原作漫画と異なる表現は、アニメファンはもちろん漫画ファンからも好評を得ている。その臨場感は、モーションキャプチャー撮影と振り付けに元オリンピック日本代表・鈴木明子氏が関わっていることは有名だが、特筆したいのは、撮影が実際の国際大会規格の中でも最大サイズに当たる60m×30mのスケートリンクで行われた点にある。
フィギュアスケートの競技会で使われるスケートリンクには小さいサイズのものもあり、特にアイスショーなどは競技会より小さいサイズのリンクで開催されることも多い。そんな中、全日本選手権やオリンピックなど公式競技会で使用されるリンクサイズにこだわって撮影を行い、広い会場で滑る際の軌道や筋肉の使い方を正確にCGアニメーションに落としこんだことが、スケートシーンのリアルさとダイナミックさにつながっているとも言えるだろう。
対する『ユーリ!!! on ICE』は、CGを一切使用せずにスケートシーンを表現。当時の制作インタビューによれば、振付師の宮本賢二氏が実際に演技を滑り、その撮影映像を参考に作画が行われたという。複雑な動きの多いフィギュアスケートを、CGなしでアニメ化したところに本作のこだわりが見える。人体の動きをトレースして作成された3DCGのリアルさとは異なるが、ジャンプした際の衣装や髪の動き、振付の美しさなどが手描きアニメーションでドラマチックに表現されており、フィギュアスケートならではのしなやかで優雅な動きや芸術的な側面も際立っていた。
CGにこだわるか、手描き作画にこだわるか。2作品の制作手法の違いは、フィギュアスケートの持つスポーツとしての臨場感とアート性、どちらを軸に表現するか作品のスタンスにも現れていると言えるのだ。
臨場感か没入感か?
また、2作品は映像のアングルや接写の度合いにも違いがある。『メダリスト』では、リンクサイドからの視点以外にも、氷上カメラやドローン撮影を思わせる煽りや俯瞰カットが多用されており、1シーンの中で画角やアングルが目まぐるしく変化する。対して『ユーリ!!! on ICE』は、リンクサイドの固定位置から選手の演技を撮影しているような、長回し映像が多めなのだ。
『メダリスト』で言えば、TV放送時大きな話題となった「名港杯 ノービスB女子FS」での狼嵜光の「死の舞踏」滑走シーン。このシーンは、光の目線アップ、手の振り付けと目線を追うようなアングルから始まり、多彩なカメラワークで彼女の姿が描かれる。ステップはカメラマンが光と一緒に氷上を滑りながら撮影しているかのような躍動感のある映像や、氷上からの煽りカット中心で構成され、ジャンプではスケート靴の接写、スピンでは氷が削れていく足元のアップカットなども描かれている。基本、リンクサイドの報道エリアから撮影を行う競技会のTV中継などでは決して観ることがないアングルだ。