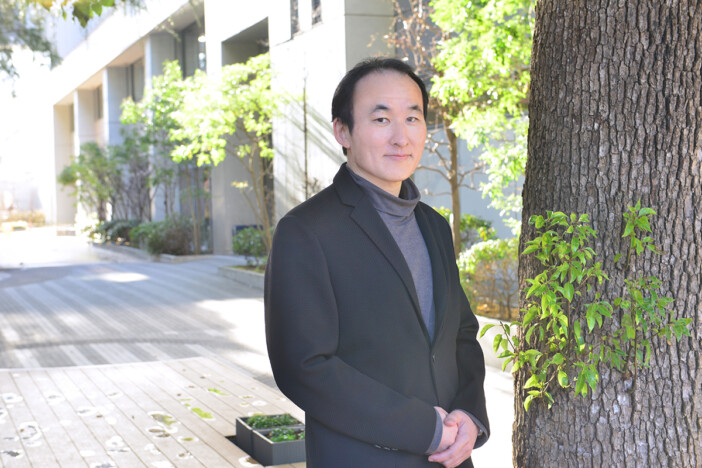千街晶之のミステリ新旧対比書評 第11回:水上勉『飢餓海峡』×柚月裕子『逃亡者は北へ向かう』

1954年(昭和29年)9月26日、青函連絡船の洞爺丸が台風により沈没した「洞爺丸事故」は、1100人を超える死者・行方不明者を出した、日本海難史上最悪の事故である。ミステリの方面では、この事故は2つの名作の着想源となったことで知られている。中井英夫の『虚無への供物』(講談社文庫)と、水上勉の『飢餓海峡』だ。
■1947年に災厄が設定された理由
ただし、前者では洞爺丸が実名で言及されるのに対し、後者では船の名前は層雲丸となっている。洞爺丸事故と同日に起きた岩内大火(北海道岩内町で発生した大規模な火災。市街の8割が焼失し、38人の死者・行方不明者を出した)も、作中では岩幌町という架空の町での出来事となっている。のみならず、この二つの大災厄が起きた年も、作中では戦後間もない1947年(昭和22年)に設定されている。
層雲丸事故の死者のうち、2人は乗客名簿にない人物だった。函館警察署の弓坂吉太郎警部補は、この2人が、岩幌町で質屋一家4人を殺害し、家に火を放って大火の原因を作った強盗だと突きとめる。だが、彼らと行動をともにしていた犬飼多吉という男の行方はわからない。弓坂は、犬飼が共犯者2人を殺害し、層雲丸事故の夥しい死者に紛れ込ませようとしたのだと推理する。
その頃、青森の娼婦・杉戸八重は、行きずりの犬飼から思いがけない大金を渡された。犬飼を追跡して青森にやってきた弓坂に嘘をついて彼をかばい通した八重は、その金を元手として東京に出た。そして10年後、事件は再び動き出す。
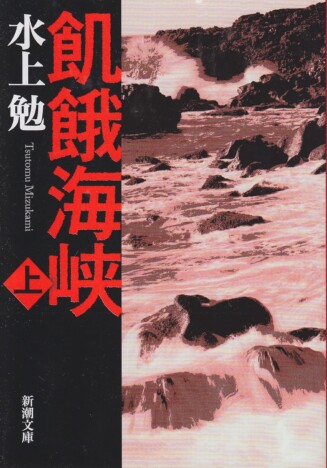
『飢餓海峡』は1963年に朝日新聞社から刊行され、現在は新潮文庫で読める。1965年には内田吐夢監督により映画化された。
水上が事件の背景を、実際に洞爺丸事故と岩内大火が起きた1954年ではなく1947年に設定したのは、戦後の貧困の中で生き抜こうとした者たちの想いが事件の背後にあったことを強調したかったからに他ならない。10年後のパートでは弓坂は既に退職しているが、新たに舞鶴で起きた事件を捜査する京都府警の味村警部補らに協力し、10年越しの彼の執念は実ることになる。
■『逃亡者は北へ向かう』が描く東日本大震災

2025年、私はある新刊ミステリを読んでいて、この『飢餓海峡』を久しぶりに思い出していた。その新刊とは柚月裕子の『逃亡者は北へ向かう』。新潮社から刊行され、第173回直木賞の候補となった。ご存じの通り、この回の直木賞は芥川賞ともども受賞作なしという結果で話題を呼んだ。
『飢餓海峡』が洞爺丸事故と岩内大火を背景としているのに対し、『逃亡者は北へ向かう』は2011年の東日本大震災を描いている。
福島在住の若い工員・真柴亮は、酒癖の悪い先輩と半グレの喧嘩に巻き込まれた。その翌日、あの大震災が起こる。混乱の中、処分保留で釈放された亮だが、彼の前には苛酷な運命が待っていた。
物語は、真柴亮、福島県警の警部補・陣内康介、そして漁師の村木圭祐の3人の視点で進行する。圭祐は津波で妻を失い、5歳の息子が行方不明となる。陣内もまた、この震災で家族を失うことになる。しかし彼は警察官として、家族のことより、自らの職務を優先しなければならない。同じ被災者でも、身内を失ったかどうかの差で諍いが始まり、かねてからの確執が震災を機に噴出したりもする。
その生々しい描写は胸に迫るものがあり、柚月の作品中でも渾身の力作であることは間違いない。ただ、力作ではあっても傑作の域に届かなかったのは、物語の骨格があまりに偶然に頼りすぎているからだ。
釈放された亮は、喧嘩相手の半グレに襲われ、誤って相手を死なせてしまう。そこまではいい。だが、それに続いて彼に職務質問をしようとした警官までも死なせてしまうのは、彼の不運さを強調するためとしても強引すぎる展開だ。冒頭で暗示される亮の末路を読者に納得させるため、2人もの死者が(「永山基準」的な意味で)必要とされたのかとも思う。
■不条理な事態に直面した人間の思考
そうした骨格の脆弱さはともかくとして、『逃亡者は北へ向かう』という小説は、『飢餓海峡』にも通じるものを感じさせる。それは、運命としか言いようのない不条理な事態に直面した人間の思考径路についてだ(同じことは先にタイトルを挙げた『虚無への供物』にも言える)。
『飢餓海峡』の弓坂は、層雲丸事故の夥しい犠牲者の亡骸を目の当たりにしたことを想起し、「それだけに、わたしは、あの男犬飼多吉を憎んだものです。このような史上空前の大事故のさ中にあって、自分の犯罪を消すための殺人をやった。その痕跡をくらますために、気の毒な事故の人々の死体の中へ殺した二人の男をまぎれこませた」と述懐する。もちろん、層雲丸事故自体は犬飼が引き起こしたものではないが、弓坂は、それを承知の上で事故の犠牲者たちの無念を犬飼への怒りに重ねているように見える。
だが登場人物がみな被災者という当事者であるだけに、『逃亡者は北へ向かう』では怒りはよりストレートに表明される。家族を失いながらも務めを果たさなければならない陣内は、「俺がこんな思いをしなければならないのは、真柴のせいだ」と亮への憤りを燃やす。それが八つ当たりであることは理解しているのだが、そうとでも考えなければ正気を保っていられなかったのだ。陣内に追われる亮は、自分の不運を嘆きつつ、愚かな選択を繰り返す。その時々で道を選んだのは自分であり、なるべくしてなった結果だということを悟るのはようやく結末近くになってからだが、それはあまりに遅すぎた。
事故であれ天災であれ、多くの死者を出すような不条理な大災厄に直面した人間の心は、自分が運命に動かされていると考え、その運命を呪う方向へと容易に傾くものである。だが、論理的に正しいか否かは棚上げされ、それを信じた途端に機能しはじめてしまうのが運命という危うい概念だ。運命と戦い、あるいは憎んだ犬飼多吉や真柴亮は、事件の決着とともにそんな運命の呪縛から解放されたのかも知れない。彼らを追う弓坂や陣内もまた同様に。
千街晶之のミステリ新旧対比書評 第10回:笹沢左保『結婚って何さ』×王谷晶『ババヤガの夜』
昭和の人気作家には、どうしてそんなに膨大な数の作品を書けたのか不思議に感じる書き手が少なくないが、そのひとりが笹沢左保である。初…
千街晶之のミステリ新旧対比書評・第7回 エラリイ・クイーン『最後の女』×斜線堂有紀『コールミー・バイ・ノーネーム』
フレデリック・ダネイとマンフレッド・B・リーという従兄弟同士の合作コンビであるエラリイ・クイーンは、日本の「新本格」の…
【新連載】千街晶之のミステリ新旧対比書評 第1回 若竹七海『スクランブル』×浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』
■新旧ミステリを比較して見えてくる作品の重層感 このたび、「リアルサウンド ブック」で、「千街晶之のミステリ新旧…
連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第2回 モーリス・ルブラン『三十棺桶島』×澤村伊智『予言の島』
■トラウマ級に怖かったモーリス・ルブラン『三十棺桶島』 1970年生まれの私が未成年の頃は、大体どこの図書館にも…
連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第3回 多岐川恭『異郷の帆』×霜月流『遊廓島心中譚』
■多作な小説家、多岐川恭の傑作 1958年に『濡れた心』で第4回江戸川乱歩賞を受賞した多岐川恭は、ミステリと…
連載:千街晶之のミステリ新旧対比書評 第4回 島田荘司『斜め屋敷の犯罪』×知念実希人『硝子の塔の殺人』
■ミステリ映画の傑作『探偵〈スルース〉』 ミステリ映画史に残る傑作として知られる『探偵〈スルース〉』(1972年…
千街晶之のミステリ新旧対比書評・第5回 泡坂妻夫『乱れからくり』×阿津川辰海『紅蓮館の殺人』
■映画『探偵〈スルース〉』に影響された国産ミステリ 前回から続く話題だが、映画『探偵〈スルース〉』の影響が垣間見…
千街晶之のミステリ新旧対比書評 第6回 コーネル・ウールリッチ『ホテル探偵ストライカー』×方丈貴恵『アミュレット・ホテル』
■ホテル探偵ものがシリーズになりづらい理由 人生の半分以上をホテルの一室で過ごした作家がいた。彼はそこで…