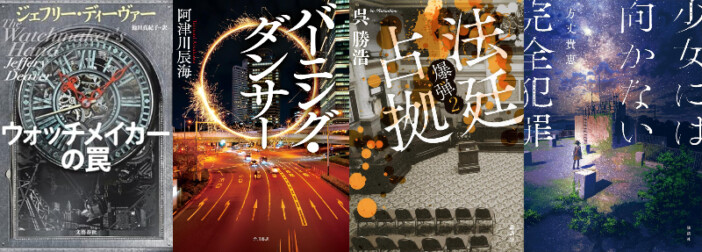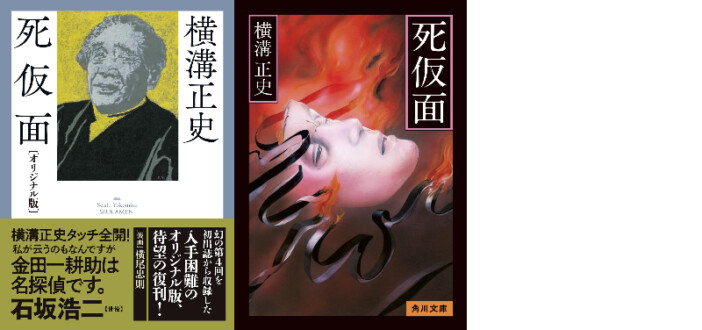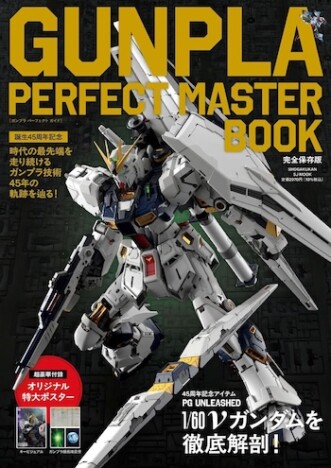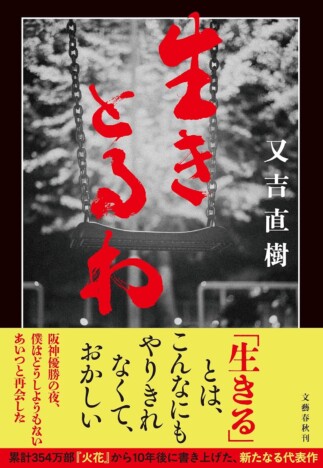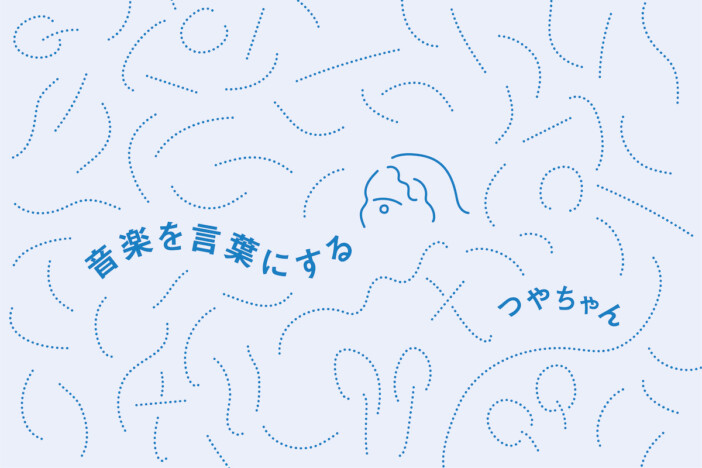【新連載】千街晶之のミステリ新旧対比書評 第1回 若竹七海『スクランブル』×浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』
■新旧ミステリを比較して見えてくる作品の重層感

このたび、「リアルサウンド ブック」で、「千街晶之のミステリ新旧対比書評」と題した連載を始めることになった。何故このタイトルになったかというと、この連載ではここ5年以内くらいに刊行された新作と、それとテーマやモチーフが共通する旧作とを対比しながら紹介する予定だからである。発表時期を異にする2つのミステリを比較することで、何が共通点で何が相違点なのか、テーマやモチーフがどのように継承されたのかを浮かび上がらせてみたいと考えているので、どうかご贔屓に。
ミステリの世界において消去法という言葉が使われる場合、読者は大抵、本格ミステリのラストで名探偵が、大勢いる容疑者の中から真犯人を絞り込むシーンを想起するのではないだろうか。「○○さん、あなたには確実なアリバイがあります。△△さん、あなたには凶器を入手する機会がありませんでした。……そう、××さん、犯人はあなたしかいません!」という、あれである。
しかし、消去法は必ずしも結末部分でしか使えないわけではない。ミステリとしての構成全体に、消去法を巧妙に組み込んだ作品も見られるのである。その恰好の例として紹介したいのが、若竹七海の『スクランブル』(集英社文庫)と、浅倉秋成の『六人の嘘つきな大学生』(角川文庫)だ。
■消去法を巧妙に組み込んだ2つの作品
『スクランブル』は1997年に刊行された作品である。「スクランブル」「ボイルド」「サニーサイド・アップ」「ココット」「フライド」「オムレット」という、卵料理に因んだタイトルの6章から成っており、各章は独立したエピソードのようでありつつ、読み進めると1つの長篇となっていることが判明する。
1980年、名門女子校で殺人事件が起きた。文芸部員である彦坂夏見・貝原マナミ・沢渡静子・飛鳥しのぶ・宇佐春美・五十嵐洋子の6人は、この事件を含む学園内で起きた幾つかの出来事をそれぞれ推理する。そして15年後、彼女たちは晴れがましい披露宴の席で久しぶりに一堂に会する——1人は花嫁として、5人は花嫁側の招待客として。だが、披露宴の最中、招待客のうちの1人は、15年前の殺人事件の真相に気づいてしまう。
第一章で、元文芸部員の1人である視点人物は犯人が誰だったかを悟るが、そのくだりではもちろん名前は触れられず、犯人の属性だけが明らかとなる。第二章以降は、残る5人が次々とリレー式に視点人物の座についてゆく。視点人物になった元部員はその属性に当てはまらず、従って犯人ではあり得ない。つまり、章が変わるたびに、6人の元部員から無実の人間が1人ずつ、容疑者の圏内から脱落してゆくわけである。
この構成であれば、最後の章まで残った1人が真犯人ということになるのだが……そこはひねりにひねった構成を得意とする若竹七海のこと、読者の先入観を利用した仕掛けが炸裂することになる。構成に組み込まれた消去法そのものが、読者へのミスディレクションとなっている例である。