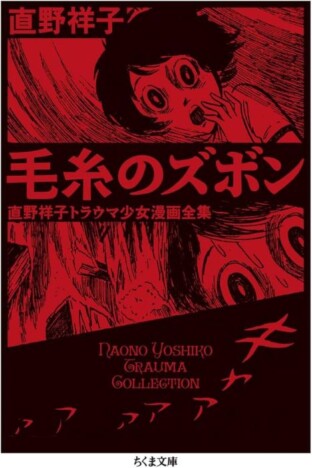【不朽の名作】生きるとは、ひとりで静かに泣くだけではないーー庄野英二『星の牧場』が描く希望の欠片

さびしさについて思うとき、いつも頭のなかに韓国の詩人、申庚林の詩が浮かぶ。〈いつからか 葦は心の中で 静かに泣いていた〉から始まるその詩に出会ってからずっと、生きるというのは静かにふるえ、ひとりで泣くということであり、それは決して特別な悲劇でもなんでもないのだと噛みしめてきた。ちくま文庫から復刊した庄野英二さんの小説『星の牧場』(初版、1963年)を読んでいるときにずっと、その詩を思い出していたのは、誰にも理解されない、知られることもないさびしさを、じっと抱きながら生きる人の姿が描かれていたからだ。
山の牧場で生まれ育ったモミイチは、馬が大好きで、軍隊でも鍛工兵として馬の蹄鉄をつくっていた。戦地で世話をすることになったのがツキスミという名の馬で、インドシナ半島にわたって数カ月は、危ない目にあうこともなく穏やかな日々をともに過ごし、絆も深めた。けれどフィリピンのマニラに移動する途中、船と一緒にツキスミが沈み、モミイチはどうにか助かったものの、マラリヤの熱にやられて記憶を失った。運よく日本に帰って、ふたたび牧場で働くことができるようになったはいいが、まわりの人からは、少しおかしくなってしまったと思われている。その理由のひとつは、誰にも聞こえない馬の蹄鉄がひびく音を、モミイチが聞くことだ。
あるとき、蹄の音に導かれるようにして分け入った山のなかで、モミイチはクラリネットを吹く男に出会う。男は蜂飼いであり、オーケストラの仲間をもつという。仲間は、一緒に暮らしているわけではなく、それぞれの持ち場で、それぞれの仕事をしていて、お祭りのあるときに集まり、演奏をするのだ。そんな自分たちは、ジプシーでもあるのだと男は言う。ヨーロッパのジプシーとはまたちがう、山のなかを愛して自由気ままに暮らす人々のことだ。
モミイチはそれから、さまざまな楽器を奏でるジプシーたちに出会い、自分もその一員になろうと鈴をつくりはじめる。その出会いと、彼らの奏でる音楽が、少しずつモミイチの心を癒し、失ったはずのツキスミの存在をふたたび近くに感じるようになっていく。
正直、あらすじそのものは、あんまり重要ではないので、くどくどと語りたくはない。ジプシーたちの愉快な会話や、差し出された宝石のようにすみきった七色の液体。谷底から響く大砲の音や、ジプシーの幾人かに仲間の面影を見出したことで、よみがえる戦地での記憶。幻想と現実をいったりきたりしながら、モミイチのまなざしを通じて描き出される世界の美しさと切なさに、読みながらきゅっと心がつかまれ、こみあげてくるさびしさに身をゆだねることこそが本作の味わいだと思うからだ。
〈ひととはなれて山のなかをさまよっていることは、そりゃさびしいさ。しかし、人間てものは、人間と人間がいっしょにくらしていてもさびしいもんだから、しょうがねえなあ〉と、ジプシーの一人が言う。モミイチが山のなかの暮らしと、溢れだす音楽に魅入られたのも、牧場での暮らしがあまりにさびしかったからだろう。相棒ともいえる大事なツキスミを失い、自分がどうして今ここに至ったのかも上手に思い出せず、まわりの人間からは腫れ物扱いされて、なんとなく遠ざけられる。モミイチがしたかったのはきっと、ただツキスミのことを想い、語り、仲間をはじめとする失ったすべてを悼む時間をもつことで、それをなくしては前に進むことなんてできなかった。それだけなのに。