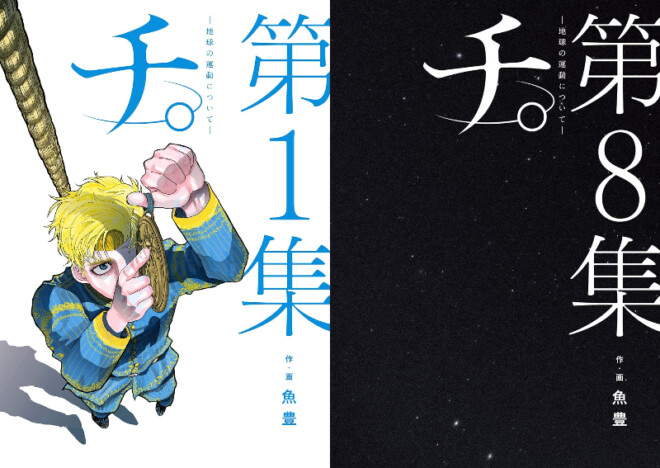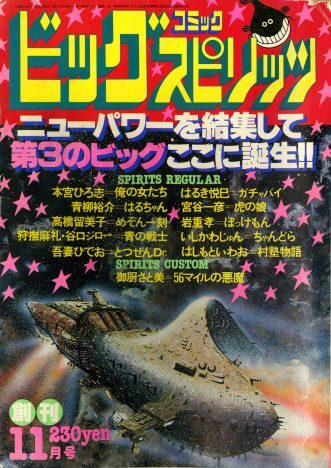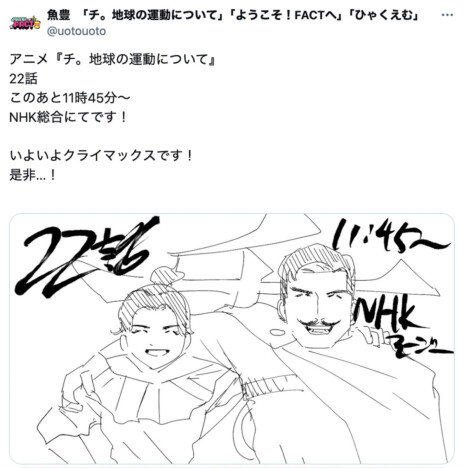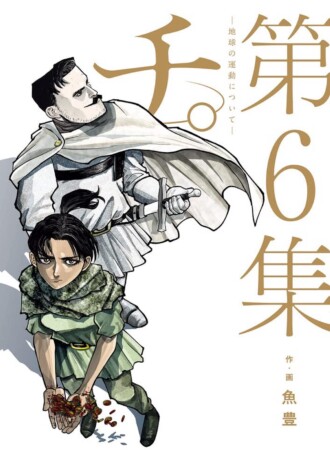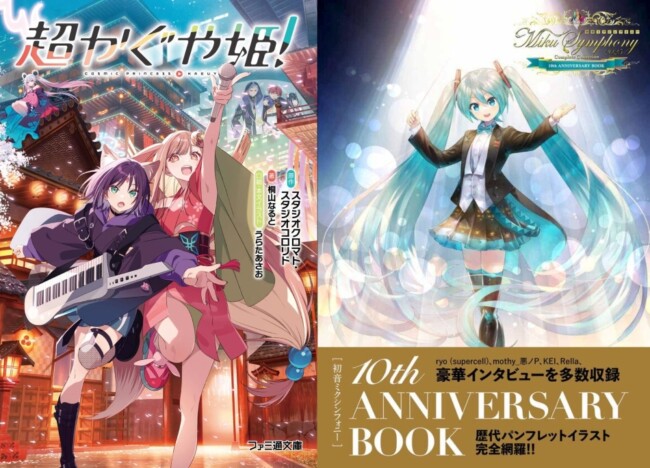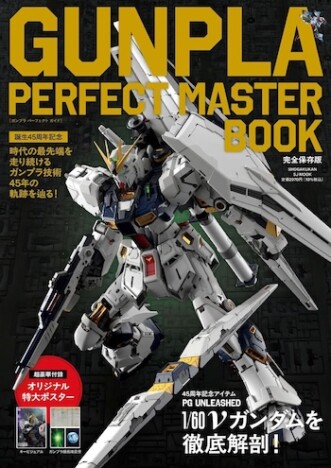『チ。』で注目の詩人・ルクレティウスが後世に与えた影響とは? 『事物の本性について―宇宙論』に書かれた2100年前の科学的思考
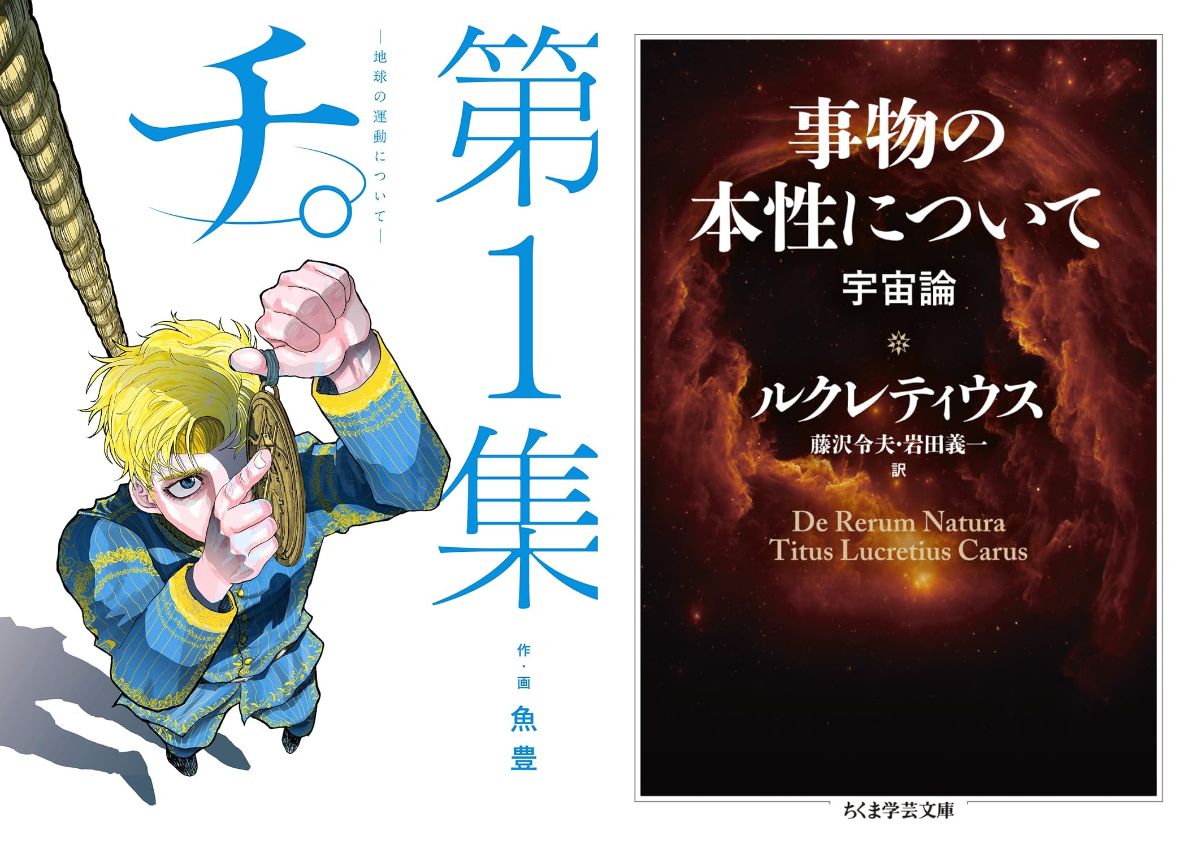
ルクレティウスが話題だ。魚豊の漫画でTVアニメにもなった『チ。―地球の運動について―』(小学館、以下、『チ。』)の中で、クラボフスキという田舎の教会の司祭が左遷されてきたバデーニに読みたいと頼む詩人のこと。3月10日に刊行されたルクレティウスの著作『事物の本性について―宇宙論』(藤沢令夫・岩田義一訳、ちくま学芸文庫)を開くと、『チ。』の世界から1500年も前にめぐらされた自然や宇宙への科学的な思索が綴られていて、ラファウやオクジー、バデーニらが繋ごうとした知的探究心の素晴らしさに触れられる。
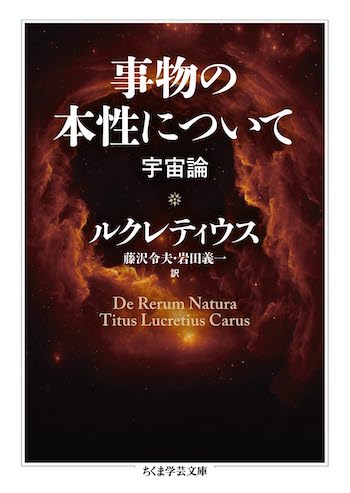
物体は原子が集まって形作られている。質量は永遠に消滅することはない。宇宙は無限に広がっている。神などおらず魂というものもない。科学というものを学んで近代的な理論に触れた人たちなら、確かにそうだと思える事柄だが、これがルクレティウスという今から2100年も前のローマ人によって唱えられたことだと言われれば、やはり驚くしかない。
物質の間に隙間があることは、原子論の研究が進んで分かって来たことだが、紀元前94年頃から同55年頃にローマに生きたルクレティウスが残した詩の中に、しっかりと記されている。曰く「しかしまた、万物は物体によりどこもかしこも透間なく詰められ保たれているのでもない。なぜなら物の中には空虚が存在するから」(『事物の本性について―宇宙論』より)。
これが素粒子物理学そのものを先取りしたものだとは言えないが、そこにある物体を探求していった果てに原子といったものの存在を思い浮かべ、それらが寄り集まって物体が形作られているのだと考えることは、現代の科学的なアプローチと変わらない。進化と淘汰を経て今の人類や他の生物が存在する世界が出来上がっていく過程で、神が何かをしたということもないといった主張も、実に科学的で合理的な考えだ。
『事物の本性について』は、ルクレティウスのこうした思索が、全6巻の詩にまとまったものだ。中には現代の科学で否定されている理論もあるが、夏目漱石の弟子で物理学者の寺田寅彦は、1929年に発表した「ルクテチウスと科学」で「問題は畢竟(ひっきょう)科学とはなんぞや、精密科学とはなんぞやということに帰着する」と書いて、観察し考えて答えに近づこうとするルクレティウスの態度を讃えている。研究が行き詰まってもがき苦しんでいる研究者に「突然天の一方から稲妻のような光がひらめいて瞬間に眼前のものの正体が見える」ことが起こる。この稲妻としての役目がルクレティウスにはあり、現代の科学者にも有効だと寺田は説く。この時から100年経った今も価値は減じていない。
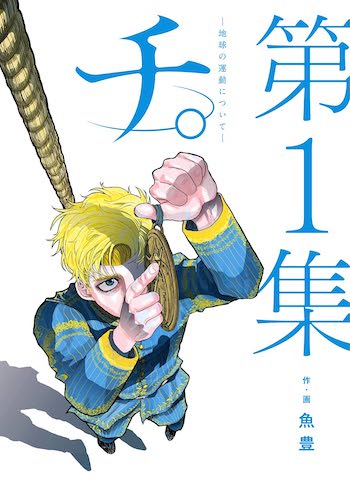
こうした考えは、ルクレティウスがひとりで思い至ったというものではない。さらに何百年も前の古代ギリシアで原子論を唱えた哲学者のデモクリトスであり、デモクリトスの思想を受け継ぎ快楽主義を打ち立てたエピクロスが残した言葉を元に、古代ローマでルクレティウスが詩の形に仕立て上げたものだ。デモクリトスやエピクロスの著作が後の世に伝わることがなかった中、ルクレティウスの言葉だけが受け継がれたことで、『チ。』の中でも名前が取り沙汰される存在となった。
もっとも、ルクレティウスもデモクリトスやエピクロスと同様に、伝説上の存在となる可能性はあった。古代ローマの政治家で哲学者のキケロや、詩人のオウィディウスが著作の中に書き記すほど有名な詩人だったにも関わらず、その作品が長く表舞台から消えていたからだ。再発見されたのは1417年のこと。イタリアの人文主義者で珍しい写本を探してヨーロッパ各地を回っていたポッジョ・ブラッチョリーニが、ドイツの修道院で見つけてこれが噂のルクレティウスかと驚き、書き写して世に出したことから改めて世界に存在が広まった。
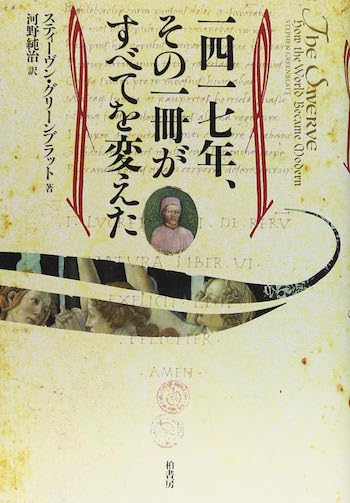
『チ。』でクラボフスキがバデーニに「ルクレティウスは読んだことあります?」と尋ねたのも、ブラッチョリーニによる再発見後に作られた写本が出回っていたのを知っていたからだろう。ルクレティウス再発見のドラマを紹介するスティーヴン・グリーンブラッドの『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』(河野純治訳、柏書房)によれば、現存する50冊ほども含む多くの写本が作られ、グーテンベルクによる印刷版も出回るようになった。
読んだ人たちへの影響も与えた。『ヴィーナスの誕生』で知られるルネッサンス期の画家、ボッティチェリが1482年頃に描いた『プリマヴェーラ』という絵が、ルクレティウスの詩を再現したものだと言われている。第5巻に書かれている「春はウェヌスとともに訪れ、それに先立ちウェヌスの翼ある先駆者がやってき、西風の足跡には母なる女神フローラがあらかじめ道いっぱいに、彼らのための母なる色と香をまき散らす」(『事物の本性について―宇宙論』より)がそれ。読んで絵を見ると確かにそうだと思えてくる。