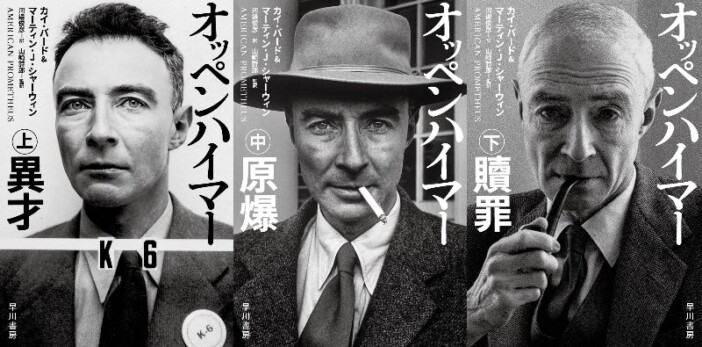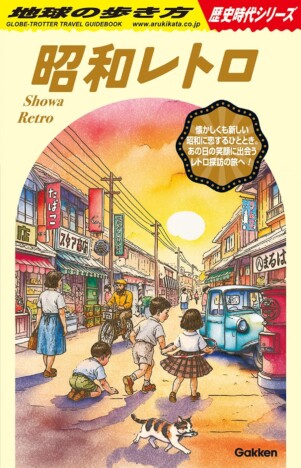ポストモダン文学はいかにして映画化されたのか? 『インヒアレント・ヴァイス』前編ーー「語り」と「騙り」に揺れる映像化

「どったの、ドック?」ヒッピー探偵、ニール・ヤングになる

さてここで「なぜニール・ヤング?」という疑問が湧き起こる。たしかに60年代のニール・ヤングはロサンゼルスを活動の拠点としていたが、ヒッピー批判を込めた楽曲「ヒッピー・ドリーム」に表れているように、ヒッピー・ムーブメントを代表するような人物ではない。ではなぜか? それは『インヒアレント・ヴァイス』の映像が、ニール・ヤング監督作『ジャーニー・スルー・ザ・パスト』(1973)にインスパイアされたものであるからだ。この映画はニール・ヤングのコンサート、バックステージ、そして幻想的な映像を脈絡なく組み合わせた、実験映画と言える一本。批評的・興行的に失敗したこの映画に、ポール・トーマス・アンダーソンは心揺さぶられた。逆光で撮られた映像の連続に陶酔感を覚えたポール・トーマス・アンダーソンは、その感覚を『インヒアレント・ヴァイス』に転写しようと試みたのだ。
そのため屋外のシーンのみならず、ほぼ全編の画作りが逆光で行われている。これは映画が持つ浮世離れしたトーンを強調することに一役買った。逆光で捉えられた非現実的な光景は、過ぎ去りし時代に対しての憧憬とも見えるし、あるいはラリッたドックに見えている世界の姿なのかもしれない。
なぜドックがニール・ヤングそっくりなのかという話に戻ろう。『ジャーニー・スルー・ザ・パスト』に影響を受けたがゆえ、そのまま主人公の見た目をニール・ヤングにしてしまった……。この一見浅薄なアプローチは、原作と映画に通底する大きな意味を持つ。前述した「人を食った」感覚とも繋がるそれとは「パロディ」である。パロディ、それこそが原作「LAヴァイス」と映画『インヒアレント・ヴァイス』が共に有する、作品の根幹を支えている概念なのだ。そもそも本作のプロットそのものがノワール小説のパロディであることは皆様もお分かりのことだろう。
さらにノワール小説を原作としながらも独自の変化を遂げた映像化『キッスで殺せ』(1955)や『ロング・グッドバイ』(1973)を参考にしつつ、そのうえ『キッスで殺せ』のパロディ『レポマン』(1984)のオフビートさも取り込んでいるのだから、『インヒアレント・ヴァイス』が模倣と変容の渦中にある作品ということは明白だ。
「LAヴァイス」の奥底に潜むモノ
模倣なる言葉を考えるとネガティヴなイメージが付きまとうが、ここに意図的なユーモアが混入されることで、事物はパロディへとその性質を変化させる。「LAヴァイス」の根底にはパロディが鎮座している、と言い切るためには、改めてポストモダン文学の話題へと立ち返る必要があるだろう。明確な語りの不在性ゆえにポストモダン文学は映画化が困難、とは先に述べた通りだ。いま紡がれている文章は「語り」か、それとも「騙り」なのか。本と読者の間におけるメタコミュニケーションの崩壊が生じた瞬間、ポストモダン文学は「全てを疑え!」と叫び、その真価を発揮する。
では、「LAヴァイス」はどうか。この本の「語り」を務めるのは、常に大麻を懐にしのばせ、LSDや白い粉をバンバカ摂取するデイ・トリッパー。その設定ゆえ、本と読者間において「LAヴァイス」には正常な語りが存在し得ないことが了解されているのである。つまるところ「LAヴァイス」とは、ポストモダン文学の代表的作家であるピンチョンによる「ポストモダン文学のパロディ」なのだ。
ポール・トーマス・アンダーソンは「LAヴァイス」の映画化にあたり、ピンチョン作品を映像へと落とし込むことへの難しさに自覚的だったと語っている。「ヴァインランド」「メイスン&ディクスン」の映画化を検討するも、挫折していたポール・トーマス・アンダーソンにとって「LAヴァイス」の映像化は「無理を承知」のマインドで挑んだものであった。ポール・トーマス・アンダーソンは、まず原作のセリフを全て書き出し、それから脚本を練ったと聞く。
そして、その過程で気づきが生まれた。「あれ? これって案外、映画化いけるんじゃないの?」。もちろん「LAヴァイス」はピンチョンの他作品と比較すると難解度は低い。だがそれのみならず、本書の抱えるパロディ構造に対する気づきが大きかったのではなかろうか。このように考えると、ソルティレージュを実在不明の語り手として登場させ、ドックをニール・ヤング化したことは、原作が持つ性質に対してのポール・トーマス・アンダーソンからのアンサー(もしくはプロレス)であると言える。
ピンチョン作品を「映画化不可能」として括ることは簡単だ。しかしその作品間におけるグラデーションを見つめてゆくと、エアポケット、あるいは特異点(ピンチョン風に言うと「時空のしゃっくり」か)のように存在しているものがある。それがポストモダン文学のパロディ……「LAヴァイス」だったのだ。それゆえ『インヒアレント・ヴァイス』は「ポストモダン文学の映画化成功例」として語られるべきものではなく、ポストモダン文学とされている作品も、その位相のズレによって映画化と親和性を見せる一例として取り上げるべきものではないか。