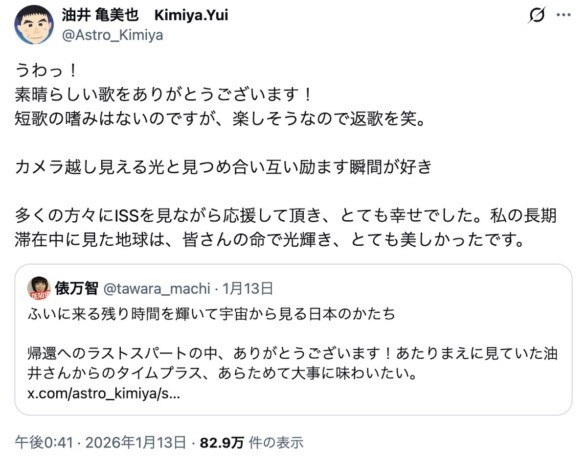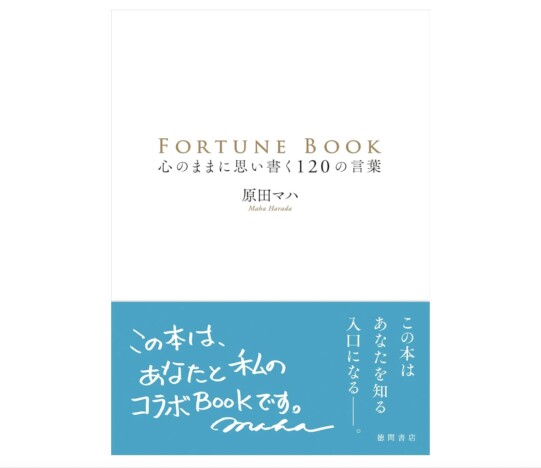自己を環境に似せるミメーシス――ヨーゼフ・ロート『ウクライナ・ロシア紀行』評

書物という名のウイルス 第11回
書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。
批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第11回では、オーストリアの文豪・ヨーゼフ・ロートによる『ウクライナ・ロシア紀行』(日曜社)を評する。
第1回:《妻》はどこにいるのかーー村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評
第2回:《勢》の時代のアモラルな美学ーー劉慈欣『三体』三部作評
第3回:インターネットはアートをどう変えるのか?ーーボリス・グロイス『流れの中で』評
第4回:泡の中、泡の外ーーカズオ・イシグロ『クララとお日さま』評
第5回:承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評
第6回:メタバースを生んだアメリカの宗教的情熱――ニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』評
第7回:感覚の気候変動――古井由吉『われもまた天に』評
第8回:帰属の欲望に介入するアート――ニコラ・ブリオー『ラディカント』評
第9回:共和主義者、儒教に出会う――マイケル・サンデル他『サンデル教授、中国哲学に出会う』評
第10回:胎児という暗がり、妊娠というプロジェクト――リュック・ボルタンスキー『胎児の条件』評
共産主義という壮大な実験に臨むソヴィエト
政治史上の20世紀を「実験の世紀」と呼ぶならば、その最大の実験場は疑いなくソヴィエトである。特に、ヨーロッパの知識人にとっては、後進国のロシアで革命が起こり、人類の変革を掲げる共産主義が国家的な綱領となったことは、大いなる驚きをもって受け止められた。それゆえ、彼らがこぞってソ連に関心を寄せたのは不思議ではない。
ソ連の旅行記を書いた西欧人作家としては、H・G・ウェルズやアンドレ・ジッドの名が思いつく。1866年生まれのウェルズはペテルブルグの旧友マキシム・ゴーリキーのもとを訪れ、続いてモスクワのレーニンと会談した。その模様を記した『影のなかのロシア』(1920年)では、ソ連の電化を進めるレーニンが「電気技師のユートピア」に屈服した「クレムリンの夢想家」だと批判される反面、がたがたのロシアを再建できるのは、彼の率いるボリシェヴィキ政権だけだという認識も記されていた。
かたや1869年生まれのジッドの『ソヴィエトからの帰還』(1936年/邦題『ソヴィエト旅行記』)は、ソヴィエトに対する幻滅の記録である(ゴーリキーの葬儀において読まれた演説も含む)。スターリン体制下のソ連を訪問したジッドは、社会を支配するコンフォーミズム(順応主義)やその閉鎖性を目の当たりにして、労働者の解放が夢物語にすぎないことを告発した。自らに同意する者しか認めないスターリンの独裁が、極度に抑圧的な収容所国家を生みつつあることは、ジッドには明らかであった。
西側のヨーロッパ人にとって、共産主義という壮大な実験に臨むソヴィエトは、彼らの政治上の願望や不安の投影されたスクリーンとなった。この前代未聞のプロジェクトの内部に入り込んだウェルズやジッドは、一般民衆にも政治的人間の顔を投射した。ジッドがロシアの風景にさほど興味を示さず「私にとって大事なのは人間であり、人類なのである。人間をどう導くべきか、人間はどう導かれてきたのか、なのである」と明言したことは、彼の姿勢をよく示している。
それに対して、1894年生まれのドイツ語作家ヨーゼフ・ロートの観察は、イデオロギーに還元されない複雑なニュアンスを帯びている。レーニン没後の1926年から翌年にかけて、ロートはドイツの新聞『フランクフルター・ツァイトゥング』の記者としてウクライナおよびロシアを取材し、その報告を本国に書き送った(ちなみに、モスクワ滞在中には同世代のヴァルター・ベンヤミンとも会っている)。本書はその一連のレポートを収録したものである。
レニングラードに到着したロートは、ドストエフスキーの『罪と罰』さながら、さっそくその幻影のような都市風景を見事に再現してみせる。ジッドが政治的人間に焦点をあわせたのに対して、ロートはむしろ風景と人間のからみあいを描き出した。「ヴェネツィアが水の上に君臨する都市なら、レニングラードは湿地の上に君臨する都市だ。しかし、都市のほうが湿地に取り込まれようとしている」(31頁)。かつてはパリよりも賑やかなヨーロッパ的都市であったペテルブルグは、今やレニングラードと名を変えたが、そこは相変わらず湿地の生み出す霧に包まれている。革命によって圧倒された旧世代の反動的保守主義たちはニヒリストとなり、この霧のなかで亡霊のように漂うばかりだ……。
もっとも、革命後の新世代にしても、もはや文化的な輝きはもたない。なぜなら、そこで求められたのは、ドストエフスキーやトルストイのような天才ではなく、国民学校の教師だからである。「英雄が活躍する時代は終わった。今は勤勉な事務員の時代なのだ。叙事詩の時代は終わった。今は統計の時代なのである」(78頁)。「ロシアの若い流行作家は、誰にでもわかるような簡単な文体を用いる。とても原始的な言葉なので、ニュアンスや心情などを正確に伝える力をもたない」(80頁)。突出した個や複雑な心情よりも、全体の合理性が優先される社会――このような平均化・凡庸化から、後にジッドの批判した順応主義まではあと一歩だろう。
英雄や文豪はお払い箱となり、事務や統計が幅を利かせる――このようなシステムの勝利を前にして、ロートはもう一つの実験国家アメリカをロシアに重ねあわせた。「私にはときどきロシアで最も古い都市(モスクワやキエフ)の通りですら、新世界の通りのように感じられる。アメリカ西部開拓地の新興都市を思い出すのである」(74頁)。ロシアは「最果ての西」であるアメリカを技術的目標として、全国民を巻き込む進歩的な「新世界」へと息せき切って生まれ変わろうとする――そのとき、アメリカとロシアはイデオロギー的には対極であるにもかかわらず、双生児のように似てくるだろう。ロートの見立てでは「電気アイロンの、衛生の、水道網の、進歩の国」(79頁)としてのアメリカは、ロシアにとって最大のライヴァルでありながら、事実上のモデルとなったのである。
しかも、ロートの鋭い観察眼は、この前のめりの前進運動が矛盾やきしみを生まずにはいられないことを見抜いていた。国家全体が「一つの途方もない装置」(74頁)と化して新世界へと跳躍しようとする、その急激なプロセスがロシアに精神的な虚無をもたらしていることに、ロートはジッドよりも十年早く気づいていた。この敏腕のジャーナリストにとって、ソヴィエトは西側の政治的な希望を投影するスクリーンというより、むしろ新しい精神が古い亡霊と交差する《コーラ》であったと言えるだろう。彼はこのコーラを渡り歩きながら、それを豊かな息遣いと明快な文体をもつ紀行文へと仕上げたのである。