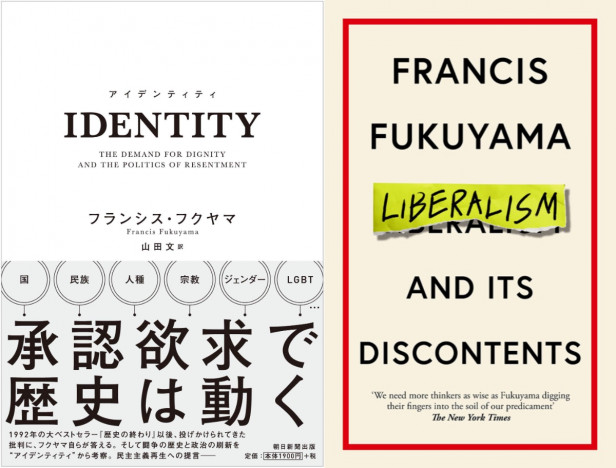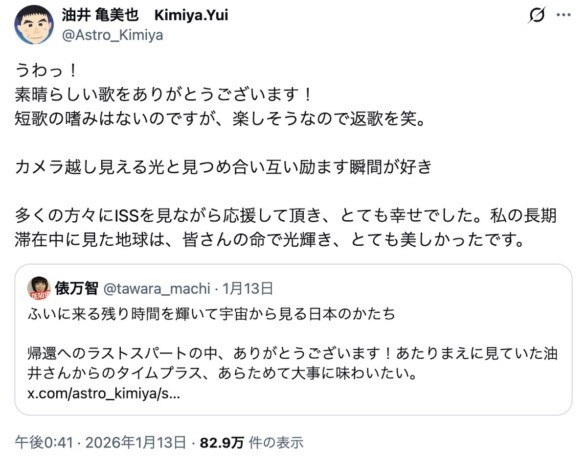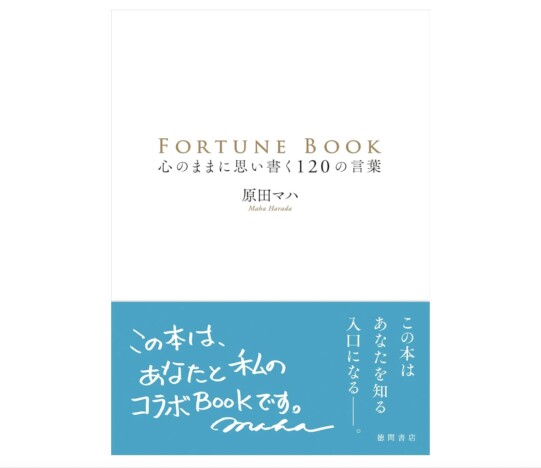胎児という暗がり、妊娠というプロジェクト――リュック・ボルタンスキー『胎児の条件』評

書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。
批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第10回では、フランスの社会学者リュック・ボルタンスキーの『胎児の条件:生むことと中絶の社会学』(2018年/法政大学出版局)を評する。
第1回:《妻》はどこにいるのかーー村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評
第2回:《勢》の時代のアモラルな美学ーー劉慈欣『三体』三部作評
第3回:インターネットはアートをどう変えるのか?ーーボリス・グロイス『流れの中で』評
第4回:泡の中、泡の外ーーカズオ・イシグロ『クララとお日さま』評
第5回:承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評
第6回:メタバースを生んだアメリカの宗教的情熱――ニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』評
第7回:感覚の気候変動――古井由吉『われもまた天に』評
第8回:帰属の欲望に介入するアート――ニコラ・ブリオー『ラディカント』評
第9回:共和主義者、儒教に出会う――マイケル・サンデル他『サンデル教授、中国哲学に出会う』評
生殖テクノロジーが突きつける難題
私事で恐縮だが、我が家には幼い息子がいる。やんちゃでおしゃべりな彼が、ついこの間まで母親の胎内にいたと思うと、呆然とせざるを得ない。人間存在の前史としての胎児とはいったい何なのか――これは数年来、私にずっとつきまとっている謎である。
胎児と新生児は個体として連続しているにもかかわらず、その社会的な扱いはまるで違う。新生児は産声をあげたときから、医療的にその存在を確認され、法的に保護される。つまり「近代」の諸制度が、その新生児を「人間」として扱うために迅速に入り込んでくるのだ。その後、周囲の大人たちはこの子を文化の網の目に組み込むために、名前と衣服を与え、写真を撮り、折々の行事でお祝いする。新生児はさまざまな「認証」の装置をくぐり抜けて、個別化されるのである。
それに対して、胎児は文化以前のミステリアスな存在である。その胎内での姿かたちは、誰も肉眼では確認できない。胎児を表象し意味づけるにはテクノロジーの力を借りるしかないが、エコー写真はぼんやりしてまるで心霊写真のようである。胎児は映像としてプロジェクト(投影)された亡霊的存在であり、社会にも文化にも帰属していない。その正体は結局、産んでみないと分からない。そのことが親を不安にする。高齢出産となれば、なおさらである。
この拭い難い不安を背景として、出生前診断をはじめとする生殖技術が近年、めざましい進歩を遂げている。もっとも、この種の診断を喜んで受ける親は、どこにもいないだろう。我が家も高齢出産であったため、出生前診断もいちおう検討したが「子どもの障害はいろいろあり得るのに、ダウン症だけがスティグマ化されているのはおかしい(かつ少ないながら流産のリスクもある)」「仮に陽性判定が出たとしても、エコー写真で存在を確認した胎児を中絶することは、どのみち心理的に耐え難い」ということで、結局受けなかった。ただ、診断を受けるか否かという以前に、心に重い枷をはめる技術がポンと与えられて、その後の選択は親に任されているのは、やはり大きな問題だろう。
思うに、妊娠はどこか地震と似ている。母体は胎児によって不意打ちされ、身体と感情を大きく揺るがされる(「娠」は『説文解字』によれば「女がみごもって身体が動くこと」を指す――「震」や「振」もそうだが「辰」という字にはもともと「動く」という意味がある)。震災の被災者と同じく、妊婦はいつやってくるか分からない「揺れ」のなかで、一定の不自由を甘受せねばならない。しかも、たいていの人間は経験も知識も乏しいまま、ある日いきなり妊婦や被災者になってしまうのだ。この新米の当事者が、生命に関わる重大な問題について「自己決定」せよと迫られても、適切な判断をくだすのは容易ではない。
生殖テクノロジーはこれまで選択不可能であったものを、選択可能にする。この急激な変化に対しては、まずは社会のなかで議論が蓄積されねばならない。しかし、本来そのような啓蒙をリードすべき「生命倫理」にしても、テクノロジーの進歩にはなかなか追いつけず、社会的な共有財産として定着していないのが実情ではないか。現に、出生前診断を受けたはいいものの、そこで出た確率をどう考えればよいか分からず、途方に暮れる親もいるようだ(クリニックによっては遺伝カウンセリングの体制すら整っていないケースもある)。今の日本では倫理的なスタンダードも確立しないまま、テクノロジーと自己決定が独走する傾向にある。「出生前診断」の読み方すら、ひとによってまちまちなのは、この問題をめぐる知の未熟さを象徴するものだろう。
加えて、もう一つの問題は、妊娠や出産に関心を寄せる世代がごく限られていることである。当事者たちが未知の新技術に右往左往する一方、社会全体としては知見がアップデートされない――ここにはテクノロジーの個人化ゆえの社会的分断がある。そのせいで、少子化がこれだけ問題視されているのに、生殖テクノロジーのほうはある意味野放しになり、当事者が選択の重荷を背負わされることになってしまう。最近よく話題になる卵子凍結も含めて、人類は「生むこと」について選択の自由を手に入れつつあるが、それは新たな「自由の刑」(サルトル)の出現を意味する。われわれはその自由の帰結を、まだ十分に理解できていないのではないか。