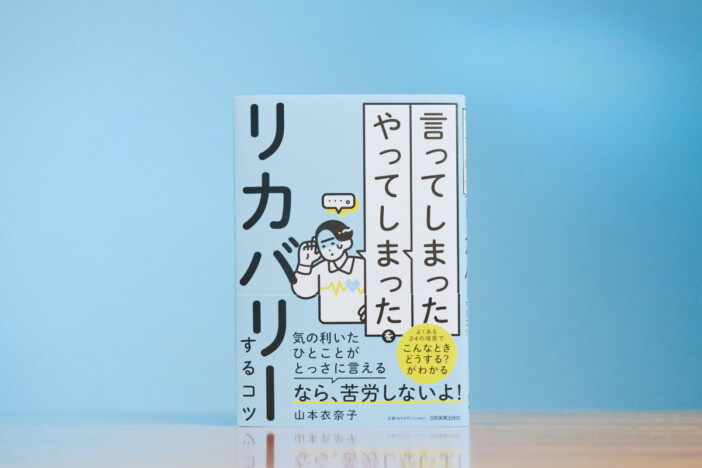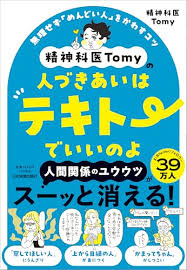大ピンチ発生! リカバリーどうすれば? 話題書の著者・山本衣奈子×謝罪のプロ・オズワルド伊藤に聞く極意

これまで5万人以上にコミュニケーションのアドバイスをしてきた山本衣奈子氏が『「言ってしまった」「やってしまった」をリカバリーするコツ』(日本実業出版社)を刊行。その実例や心理学の知見などを元にして、日常生活やビジネスシーンで起こりがちな、トラブルのシチュエーションについてリカバリーするテクニックがわかりやすく紹介されている話題の書籍だ。
オズワルド伊藤氏は特技が謝罪でありプロの「土下ザー」を自称する。キャバクラでのアルバイト時代に、土下座をすることで修羅場を何度も乗り切ってきたという実践から導き出されたピンチを回避するテクニックの持ち主だ。
今回そんな二人による「人生のピンチを乗り切るリカバリーテクニック」をめぐってのスペシャル対談。リカバリーと謝罪の極意についてのテクニックがわかります。(リアルサウンドブック編集部)
■リカバリーをする上での鉄則とは?
ーー何かをやらかしてしまってピンチに陥ることは、ビジネスパーソンのみならず多くの人が一度は経験していると思います。山本衣奈子さんにまずお聞きしたいのですが、リカバリーをする上で大事なことは何でしょうか。
山本:私が一貫して伝えているのは、「ごまかさない」「言い訳をしない」ということです。それ以上に大事なことはないと思っています。ごまかしたり、言い訳をしたりするから、余計に話がややこしくなる。そこは潔く自分の非を認めるべきです。だから伊藤さんの特技である土下座というのは、その最たる例だと思います。
ーーなるほど。伊藤さんの土下座も潔く自分の非を認めること、というリカバリーの観点では大事なことなのですね。他に大切なことはありますか。例えば相手の話をしっかり聞くことも大事でしょうか。とにかく怒りを吐き出させると、気がおさまるような、心理的な効果がありますか。
山本:コミュニケーションの鉄則なんですが、「人は話をしたい生き物だ」と言われています。怒った人も話しきるだけで、すっきりするところがある。でも途中で遮ってしまうと、話しきれていない不快感が残るんです。その不快感が別の行動・言動を引き出してしまうことがあるでしょう。しっかりと「聞き切る」というだけでも、全然違うと思います。
伊藤:僕は土下座以外で、本当に解決しにいくんだったら、時間をかけて全部聞くこと・そこでは一度も否定しないこと、この二つが一番効果的だと思っています。アルバイトしていたころの経験ですが、聞きながら「そうっすね、そうっすね」とすべてに相槌を打ちながら、「勉強になります」「全面的にうちが悪いです」「本当にクソみたいな店ですよね。前々から僕もらそう思ってました」くらいまで言うんですよ。
山本:(笑)。でもそこまで同意されると、悪い気はしませんよね。コールセンターでクレームを受け取ったときも、まずはとにかく聞き入れるのが大事だとされています。
――伊藤さんは、よく遅刻をされることでも有名ですが……。
伊藤:有名“でした”でお願いします。今は遅刻していませんから。
――遅刻したときのリカバリーはどうやっていたのでしょうか?
伊藤:どうにか「いじってもらう」努力はしましたね。遅刻したとき、誰よりもくやしそうな顔で現れて「わかります! みなさん……僕もくやしいんです!」と大声をはりあげたり。あと到着して「どういうつもりだ、こんなに遅刻して!」と共演する芸人仲間に言われても、無視するという荒業を使ったこともあります。「喋れや!」というツッコミ待ちで。
山本:効果はいかがでした?
伊藤:ぜんぜん通じません。結局、遅刻は自分が100%、僕だけが悪い局面ですからね。
山本:(笑)。ただ無視はともかく、悪いことをした自覚を持ちながら「僕もくやしい」といったような「感情を思いに変えて伝える」のは有効ですよね。リカバリーしなければ、と思った時点で、相手に愛情なり好意がまずあるわけですから。その思いをつたえればいい。「私はあなたとの関係を壊したくない」と口に出して正直に伝えるのは、悪手ではなく、むしろ誠実だし、伝わりやすいと思いますね。
■謝罪は土下座で乗り切れる?

伊藤:お客さんの怒りが長引くよりそっちのほうがいいなと思ったんです。結局、キャバクラのお客さんは形を求めている。そこでマックスの土下座を出されたら、何も言いようがなくなりますよね。そこからかかと落としをされたこともありますけど。その時はひたすら謝って乗り切りました。
ーーそもそも、キャバクラでお客さんが怒るシチュエーションとは。
伊藤:指名の女の子がなかなか戻ってこない。思っていた料金よりも高額だ。大体この二本ですね。ただ、怒る理由は人それぞれでした。「たこ焼きの無料サービスが、この間は5個だったのに今日は4個しかない」と言われて、ビンタされたこともあります。
ーー伊藤さんはnoteの記事で土下座する上での3つのステップを解説していました。まず1つ目に、「相手の怒りの温度を知る」ことが大事だそうですね。
伊藤:土下座が必要ないレベルの人に、土下座をすると逆効果なんです。そこまでの怒りじゃなかったのに、大ごとにしようとしていると思われてしまう。もしくは逆に、土下座では無理である場合も逆効果です。
だからまず顔の表情や口調を確認します。あとは女の子の前で言っているかどうか。いる場合のほうが土下座が効くんですよ。メンツを保ちたいだけであって「こちらが100%悪かった」と形を見せてあげれば、女の子の前で一応格好はつくんですよね。
ーー伊藤さんのこうした土下座、相手の怒りの温度を推し量って実行するというステップは、山本さんのリカバリー術と通ずるところがありますか。
山本:ありますね。しかし、普段のコミュニケーションにおいては、まったく推奨はできません(笑)。
伊藤:ですよね。
山本:ただ一部は納得できますし、参考になりますよね。
まず相手が何を求めているかを見極めるのは、リカバリーでも大事なんです。これは謝罪や雑談、議論でも何でもコミュニケーション全般でそうなんですが、「そこじゃない」ことを投げられても、納得ができませんよね。たとえば、求めていない相手に土下座することがかえってマイナスになることもありえる。そこはしっかりと読み取ったほうがいいですね。
ーーなるほど。ステップ2はいざ土下座をする時には「とにかくスピードを意識する」こと。途中からやると余裕があると思われてしまう可能性があると。
伊藤:いざ、土下座を決めたら、もう相手の目に触れたところで、走りながら低い姿勢になって、滑り込むように土下座をしていましたね。
山本:スライディング土下座(笑)。ただ確かにやるなら素早い間合いでバッとやるから効果があるんだと思います。それを間違えると「とりあえず土下座すればいいだろうと思っている」と思われてしまうリスクがある。それではヒートアップしてしまうでしょう。
ただ、最初に土下座という行為をいざしようとしたとき、ひるんだり、躊躇したりすることはなかったのですか?
伊藤:ありませんでしたね。土下座をただのコマンドとしか思っていないんです。僕自身は、ことさら意味があるとは考えていない。だからすぐさまできたんだと思います。
もっとも、ドラマなどのクライマックス土下座のシーンを見ても、感情移入できないデメリットはありますね。『半沢直樹』のドラマでも土下座するのにめちゃくちゃ時間かかるシーンがあったじゃないですか。「俺だったらすぐ秒でやるのにな」「尺が足りなくなるな」としか思えず、まったくのれませんでしたからね(笑)。
山本:足を折るだけで、だいぶ時間がかかってましたもんね(笑)。
伊藤:あれもだいぶ大袈裟にデフォルメしているとは思うんですけど。
ーー山本さんの新刊『「言ってしまった」「やってしまった」をリカバリーするコツ』でも、「何を言うか」だけではなく、「どう言うか」も大事だと記されています。謝罪ならば表情や態度もそれ相応じゃないと伝わらないと、土下座はそれをデフォルメしていますが、わかりやすい例ですよね。

――ただ、伊藤さんは最後、土下座の3ステップ目に「引かれるくらい大きな声で謝ろう」と提唱されています。
伊藤:そうです。土下座の効果はここにあります。多くの方が土下座はものすごくネガティブな行為だと思っているだけに、眼の前で全力でそれをやっている僕はもちろん、「土下座をやらせている相手」も極めて注目を浴びてしまう。望まぬ注目が集まってしまいます。
ようするに「恥ずかしさ」が際立って、相手は早く終わって欲しいと思い始めます。「もうわかったから、やめろ」「頼むから、やめてくれ!」となるのはそのためなんです。
山本:確かに、そうですね。とても冷静に、相手の気持ちと周囲の反応を予測して、考えていらっしゃるんですね。その「冷静さ」や「俯瞰で全体を認知する」ことは、コミュニケーションでミスをしたさいに、リカバリーをはかる基本姿勢としてとても強みになると思います。
伊藤:ああ。どこか俯瞰で周囲や自分を見ているところはありますね。正直なところ、キャバクラでの土下座も、極論、お客様に対する謝罪コミュニケーションですが、実はお店の他のスタッフや女性キャストとの関係性を高める意味で、率先してやっていたところがある。「伊藤は土下座してまで矢面に立った」事実は、以降の店内の関係性をかなりポジティブにしますからね。なんかやらしいけど(笑)。
ーー『「言ってしまった」「やってしまった」をリカバリーするコツ』の中でも「でも」などのネガティブな「Dワード」を思わず言ってしまった時は、そのままにせずに「というのも〜」と説明して相手側に立つといいと解説していました。これは役に立ちそうなテクニックですね。
山本:ただの否定で終わるのではなく説明を加えることで、相手も「あなたはそういう意見なんだ」と納得できるんですよね。それからお互い「私はこう思っている」という意見を言い合って会話できるんです。コミュニケーションは必ずしもいつも「そうだよね」「わかるわかる」となるわけではありません。お互いに違う部分を出し合ってもいい。ただそこでは攻撃し合うのではなく、相手を尊重しながら意見を言えるといいと思います。
伊藤:そのDワードというのも、難しいですよね。もしかしたら「でも、山本先生の本によると、こう言っているし」などと、だいぶだるい使われ方をされる可能性もありますからね。