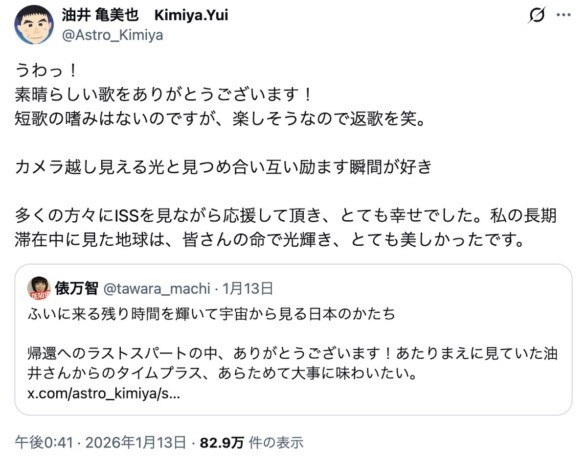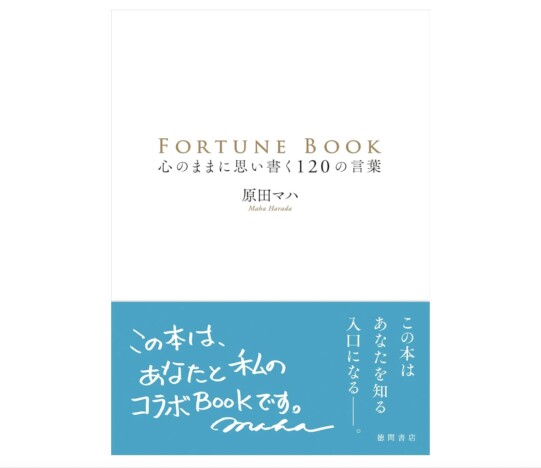自己を環境に似せるミメーシス――ヨーゼフ・ロート『ウクライナ・ロシア紀行』評

書物という名のウイルス 第11回
ロートという作家自身が「都市」である
ヨーゼフ・ロートはもともと、東ガリツィアのブロディ(現ウクライナ・リヴィウ州)に生まれたユダヤ人であったが、その出生を偽ってオーストリア国籍の取得に成功し、ジャーナリストとしてベルリンで売れっ子になる(平田達治『放浪のユダヤ人作家ヨーゼフ・ロート』参照)。小説家としても成功するものの、ナチス台頭の危機をいち早く察知して亡命したロートには、苛酷な運命が待ち受けていた。彼は苦労を重ねたあげく、わずか40代半ばでパリのホテルで客死することになるのだ。根無し草の「ラディカント」(ニコラ・ブリオー)という形容が、ロートほどふさわしい作家はいないだろう。
東方ユダヤ人にして、帝国の遺産を受け継ぐ古き良きコスモポリタンであったロートは、多民族の集合体であるオーストリア゠ハンガリー二重帝国に、終生愛着を寄せていた。帝国の東の果てにあったウクライナのレポートにも、ロートらしい視野の広い観察眼が及んでいる。
ロートによれば、当時のウクライナはオリエンタリズム的な好奇のまなざしで見られていた。「ときどき、ある民族がブームになることがある。以前はギリシャ人、ポーランド人、ロシア人が人気だったが、今はウクライナ人だ」「私たちはウクライナという土地と人についてわずかなイメージしかもっていない。だから惹かれるのである」(6‐7頁)。ウクライナは実体ではなく表象であり、だからこそそれは無造作に消費された(このような事情は2022年の「負のウクライナブーム」においても、さほど変わらないだろう)。しかも、このオリエンタリズムは東欧人にも波及する。「ロシア、ウクライナ、ポーランド人などの東欧諸国から西欧に移住してきた人々が、ウクライナブームに便乗して自分たちを古い「ウクライナ人」と呼ぶようになったのだ」(7頁)。
こうして、偽ウクライナ人たちが出現する一方、当のウクライナ人自身は国家をもてずに、他の民族のあいだで散り散りになっていた。大きな民族がまるごと放浪状態に置かれる――その不幸はウクライナ生まれのユダヤ人ロートの運命そのものである。ロートは「まれびと」としてウクライナを訪問したのではなく、いわばよそ者のふりをして故郷をきめ細やかに観察したのであり、そのことが情感豊かな文体へとつながっていた。
特に、生まれ故郷に近いリヴィウ(当時はポーランド領)のレポートでは、悟性と感性が高度に融合している。ポーランドとロシアの長年にわたる戦争のなか、リヴィウは後方基地として戦禍の余波を蒙ってきた。ロートはリヴィウで目撃した戦争負傷者の列についてレポートしている。「人間を人間たらしめる特徴が吹き飛ばされた」ポーランド人負傷者たちの無惨な姿は「恐ろしくもなまめかしい光景」(22頁)を出現させる――このモラルを超えた光景は、その後の第二次大戦を予告するものでもあるだろう。
しかし、激しい暴力の通過点であったにもかかわらず、リヴィウはその優雅で軽やかな表情を失うことがなかった。「リヴィウの豊かな色彩は、早朝目覚めたばかりの半覚半醒のような状態。いわば若々しい多彩さなのである」(18頁)。ブダペストのような「押しつけがましい派手さ」をもたないリヴィウの通りは、ロシア語、ポーランド語、ルーマニア語、イディッシュ語等の行き交う「大きな世界の小さな縮図」の様相を呈する。ロートにとって、このような多元性こそが「都市」の証明であった。
都市の特徴について書く、というのは思い上がった行為だ。都市にはたくさんの表情やムードが、あまたの方向性が、さまざまな目的がある。暗い秘密も、明るい秘密もある。都市は多くを隠し、多くを明らかにし、それ自体が一つの統一体であり、同時に多様性の宝庫でもある。どのジャーナリストよりも、どの人間よりも、組織よりも、国家よりも長生きする。さまざまな民族がやってきては去っていく。彼らがいるからこそ、都市は存在でき、そのときどきの支配者が使う言葉が都市の言語となる。都市の誕生と成長と死をつかさどる法則は数限りない。それらを分類することも、規則性を見いだすことも不可能だ。例外的な法則ばかりなのである。(15頁)
この簡潔明瞭でありながら、複雑なニュアンスに富んだレポートは、ロートという作家自身が「都市」であることを物語っている。ロートは出生を隠しつつ、誰よりも機敏にロシアやウクライナ諸都市の状況を明らかにし、ユダヤ人という秘密をもちながら、ウクライナ人やポーランド人の生活風景をつぶさに報告した。彼にとって、ジャーナリズムも小説も、都市のディテールに隠された「例外的な法則」を発見する手段であった。
ここで重要なのは、リヴィウが国境の一都市であるとともに、多民族的なオーストリア゠ハンガリー二重帝国のマージン(周縁/余白)でもあったことである。「リヴィウは境界が曖昧になった都市なのである。旧帝国の東の果て。リヴィウを越えればそこはもうロシア、もう一つ別の世界が始まる」(20頁)。ロシアと踵を接しながら、民族的・言語的な多様性を保ってきたリヴィウは、まさに《帝国の縮図》であった。オーストリア゠ハンガリー二重帝国そのものは1918年に解体されたが、その帝国の記憶はリヴィウという辺境の都市に継承され、そのありさまがロートの文体に鮮やかに転写されていくのである。