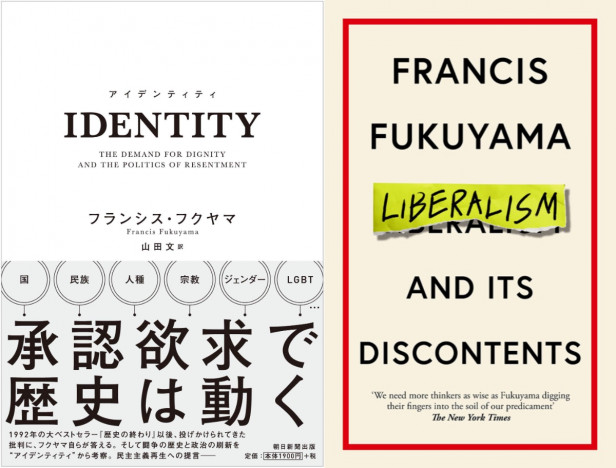帰属の欲望に介入するアート――ニコラ・ブリオー『ラディカント』評

書物という名のウイルス 第8回
書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。
批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第8回では、「関係性の美学」を提唱したキュレーター、ニコラ・ブリオーの初邦訳となる『ラディカント グローバリゼーションの美学に向けて』(フィルムアート社)を評する。
第1回:《妻》はどこにいるのかーー村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評
第2回:《勢》の時代のアモラルな美学ーー劉慈欣『三体』三部作評
第3回:インターネットはアートをどう変えるのか?ーーボリス・グロイス『流れの中で』評
第4回:泡の中、泡の外ーーカズオ・イシグロ『クララとお日さま』評
第5回:承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評
第6回:メタバースを生んだアメリカの宗教的情熱――ニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』評
第7回:感覚の気候変動――古井由吉『われもまた天に』評
ラディカントの美学
ニコラ・ブリオーと言えば、「関係性の美学」を唱えた世界的に著名なキュレーター・美術批評家だが、日本での紹介は遅れていた。本書(原著は2009年刊行)はブリオーの初の邦訳書となる。彼の書きぶりは体系的とは言えないものの、その主張はとりあえず「ラディカルからラディカントへ」「帰属のモデルから翻訳のモデルへ」「ポストモダニズムからオルターモダニズムへ」と要約できるだろう。
radicalの語源は「根」である。20世紀のモダニズムはラディカルであろうとした。絵画なら絵画の、彫刻なら彫刻の「根源」に、不純物を取り去りながら遡行し、その表現のプログラムを徹底的に洗い直す――このようなジャンルの純化がモダニズムの理論的立場(特にクレメント・グリーンバーグの「メディウム・スペシフィック」に代表されるもの)を特徴づけている。ラディカルなモダニストたちはそのジャンルの規則を根本的かつ徹底的に解析し、芸術を新たに始め直すことをもくろんだ。
しかし、ブリオーによれば、このようなモダニズムの「根」の探究は、グローバル化のなかで二つの困難に直面している。一つは根源に遡ろうとするラディカルな思考の運動が「アイデンティティという根」への帰属に置き換えられてしまったことである。もう一つは「移民、亡命者、観光客、都市の放浪者」(70頁)のように、たえず移動するノマド的な主体が出現したことである。それゆえ「グローバリゼーションの美学」を構想するには、根へのオブセッションを捨てて、主体と芸術のモデルを新たに練り上げなければならない。そこでブリオーが標語的に提案するのがradicant、つまり接ぎ木や移植のモデルである。
このラディカントという付加形容詞は、前進するにつれて根を伸ばし、また増やしてゆく有機体を指すものである。ラディカントであることとは、みずからの根を異質な文脈やフォーマットのなかで演出することであり、そこで始動させることである。わたしたちのアイデンティティを完全に定義する力を根に認めないことである。(27頁)
ラディカントなアートは「アイデンティティの実験室」として機能する。「ラディカルなアーティストがオリジナルな場に戻ろうとしていたのに対して、ラディカントは戻るべきいかなる場所ももたずに出発する」(71頁)。特定の根=場所をもたずに、たえず転位(displacement)を続けるラディカントな主体像――ブリオーによれば、それはある言語コードから別の言語コードへと移動し続ける「翻訳者」、あるいは記号の海を冒険する「記号航海士」に等しい(197頁)。
それにしても、ブリオーはなぜ「根」へのこだわりを解除しようとするのか。それは、モダニズムを乗り越えるはずのポストモダニズムが、多文化主義の旗印のもとアイデンティティ・ポリティクスに吸収されたからである。
ポストモダンの多文化主義がモダニズムの普遍主義に対するオルタナティヴを創出することに失敗したのは、それが適用されたあらゆる場所において、文化的投錨や民族的に根を張ることを再現したからである。ポストモダンの多文化主義は、西洋の古典的な思考とまったく同じく、さまざまな帰属に基づいて機能するものだからである。(43頁)
ポストモダンの多文化主義は、人類を変革しようとする大きな物語――共産主義をその頂点とする――をあきらめて、おのおのの小さな物語を等しく尊重する方向に舵を切った。しかし、その結果、アーティストの作品以上に、彼(彼女)がどのようなアイデンティティに「帰属」しているかばかりが問われるようになる。「各人は、出所を突き止められ、登記され、みずからの言表行為の場に釘づけされ、みずからの出自となる伝統に閉じこめられる」(同頁)。モダニズムの終焉の後、ひとびとはアイデンティティという分類表に基づいて、作家をラベリングするようになった。ポストモダニズムは新たな普遍性への道を開き損ね、アイデンティティという特殊な根――今やそれは「プロフィール」として明文化される――を聖域としたのである(※)。
この袋小路から脱出するために、ブリオーはモダニズムの普遍主義でもなく、ポストモダニズムの多文化主義でもない、文化間の翻訳や変換や放浪のプロセスを核とする「オルターモダニズム」の道を示そうとする。彼の考えでは、それにはすでに先例がある。例えば「移ろいゆくものから永遠のものを引き出す」という19世紀の詩人シャルル・ボードレールの有名な宣言は、プレカリアス(不安定)な生を象ろうとする現代アートに先駆けている。さらに「根無し草」であることを恐れなかった20世紀前半のマルセル・デュシャンの「レディメイド」の手法には、日常的なモノをその帰属先から引き抜いて移植するラディカントの美学が予告されていた。
ラディカルな(=根源へと遡る)モダニズムとは異なる、もう一つの近代性の系譜をとり出すこと――それはパリのボードレールやニューヨークのデュシャンの都市型モダニティを、21世紀の文脈で浮上させることを意味する(逆に言えば、安心の根を得ようとプロフィールの獲得に汲々とするのは、どこか田舎者の所業に似てくる)。エフェメラルであること、壊れやすいこと、クレオール的であること、放浪することは、偶然の異種配合をもたらす交換台として機能する。ブリオーは根無し草であることを逆用するアートの系譜に、根の牢獄から脱出するヒントを見つけ出そうとしたのだ。
(※)社会学者のハンス゠ジョージ・メラーは、唯一無二の「本物である」(authentic)ことを望むのが近代人の欲望であるのに対して、ポストモダンの人間にとっては、本物であるかどうかよりも、プロフィールの獲得が新たな価値基準になっていると見なす(Hans-Georg Moeller, You and Your Profile)。要は、自己の隠れた内奥を凝視するのではなく、むしろ他人にとって観察しやすい記号的・表層的な自己像(経歴、見た目、フォロワー数等)を操作しつつ、承認ゲームで勝とうとする動きが一般化するわけだ。ただ、プロフィールという綺麗な造花を並べ、仲間外れにされないように周囲をうかがいながら「過剰可視化社会」(與那覇潤)に適応しても、それは生き方として虚しいのではないか。ブリオーの「ラディカント」や私の「庭」(拙著『思考の庭のつくりかた』参照)は、このプロフィールの政治をすり抜けるための、別の植物的なモデルの提案である。