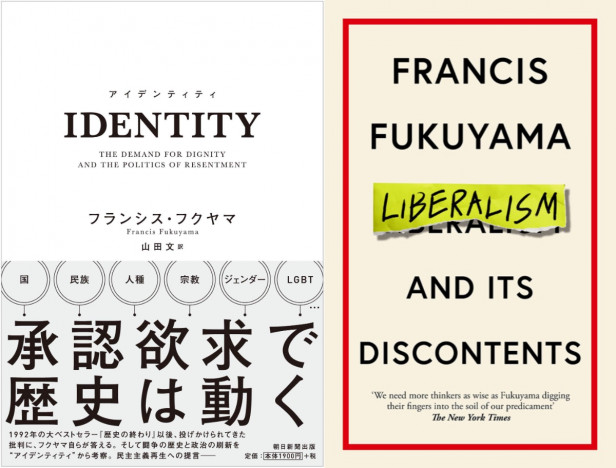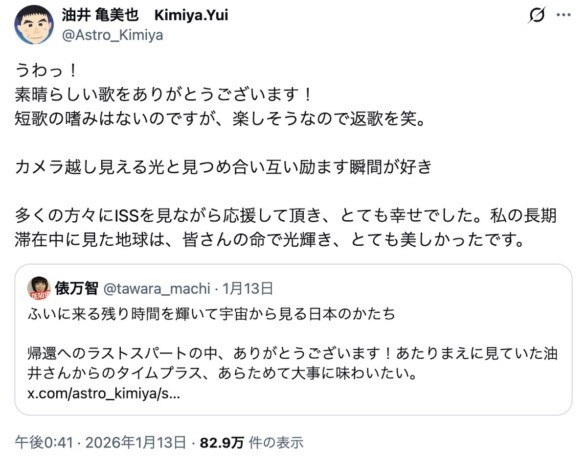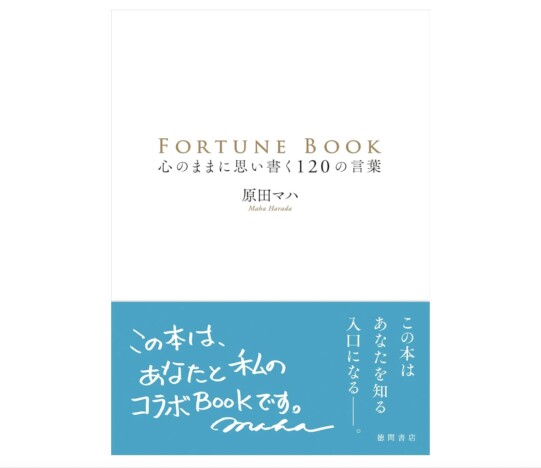共和主義者、儒教に出会う――マイケル・サンデル他『サンデル教授、中国哲学に出会う』評
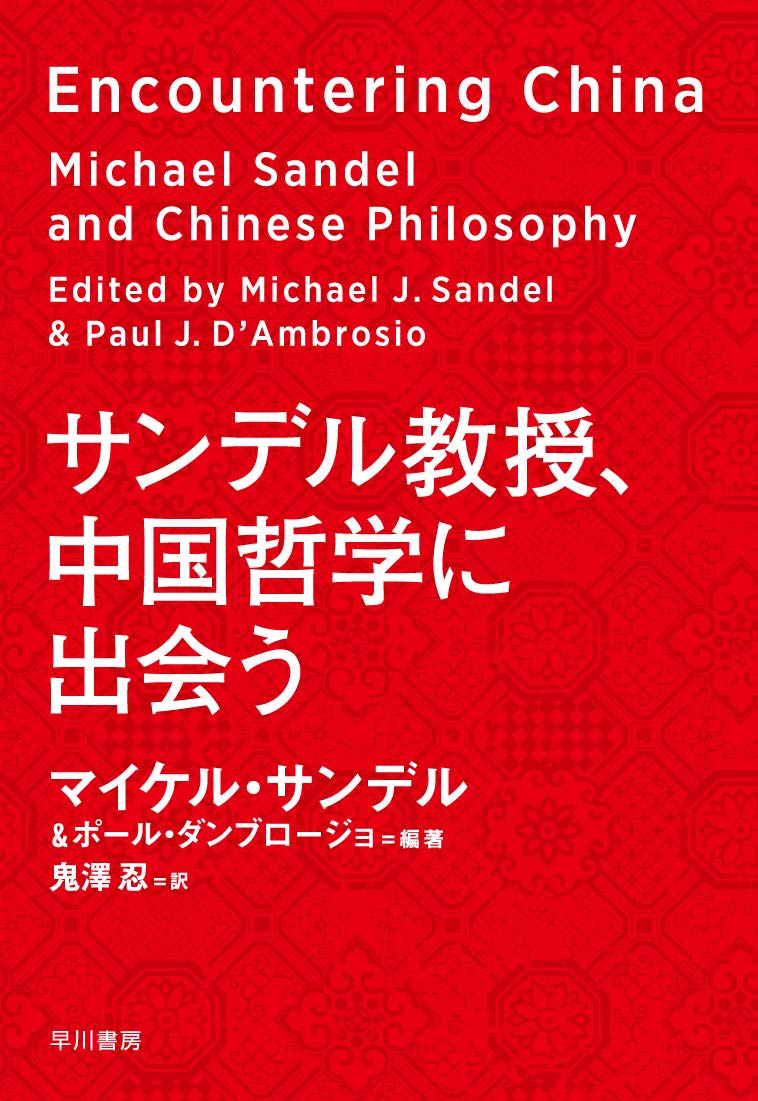
書物という名のウイルス 第9回
書評とは何か。それは「書物の小さな変異株」を作ることである。書物はウイルスと同じく、変異によって拡大する。
批評家の福嶋亮大が、文芸書と思想書を横断し、それらの小さな変異株を配列しながら、21世紀世界の「現在地」を浮かび上がらせようとする連載「書物という名のウイルス」。第9回では、ハーバード大学の人気講義「Justice(正義)」をもとにした書籍『これからの「正義」の話をしよう──いまを生き延びるための哲学』(早川書房/2010年)などで知られるアメリカの哲学者、マイケル・サンデルが儒学者ら9人の論考に応答した『サンデル教授、中国哲学に出会う』(早川書房/2019年)を評する。
第1回:《妻》はどこにいるのかーー村上春樹/濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』評
第2回:《勢》の時代のアモラルな美学ーー劉慈欣『三体』三部作評
第3回:インターネットはアートをどう変えるのか?ーーボリス・グロイス『流れの中で』評
第4回:泡の中、泡の外ーーカズオ・イシグロ『クララとお日さま』評
第5回:承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評
第6回:メタバースを生んだアメリカの宗教的情熱――ニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』評
第7回:感覚の気候変動――古井由吉『われもまた天に』評
第8回:帰属の欲望に介入するアート――ニコラ・ブリオー『ラディカント』評
サンデルの政治哲学
アメリカの哲学者マイケル・サンデルはハーバード大学での講義の中継によって、2010年代以降に世界的なスターとなった。この「思想界のパンデミック」とも言うべきサンデル・ブームは、特に日本、韓国、中国のような東アジア圏で顕著であった。本書はそのサンデルの政治哲学に対して、中国および北米の研究者たちがもっぱら儒家および道家の立場からコメントし、それに本人が応答した論文集である。ただ、その内容は込み入っているので、まずはそれぞれの思想的文脈を整理したい。
サンデルの政治哲学はよくコミュニタリアニズム(共同体主義)に分類されるが、今となってはむしろリパブリカニズム(共和主義)と見なしたほうがよいだろう(この点は本書の朱慧玲や陳来の論文で取り上げられている)。サンデル自身、主著『リベラリズムと正義の限界』第二版の序文でこの問題を説明している。もしコミュニタリアニズムが多数決主義、つまり当の共同体における一番人気の価値観に従う思想だとすれば、サンデルはコミュニタリアンではない。彼はむしろ人間にとって望ましい生き方を熟慮し、その道徳的な「目的」を完成させようとする卓越主義(perfectionism)の側に立つ。当の共同体で広く信じられているか否かにかかわらず、人間たちの共有すべき「共通善」を成就しようとする態度――サンデルによれば、これはアリストテレス哲学からアメリカの共和主義にまで及ぶ知的伝統に連なるものである。
サンデルが『民主政の不満』(勁草書房/2010年)で示したように、アメリカ建国の始祖たち(トマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズ、アレクサンダー・ハミルトン……)には、共和主義の理想が認められる。彼らにとって、政治はたんなる調整原理ではなく、市民を価値の問題にコミットさせ、社会のテロス(目的)について熟慮させ、市民道徳を積極的に涵養しようとする「魂の形成術」であった。サンデルはこのような「市民的共和主義」の伝統を引き受けつつ、ジョン・ロールズ流のリベラリズム(さらにはロバート・ノージック流のリバタリアニズム)への批判を精力的に展開してきた。
ロールズ流のリベラリズムは、善の構想がひとそれぞれ多様である以上、政治は特定の善にコミットせず中立的であることが望ましいとする。その背景には、主体の「自由」と「自律性」を尊重したカントの哲学がある。カントにとって、人間には二つの側面があった。一つは他の物体と同じく自然の因果律に従った「私」であり、もう一つは自然法則から独立して自律性を獲得した「私」である。後者の「私」は刺激の入力→行動の出力というロボット的なサイクルから切り離されている――ゆえに、その人格は他の何ものかの手段ではなく、それ自体が「目的」なのである。このような自律的な主体の自由な選択を、特定の善の押しつけによって抑圧せずに、最大限に保証しようとするのが、リベラリズムの「正義」である。「善に対する正の優先」を標語とするロールズのリベラリズムは、ここから導かれる。
それに対して、サンデルの考えでは、一切の善の構想から切り離された正義はあり得ない。サンデル的な正義はむしろ、善い生き方とは何か、共同体はどうあるべきかという道徳的な「目的」の共有と不可分である。リベラリズムの想定する「負荷なき自我」のモデルはすっかり漂白されているので、家族や隣人のことも考慮に入れられず、公民的な美徳(civic virtue)を涵養することもできない。共通善についての問いを棚上げにするリベラリズムは「われわれは望ましい生き方を選んでいるのか」という公共的な熟議そのものを不要にし、暴走する市場のストッパーにもならない。それゆえ、社会的な連帯を取り戻すためには、市民参加や熟議に基づきながら、共通善を追求してゆく共和主義的な「正義」が必要である……。
このような見地から、サンデルは倫理的かつ具体的な課題に取り組んできた。2020年に原著が出た『実力も運のうち』(原題はThe Tyranny of Merit)では、能力主義が批判の槍玉にあげられている。誰もが能力さえあれば成功の可能性をつかめる――この一見して悪くないメッセージは、しかし実際には敗者に「お前は能力がないせいで失敗した」というレッテルを貼ることになる。成功した高学歴エリートに見下された低学歴の敗者は、出口のない屈辱やルサンチマンに囚われざるを得ない。リベラルなバラク・オバマ大統領が「インセンティブ」や「スマート」のように、能力主義に与する官僚的な言葉遣いを多用したことも、このような風潮を助長した。お互いに対話を経ないまま、勝者はますますおごりたかぶり、敗者はますます屈辱を募らせる――サンデルの診断によれば、この能力主義ゆえの分断が、反エリート主義的なドナルド・トランプのようなポピュリストの台頭を許した大きな理由なのである。
連載第5回(承認の政治から古典的リベラリズムへ――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』『リベラリズムとその不満』評)で見たように、フランシス・フクヤマはリベラルな自律性の原理が加速した結果として、かえって古典的リベラリズムのめざした「寛容」が損なわれたと見なした。サンデルも大筋で同じことを言っている。リベラリズムにせよ民主主義にせよ、それを支える前提として、公民の徳=力(virtue)がなければ機能不全に陥る――日本でも宮台真司や大塚英志がそのことをつとに指摘してきたが、SNSの広がりとも相まって、それが近年いっそうはっきりしてきたということだろう。