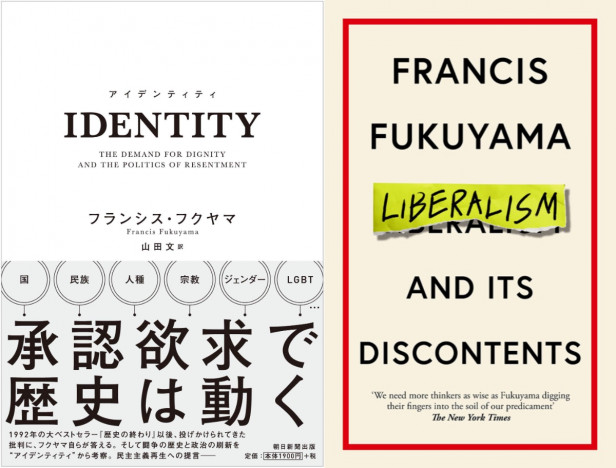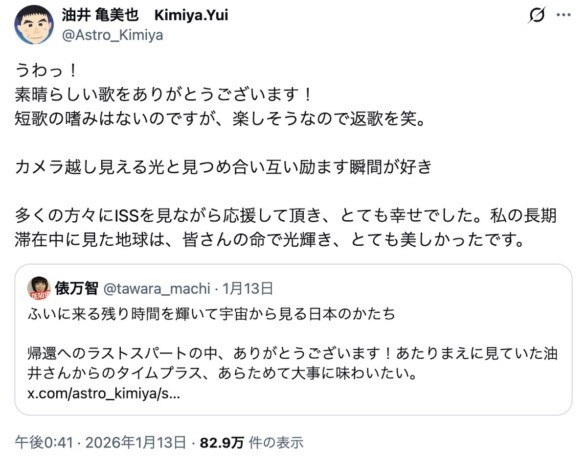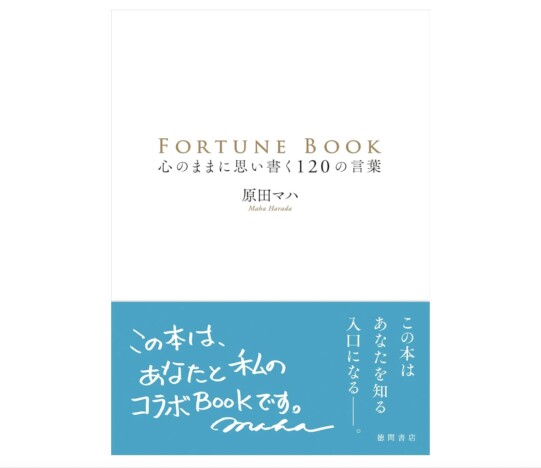胎児という暗がり、妊娠というプロジェクト――リュック・ボルタンスキー『胎児の条件』評

胎児の存在論的な位置づけ
ところで、生殖をめぐる知の未熟さや貧しさは、胎児そのものの捉えがたさとも深く関係する。新生児と違って、胎児にはきわめて貧しい意味しか与えられない。胎児としての数か月の生――子宮というトランジット(乗り継ぎ)における生、分娩=配達(delivery)が完了する前の輸送中の生――は、誰もが通過するステージであるにもかかわらず、人類の認識において盲点となっている。胎児は文化の防護壁をもたない。そのせいで、そこにはテクノロジーがしばしば留保なく入り込んでくるのだ。
ただ、このような状態を野放しにするのは望ましくない。フランシス・フクヤマ(『人間の終わり』)やマイケル・サンデル(『完全な人間を目指さなくてもよい理由』)も危惧するように、遺伝子操作が一般化し、能力を増強するエンハンスメント――イシグロの『クララとお日さま』の言い方を借りれば、giftedならぬlifted(向上措置)――が広まれば、自由や公正という近代の根幹の価値観は大きく揺らいでしまう。サンデルの考えでは、治療の領分を超えたエンハンスメントは、ひとびとの連帯の絆となる「生の被贈与性(giftedness)」(人間を規定する偶然性や脆弱性)を損なうことになるのだ。ならば、まずは胎児を認識の暗がりから救出することが、喫緊の課題ではないか。
その意味で、フランスの社会学者リュック・ボルタンスキーが「胎児の条件」の解明に挑んだことは、注目に値する。ピエール・ブルデューに学んだボルタンスキーは本書(原著は2004年刊行)のなかで、主に「中絶」の問題を中心としながら、胎児の存在論的な位置づけをめぐってさまざまなアプローチを試みた。その内容は込み入っているが、とりあえず要点を抽出しておこう。
〈1〉人類学的な視点から言って、中絶はこれまで「十分に表象されてこなかった」(32頁)。近親相姦や嬰児殺しのような、ひとをぞっとさせる「侵犯」であれば、神話や物語のなかでたびたび取り上げられる。しかし、中絶となると、イメージの次元にはほとんど記載されていない。哲学においても同様である。中絶は「自殺と異なり、西洋哲学が人間の条件について発展させてきた諸概念になんら影響を与えることはなかったように思われる」(33頁)。
ボルタンスキーによれば、中絶は近代・前近代を問わずどの社会にも普遍的にあるが、それが基本的な方針として認められることはなく、たいてい強い非難の対象となった。中絶を積極的に奨励する社会はない。にもかかわらず、その非難はたいてい道義的なものにとどまり、処罰にまで到ることは多くなかった(※)。つまり、おおっぴらに語られない秘密である中絶は、社会の憤慨を招きながらも大筋で許容されてきたのだ。
私なりに言い換えれば、中絶には禁止‐侵犯というバタイユ的なドラマがない。つまり、中絶は望ましいことではないが、秩序を動揺させる侵犯とまでは見なされない。決して称賛されないが、社会的にはおおむね許容される。中絶をめぐる価値判断は、しばしばうやむやのまま宙吊りにされる。中絶の核心にあるのは、このようなあいまいさである。
〈2〉そうは言っても、妊娠・出産の当事者にとっては、中絶という選択肢をあいまいなままにはできない。ボルタンスキーはさまざまな聞き取り調査を通じて、現代の妊娠を「マネージメント」の対象である「プロジェクト」として位置づけた(不妊治療は妊娠のプロジェクト化の象徴と言えるだろう)。妊娠の当事者たちは「親となるプロジェクト」に乗り出すが、その過程でときに、胎児に望ましくない可能性が現れるケースがある。そのとき、中絶はそのプロジェクトの「失敗」を吸収するための装置として利用される(232頁)。
ボルタンスキーによれば、当事者の女性たちは、中絶を主体的・自発的な「決定」として了解するよりも、「やむをえない過程の結果」として説明することのほうが、ずっと多い。妊娠というプロジェクトは、胎内の生命が、生まれてくるべき子どもかどうかを選別するプロセスを経る。このプロジェクトからの要求の結果として、中絶を合理化するケースが多いのである。
もとより、胎児を仕分けする絶対的な基準はないが、それでもカテゴライズしなければ中絶はできない。ボルタンスキーは「肉としての人間」と「ことばによる人間」というカテゴリーがあると想定する(71頁)。妊娠・出産というプロジェクトに迎え入れられるのは、ことばを通じて大人たちに認証された胎児、つまり「真正な胎児」である。逆に、中絶の対象となるのは、そのような認証を得られず、肉の次元に留められた「できものとしての胎児」である。「この胎児は、世界の中にできるだけ痕跡を残してはならず、たとえ記憶の中であっても残してはならない。少なくとも、中絶をした女性本人以外の人びとの記憶の中に残してはならないのである」(236頁)。こうして、プロジェクトから排除された胎児は「最小限の表象」しか与えられずに、無へと吸い込まれる。
〈3〉表象の貧しさや胎児のカテゴリー化は、中絶の社会学的分析には欠かせない現象である。しかし、妊婦の身体においては、もっと複雑な出来事が起こっているのではないか。そこでボルタンスキーは、妊娠の生じている場=身体の経験を《コーラ》――古くはプラトンの『ティマイオス』に登場し、近代の西田幾多郎やオギュスタン・ベルク、ジャック・デリダらに受け継がれた場所の概念――に引き寄せて記述しようとする。
ここで《コーラ》は《トポス》と区別されている。トポスとは「存在から分離された場」のことである。人間と場=トポスがきっちり分かれた状態で、主体が自律的に行為する――これはリベラリズムの前提でもあるだろう。逆に、コーラは「存在と相互関係にある場」を指す。人間と場がもつれあい、相互に作用を及ぼすのがコーラの特徴である。胎児と共生する女性の身体は、トポスではなくコーラに近い。先述したように、地震と妊娠は似ているが、揺れる大地/身体はまさに《コーラ》そのものである。
こうして、ボルタンスキーはリベラルな自律的主体のモデルを相対化しつつ、妊娠する身体という《コーラ》を概念化しようとする。そのアイディアは十分に展開されたとは言い難いが、それでも妊娠という体験を掘り下げると、哲学的なテーマにまで到るのは当然だろう。妊娠や出産は明らかに人間の根源に関わるが、これまでの男性たちの哲学ではまともに扱われてこなかった。ボルタンスキーはその欠落を埋めようとしたのである。
(※)むろん、アメリカのように、プロチョイス派(女性の選択を重んじ中絶を認める立場)とプロライフ派(生命を重んじ中絶に反対する立場)が「市民戦争」(3頁)のような争いを繰り広げている国もある。銃規制問題および中絶問題で国論を二分するような大騒ぎになるアメリカは、私には何とも奇妙な国家に映るが、この二つの問題がいずれも「生命を守ること」と「権利や選択を守ること」という近代の二つの原理の衝突から来ていることは、無視できないだろう。私を含めて大方の日本人は「銃を所持する権利はバツで、中絶する権利はマル」と言いたくなるだろうが、そう簡単にはいかない。アメリカの外では適当にやり過ごされている――しかしパンデミックともなれば浮上せざるを得ない――「チョイス」と「ライフ」の相克が、アメリカではむしろたえず顕在化されるのである。
なお、ボルタンスキーも言うように、日本は胎児が比較的多く表象されてきた国である。なかでも『古事記』にはイザナギとイザナミのあいだに生まれた蛭子を、葦舟にのせて海に流すエピソードがある。河合隼雄の『神話と日本人の心』によれば、この捨てられたまま帰還しなかった神は、日本神話の調和を崩す異物として際立っている。