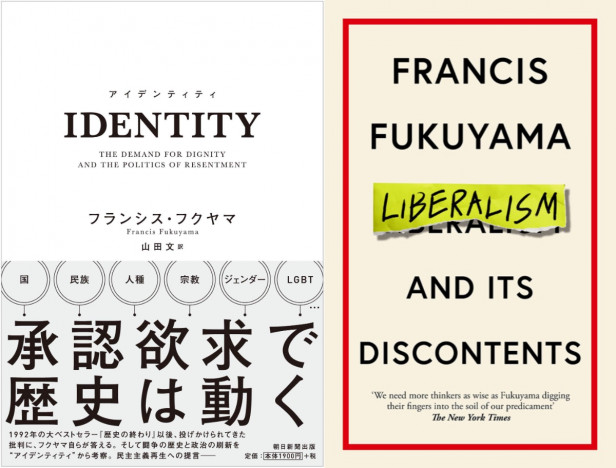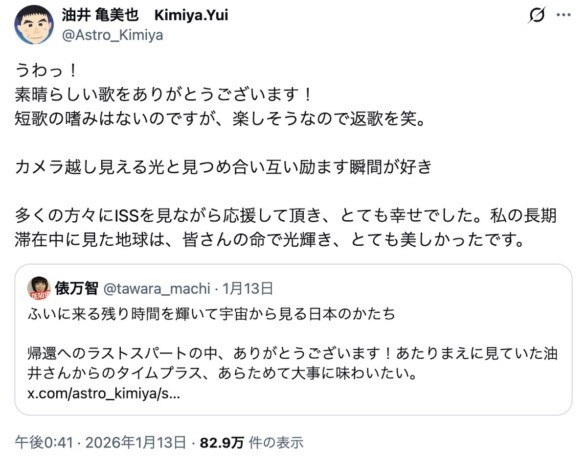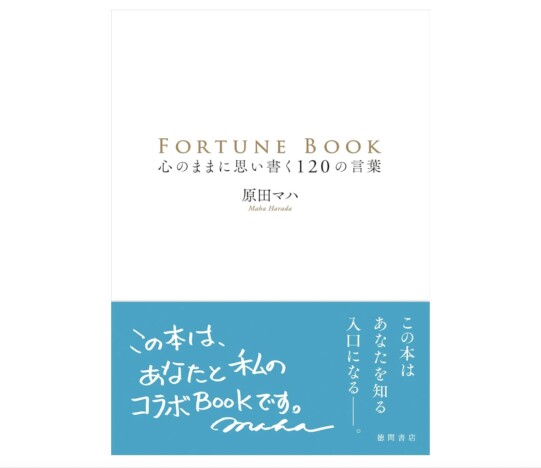胎児という暗がり、妊娠というプロジェクト――リュック・ボルタンスキー『胎児の条件』評

いかにして胎児に生まれる権利が与えられるのか
もとより、20年近く前に書かれた本書が、すでにいささか古びた印象を与えることは否めない。人工子宮の実用化はまだ難しいので《コーラ》の体験が妊婦から消えることは当分ないだろう。しかし、中絶に関して言えば、今後はいわば《肉以前》の段階、つまり受精卵への干渉が相当進むはずである。もし着床前診断(受精卵の段階で遺伝子異常を検出する技術)が定着すれば、中絶に伴う罪悪感や身体的負担はずいぶんと減るだろう。そのとき「肉としての人間」と「ことばによる人間」というボルタンスキー的なカテゴリーは、修正を余儀なくされるのではないか。
それでも、本書の試みは貴重である。そもそも「生物学的なもの」と「社会的なもの」が家族においていかに接合されるか、それによって人間の集合体がいかに持続するかは、人類学の主要なテーマであった(53頁)。レヴィ゠ストロースの人類学は、近親相姦というタブーを回避するための《婚姻》の規則を、つまり「誰が誰と結婚できるか」という親族関係の法則を重視した。それに対して、ボルタンスキーは認識の暗がりにあり、明確なタブーもない《出生》の規則を、つまり「いかにして胎児に生まれる権利が与えられるのか」という問題を浮かび上がらせる。ボルタンスキー流の「生むことと中絶の社会学」には、バタイユやレヴィ゠ストロースとは異なる人類学的モデルが必要なのだ。
こう考えていくと、リュック・ボルタンスキーの弟で著名なアーティストであるクリスチャン・ボルタンスキーの仕事が、どうしても思い出される。クリスチャンはまさに「プロジェクション」(投影)の作家である。例えば、子どものおもちゃがゆらめいて、壁に巨大な影絵を投げかけるインスタレーションでは、ほんの些細なものから亡霊的なイメージや記憶が引き出される。それは、わずかなサインから途方もなく大きなイメージを作り出してしまう、われわれの記憶の仕組みそのものの展示のようにも思える。
さらに、この亡霊的なプロジェクションは、遺物を収集するプロジェクトにまで展開される。クリスチャンは大量の古着や写真、さらには心臓の鼓動音――いずれも主体の痕跡を残した物質――を執念深く保存しては、それをアーカイヴ化してきた。本人が言うように、その大量のオブジェを集めた展示室は、ときに強制収容所のガス室を思い起こさせる(『クリスチャン・ボルタンスキーの可能な人生』参照)。ホロコーストのトラウマは、ユダヤ人であるクリスチャンを突き動かすオブセッションとなっている。彼は最もおぞましい「絶滅」の出来事をたえず喚起しながら、膨大な痕跡の「保存」を実行し続ける――まるで悪夢にうなされながら救済の夢を見るように。そこでは、事物の救出と収容はときに区別しがたい。
リュックが多くの女性の「証言」を集めて、おおっぴらに語られない中絶さらには胎児という亡霊を描き出したとすれば、クリスチャンは大量の遺物を保存し、インスタレーションのなかで死者を生き返らせる。ボルタンスキー兄弟の関心はまさに好一対である――中絶が《生前の死》だとすれば、保存は《死後の生》なのだから。そして、このいずれもが、亡霊のプロジェクション(投影)を含んだプロジェクトとして実行されるのである。人間は今や生まれる前から、テクノロジーの環境に収容され、その干渉を受けている。胎児の選別は今後、より洗練された技術的手法でなされるだろう。そのとき、われわれは亡霊の記憶を保つことができるだろうか。ボルタンスキー兄弟はそのような問いを投げかけている。